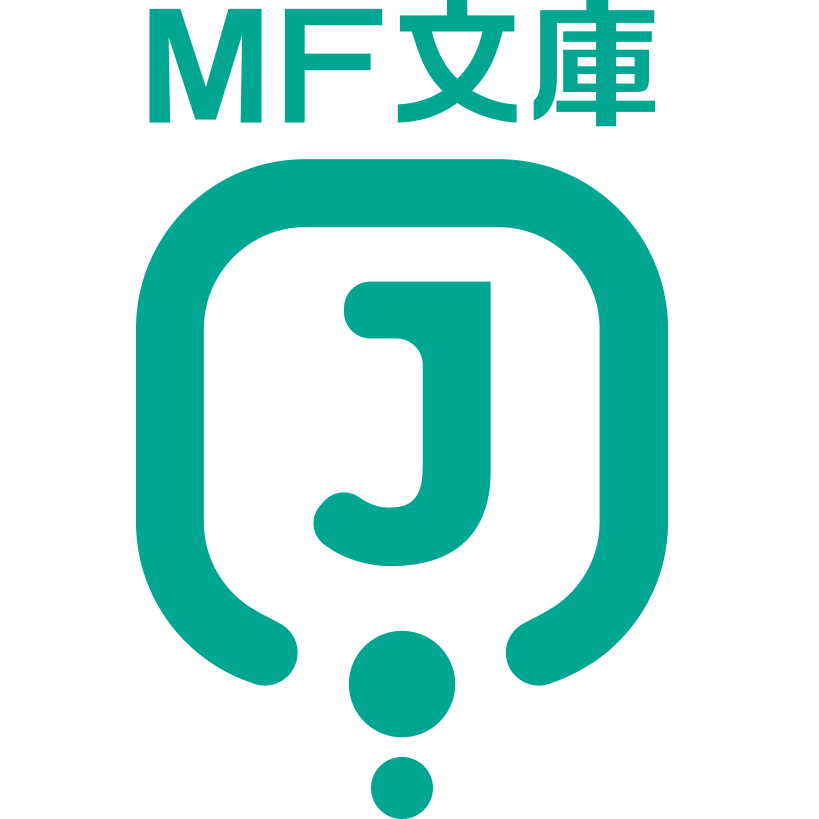概要
不運×記憶喪失な主人公がなんでもアリの〝賭け事〟に挑む!?
総ての夢と希望が叶う街──拡張都市パンドラを舞台に、
人々は「どんな望みも叶う」という希望を巡って日々〝ゲーム〟に明け暮れていた。
100の夢を持つ女子高生ストリーマー、天才チートデザイナー、ユメ狩りのために世界を闊歩する神がかり的ラッキーガール、そして〝世界の設計図〟の回収を目論む新世界運営委員会……
次々に訪れる〝不運〟に振り回されながらも、記憶喪失の少年・波止場は、バニーガール姿のコンシェルジュアプリ──《NAV.bit》と共に、「希望を賭けたゲーム」を取り巻く騒動に巻き込まれていくことになる。
そして、夢と希望に満ち溢れたこの世界にはまだ誰も知らない秘密もあって……
「──終わるんですよ。もうまもなくこの世界は、終了します」
###更新スケジュール####
※章区切
人々は「どんな望みも叶う」という希望を巡って日々〝ゲーム〟に明け暮れていた。
100の夢を持つ女子高生ストリーマー、天才チートデザイナー、ユメ狩りのために世界を闊歩する神がかり的ラッキーガール、そして〝世界の設計図〟の回収を目論む新世界運営委員会……
次々に訪れる〝不運〟に振り回されながらも、記憶喪失の少年・波止場は、バニーガール姿のコンシェルジュアプリ──《NAV.bit》と共に、「希望を賭けたゲーム」を取り巻く騒動に巻き込まれていくことになる。
そして、夢と希望に満ち溢れたこの世界にはまだ誰も知らない秘密もあって……
「──終わるんですよ。もうまもなくこの世界は、終了します」
###更新スケジュール####
※章区切