ジャック・オ・ランタンの海
管野月子
まだ緑の気配のない春の夕暮れ
冬の終わりと聞けば、誰もが青い空の下の明るい日差しと萌える緑、柔らかな花の色を思い浮かべるだろう。残念ながら見上げた空は暗く、重く、厚い雲に覆われている。
数時間に一本しか通らないような田舎の電車を降りた駅は、寂れた町だった。
景色だけを見れば村といってもいいだろう。
時刻は十五時半を過ぎたところ。陽が沈むまで二時間あまり。僕は一台のスマホを取り出し地図アプリを起動させた。わずかな読み込み動作の後に、ひどくシンプルな図が表示される。
今いる駅前こそは、幾つが枝分かれした道と駅名、公民館などの文字が浮かぶが、それ以外に目印となるようなものは無い。ただまばらな家の間を縫って、東に
この様子なら地図が無くても迷うことは無いだろう。
僕は知らず知らずの内に、笑みに似た表情に顔を歪めて、スマホをポケットにしまい込んだ。
この少し古い機種のスマホは、僕の物では無い。
詩的な表現をするならば、元所有者から別れを告げられた記憶の欠片、とでもしておこうか。あまりに自分らしく無い思いつきに、もう一度顔を歪める。
確かに今、僕がやろうとしていることは自分らしくない。
それでもここで引き返す気持ちにはならなかった。
引き返したところで次の電車が来るのは三時間後。ただ駅のベンチに座って、漫然と薄暗い天井を眺めるより他にない。
ゆっくりと東に向かって歩き始めた僕は、
ここは……遠い昔、一度来たことがある。
それなのに、これといった記憶は思い浮かばない。おそらく学生の頃、仲間と適当に田舎道を車で走り、目についた道を曲がる、といった意味の無い遊びの果てに辿り着いた場所の一つだ。
地名に覚えがあるのに景色の記憶が無いのは、その時が鮮やかな花の咲き乱れる熱い夏か、ぽつりぽつのと立ち並ぶ街路樹が、美しい紅葉に染まる季節だったからではないかと思う。
雪の消えた、けれど春と呼ぶには遠い北国の、薄暗く、肌寒い季節ではなかったから、見える景色の印象が噛み合わないのだ。
それでも道沿いに行くと、一件の喫茶店が目に入った。
古い壁はペンキも剥げ、油で浮いたファンデーションのようになっている。今は営業していないのだろう、暗く、人の気配は無い。その物音一つない忘れ去られたような店で、確かに彼女と僕は席に着いていた。
鈍い光を落とす、くすんだ窓際。メニューの種類が少なくて、氷が揺れるレモンスカッシュを前に、これが飲みたかったのだとわざと笑った。
何を話していたのか記憶は曖昧だが、おそらく前日に見たテレビやレポートのこと、卒業後の進路やバイト先のどうしようもない客の話を――時と共に流れ消えてしまうような話を、ひとつふたつと交わして過ごしたはずだ。
そしてどこか遠いところを見つめるような瞳の彼女の側には、今、僕のポケットに入ってるスマホが置かれていた。
喫茶店の前を通り過ぎ、道なりに歩いて行く。やがて民家すらまばらとなり、凡そ人工物のようなものなど見えない原野に出た。
背の高い樹は一本も無い。
地を這う草も雪の重みに潰れて、ただ大地を
砂利を、踏む音がけが耳に触る。
海鳥が黒い影となって、はるか遠くを
ポケットからスマホを取り出しホームキーに触れると、地図アプリが起動したままになっていた。アプリを閉じ、おどけた顔のジャック・オ・ランタンが浮かぶホーム画面になる。
ハロウィンは――たしか、十月末の祭りだ。
ということは、彼女が消えてから五ヶ月も経ったのだという時間の流れを今更ながら実感して、僕は顔を歪ませる。そして不意に思い立ち、カメラを起動して目の前の景色を収めた。
人ひとりいない。
それどころか時折飛来する鳥の影以外、生き物の気配もない、平坦で、荒涼とした景色。微かに潮の匂いを含んだ海風だけが吹き抜け、世界を灰と黒と赤茶けた色に染めている。遠く、潮騒が響く。
世界の何もかもが死んだように微睡む夕暮れ時。
なのに、不思議と、寂しいと感じない。
感じる心まで枯れてしまったわけではないだろうに。
黒い砂利の道も枯草に掻き消え、原野の果ては崖になっていた。
その向こうは暗い青と灰を混ぜたような、
崖はさほど高く切り立っているわけではなく、五メートルとか、目測でも二階か三階程度の高さだ。飛び下りても腕を折る程度で、死ねるような高さではない。ただ、遥か昔からそこにあるのだろう鋭い岩に当たったなら、ただでは済まない。
僕は釣りを
波が、岩肌を打ち白い泡を立てて砕けていく。
繰り返し、繰り返し。
壊れた機械のように、同じ動きを繰り返している。
その海をぼんやりと見つめ、手の中のジャック・オ・ランタンに視線を落とした。
元はイングランドに伝わる、旅人を迷わせ底なし沼に引きずり込む悪魔だと、得意げに語る彼女から聞いたことがある。
悪魔も
その話がアメリカに渡り、カブ頭はハロウィンでよく見る黄色いカボチャのモンスターと変っていった。
お菓子をねだったりイタズラをするだけの、可愛いキャラクターではないのだと。
スマホだけを置いて消えてしまった彼女に、何があったのか詳しいことは分からない。ただ常々、自分はカボチャのお化けなのだと呟いていたから、言い伝えにあるモンスターと自分を重ねる所があったのかもしれない。
冬の始めに失踪した彼女の行方を知る者は無く、僕の部屋に残されたスマホを見つけたのは随分経ってのこと。
勝手に触るのは悪いと思いつつ手がかりは無いかと見れば、ロックはかかっておらず、電話の履歴やアドレス、SNSは全て消されていた。残っていたのは、僕と撮った幾つかの写真データのみ。
意図的に置いて行ったのだとわかった。
彼女の家族に連絡を取る方法も分からず、誰からの連絡も無く、月日だけが流れたある日、彼女のスマホが鳴った。
かけてきたのは彼女自身だった。
生きていた。ただそれだけで安心した。
彼女は全てを捨ててしまいたかったのだと、沈黙を挟みつつ僕に伝えてくれた。けれど死ぬことは選べなくて、一人、異国に渡っていた。そこで本当にやりたいことを見つけたのだという。
たぶんもう日本には帰らない。
帰化できるまで手続きに行くことはあるかもしれないけれど、誰にも会わないと。だからゴメンとスマホの向こうで彼女は謝った。謝ってから、怒っているでしょうとも訊いてきた。
僕は、不思議と怒りの感情が無かった。
自分でもわからない。
君が生きていて、生きがいが見つかってよかった。
ただそれだけを想える自分が不思議でならない。
彼女はスマホの向こうで、泣いていた。
僕と彼女は恋人同士にはなれなかった。
それでもいい。今はただ、彼女が未来に向かって歩けるのが嬉しい。
このスマホは間もなく解約するという。今は書類を準備しており、整い次第、家族を代理人に行うという。スマホ自体は無くしたことにしたから、処分は任せると、最後の我が儘だと伝えてきた。
個人の番号データは全て消しても、どうしても消せないものがあったのだ。それが僕との写真なのだとすぐにわかった。残していたということは、少なくとも失踪した時点では戻る気持ちもあったのだろう。
どちらにしろ、さまよい続けていたジャック・オ・ランタンは人間に戻って、安住の地を見つけたのだ。
解約されれば通信機としての機能は無くなる。彼女との繋がりも消える。
ちゃんと捨てるよ――と伝えた言葉で、通話は終わった。
ここは海水浴にも使われない、北国の、寂しい海辺。
彼女のスマホは少し古い機種で防水ではない。一度海に落ちたなら、リカバリーは難しいだろう。それでいいと思う。
僕はスマホを握ったまま振りかぶり、遠くへ、可能な限り遠くへ飛ぶように、手を離した。
ホーム画面の、ジャック・オ・ランタンの灯火が、夕暮れの空に弧を描く。
風が吹く。
泡立つ波が受け止める。深い海の底へと誘うように。
消え、安住の地へと流れ行く。
灰色の雲間を割って、薄紅の夕陽が海を照らしていた。
ジャック・オ・ランタンの海 管野月子 @tsukiko528
★で称える
この小説が面白かったら★をつけてください。おすすめレビューも書けます。
カクヨムを、もっと楽しもう
カクヨムにユーザー登録すると、この小説を他の読者へ★やレビューでおすすめできます。気になる小説や作者の更新チェックに便利なフォロー機能もお試しください。
新規ユーザー登録(無料)簡単に登録できます
この小説のタグ
同じコレクションの次の小説
関連小説
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。










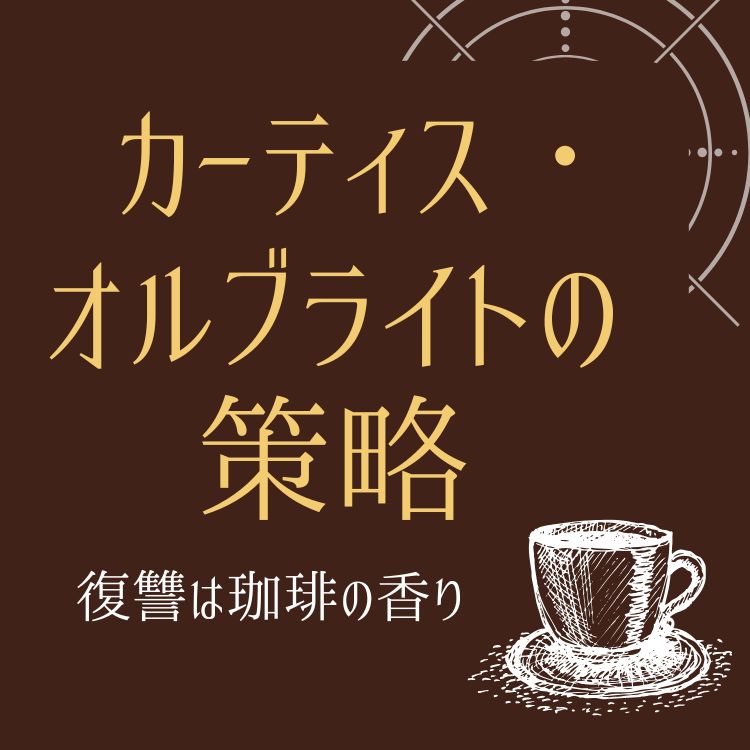
応援すると応援コメントも書けます