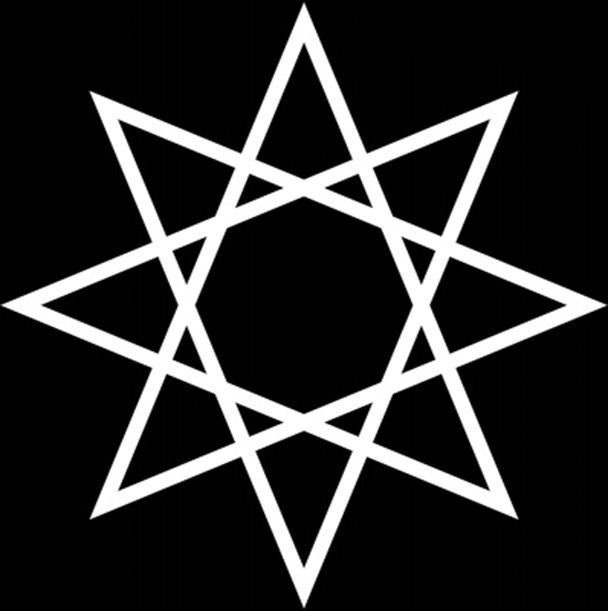歌手一年、総理二年の使い捨て
竹下登元首相が残された言葉だ。
今の岸田首相は人気が無い。
マスコミがどう叩こうと、人気がある首相他大臣連は、ネットでいいところが切り取られて拡散されたりする。
今だと小野田紀美議員の人気が熱い。
泡グラビアの三重国籍議員とか、生コン前科議員とか、大声でキーキー言って、そこをマスコミが切り貼りして流してたんだな、と思う。
その岸田首相が同性婚に後ろ向きな発言をしたという。
僕はその発言は極めて正しいと思う。
もう一度いうけど、僕は百合マンガというジャンルを極めて尊いものだと評価して愛読している。
ちなみにいうとさっきcitrus+の5巻や、ささ恋の7巻、きみ死ぬの6巻、citrusの特装版5冊、宮原都先生の「夏とレモンとオーバーレイ」、生王子の一巻二巻とか買って「こんな文章書いてる場合じゃない」とウハウハだ。
でも、自分の……性的志向?……? と、行政の制度とは厳しく分けて考えなければならないと思う。
そもそも結婚が両性の合意の基に成立するということは、日本国憲法第二十四条第一項にまで遡って制定されていることであり、同性婚を認めるのであれば、まず憲法を改め、その上で民法を改めなければならない。
ただ、僕が幾ら低学歴でも、そんな僕でも透けてみえてしまうくらい、同性婚制度推進団体は、地続きで改憲反対派や、自衛隊違憲派とつながっている。
だから憲法はそのままに、小手先の民法だけを改ざんして済ませようとしている。
そもそも、この国を弱体化することを目的とした団体が取り組んでいる時点で、反対すべき事項だということがわかる。
が、そんな下衆の勘繰りを除いても、そもそもこの国の社会制度にはいろいろな不可思議が紛れ込んでいる。
日本人は一夫一妻の国だと思っていないだろうか?
「思っているも何も、重婚は法律で禁止されており手続き上も認められない」という向きもあろう。
ところが外国人から「日本は一夫一妻の国だと聞いていたが、一夫多妻をみとめているのかい?」とたずねられることがあるという。
日本人は結婚を「二人の愛の総決算」とか「二人の愛を生活スタイルという形に表したもの」と何となくロマンチックに受け止めている向きも多い。
救世主教の婚姻の式辞で、「死が二人を分かつまで」という言葉をロマンチックに受け止めている向きも多いし、そう誓ったにもかかわらず、配偶者の死後も思い人への想いを大事に秘め、一人静かに暮らしている人も多い。
外国人は違う。
「いや、神様にだって『死が二人を分かつまで』って誓ったんだから、妻が亡くなるまで不貞は働かないが、もし妻が先に旅立つことになったら、別の恋をみつけることにするよ。
だって『死が二人を分かつまで』って誓ったんだから」
という風に考えて、倫理上何の問題もないと受け止めることが多い。
ここが実に日本人の倫理観と違うところで、こういう倫理観の違いの蓄積が日本が救世主教に染まらなかった一因でもある。
そんな風に、外国人にとっての結婚は、その地域、その地域ごとにいささか異なる部分はあろうとも、「契約」の一つに過ぎない。
そしてその「結婚契約」の大きな所は二つ。
不貞を働かない、そして財産の共有にある。
たとえば住居について、そのローンのほとんどを夫が負担し、その夫が先に旅立ったとしても、正式に婚姻した妻であれば(それなりに色々と手続きがあるものの)自分の住居として住み続けることができる制度が用意されている。
これが、正式に婚姻届を提出していない、いわゆる内縁関係の場合、残された内縁の妻は居住権を維持できない。
「ほら、ちゃんと正式に婚姻した妻が法律上も守られているじゃないか」
という考え方を否定はしない。
ただ、相続となるとやや話が変わってくる。
正式な結婚の基、男女の間に生まれた子は婚内子といわれる。
その夫が外で愛人を作り、産ませた子は婚外子とされる。
この婚外子を、夫が「確かに自分の子で有る」と認知したばあい、戸籍に認知の事実が書き込まれ、その婚外子は、遺産相続の財産分与割合で、婚内子と同じだけの割合を相続する権利を有する。
これが、一夫一妻の国ならおかしかろう、というのが外国人の考え方だ。
確かに愛人には財産の相続権こそないが、その間にできた子は、正妻との間にできた子と、同じだけの遺産を相続できるのだ。
これは正統な妻と、その子女の財産権を毀損させるもの、と考えるのが当然なのだ。
そうではなく、愛人が何人もいて、婚外子が何人もいて、その子らが認知されていれば、いや、認知されていなくても、夫の死後三年以内の時効の中であれば「認知を求めて裁定を受けることができる」という制度まである。
ここまで手厚く、そして広く相続権を認められていて、何が一夫一妻の国だ、事実上一夫多妻の国じゃないか。
ということだそうだ。
おおかた、平等、という言葉が好きな左巻きが、ああでもない、こうでもない、と騒ぎ立てて仕立て上げたのだろう。
正妻と、その子達にとってはたまらない。
ざっくりと「妻と、子達のみが相続人」の場合、夫の遺産の半分を妻が相続し、のこりの半分を、子供達の頭数で割った分が、一人ひとりの取り分となる。
夫を失った失意も癒えぬ間だというのに、「私は認知されています」「私も認知されています」「わたしも」「わたしも」とどんどん相続人が増え、見る見る間もなく婚内子の相続分が目減りしていってもどうすることも叶わない。
「今まで、正妻の子として生きてきた人生は何だったのだ」と思わずにはいられないだろう。
こんな、一見平等なようで、不公平な制度がまかり通っているのが日本なのだ。
僕として「ここまでなら社会を大きく毀損しない」と思える、同性カップルに法的に与えられる権利には、まず、性志向が同性を向いていることを複数の医師の診断で認められ、且つ、お互い相手を唯一の性的バートナーとして認め合っており、且つ同一の居所に相応の期間同居している前提が、最低限必要だと思う。
こういうことは全然同性愛と無関係の人物達が悪用できる制度であってはならない。
そして、婚姻とは別の言葉が用意され、「あくまで婚姻ではないが、財産などの共有を認める制度」と区別されるのがよいと思う。
姓氏は別姓のまま、戸籍も別々のままが基本で、同姓になりたければ養子制度をベースに、本来の養子制度の権利の中で、同性婚の関係にはそぐわないものはばっさり斬り落として使えればよいと思う。
そして住居などの生活基盤になる大きな財産には共有権を認め、名義上片方のパートナーの資産となっていても、そのパートナーと死別した際は、残されたパートナーの相続権と居住権を認める制度であると良いと思う。
ただし、片方のパートナーが、別の同性、もしくは別の異性と不貞関係にある場合は、離縁する制度があり、不貞行為を働いた方が、慰謝料などの負担を重く持つ制度でなければならない。
あっちとくっついたりこっちとくっついたりして、財産関係が混乱するような制度であってはならないと思う。
このほかにも、僕が法律の専門家でもない、学もない人間だから思いの至らない整えるべき制度が山ほど合って、それらを総合的に整えるプランがまとまったところで、
まず憲法を変えて、
その上で民法及び諸制度を変えて、初めて成立するのが「同性婚」という生き方だと思う。
「二人が愛し合ってればいいじゃないか」と同性カップル達がいったところで、「愛」じゃ制度は整わない。
改憲にまで関わる事柄について、首相という重い責任を担う職の人が、軽々に「いいじゃない、進めよう」といいだす人柄であったら、それこそ国政を任せられないと判断するのが、知性と理性を兼ね備えた人の選ぶ所であると思う。
ぐだぐだと長々書いたが、「柚子と芽衣」がダブルウェディング姿で祝福される日は、早く来るといいと思う。
今の岸田首相は人気が無い。
マスコミがどう叩こうと、人気がある首相他大臣連は、ネットでいいところが切り取られて拡散されたりする。
今だと小野田紀美議員の人気が熱い。
泡グラビアの三重国籍議員とか、生コン前科議員とか、大声でキーキー言って、そこをマスコミが切り貼りして流してたんだな、と思う。
その岸田首相が同性婚に後ろ向きな発言をしたという。
僕はその発言は極めて正しいと思う。
もう一度いうけど、僕は百合マンガというジャンルを極めて尊いものだと評価して愛読している。
ちなみにいうとさっきcitrus+の5巻や、ささ恋の7巻、きみ死ぬの6巻、citrusの特装版5冊、宮原都先生の「夏とレモンとオーバーレイ」、生王子の一巻二巻とか買って「こんな文章書いてる場合じゃない」とウハウハだ。
でも、自分の……性的志向?……? と、行政の制度とは厳しく分けて考えなければならないと思う。
そもそも結婚が両性の合意の基に成立するということは、日本国憲法第二十四条第一項にまで遡って制定されていることであり、同性婚を認めるのであれば、まず憲法を改め、その上で民法を改めなければならない。
ただ、僕が幾ら低学歴でも、そんな僕でも透けてみえてしまうくらい、同性婚制度推進団体は、地続きで改憲反対派や、自衛隊違憲派とつながっている。
だから憲法はそのままに、小手先の民法だけを改ざんして済ませようとしている。
そもそも、この国を弱体化することを目的とした団体が取り組んでいる時点で、反対すべき事項だということがわかる。
が、そんな下衆の勘繰りを除いても、そもそもこの国の社会制度にはいろいろな不可思議が紛れ込んでいる。
日本人は一夫一妻の国だと思っていないだろうか?
「思っているも何も、重婚は法律で禁止されており手続き上も認められない」という向きもあろう。
ところが外国人から「日本は一夫一妻の国だと聞いていたが、一夫多妻をみとめているのかい?」とたずねられることがあるという。
日本人は結婚を「二人の愛の総決算」とか「二人の愛を生活スタイルという形に表したもの」と何となくロマンチックに受け止めている向きも多い。
救世主教の婚姻の式辞で、「死が二人を分かつまで」という言葉をロマンチックに受け止めている向きも多いし、そう誓ったにもかかわらず、配偶者の死後も思い人への想いを大事に秘め、一人静かに暮らしている人も多い。
外国人は違う。
「いや、神様にだって『死が二人を分かつまで』って誓ったんだから、妻が亡くなるまで不貞は働かないが、もし妻が先に旅立つことになったら、別の恋をみつけることにするよ。
だって『死が二人を分かつまで』って誓ったんだから」
という風に考えて、倫理上何の問題もないと受け止めることが多い。
ここが実に日本人の倫理観と違うところで、こういう倫理観の違いの蓄積が日本が救世主教に染まらなかった一因でもある。
そんな風に、外国人にとっての結婚は、その地域、その地域ごとにいささか異なる部分はあろうとも、「契約」の一つに過ぎない。
そしてその「結婚契約」の大きな所は二つ。
不貞を働かない、そして財産の共有にある。
たとえば住居について、そのローンのほとんどを夫が負担し、その夫が先に旅立ったとしても、正式に婚姻した妻であれば(それなりに色々と手続きがあるものの)自分の住居として住み続けることができる制度が用意されている。
これが、正式に婚姻届を提出していない、いわゆる内縁関係の場合、残された内縁の妻は居住権を維持できない。
「ほら、ちゃんと正式に婚姻した妻が法律上も守られているじゃないか」
という考え方を否定はしない。
ただ、相続となるとやや話が変わってくる。
正式な結婚の基、男女の間に生まれた子は婚内子といわれる。
その夫が外で愛人を作り、産ませた子は婚外子とされる。
この婚外子を、夫が「確かに自分の子で有る」と認知したばあい、戸籍に認知の事実が書き込まれ、その婚外子は、遺産相続の財産分与割合で、婚内子と同じだけの割合を相続する権利を有する。
これが、一夫一妻の国ならおかしかろう、というのが外国人の考え方だ。
確かに愛人には財産の相続権こそないが、その間にできた子は、正妻との間にできた子と、同じだけの遺産を相続できるのだ。
これは正統な妻と、その子女の財産権を毀損させるもの、と考えるのが当然なのだ。
そうではなく、愛人が何人もいて、婚外子が何人もいて、その子らが認知されていれば、いや、認知されていなくても、夫の死後三年以内の時効の中であれば「認知を求めて裁定を受けることができる」という制度まである。
ここまで手厚く、そして広く相続権を認められていて、何が一夫一妻の国だ、事実上一夫多妻の国じゃないか。
ということだそうだ。
おおかた、平等、という言葉が好きな左巻きが、ああでもない、こうでもない、と騒ぎ立てて仕立て上げたのだろう。
正妻と、その子達にとってはたまらない。
ざっくりと「妻と、子達のみが相続人」の場合、夫の遺産の半分を妻が相続し、のこりの半分を、子供達の頭数で割った分が、一人ひとりの取り分となる。
夫を失った失意も癒えぬ間だというのに、「私は認知されています」「私も認知されています」「わたしも」「わたしも」とどんどん相続人が増え、見る見る間もなく婚内子の相続分が目減りしていってもどうすることも叶わない。
「今まで、正妻の子として生きてきた人生は何だったのだ」と思わずにはいられないだろう。
こんな、一見平等なようで、不公平な制度がまかり通っているのが日本なのだ。
僕として「ここまでなら社会を大きく毀損しない」と思える、同性カップルに法的に与えられる権利には、まず、性志向が同性を向いていることを複数の医師の診断で認められ、且つ、お互い相手を唯一の性的バートナーとして認め合っており、且つ同一の居所に相応の期間同居している前提が、最低限必要だと思う。
こういうことは全然同性愛と無関係の人物達が悪用できる制度であってはならない。
そして、婚姻とは別の言葉が用意され、「あくまで婚姻ではないが、財産などの共有を認める制度」と区別されるのがよいと思う。
姓氏は別姓のまま、戸籍も別々のままが基本で、同姓になりたければ養子制度をベースに、本来の養子制度の権利の中で、同性婚の関係にはそぐわないものはばっさり斬り落として使えればよいと思う。
そして住居などの生活基盤になる大きな財産には共有権を認め、名義上片方のパートナーの資産となっていても、そのパートナーと死別した際は、残されたパートナーの相続権と居住権を認める制度であると良いと思う。
ただし、片方のパートナーが、別の同性、もしくは別の異性と不貞関係にある場合は、離縁する制度があり、不貞行為を働いた方が、慰謝料などの負担を重く持つ制度でなければならない。
あっちとくっついたりこっちとくっついたりして、財産関係が混乱するような制度であってはならないと思う。
このほかにも、僕が法律の専門家でもない、学もない人間だから思いの至らない整えるべき制度が山ほど合って、それらを総合的に整えるプランがまとまったところで、
まず憲法を変えて、
その上で民法及び諸制度を変えて、初めて成立するのが「同性婚」という生き方だと思う。
「二人が愛し合ってればいいじゃないか」と同性カップル達がいったところで、「愛」じゃ制度は整わない。
改憲にまで関わる事柄について、首相という重い責任を担う職の人が、軽々に「いいじゃない、進めよう」といいだす人柄であったら、それこそ国政を任せられないと判断するのが、知性と理性を兼ね備えた人の選ぶ所であると思う。
ぐだぐだと長々書いたが、「柚子と芽衣」がダブルウェディング姿で祝福される日は、早く来るといいと思う。