物語の構成篇
起承転結ではなく、なぜ「三幕構成」なのか?
いよいよ今回から「
小説の書き方を解説している本やウェブサイトの多くは、物語構造の解説に多くのページを割いています。フィルムアート社がこれまで刊行してきたハリウッド式の脚本メソッド本も例外ではありません。
日本では従来より「序破急」や「起承転結」が物語構造のテンプレートとして物語創作者に親しまれてきましたが、この連載ではハリウッド式の脚本メソッドで主流となっている「三幕構成理論」をベースに物語構造について解説していきたいと思います。
本連載は必ずしも「序破急」や「起承転結」を否定するものではありません。「序破急」や「起承転結」を用いて上手く
さて、日本でもすでに定着した感のある三幕構成理論ですが(日本語版のWikipediaもかなり充実しています)、この理論を体系化したのが、かの有名なシド・フィールドです。

シド・フィールドの著作『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』(原題:Screenplay: The Foundations of Screenwriting)は、1979年の初版刊行以来多くの版を重ね、29の言語に翻訳され100万部以上の売り上げを誇る、いわば「脚本の教科書」ともいうべき一冊です。

本書によれば、どんな物語も必ず「発端、中盤、結末」をもっています。
三幕構成とは、「発端(=第一幕)」、「中盤(=第二幕)」、「結末(=第三幕)」で構成される「物語構造のパラダイム(見取り図)」のことを意味します。

物語に「始め、中、終わり」を設定する、というずいぶんと当たり前の(ように思える)ことが、なぜ物語構成の有力なメソッドになり得るのでしょうか。それはこの三幕が、人類にとっていちばん魅力的な普遍的な物語の型として、有史以来ずっと受け継がれているからです。


英雄の旅や、脚本執筆の22段階、七幕構成等、構成に関する理論はたくさん存在する。あなた好みの構成理論がどれであっても、結局はどれを選んでも同じ結論が待っている。つまり、すべての物語は、始め、中、終わりという三楽章から成っているのだ。例えば別の観点から、物語を「お膳立て、混乱、解決」に分けても構わないし、読者に与える感情という視点から「関心を引く、緊張させる、満足を与える」と分けても構わないが、どうやら3という数字がぴったりはまる。それが、普遍的な物語の語り方を教える体系化された規範として、三幕構成が取り入れられた理由だろう。
この三幕構成というものは、誰かが長い間思索を巡らした末に考案して、今日から三幕構成に従うようにと宣言したというものではない。人間が話を作って語り始めた昔から、ずっとあったのだ。そして、それは科学者が自然の法則を発見したのと似た要領で、アリストテレスによって2400年ほど前に発見された。アリストテレスは、ただ芝居を観察しただけだ。感情的に満足感の高い、ゆえに人気の高い芝居が持っている共通の法則性に気づき、『詩学』にまとめたにすぎないのだ。
――『「感情」から書く脚本術 心を奪って釘づけにする物語の書き方』

上に示した「三幕構成の見取り図」には、「発端(=第一幕)」、「中盤(=第二幕)」、「結末(=第三幕)」以外にも、「状況設定」「葛藤・対立」「解決」や「プロットポイント」「ミッドポイント」などの単語や「25%」「50%」という数字が示されています。これらの単語の意味ついては、これからの連載の中で解説していきたいと思いますが、シド・フィールドの偉大な点は、物語の普遍的な型である「発端(=第一幕)」、「中盤(=第二幕)」、「結末(=第三幕)」とプロットを紐づけ、そこで何を語る必要があるのか、幕のつなぎ目にはどのような出来事を描くべきなのか、さらには各幕のボリューム(全体の何%になるべきか)を具体的に示した点にあります。
シド・フィールドが三幕構成理論を体系化してくれたおかげで、物語創作者は、これから何をするべきか、いま自分が何をやっているのか、を把握できるようになったのです。

脚本を書くことに関して、もっとも難しいのは何を書くかということである。120ページの真っ白な原稿用紙を目の前にして、この難解な道筋をうまく通り抜けてゴールにいたる方法はただ一つ、自分が何をしているのか、今自分がどの段階にいるのか、ということを知ることである。つまりロードマップが必要なのだ。始まりから終わりまでの一本の道、方向性を持たなければならない。
――『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』

前述のとおり、シド・フィールドの原書(Screenplay: The Foundations of Screenwriting)が刊行されたのが1979年です。実は三幕構成理論は、その後多くの脚本家や小説家、そしてストーリーコンサルタントたちによって、さまざまな発展形・応用形が生み出されています。

いちばん有名なところでは『SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術』の著者、ブレイク・スナイダーが発明した「ブレイク・スナイダー・ビート・シート(=BS2)があります。これは物語を3つ(三幕)ではなく、15個のビートに分割するというメソッドです(「最強の物語構成テンプレート「ブレイク・スナイダー・ビート・シート(BS2)とは何か?」で詳しく解説しています)。https://kakuyomu.jp/works/1177354055193794270/episodes/16816452220204266392)

また、古今東西の神話やおとぎ話などに普遍的に見いだされる物語の構造(=「型」)を物語創作用のテンプレート「
現在、ハリウッド式脚本メソッドには、物語構成について数多くのバリエーションが存在します。ただ、それらすべての基礎となっているのが三幕構成です。
この連載では、まずはこの三幕構成を理解したうえで、その発展形についても言及していきたいと思います。
本連載の「はじめに」でも触れましたが、「三幕構成」と聞いて多くの方が疑問に思う(であろう)点について、改めてお答えしておきます。
【三幕構成への疑問】
①それってただのテンプレートなんじゃないの?
→同じような(紋切型の)小説が量産されるのでは?
②映画脚本のメソッドを小説に応用できるのか?
→特に短篇には応用できないのでは?
まず、①それってただのテンプレートなんじゃないの? という疑問について。下記引用をご一読ください。
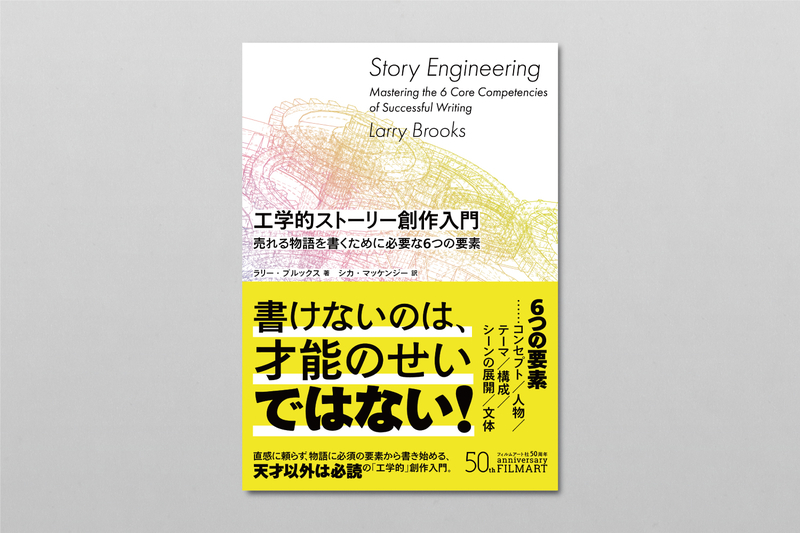

映画学校の学生は最初に「三幕構成」を学ぶ。映画は小説と無縁ではない。シナリオの原則を少し変えれば小説にも当てはまる。
(中略)
型にはめると無個性になるとは、僕は思わない。型は普遍的な法則のようなものだ。「ジェネリック」は悪いものではない。人間はみなジェネリックだ。腕が二本、脚が二本と胴体、頭がある。それが人体の構成だ。それでも同じ人は二人といない。その例えを聞いてもまだストーリーの構成がいやなら、どんな説明を聞いても変わらないだろう。世界にいる70億人は同じ構成だが一人ひとりユニークだと聞けば「構成に従えばアートでなくなる」「他の作品とそっくりになる」という不安は消えるはずだ。
――『工学的ストーリー創作入門 売れる物語を書くために必要な6つの要素』

そして②映画脚本のメソッドを小説に応用できるのか? という点については、幸いなことに、日本の著名な小説家や編集者の方々がいろんなところで言及してくれているので、それらを紹介することにしましょう。
「万能鑑定士Q」「高校事変」「千里眼」シリーズで知られる小説家の松岡圭祐さんの著書『小説家になって億を稼ごう』(新潮社)に三幕構成についての記述があります。
松岡さんは、脳内で物語を作り出す方法を『想造』と名付け、『想造』をアウトプットする際には、三幕構成に基づきながら、それぞれの幕を一行(40字)で表現する方法を推奨しています。その結果、三幕=三行で構成されるあらすじが完成するというわけです。


三幕構成は「第一幕=設定」「第二幕=対立」「第三幕=解決」です。三行を読み返せば、それぞれの要素が当てはまるはずです。『想造』段階で登場人物とともに波乱を乗り越えたことで、三幕構成に分かれる物語が、すでに構築できているのです。
三行はいずれも三幕の見出しです。行間をそれぞれ開けます。一行目と二行目の間は十行、二行目と三行目の間は二十行にします。
これは第二幕が第一幕の倍の長さになるからです。三行目から下はまた第一幕と同じ長さ、十行だと思ってください。第一幕が25%、第二幕が50%、第三幕が25%ぐらいの長さと考えます。
――『小説家になって億を稼ごう』

また、最前線で活躍する著名なミステリ作家たちが自身の執筆ノウハウを紹介した『ミステリーの書き方』(日本推理作家協会編著、幻冬舎)では、『GOTH』や『失はれる物語』で知られる乙一さんが、執筆に三幕構成を取り入れていることを明らかにしています。
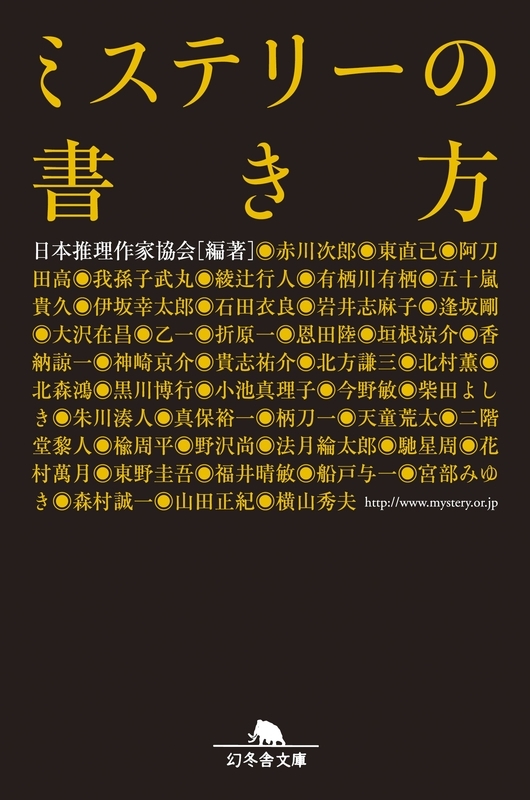

シナリオ理論は、科学であり技術だ。(中略)しかしこれまで、私自身の経験において、執筆における科学性の部分をないがしろにされることがおおかった。(中略)理論や技術によってオリジナリティがなくなるのではないか、という危惧は自分も抱いたことがある。しかし学んでみると、シナリオ理論は道具でしかないということがわかったのだ。鉛筆やボールペン、パソコンのワープロソフトとおなじように、物語を紡ぐためのツールの一種なのだ。全員が同じワープロソフトを使用したところで、完成する小説が似てくるなんてことはありえない。画一的になることを心配するよりも、ひとまず頭の片隅にこの理論をインストールしておくことを私は友人にすすめた。
――『ミステリーの書き方』

乙一さんはこのように述べた後、短篇集『GOTH』に収録されている「暗黒系」という作品を事例に、三幕構成を用いてどのように執筆したのか具体的に解説しています。「暗黒系」全体の尺は31ページですが、それを四等分して各章が8ページになるように本作品は書かれています。

「三幕構成なのになぜ四等分なのか」という疑問が生じた方もいると思いますが、三幕構成における二幕目の真ん中に「ミッドポイント」を置くという考え方に従うと三幕構成は実質四つのパートに分かれることになります(「ミッドポイント」については後述)。用語こそ乙一さん独自のもの(例:変曲点)に置き換えられていますが、その構造はシド・フィールドの「三幕構成の見取り図」とピタリと一致することがわかっていただけると思います。

また、直木賞作家の朱川湊人さんも同じく『ミステリーの書き方』の中で、ハリウッド式の脚本術のメソッドについて言及しています。上の図にある「ミッドポイント(=第二幕の真ん中にある前半と後半をつなぐ重要な事件)について下記のように述べています。

簡単に言ってしまうと「とにかく真ん中部分で何らかの事件を起こすと、全体のバランスが取りやすくなる」ということです。たとえば五十枚の作品なら二十五枚目あたり、百枚なら五十枚目あたりに、物語の大きな変化を与える事件を起こすのです。そんな機械的で単純なものなのか……と思われる方もおられるかと思いますが、実はこれは私の編み出した秘技でもなんでもなく、映画脚本を書く際のオーソドックスな技法で“ミッドポイントの設定”といいます。
――『ミステリーの書き方』

また、大手文芸出版社の新潮社に入社後「新潮ミステリー倶楽部」他3つの叢書を手がけるとともに、「日本推理サスペンス大賞」をはじめ5つの文学新人賞を立ち上げた敏腕編集者、佐藤誠一郎さんは著書『あなたの小説にはたくらみがない 超実践的創作講座』(新潮新書)で、「『起承転結』はウソかも知れない」という章を設け、「小説の制作現場での経験から」、「起承転結」の「承」は不要なのではないかという論を展開しています。そのうえで、物語の構成について次のように述べています。


三幕構成理論においては、一幕分に要する時間を指定してある。映画は平均的に言って約2時間の尺を持つ、いわば時間芸術だから、例えば第一幕に30分、第二幕に60分、第三幕に30分というふうに配分してあるわけだ。
これは小説にあてはめるならばページ数に相当するものだ。全部で300ページの小説作品であれば、第一幕にあたる部分が75ページ、第二幕が150ページ、第三幕が75ページという配分になってくる。実際、ページをめくる読者からすれば、その時間のかけ方は音楽や映画と同じだから、言語芸術である小説は、実は時間芸術でもあると言える。
オーソドックスな小説の構成が時間芸術のどんな理論から来ているか、と問うならば答えはただ一つしかないではないか。
それは「ソナタ形式」である。(略)
私の場合は、時間芸術としての小説の構成を「ソナタ形式」に求め、映画の構成術である「三幕構成」がまさにソナタ形式であるということから、この形を構成についての基礎理論としてお勧めする次第である。
――『あなたの小説にはたくらみがない 超実践的創作講座』

さて、疑問は解消されたでしょうか? もちろん三幕構成に当てはまらない事例(=例外)を見つけることは簡単です。ただ、日本の小説家や編集者(しかもかなり著名な)が、三幕構成を使って小説を書いていることもまぎれもない事実です。
また日本人の著者が、日本人読者向けに書いた『「物語」のつくり方入門 7つのレッスン』(円山夢久著、雷鳥社)でも、三幕構成をベースにして物語創作について解説しています。
三幕構成理論を使うか使わないかはみなさん次第です。苦手意識を持たれている方も、まずはこの連載を通じて三幕構成がどんなものなのかを知っていただければと思います。
さて、今回はまずは物語構成の基礎の基礎といわれている「三幕構成」について、イントロダクション的な内容をお届けしました。
次回からは三幕構成の具体的な内容について複数回にわたってお届けしたいと思います。一足先に予習したいという方は、ぜひシド・フィールドの『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』をご一読いただければと思います。三幕構成の解説が終わったあとは、その応用形であるいくつかの物語構成メソッドについても言及していく予定です。
【お知らせ】
物語やキャラクター創作に役立つ本
https://www.filmart.co.jp/pickup/25107/
【お得なセール情報】
フィルムアート社のオンラインショップで創作に役立つ本を20%オフの割引価格でセット販売しています。
https://onlineshop.filmart.co.jp/collections/20-off
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます