やっちまったんだぜ
とうとう古ノルド語に手を出しちまったんだぜ。
……そして、初っ端から複雑な音韻変化の説明に「こいつぁ、そりゃ大学でもそうそう講義がねーわけだわ」などという感想に至る。
で、腱鞘炎になりかけつつ、久々にノートにまとめるなどしました……形容詞の変化に強弱があるの、不思議……
手を出した理由は、まあ、「エッダ原文にアクセスはできるし、アイスランド語と文法的な互換性がまだ残ってるとはいえ、完全に追いつけるわけじゃねーなこれ……やるか(文法書を密林でポチー)」
ちょっとコンパクトな文法書なので説明順とかいろいろアレなところはあるけど、そこはそれ、ノートにまとめることで回避回避。
やっぱりね、名詞や動詞、形容詞を活用する言語は表を作って分析するのが手っ取り早いのですよ(ラテン語と古典ギリシャ語経由で身につけたやつ)
ところで、受動態のまともな説明がこの『古アイスランド語入門』の中にない気がする……でも日本語書籍で古ノルド語(=古アイスランド語)の文法説明してるのこいつぐらいしか……
というわけでこれはOJT的(訳しながら覚える)な気配ですね……
……そして、初っ端から複雑な音韻変化の説明に「こいつぁ、そりゃ大学でもそうそう講義がねーわけだわ」などという感想に至る。
で、腱鞘炎になりかけつつ、久々にノートにまとめるなどしました……形容詞の変化に強弱があるの、不思議……
手を出した理由は、まあ、「エッダ原文にアクセスはできるし、アイスランド語と文法的な互換性がまだ残ってるとはいえ、完全に追いつけるわけじゃねーなこれ……やるか(文法書を密林でポチー)」
ちょっとコンパクトな文法書なので説明順とかいろいろアレなところはあるけど、そこはそれ、ノートにまとめることで回避回避。
やっぱりね、名詞や動詞、形容詞を活用する言語は表を作って分析するのが手っ取り早いのですよ(ラテン語と古典ギリシャ語経由で身につけたやつ)
ところで、受動態のまともな説明がこの『古アイスランド語入門』の中にない気がする……でも日本語書籍で古ノルド語(=古アイスランド語)の文法説明してるのこいつぐらいしか……
というわけでこれはOJT的(訳しながら覚える)な気配ですね……
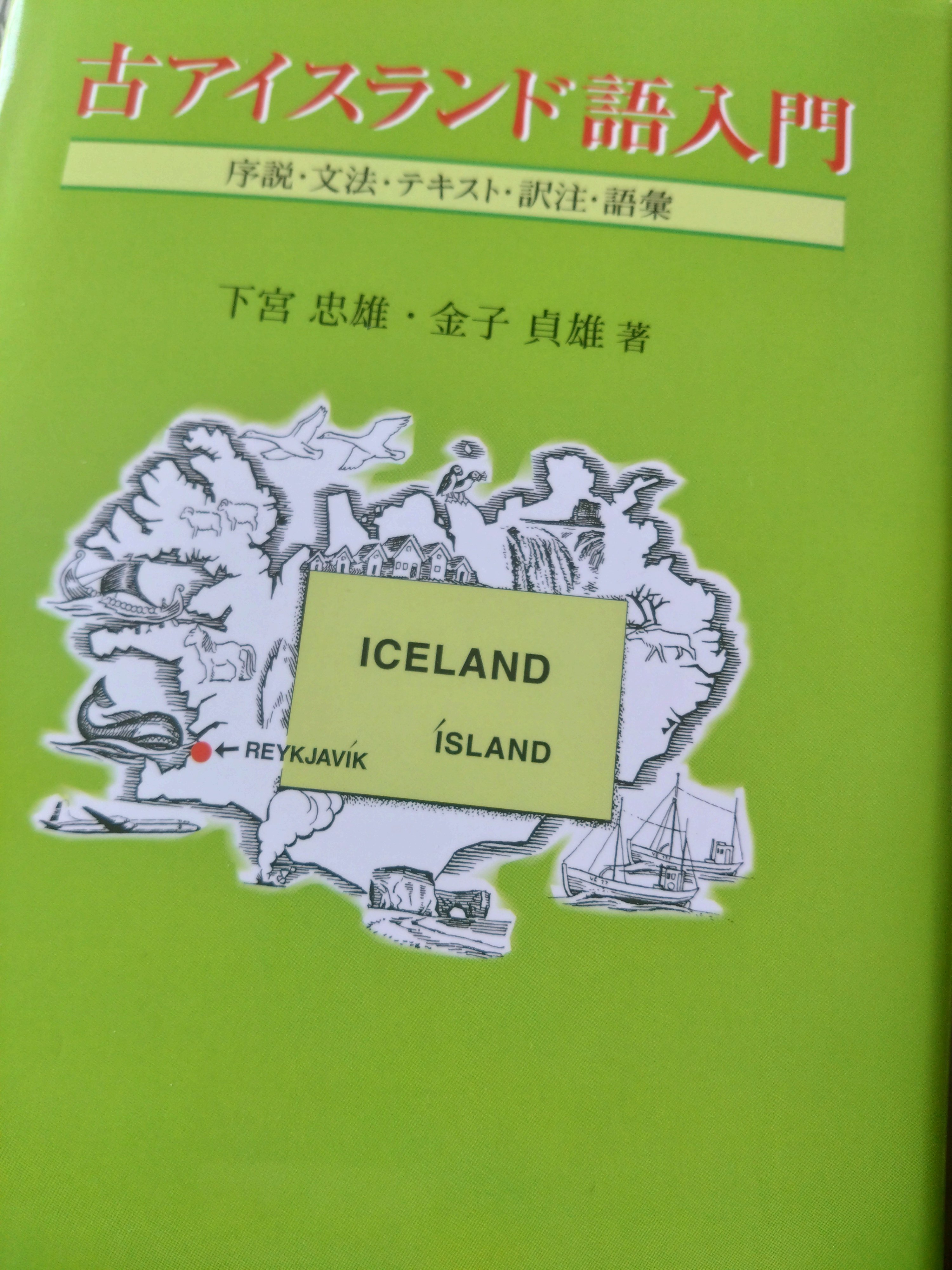
3件のコメント
- 松川さん
コメントありがとうございます〜!
レビューについては、「ちょっとでも露出度上げた方が訂正広まるよね〜」の気持ちでした(確かシステム的に前日星入ってると翌日のピックアップで表示される率高くなるので……後は同じ事象遭遇者の情報が集まれば集まるほどシステム担当者的には助かるので……)
……いや、本当にレアケースのバグ引き当てちゃうと、ユーザ的にもシステム担当者的にも辛いんですよね、再現性って点で……(私のトラウマの扉が開かれそうになるぐらいには)
で、話を戻しまして、古アイスランド語入門ですが、まず、前提として
①私が大学時代にラテン語と古典ギリシャ語やったことある(日文科卒なのに←重要)
②私は極度のオカルトと民俗学と文学の混沌地帯オタクであり当然神話も範疇である
③私は知識をネタとして使いたいがために小説書いてる節がある(本末転倒)
という三点がありまして……。
「印欧系の古い言語なら経験あるしいけんじゃね」という感覚+「北欧神話、つまりはエッダの内容使いたいが、手持ちのエッダ日本語訳引用そのままは著作権的にマズくね(原文はネットに転がってるのでアクセスできる)&原語のニュアンス知りたい」の欲望が爆発しました(∵)
無事に自力訳を書き溜めに反映はできたので、欲望爆発してよかった〜、とうはうはでもあります( `・ω・´)
※なお古ノルド語語彙については、古ノルド語の英語辞書がすでに著作権切れのため、割といろんなとこでDB化されてるのと、英語版Wiktionaryさんが結構いい仕事されてるのでどうにか追いつけた感じです〜
ちなみにラテン語、古典ギリシャ語、古ノルド語の三つを比較すると、ラテン語が一番辞書引いて単語同定がしやすい素直なイイ子です!
(古典ギリシャ語は時制変化で動詞の語頭が変化する、古ノルド語は音韻の問題で一単語のスペルがころころ変わるという辞書引き泣かせ仕様) - 松川さん
コメントありがとうございます!
ラテン語でしたら、東洋出版の『新ラテン語文法』、白水社の『標準ラテン語文法』がオススメというか、大学時代に二種類取ったラテン語の講義の教科書でした。
白水社の方が整理はされてますけど、そんなに厚さがなくて情報量が少なめな初心者向けって感じですかね……後は山下太郎さんという方が、ご自身のサイトで多くのラテン語名文の意味や逐語訳や品詞分解などの解説されてますので、そちらも参考になるかと(「山下太郎 ラテン語」で調べると出て来ます)
※ちなみに、ラテン語語彙については米タフツ大学がペルセウスデジタルライブラリで辞書DB公開してくれてるので調べやすいです。
う〜ん、翻訳関係については、私も寡聞にして知らない部分が多いので、あんまりお役に立てないかな〜というところなのですが、
>「異なる言語を使用する集団は、どのようなファーストコンタクトがあり」
この部分がちょっと気になって。
というのも日本は島国ですので、あんまり実感がない部分ですが、大陸の国というのは基本的に地続きです。
勿論、その境目の多くが山や川といった交通の難所に置かれやすくはありますが、往来がまったくなかったわけではありません。シルクロード考えればなおさら。
ということは、大陸上の言語の分布って方言込みで考えると、ある程度グラデーション的な分布になってておかしくないと思うのです。
なので、例えばA語が使われる集団の地域とB語が使われる集団の地域があった場合、両者の境付近ではそれぞれの集団内部で「B語寄りのA語話者」と「A語寄りのB語話者」がいたと考えられます。
勿論、この「もう片方に寄った語」は、両者の母語上においては方言扱いになるでしょう。
となると、「隣接した異なる言語圏における翻訳・通訳」というのは、それぞれの母集団がそういう境界寄りの人間を介する事ではじまったんじゃないかな〜……などと考察する事はできるかな、と思います。
ファーストコンタクトの目的自体は古代時点なら、たぶん基本は物資交換だとは思うんですよねえ。
最初から蹂躙目的なら対話の必要性はないですし。
それがどんどん現代に近づいていくと、学術的調査みたいな色が出だして、それこそ金田一京助先生のアイヌ語調査の逸話(まずその語彙における「何?」という言葉を聞き出す)みたいになるのかな、と。
なんというか、古代の人間にとって、世界は広い(概念的に)と同時に狭い(実質的に)はずなのと、日本国内でも見られる中央から発信された古語が僻地の方言として残る例を考えると、翻訳・通訳の発生はそういうものなのかなと……あくまで私見ですが、私見ですが!!!(重要なので2回)
そうしたマニアックなネタや知識については、私、一応スパイスだと思ってはいるのですが、大体気が付いたらスパイスのスパイス煮を生成しております(今書いてる書き溜めも死ぬほどマイナー文献読み込んで、古アイスランド語やって自力翻訳してという始末)
つまり、そうしたネタや知識をつっこまずにはいられません!
結果、別途注釈書も書くなどという事をしております〜!
※なお、これはPVとか、そういう読者側の事を諸々無視した「ついてこれるやつだけついてこい!」なストロング趣味字書きスタイルとなりますので、目指すところによっては反面教師になるかと…… - コメント、ありがとうございます。
文章の筆致やコメントでの反応から、松川さんがとても真面目な方である、と思えたからこそ、心的疲労の面を心配しておりました。
あのエッセイでだいぶ回復されていたようで、ホッとしました、良かったです。
引用については全然気にしてませんよ〜。
レビューであえて書いたのは、あの創作論の方を知らない方が、私を「こいつなんぞや」と思わないためだけの補記的な何かです。
まあ、私の場合はプログラミングもやるweb系SEという経歴がそれなりにあるので……
カクヨムさんがブラックボックスとはいっても「まあ、これを基準に考えるなら、普通はこういう処理でこういう設計になるやろ……」とうっすら透視できるが故の検証と、私が担当してたシステム自体が複雑な計算をするので、お客様に毎回「だーから、結果がおかしいってだけじゃなく入力値よこせおらー!」をオブラートに包んで返していた経験という、個人の経験に由来するものなので……
あと、松川さんのエッセイ冒頭を読んで、他にもそういうエッセイとか創作論が(今回ほどの大騒ぎになるほどのものでなくても)点在するなら、やはりレアケースバグの可能性が高いな、と思ったので、松川さんとカクヨムさん、両者に対してお節介ながらも、チェックポイントと遭遇した場合に報告すべきデータを明確にして、「レアケースバグは撲滅したいよね」というSEの性をまた発揮してしまっただけです……私、長子なのでお節介傾向が強いのです……
しかしながら、そのお節介な私のレビューで完成したというのであれば、とても幸いなことです。
これからもお互い、カクもヨムもがんばりましょう!