画竜点睛
Tempp @ぷかぷか
第1話 画竜点睛
「なあなあ、馬鹿馬鹿しい噂を聞いたんだよ」
「馬鹿馬鹿しいってなんだよ」
「なんだかよ、安楽寺の壁にすげぇ絵かきが目のない竜を書いたらしいんだよ。それで目を書いたら竜が本物になって飛んでいくとかなんとか」
「そんな馬鹿馬鹿しいことがあってたまるか」
「それで今日はその竜に目を書くんだってさ。だからみんなで示し合わせて見に行こうって言ってんの」
そんな仕込みが市中を練り歩いていた。
吾輩は
今サクラが散々噂をばら撒いてるから、それに従って、吾輩はこれから壁に書いた竜を空に飛ばさねばならぬ。
はーあ。吾輩は絵師であるのに何故このような茶番を繰り広げねばならぬのか?
我輩は
だがこれがお上の意向であれば従うしかないのだ。我輩はしがない宮廷画家であるゆえ。
我輩の得意は
古来より我が国に存在する道教と天竺よりもたらされた仏教の融合が期待されたこの時代だ。我輩も西域流の画法を学び、墨をぼかしながら立体的な絵を描く
それでわしが
「張僧繇様。頃合いです」
現実逃避をしていたら、時間だと呼ばれた。
よし、そろそろ予定の時刻か。
寺内の柱の影からチラリと眺めれば、大勢の人間が所狭しとひしめいていた。こんなに集めなくても良いように思うのだが、まあいいか。うむ、寺の壁の前には一定間隔で兵隊が並び、聴衆が壁に近寄りすぎないように見張っている。
近すぎるとネタがバレてしまうからな。吾輩の絵は少し離れて見ると良いのだ。
さてと。
ふうと深呼吸して気合を入れ、羞恥心を我が身から追い出す。そしてなるべく威厳があるように足を踏み出したのだ。
「我輩が張僧繇である。これよりこの竜に目を入れる。そうすると竜は飛び立つであろう」
観客がどよめく。やけに大きな声をあげているのがサクラか。10人ばかりはおるな。
「しかし四匹とも飛んでいってしまうと困るゆえ、二匹のみ目を描く」
今度はくすくすと笑い声が広がった。ところどころ指差す者が見え、できないんだろ、という呟きが聞こえる。なんだか馬鹿にされておる気がするが、我輩も乗ってしまったのだからしかたがない。目立つように妙にテロテロとした袖をブワと広げて筆を掲げると、なんだかもうどうでもよくな理、さかえって楽しくなってきた。童心に帰ったというやつかもしれぬ。
くるりと振り向き、既に書いてあった竜の目に素早く目を描く。
境内に控えた芸人がどろどろどろと太鼓を打つ。
壁の周囲に控えた芸人が黒煙を焚く。
黒煙が我輩と絵を隠し、それら全てが人目を奪った瞬間、寺裏に控えた芸人がシュパッと花火を2本打ち上げる。当然のように全ての耳目は花火に移る。
我輩は煙くて仕方がなかったが、懐から取り出した墨袋を竜二匹の上にぶちまける。勿体無いのう。一匹あたり描くのに三日ほどかかるのだが。其の時ばかりはなんだか妙にしんみりした。
そうして後ろを振り返り呵々大笑。
「ああー。やはり言った通り竜は飛んでいってしもうたー。壁の竜がおったところが黒々と闇に包まれておる。全部飛んで行ってはかなわぬから、残り二匹はこのままとする」
我輩の声に民衆は改めて壁を、見て目を丸くする。
……
画竜点睛?
画竜点睛!
画竜点睛と唱和し叫ぶ衆目。吾輩は大きく両手をあげる。
「さらばだ!」
そしてするりと退場。ふん。この壁はすぐに白く塗り直させるのだ。近くでみればやはり穴ではなく墨ということがわかるからな。
……なんでこんな茶番を繰り広げているかというとだな。
吾輩の主君である
武帝は筋金入りである。
これまで生贄を捧げていた祖先霊への祭祀を仏教の不殺の教えに従い、捧げ物を生贄から果物にかえ、国費から莫大な財物を寺社に喜捨し、その治世の中後半は民を圧迫するほどの仏教グルイを見せた。まさにガチ勢。
ご自身の生活も皇帝なのに菜食主義に徹したり仏典の注釈書を作ったり。それでつけられたあだなは『皇帝大菩薩』。
吾輩も仏寺で権威付けに様々な絵を描いてきたが、今回の茶番も仏寺に耳目を集めるためと言うことであった。本当に意味があるのかはわからぬが。
思えば武帝も珍妙な生涯を送られていたのである。
若い頃から文武両道、王室の縁戚。きらめかしい人生を送られていた。このころから仏教を学ばれてはいたと聞いている。ところが突然兄の
この蕭宝巻はもとより頭がおかしい。
前帝の葬儀の際に配下が激しく慟哭し帽子が脱げたのを見てゲラゲラと大笑いしたり、臣下をぱかぱか殺したり、通行人、特に妊婦や子どもを狙って馬で踏みつけるのがマイブームになったりと、とにかく頭がおかしく放蕩三昧で、結局国家財政を枯渇させ、起こった反乱をせっかく鎮圧した蕭懿をもあっさり殺した。
耐えきれなくなった武帝は兵を起こしてあっという間に蕭宝巻を追い落とし、建国したのが粱である。
それで武帝は蕭宝巻のせいで疲弊した国を立て直すために減税し科挙の前身となる登用制度を整備して大学を設立して復興に努め、戦争でも外敵北魏を弾き返した。
それで国政が落ち着いてきたら今度は仏教にのめり込みだしたのだだ。一旦のめり込んだら脇目も振らず、治安も乱れて賄賂が横行し、白昼でも強盗が発生するようになった。そのうち北魏から亡命していた宇宙大将軍を自認する
遺言は『蜂蜜が飲みたい』である。
結局その氾濫も鎮圧されたけれども粱自体は疲弊して、建国してから60年もたたずに滅亡した。けれどもこの武帝が整えた学問奨励は南北朝時代を代表するような文化を排出し、武帝が纏めて振興した仏教は百済を通じて日本に伝わっていったのである。
了
ー付言
なお粱を建てた武帝の蕭家は前漢の
画竜点睛 Tempp @ぷかぷか @Tempp
★で称える
この小説が面白かったら★をつけてください。おすすめレビューも書けます。
カクヨムを、もっと楽しもう
カクヨムにユーザー登録すると、この小説を他の読者へ★やレビューでおすすめできます。気になる小説や作者の更新チェックに便利なフォロー機能もお試しください。
新規ユーザー登録(無料)簡単に登録できます
この小説のタグ
同じコレクションの次の小説
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。









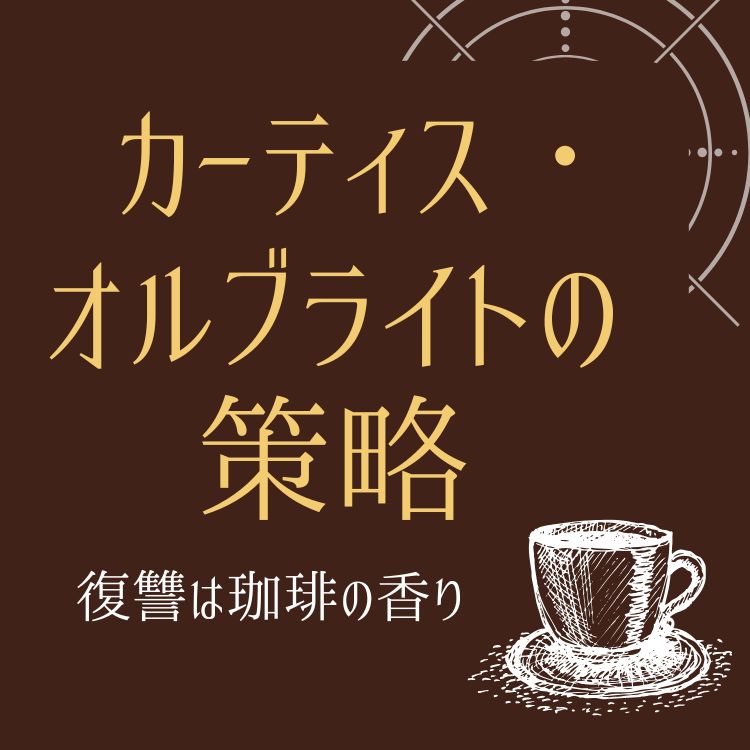

応援すると応援コメントも書けます