大寧寺逢瀬
森田季節
大寧寺逢瀬
近習(きんじゅう)がたてつけの悪い戸を開けようと足掻いていた。
この城の主の部屋は、重い戸で隠すように締め切られている。そのせいで澱んで湿った空気がいつも籠もっていたが、主はいっこうに気にせずに糸で綴じられた書物を読み続けている。城の主が十一の時に主君から借り受けて、筆写した源氏物語だ。
当時はまだ髪を後ろでくくらず、長く伸ばしたままにしていたから、主は自分を話の中の姫君に重ねることができた。今もなんとなく、昔の自分に話に出てくる姫君をだぶらせていた。
ようやく戸が開き、近習が入ってきた。近くの村の土豪の娘だ。頬が南天の実のように赤い。
「守護代(しゅごだい)様……」
あわてていた割には、近習は主を見ると、先の言葉に詰まった。
だが、覚悟を決めたように、来客の実名を呼んだ。
「……冷泉隆豊(れいぜいたかとよ)がお見えです」
「わかった。私が案内しよう」
ゆっくりと書を閉じると、主は静かに立ち上がった。彼女の服は陰鬱な部屋に似合わない、紅葉色の派手な素襖(すおう)だった。到底、普段着の色ではない。戦装束でも、これほど目立つものはそうないだろう。
城には家臣たちが使う玄関と、客人用の破風のついた玄関が並んでいる。破風のついたほうに、冷泉隆豊が立ったまま待っていた。供は誰も率いていなかった。勇将らしく顔にはいくつも傷が残っているが、それでも彼女の美貌を損なってはいない。
冷泉とは本来、公家の苗字である。武家である彼女の親は冷泉家とつながりのある男を婿にし、そのまま苗字を冷泉に改めていた。
「山口からこんなひなびた土地までご足労くださり、かたじけない。しかも、供もつけずにいらっしゃるとは。この陶隆房(すえたかふさ)、恐悦至極に存じます」
城の主、陶隆房(すえたかふさ)は慇懃(いんぎん)にそう言って、頭を下げた。
隆豊はすぐには何も答えなかった。どこか据わりの悪い空気になり、それは自然と緊張を呼んだ。そのせいで、隆房は次の瞬間に首を斬り落とされている自分を想像した。
同時に、すぐさま刀を抜き、隆豊を突き殺す様子も思い描いた。
「こちらに寄る用事があったのでね」
ようやく、隆豊は口を開いた。気安い笑みが顔に宿った。
「そのついでだ、周防守護代殿。急なことで申し訳ない。元より歓待を望んだりはしない」
それから、こう続けた。
「前々から会いたかったのだが、君が山口の城にいっこうに姿を見せないのでな。こちらから出向いてきた」
隆房の後ろにいた近習はその言葉を聞いただけで、血の気が引いた顔をしていた。
「守護代は首府山口にとどまらず、それぞれの領地にて政治(まつりごと)をせよ――これが御屋形様のお考えのはず。私は周防守護代を代々務める家として、それをまっとうしているだけです。それが大内の家名を守ることにもつながると思い、この若山(わかやま)城に詰めているのです」
淡々とそんな言葉が出ることに隆房本人が一番驚いていた。
これは戯言(たわごと)ではない。胸中にまだ大内家に対する忠義の心が残っているのだ、そう彼女は自分に言い聞かせた。
「少しでいいので休ませてくれないか。馬に乗ってきたのだが、道が悪かったのか、疲れてね」
「あなたほどの重臣が本当に一人で」
「そのほうが話しやすいこともあるだろう」
小さくうなずくと、隆房は隆豊を招き入れた。
秋がひたひたと迫ってくる頃で、城に差し込む日の光も強くなかった。
客人用の部屋からは池泉の庭がのぞめた。山陽道を扼(やく)するように、この若山城は築かれている。城の縁に立てば、街道を行く者の姿も見えた。
冷泉隆豊は山口にいたから、自然と山口の話が多くなった。隆房もそれを求めているところがあった。
「では、イエズス会とかいう連中は九州へ発ったのですね?」
「まあ、いずれ戻ってくるだろうが。九州は九州で荒れているからな。静かなのはこの大内の領国だけよ」
そう言って、隆豊は盃を干した。
当時の山口は大内氏の拠点であり、西日本最大の都市と言ってよいほどに栄えていた。内陸の土地とはいえ、そう瀬戸内からも離れておらず、防府(ほうふ)からも街道がまっすぐ伸びていて、ありとあらゆる文物が集まってくる。西の京の呼び名に恥じず、都からは高位高官が多く疎開していた。
とくにたおやかな瑠璃光寺(るりこうじ)の五重塔とその下に広がる庭は、こここそが生身(しょうじん)で行ける浄土だと主張しているようだった。疎開している貴族が逃げ出さないということは、それだけみやびな土地なのだろう。
そのうちの何割かは今の当主、大内義隆(よしたか)の手によるものだ。
大内氏の家督継承には血がつきもの――それは長らくの常識となっていた。その中で珍しく、平和のうちに母親から数え年二十二歳で地位を受け継いだ彼女は、大内氏の絶頂期を現出した。
だが、その義隆の権勢も揺らぎつつあるという話が聞こえてきていた。
「――なあ、守護代殿、もう、山口に戻ってもよい頃合いではないかな」
酒で顔を上気させていた隆房の心は、隆豊のその声で現実に引き戻された。
「守護代殿、出雲の月山富田(がっさんとだ)城のことは過ぎた話だろう。尼子(あまご)にしてやられはしたが、それで大内が滅んだわけではない。むしろ、山口はいよいよにぎわっている。尼子も大友もとても山口までは攻め寄せてはこれない。もう忘れていい時だ」
とうとうと隆豊は語り続けた。
それは説得だった。
隆房が山口にいないそのことこそが、今の山口を不安に陥れている。
「私が戻ったところで、御屋形(おやかた)様は私を必要とはしません」
他人事のように隆房は言ってから、胸に手を当てて押さえた。
そこには月山富田城の戦いで受けた傷が残っている。
隆房は生きながらえ、主君の義隆も山口に戻ることはできたが、それが何になると言うのだろう。
「私のような根っからの武人を御屋形様はもう用いることはないのです。いつも横に侍らせているのは相良武任(さがらたけとう)とかいう怪しげな女と都落ちの公家衆ばかりなのは、あなたもよくご存じでしょう」
「それでも、君が周防守護代という重職である以上は――」
「あの負け戦から十年近くになるのですね」
隆房は隆豊の声をさえぎった。
「あの時に私は死んだものと思ってください。御屋形様が私を遠ざけたのも当然です。死人が顔を出すなど、おかしな話ですから」
自嘲気味に隆房は笑った。
用心していたはずなのに、酒が進みすぎていた。
いっそ、隆豊がここで自分を殺してくれれば話が早いのに。
「山口では…………君が謀反(むほん)を起こすのではという噂が連日駆け巡っている」
隆豊がしぼり出すように言った。
「最初は文弱の連中がつまらないことを抜かしていると思っていた。だが、近頃、大友に放っていた間者からも同じ話がもたらされた。相良の間抜けは怖くなって一度逃げだしたぐらいだ」
「陶の家を滅ぼして、大内の力を削ぐ――どこかの大名が流した単純な策でしょう。陶をやったあとは、次は杉(すぎ)の家が狙われるか、はたまた内藤か」
新しい盃を干しながら、隆房は客人の目を見据えている。
「私は御屋形様と一心同体。この命は御屋形様のためにあります」
元服の前からずっと義隆に出仕し続けてきた隆房の言葉は重かった。
彼女がこうも言ってしまえば、隆豊も話をこれ以上続けられない。
「ただし――」
天を仰ぐように隆房は板張りの天井を見上げた。
「御屋形様が私を謀反人だと断じたならば、潔く腹を切りましょう。その程度の覚悟、いつでも有しております。そう、御屋形様にはお伝えください」
隆豊が唾を飲んだ音が隆房の耳に聞こえた。
感覚が鋭敏になっている。
「なんなら、今、ここで偽の君命を伝えてくださってもいい。この隆房を殺したくば、それほど容易に事は果たせますので、ご心配なく」
わずかだが、隆豊が迷ったことを隆房は理解した。
「……君の強い気持ちはわかった。御屋形様にもご理解いただけるだろう」
臆したか。
独断で周防守護代を斬ったとなれば、みずからも処断されてもやむをえない。
主君のためという大義名分だけでできる領分を超えていた。
「今日はこれで帰らせていただくとしよう」
隆豊はさっと座を立った。立ちくらみでもしたように額に手をやったが、姿勢を崩すようなことまではなかった。
「ところで、御屋形様にお変わりはないでしょうか?」
「ああ、いつまでもお美しい。我々が出仕した頃から時が流れていないかのようだよ。むしろ、底の知れない色気のようなものが増した」
呼び止められた隆豊は着座していた時よりはいくぶん落ち着いた声で答えた。
「しかし……以前にも増して戦をまともにしたこともない連中をはべらせている……。君でなくとも、度を越しているとは思う」
「御屋形様を諫められるのはあなたぐらいでしょう」
「君に言われると、皮肉にしか聞こえんな」
冷泉隆豊が去ると、城から張り詰めた空気がすっと抜けた。隆房でなくとも、城で働く者は皆、それを感じただろう。おずおずと近習の娘がやってきた。
「何事もなかったようで、ほっとしております……」
隆房は自分の首の後ろを触った。
「この首が離れるかもと思っていたのだが、案外と私もしぶといものだな」
その日、隆房は九州の大大名の大友氏に使者を出した。
大内義隆殺害後の新しい守護の件についてだ。
◇
隆房が持っている最初の大内義隆への記憶は彼女に抱えられているものだった。
自分の小さな体が浮き上がっている。その前に年頃の女がおかしそうに笑っている。自分の親より高価な服を着ている、隆房は幼心に思った。
「あははははっ!」
幼い自分よりずっと、無邪気にその女性は笑っている。
「本当に小さな子ですね。それにしても小さすぎるわ」
知らない人間に抱えられると泣いてしまうことが多かった。ただ、この人の前では泣いてはいけないという気がした。それに、こんなに楽しそうな顔で自分に接する者が珍しかった。
この人は、こちらのことなんて考えてない。ただ、自分が面白がるためだけに抱えている。でないと、こんなに見事に笑ったりできない。
隆房を抱え上げたまま、女性は隆房の母親に顔を向けた。
「ねえ、興房(おきふさ)、陶の跡取りにしてはいくらなんでも、なよなよしすぎじゃないですか? まるで男のようですよ」
母親が実名で呼ばれている。やはり、この人は特別なのだと感じた。母親が頭を下げることなど、滅多なことではないはずなのだ。
「耳が痛いです。ですが、いずれ私に代わって、周防守護代として大内の家に尽くすことになるでしょう」
「こんなのが興房の代わりになるの? 元服する前に死んじゃうんじゃありません?」
その言葉には、彼女についてきた者からもたしなめる声が上がった。でも、その相手はなんら反省する様子もなく、隆房をさらに抱え上げた。
「ねえ、あなたの名前はなんていうんです?」
女は隆房の顔を自分に寄せながら尋ねた。とにかく、自信に満ちあふれた表情だと思った。
「わ、私は――」
「あっ、やっぱりいいです。どうせ、あなた、わたしの一字と母親の『房』の字をもらうんでしょう。じゃあ、元服した時の名前は隆房だと決まってるようなものじゃないですか。もう、今から隆房でいいです」
幼い自分にはないはずの実名が隆房は変にくすぐったかった。
「よいですか、隆房。あなたはわたしにだけ従っていればいいのですからね」
その言葉は呪いのように幼い隆房の耳に残る。
「お母様の代では筑前の少弐(しょうに)は滅ぼせないでしょうけれど、わたしは少弐も尼子も浦上(うらかみ)も全部倒してみせます。西国にほかに大名がいるのがおかしいんですから。それから大友も阿蘇も伊東も島津も組み伏せてやりますわ」
そんな大言壮語を吐いて、その女はまたなんともおかしそうに笑った。
◇
「守護代様、時は至りました」
隆房の家臣の花岡という女が逼迫した表情で言った。こめかみに汗がにじんでいるのが、隆房にもわかった。
「西の大友との手筈がまだ整っていません。主家乗っ取りになってはならないのです」
「愚考を述べますならば、大友側も我々が動くのを待っているかと。熟慮も度が過ぎれば先手を打たれます。冷泉隆豊が来たと聞いた時には肝が冷えました。いよいよ御屋形様が謀反を認めたのかと」
花岡八幡宮の社家の出であるこの女は言葉を変なところで切る癖があった。どんな事態でもそれは変わらないのだなと隆房は思った。
「ああ、私も怖かったですが、隆豊一人で来たということは、まだ謀反ということにはなっていないということ。あの女としては、実のところ、私より相良武任や役に立たぬ公家衆のほうが憎いでしょうし」
脇息に重心をかけながら隆房は話す。眠いわけでもないのに、最近、どうも頭がぼうっとすることが多い。近習などは部屋の換気が悪いだけだと言うが、それだけではないと隆房は思っている。
自分の命が明日にも知れない事態になり、すべてが夢物語のように感じるのだ。今、この場に密命を帯びた者が飛び出てきて、自分を斬り殺すことだってありえよう。
「失礼は承知で申し上げますが……」
「好きなように申しなさい。謀議に礼も何もない」
「守護代様は『御屋形様に討ち果たされたい』と願ってはいませんか?」
自分の顔から笑みが消えたことに隆房は気づいた。
人間、本当のことを言われると、無性に腹が立つものだと思う。
「守護代様は下克上を起こしたくなどないのです。ただ、ご自身を冷遇してきた御屋形様を後悔させたいだけではないかと。だから、こうも時間をかけて、わざと計画が露見することを待つかのように――」
隆房はやおら立ち上がると、扇子で花岡の顔を打擲(ちょうちゃく)した。
何かがはじけるような乾いた音が響いた。
「すみませんね。これでも猛将と恐れられた女でして。血の気が多いのです」
「かまいませぬ。ただ、話は続けさせてもらえれば、それでけっこうです」
花岡は頬を押さえながら、厳しい目をした。
「好きにしてください。でも、また叩いても知りませんが」
「では、続けさせていただきます。御屋形様に兵を起こさせるのは何をなさっても無理です。あの方は決して守護代様を討とうとはしません」
「なぜ?」
隆房はある答えを期待している自分がいると思った。
――それは、御屋形様が守護代様を今でもご昵懇(じっこん)に考えられているからです。
「御屋形様は尼子との負け戦で、戦をする心を喪われたのです。跡を継がれるはずのご息女も亡くして、完全に抜け殻となってしまわれました」
自分の期待があっさりとはずれ、隆房は笑いそうになった。右の手で左の手の甲をつねった。
「もう十年近くも御屋形様の戦装束を見た覚えがありませぬ。この乱世にとても例(ためし)のないこと。戦というものから御屋形様は逃げ続けておられるのです」
「そんなこと、とっくに知っています。私は御屋形様のお隣で育ったも同然の女なのだから」
嗚咽が交じっていた。鼻がむずむずとする。
「守護代様、涙が」
花岡に指摘され、かっと頭が熱くなった。
隆房は部屋の隅に置いてあった源氏物語の書写本を床に叩きつけた。
「私は源氏物語は嫌いです。こんな大昔の話で腹がふくれますか。何度読んでも面白いと思ったことない!」
自分は所詮、戦一辺倒の女だ。
だから御屋形様が戦から目を背けて、側近たちと遊ぶようになれば自分は用済みとなった。付け焼刃の勉強では、都から落ちてきた生粋の公家の学問にかなうわけもない。そんなところに自分の浮かぶ瀬はない。
花岡は何も言おうとせずに黙っている。自分が道化のようだ、そう隆房は思う。いや、生まれた時から自分は踊らされていたのではないか。これが自分の決断だと思えたことなどあっただろうか?
もう、待てない。
「山口に攻め入る日を決めました。それと、安芸の毛利に使いを出しなさい。まずは安芸で蜂起の兵を挙げさせるのです」
一息で隆房はそう言った。
「そのお言葉をお待ちしておりました!」
花岡の声が部屋に響いた。
◇
隆房が八歳の時、御屋形様が代わった。
義隆が大内家の家督を継いだ。何代ぶりの血を見ない家督交代かと人々は言い合った。
その新しい御屋形様の山口の館に隆房はたびたび呼ばれた。そこで小難しい書物をいくつも読まされた。勉強のために寺に通っているようなものだった。
何冊も典籍が隆房の前に差し出される。剣の稽古で、母親に木刀で叩かれるよりよほどつらい。女はひとたび元服すれば身重の時を除けば戦に出る――そう母親は厳しく隆房をしつけた。最初の頃は泣きべそをかいていたが、そのうち泣いているともっと怒られるから涙も流さなくなった。
「わかりませぬ」
正直に隆房が告白すると、御屋形様は笑いながら、「わからないといけませんよ」と言って、講釈を垂れた。
若い御屋形様もその周囲も、隆房の目から見ても華があった。
彼女の居城である若山城とは比べ物にならないほど調度品から何から豪華で、それに人の数も多かった。京下りの公家のせいか、派手な着物の女もいくらもいた。
「御屋形様、陶(すえ)は周防守護代の家。弓馬の道のほうだけで許してもらえないでしょうか。母上もそうやって先代の御屋形様にお仕えしてきたかと思います」
隆房は御屋形様に泣きついた。
「いけません。文武両道が武士の道ですもの」
さっと、御屋形様は隆房の横に並ぶ。筆を持つ手を取って、紙に筆を這わせた。
「いいですか、こう、こう」
さらさらと文字が紙に現れていく。それは山伏が使う魔法のように見えた。
「西国一の大名の家臣にはそれなりの見識が必要です。でないと、恥をかきますからね」
それを見ていた公家衆の一人が「すでに大内殿は西国一の大名ですよ」と言った。相伴する者たちが笑う。今度は誰かが「日の本一の大名でしょう」と続けた。
「否定はしません。けど、まだ敵がいくつも残っているでしょう」
そのまま、御屋形様は隆房につきながら、経略を語りだす。
「まずは九州の北を取ります。肥前(ひぜん)の竜造寺剛忠(りゅうぞうじごうちゅう)が完全にこちらに寝返れば、少弐(しょうに)は自力ではやっていけないでしょう」
「大友はどうします?」
隆房が尋ねた。これなら、自分も話に参加できる。
「大友はひとまず豊後に押し込めておきます。できないことはありません。あれは後回しです」
「では、尼子は?」
長年、西国は西の大内と東の尼子が覇を競っていた。
「尼子も大きくとも、国衆が集まっているにすぎません。一度、打ち破れば寝返る者がどっと出ます。安芸の毛利を楔(くさび)にして攻め寄せてやりましょう。尼子が消えれば、その先の山名も浦上も素直に従うしかないはずです」
それは決して夢想ではなかった。大内の力はそれほどまでに大きかったし、なにより御屋形様が意気盛んに九州攻めの計画を立てていることは隆房も知っていた。
おそらく元服して最初の戦は九州でのものになるだろう。
「わたしは自分の代ですべてを手に入れます。その資格がこの義隆だけにあるのです」
隆房はその日を待ちわびていた。
自分が御屋形様のために活躍できるのは、戦しかないのだから。
そして、元服を終え、隆房が正式に陶隆房となって初出仕の日――
隆房は夜伽を命じられた。
御屋形様の手は雪のように冷たかった。
その手が隆房の頬を包んだ。隆房は御屋形様が人ではないのかと思った。
服を脱がされている間、隆房は何も言わなかった。
守護代の子ではなく、女として見られている――その意識は以前からあった。同世代の女よりは自分の顔が整っているということも、なんとなくわかっていた。そこに勝気な性格が凛とした一本の筋のようなものを体に通している。
それと、御屋形様が男だけでなく、百合の道も達者だということも家中では有名な話で、隆房も聞き知っていた。
ただ、呼ばれる前ぶれがなかったので、少し驚いただけだ。
「少しの間、楽しませてくださいね、隆房」
御屋形様は大胆に迫ってきた割には落ち着き払っていた。御屋形様の命令を拒める者などいない。当人も知っているのだ。
「御屋形様、どうぞ、お好きなように」
「いい心がけですね。わたしに尽くしなさい。いつまでも」
御屋形様の言葉に傲慢なところは少しもなかった。それは生まれながらにすべてを持っている者の言葉だった。
「もう、筑前の少弐は虫の息です。隆房が戦場に出る前に滅ぶかもしれませんね」
ずっと御屋形様が話していた言葉が現実のものになっている。隆房はやはり主君が不思議な力を持っているように思う。
「では、私は尼子退治で武功を立てたいと思います」
「ええ、励みなさい。隆房、あなたは本当にいい子ね」
御屋形様が自分の胸に巻いているさらしを取る。大きな乳房が重そうにしがみついていた。御屋形様はその胸に隆房を押しつけた。
「わたしの土地のものはすべてわたしのもの」
隆房も何も逆らう気が起きなかった。
自分は御屋形様の一部なのだ。幼い頃から感じていた気持ちがまた強く甦ってきた。
◇
八月二十四日、隆房はついに挙兵した。
若山城の周りには味方する将の旗がいくつもはためいている。隆房自身も日中は城ではなく、陣幕の中にいた。
周防国(すおうのくに)南部の瀬戸内海側は大半が隆房の側についていた。周防の東の要(かなめ)、岩国の弘中隆包(ひろなかたかかね)も隆房に従っている。
弘中隆包は安芸の経略も順調に進んでいると報告した。
郡山城主の毛利元就が義隆側の国衆を攻撃し、周防に入れないようにしていた。
しかし、隆房は数日の間、進軍命令を出さなかった。
周防の西の分国である長門からの援軍が来るのを待つ。長門守護代の内藤興盛(おきもり)の動向がはっきりするまではうかつに動くのは危険である――それが隆房の説明だった。
理窟としては合っている。長年、周防守護代家の陶と長門守護代家の内藤は不仲で有名なのだ。援軍が見えないと信用できないと言い張ることはできた。
だが、ここに兵を集め、安芸で軍事作戦まで行っている以上、発向しないのは多くの者に奇妙に映った。すでに引けないところに隆房は来ているのだ。
兵の中でも、まだ守護代は御屋形様の肌が忘れられないのだといった声が漏れた。
さらに長門守護代の内藤興盛の参加が確定的となってからも、いまだに隆房は軍を進めなかった。
隆房は御屋形様からの反応を待っていた。
御屋形様から詰問の使いか、あるいは降伏を願い出る使いが当然来るはずだった。若山城から山口までは一日で到達できる距離である。悠長に構えていられる距離ではない。
主君のあわて惑う姿を隆房は見たいと思った。それを見られれば、主君がただの人間だということがわかって安堵できる。
御屋形様は笑みを絶やさない女だった。命からがら出雲の月山富田城から山口の館に戻った時も、悔やしそうな顔すら見せなかった。
それでもあの時以来、御屋形様は戦をしなくなり、ただ、ただ、遊び続けるだけになった。あれほど戦好きだった彼女が刀の持ち方も忘れてしまったみたいに変わってしまった。
隆房の役目も長らく消えた。
そして、ついに今日に至ってしまった。
これまでも謀反騒ぎは何度もあった。負け戦から十年も過ぎている。どんな形であれ、御屋形様が乱世の大名らしく、武の道に戻る機会も、行状を改める機会もあった。それで丸く収まればいいと隆房も思っていた。
だが、そうはならず、隆房は反乱軍の総大将となっている。
事ここに至っても、明日のことも明後日のことも、隆房は想像がつかずにいる。
――御屋形様に振り向いてほしい。
そのためだけに仕掛けたも等しい戦だ。
泣いて赦免でも求めてくれれば、どうとでも助けられる。
しかし、若山城に御屋形様の使者が姿を現すことはくなかった。
まさか本当に謀反のことを知らされていないのか。否、そんなことはありえない。寵臣たちが隆房に気をつけろ、早く誅殺しろと言っていたのは確かなのだ。相良など隆房の名前を聞くだけですくみあがるのだから。
奇妙なほどに遅滞する戦――それは、月山富田城の敗北を兵たちに思い出させた。兵によっては一年以上も故郷を離れる羽目になったあの出雲の戦いも何かがおかしかった。
挙兵から三日後、隆房の放っている間者の一人が陣に現れた。
「御屋形様はどうなさっています?」
間者は隆房を見上げ、すぐに目をそらした。
「それが……側近と公家衆を集めて、能楽を催しておりました……」
「ふざけないでっ!」
隆房は声を荒らげた。陣の幕がその声に波打つほどだった。
「挙兵すらせずに能楽ですって……? そんな大名がいるわけがない!」
「いまだに信じられません……。しかし、興行はたしかにありました。守護代様が攻めてくることに恐れをなして逃げたのか、顔を見せない者もおりましたが……」
隆房は床几に座り込んで、頭を抱えた。
まるで負け戦に呆然としている将のようだった。
これは夢なのか。ここまで都合よく事が運ぶ謀反などありうるだろうか?
罠なのか? 攻め入った途端、敵にはさまれるのか?
それならば、いっそ、罠にかかってやろう。
「ここまで極まっても、私が裏切ることなどないと信じておられるのですか? 私を支配しているとお考えなのですか?」
ぶつぶつと隆房は独り言をつぶやいていた。
間者が「守護代?」と怪しんで声をかけたが、それも聞いてはいなかった。
「まさか。私を愚弄しなければ気が済まないのでしょう。あなたの考えそうなことです」
頭に御屋形様の笑い声が響く。
幻聴だということはわかるが、それが真に迫ってくるぐらいにその声は子供の頃から聞き続けてきた。
驚くほどに身勝手で、美しい女だった。
少なくとも、西国の太守にふさわしい女だった。自分が仕えるに足る女だった。
だからこそ、憎しみが湯のように湧いてきた。
この手にかけるしかないか。
隆房は将を集めて、こう伝えた。
「明日の朝、全軍で山口に攻め入ります」
歓声が将たちから上がる。
将たちも長らく、戦乱で生きてきた者たちだ。自分たちが仕える者が国持ち大名の顔になっていることを感じ取っていた。
最低でも周防一国はすでに隆房の手に落ちたも同然。長門国(ながとのくに)でも従う気がないのはせいぜい津和野(つわの)の吉見正頼(よしみまさより)ぐらいだろう。その二国をまとめられれば、ほかの分国の国衆たちもこれまでのように従うはずだ。
「ただし、山口の町にも寺社にも火はかけないように。我々の敵は山口ではなく、義隆とそれにおもねる者だけです。町を焼いたとあっては、大友から迎える次の御屋形様に笑われます」
大友から来る御屋形様など傀儡と決まっている。もう、隆房の主家簒奪は目前に迫っているのに、なぜか隆房だけがその未来のことを詳しく考えられずにいた。
◇
八月二十八日早朝、隆房は北の峠道である徳地(とくじ)に向かって軍を進めた。荷卸峠(におろしとうげ)を越えて東から山口に入る道である。険しいが、西に出て防府から北上する道よりは速く山口に入れる。
隆房は途中、周防国二宮である出雲神社に寄り、戦勝祈願を行った。
そばには長門守護代の内藤興盛(おきもり)の姿もあった。大内分国の最重要拠点である周防・長門の二国の守護代が揃った以上、勝負は決していると言えた。
さらに日本海に面した長門北部の都市益田(ますだ)を支配する益田藤兼(ふじかね)も隆房方についており、御屋形様が山口から北西に出る道もふさいでいる。
また、別働隊は防府(ほうふ)から北上して、山口に攻め込む手筈となっていた。こちらの中心は周防高森(たかもり)の領主、宮川房長(みやがわふさなが)と岩国の領主、弘中隆包(ひろなかたかかね)だった。これに隆房の重臣である江良房栄(えらふさひで)がつく形である。
朝日を浴びながら徳地口を進軍する隆房は敵を待っていた。
御屋形様の側は自分が挙兵をしていることなど、とうの昔に知っているはずだ。若山城から山口まで十里ほどしかない。
そして、荷卸峠の急坂に差しかかるあたりで、旗が峠のほうでたなびいているのが見えた。
陶とは長年険悪な豊前守護代の杉重矩(すぎしげのり)の旗だ。
いよいよ敵か。
杉一族は豊前守護代を継ぐ家と、筑前守護代を継ぐ家に別れていたが、どちらも隆房とは対立関係にあった。
峠を固められれば、激戦になる。どれだけ被害が出ようと峠を突破して、自分は山口に入るよりない。
「周防守護代、ずいぶんと機嫌がよいようだな」
隣にいた長門守護代の内藤興盛に言われた。
「やはり、そなたも戦をせずにはおられぬ女のようだ」
「ああ、そうか。私は笑っていたのか」
隆房は声を上げて高笑いした。
その態度に周囲の者たちが怯えるような顔になっている。
自分は早く御屋形様を殺したい。
そして、かなうならそれよりも――殺されたい。
そうすれば、何もかもが終わりになる。御屋形様を殺したあとのことなど考えずともすむ。
どうせ、自分に政治(まつりごと)は向かぬ。母上のように、守護を支えるような役目は果たせぬ。大友から御屋形様の姪を主君に迎えたところで、そこから先のことは見通せないままだ。
さあ、殺してくれ。高みから矢で射殺してくれ。その代わり、自分も全力でそちらに向かおう。存分に殺し合おうではないか。それが武家の本懐だ。
しかし、峠から聞こえた大音声は、
「この杉も陶殿にお味方いたしますぞ!」
というものだった。
杉も味方か。もはや万に一つも負けはない。そんな声が味方から響く中で、隆房だけがほうけた顔をしていた。
天が自分に味方をしすぎている。
それが過度だから気持ち悪い。
一度も妨害に遭うこともなかったおかげで、隆房率いる本隊は昼には山口に入った。ちょうど、防府から北上してきた部隊も流れ込んだ。
戦と呼ぶべきようなものにはならなかった。
隆房の軍は合計一万近くに達した一方で、長年御屋形様と呼ばれてきた大内義隆の部隊はその二割に満たない。
とっくに義隆は見限られていた。誰が負け戦から十年近く戦をしない大名を信じられるだろう。まして、山口の周囲にもさほどの兵を置いていないのだから、どうにもならない。
こんなものか。
隆房は自分が刀を振るうまでもなく決着していることに空しさを覚えていた。
これならば――命からがら帰還した月山富田城の戦いのほうがずっと楽しかった。
そして、どうにかこうにか山口に戻った二十二の隆房を御屋形様はすぐに閨(ねや)に呼んだ。あきれるよりもうれしかった。ここまで気丈な御屋形様ならまた尼子を滅ぼせると思った。
しかし、御屋形様は隆房の背に指を這わせながら、唐突にこう言ったものだ。
「飽いたわ」
子供が遊ぶのをやめた時のような声で。
何にですか。そう尋ねる勇気は隆房にはなかった。唇がふるえるのを止めるように隆房は御屋形様の乳房に口をつけた。娘を産んだ後だったので、御屋形様の胸から乳が垂れた。隆房は苦みを感じた。心細さを紛らわすように御屋形様に抱きついた。
あれから、隆房が夜伽に呼ばれることも、御屋形様が戦に出ることもなくなった。
飽いたのは隆房か、戦か。いまだに隆房にはそれがわからない。
今日はあの尼子領から逃げ帰ってきた日の、翌日のように感じる。あの時と同じ、殺伐とした山口の匂いを感じる。
まともな合戦もないうちに、隆房のところに御屋形様逃亡の報が届いた。
もっとも、逃げられる場所などほとんどない。御屋形様が頼れる有力者があるとしたら津和野領主の吉見正頼だけだろうが、すでにその北東に進む道は隆房の軍が最優先でふさいでいた。
やがて、冷泉隆豊が長門の仙崎(せんざき)を目指して御屋形様と落ちていったという続報が来た。
日本海に面した仙崎は北に青海(おおみ)島が突き出ている地形のおかげで、西と東に深川(ふかわ)湾、仙崎湾という二つの湾がある良港だ。そこで船を出して、逃げられるところまで逃げようという腹だろう。
西から北へ上がる仙崎への道も深い山道ではあるが、抜けられないわけではない。大軍では通れないだろうが、どうせ軍は瓦解している。少人数なら逃げおおせる。
御屋形様を生かしておくわけにはいかない。
山口の占拠を家臣と長門守護代の内藤興盛らに任せると、隆房は敵を追った。
御屋形様主従は長門湯本の大寧寺(たいねいじ)にこもっている――そう隆房は報告を受けた。
仙崎の浦は荒れており、とても船を出して逃げられる状況ではなく、御屋形様は再び道を引き返して大寧寺にやってきたという。たしかに野分(のわき)の季節だからか、風が山中でも強かった。
大寧寺は越前永平寺と本末関係にある長門国最大級の曹洞宗寺院である。しかも、大内氏ともかかわりが深い。死を覚悟して砦代わりにこもるには正しい場所だった。
家臣たちは総大将として山口を押さえておくように言ったが、隆房は首を横に振った。
「大寧寺には自分が行きます」
◇
隆房は休まず兵を進めた。つらい行軍ではあるが、追う者の強みで、味方の足は軽かった。
九月一日、隆房は大寧寺に迫った。
すでに御屋形様主従の数は数十騎ほどにまで減っているということだった。数万の兵を動員した西国一の大名の最期にしてはあまりにみすぼらしかった。
山門から矢を射かける兵を逆に射落とすと、いよいよ隆房の兵が境内に踏み入った。
隆房も境内に立ち入ると、御屋形様の姿を探した。
「御屋形様はいずこか! 周防守護代が首を獲りに参上いたしました!」
その声に敵がばらばらと出てきた。隆房は息を切らせながら、刀を抜いた。
すぐに足軽の一人の首を刎ねた。
それから返す刀でもう一人の胴を横に薙ぐ。
隆房は生きていると思った。
やはり自分は武士だ。こうやって誰かを殺さなければ意味がないのだ。
自分は早く御屋形様を殺したい。
わらわらと自分を止めに出てくる兵たちに向かって、隆房は迷いなく刀を振るった。そのたびに血が舞った。隆房の顔にもその血がかかった。
「しょっぱい」
汗をかいているし、ちょうどいいかと隆房は思った。
たいして敵は残っていないはずなのに、次から次へと敵は繰り出してきた。御屋形様と命を捨てる決心をした者がこんなに多くいるのが隆房には不愉快だった。だいたい、それでお前たちは何を守り、残せるというのだ。
隆房はことごとく一刀に斬り捨てた。最期に名乗ろうとする者も名乗りも聞かずに斬った。
「すでに御屋形様はご自害なされた!」
聞き覚えのある声が隆房の耳に響いた。
冷泉隆豊が寺の堂舎の一つに背を向けて立っている。
「ああ、そこですか」
その中に御屋形様はいるのだろう。
ふらふらと隆房は堂舎に向かっていく。
たとえ、すでに命を落とされたとしても、自分が見届けなくては。
すぐさま、隆豊が斬りかかってくる。
隆房も刀で受ける。つばぜり合いが起こる。
「どうして、お前はこのようなことをしでかした? 答えろ、隆房!」
「どうして?」
この忠義者はそんなことすらわからずに戦っているのか。そう思うと、隆房は本当におかしくなった。
「御屋形様は私に殺されたかったのですよ。だから、ずっとずっと待っていたんです。あるいは――生きることに飽いてしまったのかもしれませんね」
刀に力を込めつつ隆房は言った。
今の自分は命の取り合いに夢中になっている。そこに生きている意味を見出している。
しかし、御屋形様はそういったものがなくなってしまったのだ。
「痴れ者め!」
隆豊の刀は重いが、隆房はそれも受け止めた。
「御屋形様はお前を信じていたから討伐の兵を出さなかったのに! この不忠者が!」
腕に甲冑の上から隆豊の刃が当たった。だが、何の痛みも感じない。
「信じるとか、そんな浅はかなものではないのです」
これは呪いだ。
大内義隆という日の本一のわがままな女の呪いだ。
生まれながらにいくつもの国の支配者としての地位を約束させられて、大内義隆は普通の女の領分をはるかに超えていた。だから、自然と呪いを周りの者に容赦なくぶつけ続けた。
その呪いに自分は動かされている。
「どけ、隆豊」
冷たい目でそう言った。
「もはや御屋形様自刃のうえは、あなたの役目も終わったでしょう。腹を掻き切る時間はくれてやります」
隆豊の刀からすっと力が抜けた。
「……わかった」
彼女の脇腹にはすでに何箇所も矢が刺さっている。気合いだけで戦っていたことは隆房も知っていた。
「御屋形様の介錯は?」
「していない。不要と言われた。昨日、この寺の僧の弟子となったから、武士として死ぬ意味はないと」
それだけ聞くと、隆房は堂舎の前にまで行き、その戸をゆっくりと開いた。
乾いた、冷えた風が頬に当たった。地面はよく叩いた土で、足の裏から体温を奪っていくようだった。
その隅に、長い髪を垂らして横たわっている女がうずくまっていた。御屋形様だ。
腹はすでに赤く染まっている。事切れたのか。
御屋形様の前にまで来ると、見参の礼をとり、隆房はこうつぶやいた。
「周防守護代陶隆房、若山城より参上いたしました」
途端、甲高い笑い声が堂内にこだました。
御屋形様が目を開けていた。実に楽しそうな顔で。
「遅いわ。遅すぎるわ。待ちきれないから自分でおなかを刺してしまったじゃない。とっても痛かったわ!」
隆房も生きている御屋形様を見て、思わず涙がこぼれた。
ほとんど、噴き出すと言っていいように、ぼたぼたと地面に落ちた。
「御屋形様、お戯れがすぎます。せっかく歴代のご当主が築き上げてきたものを、こうもあっさりと手放してしまうとは」
「だって、わたしは西国で一番偉いのですよ。ならば、終わらせ方も派手にしたいでしょう?」
それから、さも不服そうな顔になって、
「それに、そんなつまらないことを言う時でもないでしょう」
まったくだ。
隆房は刀を握る手に力を込め、それから、ゆっくりとその手をゆるめた。
その刀を御屋形様のほうに差し出した。
「私を殺してください、御屋形様」
自分は早く御屋形様を殺したい。
そして、かなうならそれよりも――御屋形様に殺されたい。
これこそ、自分の命を使いきる正しい生き方だ、そう隆房は悟りきった。
「嫌です。あなたはすべての後片付けをしなければいけないのだから。そんな面倒なことはしたくありません」
あっさりと御屋形様は言い捨てた。
「もっと、寄りなさい」
言われるがままに隆房はにじり寄った。御屋形様の手が隆房の手に伸びた。
その手は昔のようにぞっとするほど冷たかった。
「やっぱり、あなたの顔は凛々しいわ。きっと、魂が単純なんでしょうね」
「ええ、そうかもしれませんね」
御屋形様が何度か咳き込んだ。血が口からずいぶん流れていた。
「死ぬのは……退屈も……しないものですね……」
「この陶隆房、すべて御屋形様のものでございます」
「あなたも……勇ましく、そして、大きく……散りなさい……」
御屋形様は隆房の首筋を小さく噛んだ。
わずかな痛みが隆房に走ったが、すぐにその痛みはやんだ。
西国一の太守は隆房の腕の中で静かに息絶えていた。
◇
数年後、隆房は名を晴賢(はるかた)と改めた。
新たな主君である大内晴英(はるひで)から一字を拝領した名だ。実権はすべて晴賢にある。もっとも、その実権の重さは晴賢の手に余るもので、分国は動揺をきたした。
自分に何箇国もを保つほどの器がないことは、最初から晴賢も知っていた。
どうせ、御屋形様を討ってからの計画など、真面目に考えてはいなかったのだ。
彼女は自分に逆らった毛利元就を討つため、安芸の宮島に渡ろうとしていた。ただ、弘中隆包は宮島に入るのは危険であると再三諫めていた。岩国を領している隆包にはほど近い宮島の地形が晴賢よりずっとよくわかっていた。だいたい逃げ場の少ない島に渡って合戦する意味がない。
だが、晴賢は鷹揚にこうつぶやいた。
「罠だとしても、それはそれで大きく散れるではないですか」
◆了◆
大寧寺逢瀬 森田季節 @moritakisetsu
★で称える
この小説が面白かったら★をつけてください。おすすめレビューも書けます。
カクヨムを、もっと楽しもう
カクヨムにユーザー登録すると、この小説を他の読者へ★やレビューでおすすめできます。気になる小説や作者の更新チェックに便利なフォロー機能もお試しください。
新規ユーザー登録(無料)簡単に登録できます
この小説のタグ
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。









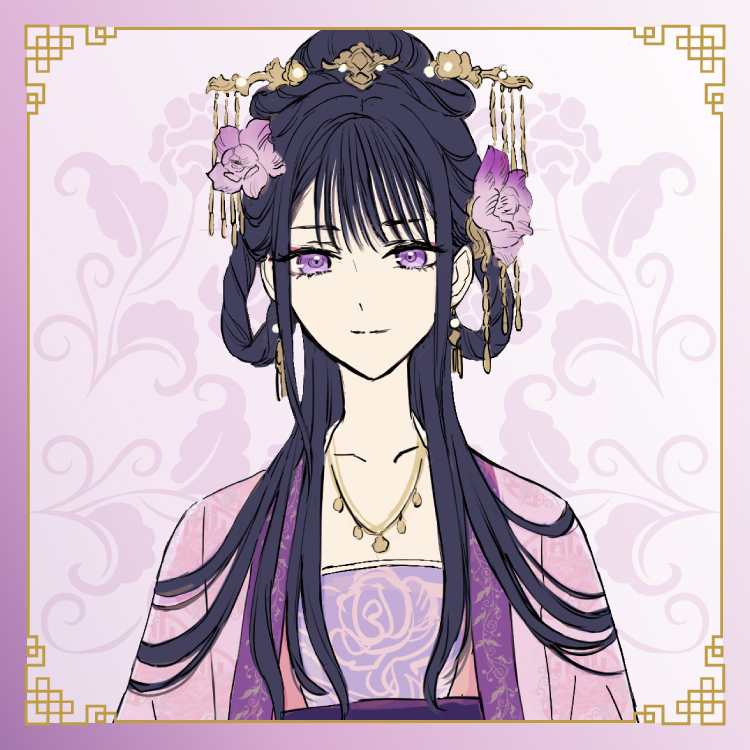

応援すると応援コメントも書けます