#2
@polyphenol
-1 名古屋→松本→野沢→新潟
6時10分発の東海道本線大垣行きと6時12分発の中央線中津川行きが顔を揃えて入線してきた。こと青春18きっぷの期間中の東海道線は大変盛況であり、この早い時間でも大垣行きの方は忽ち座席が6割ほど埋まる。かたや中津川行きは1両あたり10人いるか、という具合である。しかし今日は中津川行きに乗る。
中央線は東京を起点に甲府・塩尻・木曽谷を経由して名古屋に至る路線であるが、ひとくちに中央線といっても実際は塩尻を境にほぼ分断されており、実質別の線区といってもよい。中央東線・中央西線などという呼び方もされる。関東の人から見れば、特急あずさの通う松本までが中央線、のような認識もあろうが(実際私が関東におりあまり出歩かなかった頃はそんな認識であった)、西側も中央線であり、名古屋と長野を結ぶ特急しなのが走るれっきとした幹線区間である。但し、あずさ・しなの両名とも東京・名古屋と長野県の間の需要を見込んでのものであり、この全線区を通って東名間を行き来しようなどと思うのは、気のふれかけた鉄道教信徒ぐらいであろう。
高蔵寺までは名古屋都市圏という様相だが、定光寺・古虎渓あたりは庄内川の渓谷沿いの鄙びた車窓となり、川と離れた多治見からは平凡な田舎の風景となる。7時35分中津川着。ここで7時40分発の松本行きに乗り換える。ここ中津川から西側は8-10両の長編成が走るが、ここから長野方は主に2両編成である。こういう都市圏と田舎圏の境界の駅では得てして椅子取り合戦が催される。実際中津川もそんな”戦場”の一つであるが、通行する絶対量が少ないからたかが知れており、出遅れた1-2割ほどが立っているぐらいである。但し東海道本線と異なるのは、この次の松本行きが10時まで無いことである。途中の駅も山中の小さい駅ばかりであまり乗り降りも期待できぬから、席を確保しかねると辛い長丁場になることもある。
この中央西線に乗る客のうち、長野まで用がある普通の客は特急しなのを利用する。鈍行などを利用するのは普通でない客か、もしくは途中で降りて山に向かう登山客が殆どである。今日も登山に向かうとみられる老人の団体と乗り合わせたようで、婆さん同士のけたたましい会話が車内に響いており「折角鈍行に乗るんだから駅名ぐらい覚えて帰ろうと思って」等と談笑している。私もかれこれこの中央西線には20回は乗っているはずであるが、中津川から先はあまり自信が無い。
坂下で後続の特急に抜かれ、南木曽と十二兼で対向の鈍行と特急と待ち合わせ、材木が積まれた野尻の駅を過ぎたあたりから、左手に木曽谷を眺めるようになる。須原で件の老人団体が降りて行ったが、中央アルプスにでも登るのだろうか。
大分大人しくなってきた木曽川と藪原で別れ、トンネルで鳥居峠を越えると積雪が目立って増えてくる。薄っすらと雪化粧された奈良井宿の街並みが美しい。塩尻で中央東線から来た列車に乗り換え、10時16分松本着。松本は到着時のアナウンスが独特で「まつもとーーーまつもとーーーまつもとーーー」と長々と3回も駅名を連呼しているが、こういう個性がある駅に訪れると嬉しくなる。次の長野行き鈍行は11時9分発と随分間があく。特急で行ってもどうせ長野から乗る飯山線の列車は変わらないので、駅蕎麦でも食べて時間を潰すことにする。蕎麦といえば信州というだけあって、長野県の駅蕎麦は松本・塩尻などレベルの高いところが多い。
篠ノ井線の列車はいつも混んでいるように思う。県都長野と第二の都市松本を結ぶ路線であるから致し方ないが、立ち客が出るほどに混んでいると安曇野や姨捨の車窓が満足に眺められないのが残念である。姨捨は日本三大車窓の一つであり、善光寺平側に位置する下りホームのベンチはレール側ではなく善光寺平の方を向いている。特に田んぼに水が張ってある時期の夜景は「田毎の月」とも称され、春から秋にかけてナイトビュー姨捨なる臨時列車が運行されるほどだという。12時22分長野着。
長野から新潟に出るには旧信越本線か飯山線の2択であるが、今回はJRしか利用できない青春18きっぷを使用していることもあり、飯山線を利用する。北陸新幹線開通後の第三セクター移管によって北陸地方の旅行はやりにくくなった。新幹線が敦賀まで開通するともはや絶望的である。大人しく新幹線を使えという話かもしれないが、新幹線では早く着きすぎるし、最近着工されたものは特急料金も高いから、どうしてもやむを得ないとき以外はあまり気が進まない。東海道のように在来線区間も散々乗りなれていて、ずっと都市圏を行くような路線ならば新幹線もやぶさかではないが、北陸や東北は鈍行を使いたい。
キハ110系を2両繋いだ12時34分発の越後川口行は7割ほどの着席率で長野駅を出発した。車窓右手一面にリンゴ畑の広がる豊野を過ぎると、旧信越本線・現しなの鉄道北しなの線と別れ、代わりに千曲川が寄り添ってくる。飯山線沿線は国内有数の豪雪地帯だが、このあたりはまだ雪が少ない。対岸に聳える形のいい山は高社山で、高井富士とも呼ばれるらしい。
明日のスケジュールの都合上今日は新潟に泊まるつもりだが、このまま乗り続けても早く着きすぎるので、どこかで途中下車したいと思う。前回同じルートで新潟まで乗った時は十日町で降りて松之山温泉に向かったのであった。このあたりは温泉地が多く、なかでも秘境秋山郷の切明温泉には一度行ってみたいと思っているのだが、津南から秋山郷まで行くバスは1日3本しかなく、日帰りで行くなら長野か長岡あたりに泊まるしかない。 他に沿線で温泉といえば、大きなスキー場を有する野沢温泉が有名である。4年前に一度降りているが、近年オーストラリア人など外国人訪問客がとみに増えているという。様子を見に行ってもいいか、と思う。13時19分、飯山着。ここで下車する。
実は飯山の3つ先に戸狩野沢温泉という駅があり、いかにもここから野沢温泉まで行けますよ、というていである。実際4年前に野沢温泉に行ったときはそこからバスで向かったのであるが、翌年北陸新幹線が金沢まで延伸し、飯山が新幹線接続駅となったときにその路線が廃止され、野沢温泉へのアクセスは飯山からのバスに一本化されてしまった。合理的な措置ではあるし、飯山線車内でも野沢温泉へは飯山からバスを利用する由を繰り返しアナウンスして誤乗を防ぐ努力はなされているからとやかく言うつもりはないが、やはり紛らわしいことに変わりはない。「戸狩温泉」にでも改称したらよいのではないか。
新幹線との接続駅となった飯山駅は見違えるほど立派になっていた。案内板には英文併記が目立ち、構内のモニターでは近隣の観光地情報が英語で発信されている。野沢温泉目当てでやってくる外国人訪問客をうまく引き込んで復権を図る飯山市の意気込みが伝わってくる。
飯山からの「野沢温泉ライナー」の乗客の半数程度は外国人であった。それもおそらくオーストラリア人であろう、車内は英語が飛び交っている。30分ほどで温泉街に着くと、バスターミナルから温泉街にかけて外国人であふれている。4年前も冬に訪れたはずだが、外国人は数人見かけたぐらいでこれほど多くはなかったように思う。この4年の間に地元住民の対応や外国資本の投下も進んだようで、英文が併記された案内板や、見るからに欧米的な店舗も見られる。しかし一方で温泉街全体の雰囲気や、傾斜地に立ち並ぶ旅館や土産物店の景観は大きくは変わっていないように思われる。
地元住民が野沢菜を茹でるのに常用するという温泉湧出源の麻釜を見物し、黒い湯の華の浮かぶ温泉に浸かってからスキー場の方に上がってみる。温泉街からスキー場までは高低差が結構あるが、動く歩道が整備されており15分程度で移動できる。この温泉とスキー場の近さも魅力の一つだという。実際この野沢温泉スキー場が外国人訪問客に人気であるのは内陸の豪雪地帯で雪質に優れることのほか、温泉街が近く、過度に外国資本が入らず日本的な景観を残していることが大きな理由として挙げられるそうだ。近隣に善光寺や地獄谷野猿公苑のような観光地もあり、長期滞在する割合の多い外国人スキー客の観光需要に合致しているとのこと。地元でも増大する外国人対応のため、設備の改装や語学留学に精を出しているという。元の景観を守りつつ、うまく付き合ってゆくのは苦労も多かろうが、頑張ってほしいと思う。
バスで再び飯山駅に戻り、17時15分発の越後川口行に乗り込み北上を再開する。進むほどに雪が深くなっていき、JR日本最高積雪記録を有する森宮野原のあたりでは1~1.5mほどの積雪であった。ほくほく線との接続駅である十日町を過ぎ、下条のあたりでついに積雪が列車の窓枠に被る高さになってきた。私は雪景色が好きで冬場はよく東北や北陸を訪れるのだが、非日常感を感じられるからよいのであって、これが日常であったらたまったものではないと思う。
19時35分越後川口着。4分の接続で上越線に乗り換える。車両は真新しいE129系である。新潟支社は数年前までは115系が主力の地域であったが老朽化もあり、このE129系という新型のステンレス車に置き換えられつつある。セミクロス車で乗り心地に文句はないが、東海道線や横須賀線を走る重厚な115系を見て育った身としてはやはり寂しい。吾妻線などでもしぶとく生き残っていたのだが、関東地方ではついにこの3月のダイヤ改正で定期運用を終了するという。まだ中国地方での運用はそれなりに残っているが、若くても30歳、年老いたものだと50歳を超える車両もあり、もう長くないかもしれぬ。乗れるうちに乗っておきたい。長岡20時2分着。7分の接続で新潟行きがあるからこのまま乗り継いでもよいが、腹も減ってきたのでこのあたりで夕飯にしたい。長岡生姜醤油ラーメンというのがご当地ラーメンにあり、これが好物というのもある。生姜の程よく効いたスープは美味で飽きない味だし、寒い時期は身体も温まる。
新潟行きのE129系は越後平野を快速で飛ばしてゆく。長岡から新潟にかけては、ひたすら田園が広がる車窓であったように記憶しているが、今は闇の中である。景色の見えない夜の列車というのは、何故か実際の速度よりも速く感じられる気がする。三条、加茂など、何やらみやびた名の駅をいくつか過ぎて、22時10分新潟着。博多を抜きにすれば、新潟は日本海側最大の都市で、こんな時間でも駅は随分賑わっている。向かいのホームにとまっている115系6両編成の村上行きは混雑しており、発車間際も遠くの改札から駆けてくる乗客が絶えないが、車掌はそれが尽きるまで急かすことなく待っている。次の村上行きが1時間後ということもあろうが、都会では終電でもない限りこういう光景はなかなか見られない。
ところでこの115系、前方3両は見慣れた新潟色の塗装であるが、後ろ3両は赤と黄色の見慣れぬ組み合わせであった。これは70年代に運行していた車両に使われていた初代新潟色と呼ばれるものらしく、雪の中でも目立つように、との意図で配色されたものだという。つい1年前にこの色に塗りなおされたそうだが、115系自体が消えゆく中での再塗装というのはやや不自然に思える。新潟地区からの引退に合わせ「有終の美」を飾らせるために塗り替えたとも見れなくもない。まさかこれが今生の別れでもあるまいが、妙に気になる。そうこうするうち、最後の駆け込み客が列車に乗り込み、115系は北へ向かって走り去っていった。
#2 @polyphenol
★で称える
この小説が面白かったら★をつけてください。おすすめレビューも書けます。
フォローしてこの作品の続きを読もう
ユーザー登録すれば作品や作者をフォローして、更新や新作情報を受け取れます。#2の最新話を見逃さないよう今すぐカクヨムにユーザー登録しましょう。
新規ユーザー登録(無料)簡単に登録できます
この小説のタグ
関連小説
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。










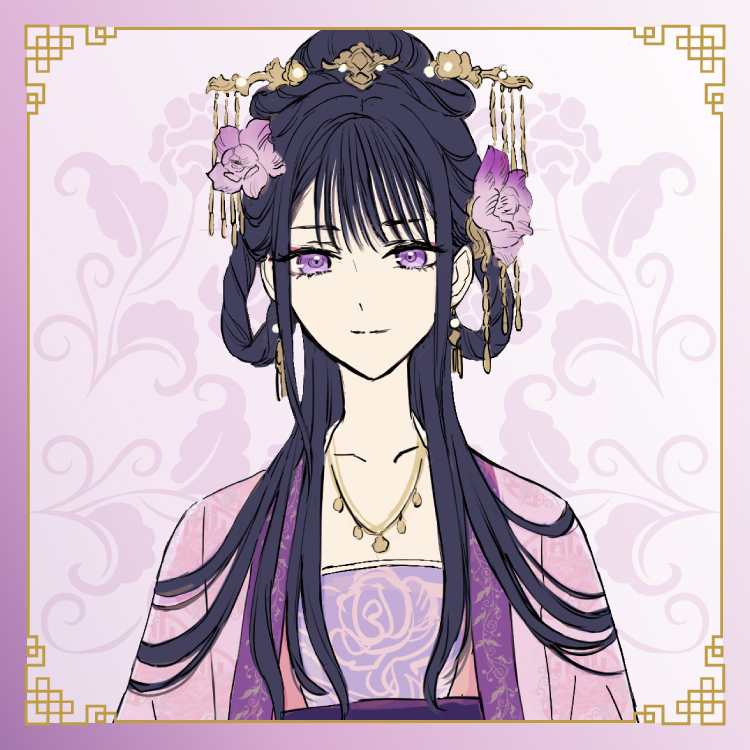
応援すると応援コメントも書けます