第8話 次の花が咲く前に
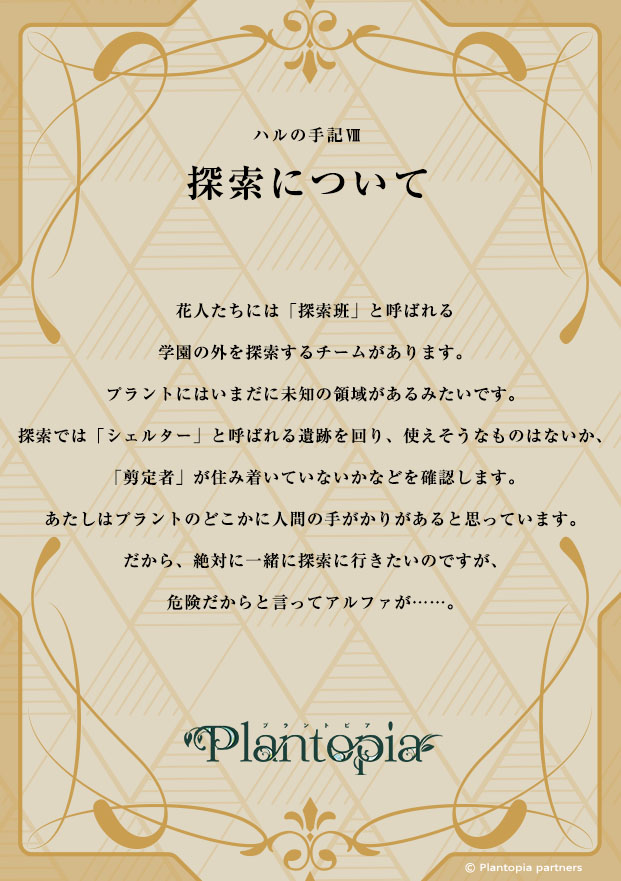
「ん~~~~~……」
「――つまり、ここに書かれてることは大筋じゃ間違ってない。けど所詮は大昔の情報だ。そのまま真似しようとしたって、『月の花園』には合わないこともある」
「プラントの環境は本の内容とは違うってこと?」
「そうなる。環境が変われば、花の咲き方も違うからな」
ある昼下がり、図書館にて。ハルは机の一角に陣取って「勉強会」を行っていた。
内容は園芸について。ただし今回は、これまでのように知識を頭に詰め込むだけとは違う。アルファが教師役となり、間違って覚えていたところを教え直してくれている。
「本で得た知識と合わないところは、もう実際にやって慣れるしかない。慎重にな」
「例えばどんな?」
「例えば……そうだな。昔あって、今は無いもの。『季節』っていうのがそうらしいと聞いた」
『季節』。
聞いたことがある。
プラントで目覚めてからというもの一度も耳にしたことのない単語だった。しかし、記憶の片隅になんとなく残っていた。
「それって、一年を四つに分ける時期のことだっけ?」
「らしい。暑かったり寒かったり、湿気があったりなかったり。昔はそれに合わせて花が咲いたり枯れたりしてたみたいだ。今は基本、気候はずっと一定だから、その点じゃ楽かもな」
「けど、その暑い時期や寒い時期が好きな花だっていたんじゃない? そういう花は今どうすればいいのかな」
「こっちで生きやすい条件を整える。研究班に機材を作ってもらっててな。そっちの操作を覚えるのも花守の仕事だ」
なるほど奥が深い。環境がずっと一定というのは一見楽なようだが、逆にある程度こちらが条件を整えてやらねばならない場合もある。
それにしてもこの本は、随分読み込まれているようだった。
遺跡から発掘したものである以上、紙媒体の本はどれもボロいのがお決まりだが、これは輪をかけている。幾度となくめくられたページは擦り切れ、あちこちに古い付箋や古代文字の記されたメモが挟まれている。園芸に関する本は全部漁ったつもりでいたが、アルファが隅っこから引っ張り出したこの本はフライデーすら存在を知らなかったものだ。しかも、かなり読みやすい。
「ベルタが参考にしてた本だ」
墓に刻まれた名を告げるように、アルファが言う。
「あいつはわたしたちの中で一番古代文字に詳しかった。だから、この本を下敷きに花園の管理の仕方を勉強したんだ。お前ならメモ書きの内容がわかるんじゃないか?」
「……そっか。わかった、読んでみるね」
メモの筆跡は独特で、いかにも形だけを真似た凸凹の象形という感じがする。それでも、ちゃんと読み解くことができた。元の本に記された情報に、今のプラントの環境に即した訂正や注意書きが添えられている。
これが、ベルタの文字。
ハルは本を読み進めながら、自分自身の手帳にも覚えたものを整理して記す。もしかしたらこの手帳も、いつか誰かの参考になるかもしれない。そう思うと少し愉快だ。
「――今日は、ここまでにするか」
そこからしばらく勉強を続け、ステンドグラスから差し込む陽が赤みを帯びてきた頃、アルファは静かに本を閉じる。壊れ物を扱うように胸に抱え、元あった場所へと戻すため立ち上がった。
「あ、そっか。もう夕方!」
「約束の時間を過ぎてる。そろそろ出来上がってる頃じゃないか」
勉強の後、研究室に大事な用があった。今日は紋様蝶を使った実験ではない。
頼んでいたものを受け取らねばならない。
✿✿✿
「おお、よくおいでになりましたな!! 約束の品はちょうど今できるところでありますぞ!!!」
ドアを開けるなり、壁のような大声に迎えられた。
思わずのけぞるハル。アルファはドアが開く前から耳を塞いでいた。微妙にやりにくそうな顔をしている。どうもクドリャフカのことが苦手らしい。
「ありがとう! どこで作ってるの?」
「こ、こっち、です」
見れば、スメラヤがある機材を操作しているところだった。碧晄流体を調合する装置のようだ。タンクの片方には流体が、もう片方には
その中に、彼もいる。
「こ、この手の保存処理をすることは、何度かありましたけど……こういう形にするのは、は、初めてです。よかったんですか?」
「いい。封じ込めてさえいれば、どんな形でもちゃんと治る」
「こういう形って?」
頼んだのは二人でだが、ハルは細かい部分まで関与していない。何か特殊な形になっているのだろうか。アルファはけろっとしたもので、
「見ればわかる」
いくらもしないうちに、処置が完了した。
スメラヤが装置を動かし、チャンバーを開く。白い冷気が溢れ出て、その向こうに、重いのほか小さな塊があった。
ベルタ。ハルが踏んでしまった、ワスレナグサの小さな花。
傷付いた花は、碧晄流体と樹液の混合液で固めることで、癒すことができるという。ハルが手に取ったのは、ベルタが封じ込められた、仄かに碧く光る琥珀だった。
ただ、その形というのが。
「これ……栞?」
片手に持てる短冊状で、少し大きいが、栞といって差し支えないだろう。
固めるだけなら球でも四角でもよかったろうに、どうしてわざわざアルファはこの形を指定したのだろう。
「持ち運びやすいと思ってな。――それは、お前が持ってろ」
「え? あたしが? ……いいの?」
「いいも何も、
それを言われるとぐうの音も出ない。荷が重いような気もしたが、断る線は無かった。
しかし、決して悪い気はしなかった。
アルファはハルの罪悪感を清算しようとしてくれているのかもしれない。何から何までやってもらって、あとはベルタの回復を待つだけとなれば、どうしても後ろめたさは残る。けれど治るまでずっとハルが守り続けることができたら、それでもう差し引きはゼロになるだろう。
「それに」アルファは目を逸らして、「……お前は本だの手帳だのをいつも持ってる。一緒に使ってやれば、忘れるってこともないだろう」
あ。
「……もしかしてあたしが使いやすいように気を遣ってくれたの?」
「合理的に考えただけだ」
「あ! 素直じゃない! いいじゃんそういうことで! あたしすっごい嬉しいよ!」
「違う、普通に考えればこれが一番いいと思っただけだ、お前がどうこうの話じゃない余計なこと考えるな」
やっぱり素直じゃない。ハルは早速、愛用の手帳に栞を挟んだ。最新のページ。新しいことが記される度に、この栞も前進する。
もし今のベルタに意識があったら、一緒に手帳を読んでくれるだろうか。
「――ありがとう。この子は、あたしが責任を持って守り続けるよ」
「……ん。頼んだぞ」
改めて礼を言うと、アルファの表情もふっと和らいだように見えた。
ハルとアルファが研究室を去り、スメラヤたちはいつも通りの業務に戻る。
「アルファさん、た、楽しそうでしたね」
「む? そうでありますか!?」
「いつもは、も、もっとむすっとしてますから。――よかったなぁって思います」
アルファがいつも言葉を飲み込み、心に何か重いものを背負っているような気配は、常にあった。それが少しでも軽くなったのなら、いいことだとスメラヤは思う。
研究班の目下の最優先は、剪定者の調査だ。キウ班の襲撃で撃破した「隊長機」含む複数の残骸は貴重な情報源で、紋様蝶を読み解くハルの協力により、かなり修復と解析を進めることができた。
そしてようやく、隊長機から取り出した通信装置の修理が完了しそうだった。
スピーカーは完璧。受信装置もまずまず。紋様蝶を介したコンタクトに応じ、ハルの声を正確に受信してスピーカーから出力できた。
問題は受信距離である。過日の実験では学園の頂上から研究室までの距離でノイズ交じりだった。今回はより調整を重ね、更にアンテナと接続してみたが、果たしてどこまで届くかわからない。
「クドリャフカくん。ひ、ひとまず、『第一の指』までお願いします。そこを起点として、通信距離を広げていきます」
「了解であります!! では早速――」
ざざっ。
突然だった。
スピーカーが不意にノイズを吐き出す。
こちらからは何も働きかけていない。このノイズの入り方は、「距離がありすぎてギリギリ通信を拾えていない」時のパターンだ。では誰が、どこから、何故。
よく耳を凝らせば、ノイズに紛れて誰かの声がする――ような気がする。
『――――け――#%た』
途切れ途切れの、どこの誰かも知れない者の声。
何かを言っている。唄うように、訴えるように。
確実に聞き取ることができたのは、次の単語だけだった。
『せんせい』
✿✿✿
展望台は、図書館から更に枝の回廊を登った頂上にある。
ここが学園で最も高い。樹海の木々より何十、何百倍も大きな巨木の化石の最上層なのだから、見える景色は絶景の一言だった。おそらくプラントの中でも『世界樹』の次に標高が高い場所と言えるだろう。
見渡す限り、緑の樹海。あちこちから機械的な遺跡が顔を出し、それがまるで湖に浮かぶ魚のようだった。雲を追うように鳥の群れが飛んで、翼の向かう果てには天を衝く『世界樹』がある。
ここから見える景色が、昔からアルファのお気に入りだった。
樹海を見下ろしていると、そのままどこかへと飛んでいけるような気がする。自分もあの雲を追うことができるだろうか。『世界樹』にまで届けば、そこには何があるのだろう。もっともっと上って、空の遥かな高みを目指せば、どんな景色が見られるのだろうか。
あるいは、この世界の果てさえも、目の当たりにできるのだろうか。
誰にも言ったことはないが、そんな空想に耽っていたこともある。最近はめっきりご無沙汰だが、今も考え事がある時や気が塞いだ時はここに上がる。その度に、昔の感覚を思い出すのだった。
「ここにいたか」
後ろから声がかかる。振り返ると、見慣れた赤い奴が苦労して登ってきているところだった。
「ナガツキか。無理するなよ、もう若くないだろ」
「お前には言われたくないがな」
手を取り、引っ張り上げてやる。若さ云々は冗談としても、ナガツキは昔と比べて随分ひ弱になった。彼の力の行き場を考えると当然のことだ。アルファは嘆くつもりも、嗤うつもりもなかった。
「花園はどうした? 世話をしなくていいのか?」
「試しに、ハルが一人でやってる。もし何かあったら」アルファは肩に留まった紋様蝶を指差し、「こいつ越しに伝えるって」
「驚いたな。お前が誰かに花守の仕事を任せるとは。ベルタがいなくなって以来のことだから、久しぶりどころの騒ぎじゃない」
「そうか?」
そうに決まっている。アルファは改めて自分の経歴を思い返してみて、気が抜けたように息をついた。
「……いや、そうかもな。こんな風にぼけっとしてるのも、しばらくぶりだ」
「ハルはどうだ?」
「よくやってるんじゃないか。思ってたより覚えが早い。このままいけば、すぐにわたしの助言もいらなくなりそうだ」
「そうか」
少しの沈黙。アルファは隣に横目を流し、
「で?」
「ん?」
「ん、じゃないだろ。わたしに用があって来たんじゃないのか。やけに前置きが長いな」
「ああ、そうか。そうだな。――いやなに、聞きたいことがあってな。誰かの前じゃできない話だったからちょうどいい」
「何だ?」
応じて、ナガツキは言った。
今日の予定を確かめるように。
探し人の居場所を尋ねるように。
そういう気軽さで、必要なことの確認を取る。
「お前は、あとどれくらいで枯れる?」
桜の花人アルファと、彼岸花の花人ナガツキは、学園でも最古参の花人である。
同期や近い世代はもういない。みんな花園で眠っているか、あるいはプラントのどこかに根付いているかもしれない。
学園の黎明期からここにあり、咲き続けていた花には、必然の結末があるものだ。
「――心配するな。お前より短いってことはない」
「そうも言い切れないだろう。おれより後に咲いた花だって何度も見送ってきた。花の寿命には個体差があるし、消耗の度合いも違う。……お前が戦ってきた時間は、長い」
アルファは何も言わなかった。おおむねナガツキの言っている通りだったからだ。
花人は不死でなければ不老でもない。戦いで命を落とさずとも、この学園で静かに枯れていった花々のことを覚えている。彼らが幸せなのかどうかは、判断がつかないが。
「高純度古代兵装は封印しろ。あれはお前にはもう荷が重い。この間の戦闘でさえ、勝手に持ち出されてヒヤヒヤしたぞ」
「緊急事態だったから仕方ないだろ。それに、あの時は力を使い過ぎないよう手加減した」
長い時を生きた者。戦闘などの過酷な活動で体に負荷をかけすぎた者。そうした花人から色褪せ、乾いて、土に還っていくこととなる。その点、アルファほど長く学園にいて、なおかつ最強であり続けた例は他に無い。彼がどこまで「保つ」のかは、ナガツキはおろかアルファ自身でさえ知らないことだった。
「おれたちにはまだお前が必要だ。花守だって、学園にはお前一人しかいないんだぞ」
「花の世話なら
自分でも驚くほど、するりとその言葉が出た。
ほんの少し前までは、口が裂けても言わないであろうことなのに。
樹海の果てを遠く見通すアルファの表情には、不思議な透明感があった。何かが抜け落ちたような、重いものを下ろしたような。――より正確には、重い荷物の幾つかを、誰かにやっと分けることができたというような。
その横顔を見て、ナガツキは笑う。
「まるでもう終わるみたいな口ぶりだな。流石に気が早すぎるだろう?」
「かもな。最近、色んなことを考える余裕ができたせいかもしれない。わたしもちょっと変なのかな」
「……お前がいなくなると、おれは寂しいよ」
「花はまた咲く。
アルファは立ち上がる。地表から巻き上がる風は、いつもいい匂いがする。
決心した。
「ナガツキ。ひとつ頼みがある」
切り出され、ナガツキは大きく目を見開いた。アルファからそんなことを言い出すことこそ、もうずっと昔に一度や二度あるかないかだったから。
✿✿✿
「――まさか、花園の世話を頼まれるとはな」
独りごち、ナガツキは『月の花園』で作業を続ける。
手順はおおむね知っている。なにしろずっと学園にいたのだ。アルファや、アルファの直伝を受けたハルほどではないかもしれないが、一時の留守番としては充分だろう。
しかし学園長が花園にいるというのは凄まじく珍しいようで、キウを見に来たウォルクやネーベルのみならず、フライデーや他の花人までもがその様子を見守っている。別に、起きている間は頼まれればこれくらいするのだが。
しかしこうなると気恥ずかしいものがある。ナガツキは水の入った如雨露を右手に提げながら、南の空を見上げて、呟く。
「気を付けてくれよ、アルファ、ハル。無事の帰還を」
先日、アルファが展望台から見ていたのも南の方角だった。
世界樹の播種が行われたあの日、彼がいち早く異常を察知して急行した、遥か遠くの森だ。
二人は、夜明けと共に出発した。
探索はせず、幽肢馬でひたすら一直線。一人か二人でようやく通れる狭いルートを突き抜ければ、日が高くなる頃には目的地に着くという。
向かう先は、南の森の奥地。
ハルが目覚め、アルファに発見された、出会いの廃墟だ。
木々の間を抜け、小高い丘に出たあたりで速度を緩める。ルートをしっかり確認しながら、アルファは次の抜け道に案内してくれた。
「――けど、大丈夫なのかな。今から通る道って本当に安全なの?」
「大丈夫だ。考えてもみろ、最初にお前を連れ帰った道だぞ」
確かに。記憶が無いどころか意識もはっきりしていなかったハルを連れ帰るからには、確実に安全と言える道を通るしかない。
そう考えるとアルファのルート選択は流石の一言ではあったが、だからこそ不思議だった。
「いつもは学園から出ないんだよね? なのになんでこんな道知ってるの?」
「昔から知ってただけだ。ベルタから逃げて、遠くまで探索するために作った道のひとつだからな。あいつに見つからないルートが他の奴に見つかるはずがない」
「おお、なるほど……」
たちまち腑に落ちた。物凄い説得力だ。
「それより、次はかなりの獣道だ。その次は細い洞窟を通る。ぶつからないよう気を付けろ。紋様蝶はちゃんと連れてきてるな?」
「うん、リュックに入ってる。急ごう」
例の場所に行くことを切り出したのは、アルファの方からだ。
これがハルには意外だった。『第一の指』の一件から、彼の中で何かしら心境の変化があったのは感じ取っていたが、まさかあちらから提案されるとは。
――お前がいた場所には、たくさんの紋様蝶がいた。
彼はまずそう言った。
今のハルは、紋様蝶のことを「読む」ことができる。ならば最初の場所にいた群れを読めば、何かがわかるはず、ということだった。
断る理由など無かった。むしろ望むところだ。念のためハルが慣れ親しんだ蝶を数匹、学園との連絡用を兼ねて借り受けてきた。研究室はこの提案を快諾してくれた。――なにやら別の作業で忙しいようだったが、邪魔をしては悪いと思い、深く首を突っ込まないでおいた。
馬を急がせる。まだ先は長そうだ。
出発前の見立て通り、その廃墟に到着する頃にはもう日は高く昇っていた。翅の二刻。プラントの生き物が最も活発に動く時間だ。
静かな場所だった。目的が無ければ素通りしてしまいそうな、ささやかな廃墟だ。かつてあったらしき建物の残骸は確かにあるが、それもわずかばかりで、全体の印象としてはまるで何かの墓標に思える。
目指していたものは、そこにあった。
「……これ、だね」
「ああ」
ハルが眠っていた場所。その残骸。
研究班をはじめとした花人たちはこれを「ポッド」と仮称していた。
ポッドは機械というよりは生物的な印象だった。植物の種か、卵のようにも見えたと、最初に発見したアルファは言う。確かにこれは、ハルが眠る
今でも思い出す。記憶の始まりは、空と桜だった。
明るい陽射しと、豊かな木々と草花の匂い。こちらを見下ろす花人の、その美しい桜の花弁と――
「いたぞ。紋様蝶だ」
声に意識を引き戻され、ポッドの上を見ると、何匹もの紋様蝶がひらひらと寄ってきていた。白く仄明るい翅が集まり、まるで小さな光の雲のようだ。
「覚えてたのより数が多いな……。読めそうか?」
「大丈夫、やってみる」
リュックから放った一匹を起点として、群れにアクセス。こちらから信号を飛ばしてみると、一匹また一匹と反応を返してくる。感度良好、問題無く解析できそうだ。しかし――
「ちょ……っと、時間かかりそうかも。待っててくれる?」
「わかった」
アルファは量産型の斬甲刀を肩に担ぎ、その辺の残骸に腰掛ける。確実に安全なルートを選んだとはいえ、警戒を怠ってはいけない。
紋様蝶の信号は複雑だった。数が多いのもそうだが、破損した部分や暗号が難解すぎる部分も少なくない。今の状態で100%解読することは不可能だろうが、できる限りの情報を拾い上げなくてはならない。
ちかり、ちかり。ハルのコマンドに合わせて、紋様蝶がさんざめく。アルファは邪魔をせず、静かにハルを待っている。しばしの沈黙。
「――あのさ。ひとつ聞いてもいいかな」
ハルの方から口を開いた。こういう作業をしている時は、黙っているよりむしろ喋っている方が捗ることも多い。
それに、ある疑問が心に引っかかったままだったから。
「なんだ?」
「ええと。もしかしたら、デリケートな質問なのかもだけど」
「……? 何を勿体ぶってるんだ。話しかけたのはそっちだろ、早く言えよ」
ならば――
ハルは紋様蝶を操作しながら、少し遠慮がちにアルファを見る。
「あの時、どうして泣きそうな顔だったの?」
問われて、アルファは硬直した。
そう、ハルは確かに覚えている。
目が覚めた時、最初に見たのは桜の花びら。
そして桜のように美しいひとの、泣きそうな顔だった。
今だって忘れたことは一度も無い。ハルの中でアルファへの認識はころころ変わっていったが、最初の「哀しそうなひと」という印象はずっと頭の中に残っている。
「……覚えてたのか」
「覚えてるよ。最初に見たのがそれだもん」
「というか、わたしはそんな顔をしてたのか」
「してた」
「本当か?」
「本当だってば。あたしの目がおかしくなければだけど」
アルファはものすごくばつが悪そうな顔でそっぽを向き、しばらく考え込む。
ハルは根気強く待った。
「……誰かに、それ言ったか?」
「言ってない。理由もわかんないことだったし」
「笑わないな?」
「笑わないに決まってるでしょ! もう、そっちこそ勿体ぶってるじゃん!」
やがてアルファは、観念したように頭を掻いて、はっきりと答える。
「怖くなったんだ」
「へっ?」
笑うどころか、呆気に取られた。
怖い?
ハルを見つけて、アルファほど強い花人が、何を怖がることがあるのか。
「……怖いって、何が?」
「ベルタの話をする時、言ったろ。最初の頃のわたしは、今みたいな感じじゃなかった」
曰く、咲いたばかりのアルファは、なんとかして外に出ようとしていた。
理由は今のハルとほとんど同じだ。学園の外をもっと知りたい。プラントの謎を解き明かしたい。自分たちが何者で、どうしてここにいるのかを、知りたい――
「だけど、ベルタが死んだ時から、色んなことを諦めた。何も変えたいと思わなくなった。何も忘れない代わりに、何も知らなくていいと。そう、思い始めた」
アルファは一つ一つ、順を追って、刻むように語る。まるで、自分の中で散らかった何かを整理しているかのような口ぶりだった。
「そんなことにも慣れた時、あの播種が起こった」
播種。『世界樹』が定期的に行う、プラント全域へ種をばら撒く機能。
播種自体は珍しいものではない。ほぼ毎日のように行われているため、花人にとっては時報とさして変わらない認識だ。
しかし、その日は違った。アルファは、今や枯れ果てた白いポッドに目をやる。
「『それ』が落ちるのが、花園からでも見えた。遠すぎて形まではわからなかったけどな。ただ、緑色の光にしか見えなかった。ちかちかしながら南の森に……つまり、ここに飛んでいったんだ。――流星みたいだと思った」
流星の落ちた日。
アルファの心に、深く刻まれた記憶。
「まるで、ベルタが言ってたみたいだ。そう思った時、気が付けば走ってた。今にして思えば、わたしは期待してしまったんだと思う。何かが変わるかもしれない。ベルタが探そうとしてたものが、わかるのかもしれないって。無我夢中で馬を走らせて、いつの間にか着いてた。そしたら、ポッドがあって――」
視線が、こちらに戻る。桜色の瞳と目が合う。
「お前が出てきた」
そして、ハルの記憶に繋がる。
ではハルの意識が焦点を結んだ時、アルファは何を思っていたのか。
「――どうだった?」
「驚いたなんてもんじゃない。資料でしか知らなかった『人間』がいたんだ。……期待通りかと言われれば、それ以上だったと思う。ああ、やっと何かが変わるんだと思った。ずっと変わらなかった
言葉に詰まる。
望み通りだったはずだ。
ハルとは、待ち望んでいた「変化」そのものだったはずだ。
停滞に風穴を開けるであろう存在が、人の形をして目の前に立っていた。
そんな、諦めていたはずのものを突き付けられ、アルファはしかし。
「怖い、と思った」
絞り出される声は、少し震えていた。
「変わってしまう。昔はあんなに嫌ってた『変化の無い』生活が終わってしまうかもしれない。わたしはそれを、怖がった。ここに来るべきじゃなかったとさえ思った。そのことを自覚すると、頭の中がぐちゃぐちゃになって、わけがわからなくなった。わたしは……お前のことが、怖かったんだ」
それこそ誰にも、ナガツキにも打ち明けなかったであろう、アルファの心の最奥だった。
変化を望みながら、それを恐れる。心を守るために築き上げた「諦め」の壁は、強固ゆえの重さで彼自身をも押し潰そうとした。
座ったままうなだれるアルファは、まるで許しを乞うているように見えた。それは恐れの対象であったハルにか、かつての自分へか、それともベルタであっただろうか。
「大丈夫」
だからハルは、そう言った。
ポッドから離れ、座り込むアルファに寄り添い、はっきりと告げる。
「確かに、何か変わるかもしれない。それはすっごく大きなことかも。学園やみんなの生活だって、もしかしたら変わっちゃうかもしれない。けど大丈夫」
「お前……」
「何があっても、あたしは変わらない。みんなと――アルファと一緒にいる。そっちが良ければ、だけど」
「どうして、そこまで言ってくれる? わたしはお前を突き放してばかりいたんだぞ。それも自分勝手な都合でだ。なのに、なんで……」
何故、と言われると、気の利いた返しが浮かばない。
月並みな言葉しか出てこない。
それでいいと思った。
「アルファは、友達だから」
顔を上げたアルファの表情は、今まで見たこともないものだった。
驚いたような。呆けたような。いつも気だるげだった目が大きく見開かれて、ハルはその虹彩を改めて綺麗だと思う。
「――――友達」
「だと、あたしは思ってる」
「ともだち」
「……わけ、ですけど……」
「ともだち……」
「……友達って意味、わかる?」
「わかる」
その割には「生まれて初めて聞きました」という顔をしている。
「――――や、いや。わかるんだ言葉の意味は。だけど、つまり、あれだ。学園のみんなは仲間だったから。つまり同族というか。だからそういう、改めてそんな、それを言われるのが初めてだったから。こう、あの」
もたもたしている。いつも単刀直入なアルファとは思えない。試行錯誤の末に結局うまく言い表せず、ただ気持ちをありのまま述べる。
「……変な気持ちだ。だけど、嫌じゃない」
「あたしのこと、まだ怖い?」
「いや」アルファはゆっくり首を振って、「もう、とっくに怖くないよ」
今度こそ見間違いではなかったと思う。
アルファが、穏やかに微笑んだ。
「お前をここに連れてきたのも、それが理由だ。――何かが変わるとしても、悪いことにはならない。今はそんな気がする」
「うん。ならない。あたしが、しない」
「わかってる。それでいいよ」
その時、紋様蝶がちかっと一度眩しく輝く。
解析が終わったのだ。
「!」
「読めそうか!?」
「拾えた範囲は、多分。ちょっと待ってて!」
ポッドに駆け寄り、群れが描くコードのパターンを読み取る。完璧な形で拾えたものは全体の30%ほど、それを手掛かりとして虫食いのようになったバグや欠損データを可能な限り繋ぎ止めて最低限の推測がつく形に復元する。結果として、情報の約60%余りを読み取ることに成功した。
わかったのは、このポッドにまつわる情報。
どこから、何故、どうやって来たのか。
それは、驚くべき情報だった。
「アルファ……」
「……どうだ? あの播種は何だったんだ? これは一体……」
「地下だよ」
「地下?」
「このポッドは世界樹の地下にあった。ううん、これだけじゃない、もっとたくさんのポッドがある! それが世界樹の幹をずっと上に送られて、最上層から射出されるんだ。これはその、ほんの一つに過ぎなかったんだ!」
「……!! ちょっと待て、じゃあこういうことか? そのポッドの中に……!」
「あたし以外の人間が眠ってる!!」
飛び跳ねそうだった。アルファも唖然としていた。ハルは会心の笑みを浮かべ、手帳にペンを走らせる。そこには栞となったベルタも挟まっている。みんなにも伝えなくては。こんな発見は、花人たちが生まれてから前代未聞のはずだ。
「そうか。人間か、――……!」
「人間は滅んでなんてなかったんだよ。なんとかして世界樹の地下施設に行ければ、みんな目覚めさせられるかもしれない! そうなったらみんなで暮らそう! あたしも――」
そこまで言いかけてハルは、アルファが自分ではない別のどこかを見ていることに気付く。
「……アルファ?」
彼は目を見開いていた。そこに宿る感情は、ハルには想像もつかないもので。
目線はハルの頭上、遥か向こう。振り向いて空を仰ぐと、「それ」はハルにもはっきりと見えた。
赤い光。
空から、落ちてくる。
昼間の空にもはっきりとわかる光源が複数。今いる場所よりずっと北――学園のある方へと、落ちていく。
青空を切り裂く、赤い流星群だった。
✿✿✿
降り注ぐものが森を薙ぎ倒す。
それらは一つ一つが、見上げるほど巨大な鋼鉄製のポッドだった。
木々が折れ、岩が砕け、地面が爆ぜ飛ぶ。着弾点はたちまちのうちに焦土の様相を呈し、次々にポッドが開いていく。
濛々と立ち込める煙の中、赤い交点が二、四、八、十六、三十二、六十四――
それら全てが、剪定者のアイセンサーであり。
先頭に立つ一対が最も小さく、しかし最も獰猛かつ冷酷な光を宿す。
「寂しがっているかなあ。待たせてしまったかなあ」
唄うような声色は、しかし、とても楽しそうに弾んでいた。
無数の剪定者を従え、機械仕掛けの少女は笑う。
「もう少しですよ、先生。僕がすぐ迎えに行きますからね」
携える刃は恐ろしいほど鋭利で、巨大な剪定鋏の形をしていた。
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます