第7話 忘れ得ぬもの
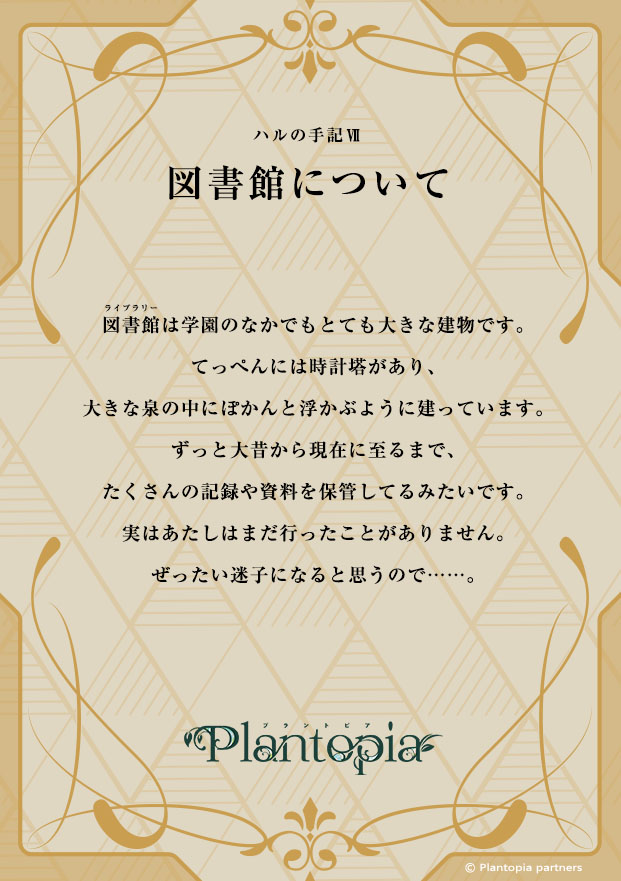
『月の花園』には、常に学園の最高戦力が配備される。
花園は、人の姿をなくした花人たちが行き着く場所。いわば最後の安息の地である。そんな場所を管理するのは花園を確実に守り抜ける存在でなくてはならず、『花守』とはすなわち、最強の花人の称号でもあった。
それが、ワスレナグサのベルタ。最初の花守である。
✿✿✿
「アルファー? あーるーふぁーさーん」
桜の花人は、最初それを自分のことだとは思わなかった。
目の前に広がるのは鬱蒼たる森。背中には大量の装備を詰めたリュック。ついでに試作品の武器も持ち出しており抜かりはない。ちなみに全部無許可である。
今日は東へとひたすら進む。『第三の爪痕』から先は行ったことがない。最低でも三日は帰らないつもりでいた。
が、その計画はあえなく破られることとなる。
「あ、いた。アルファ! 何してんのこんなとこで!」
がさっ! と茂みの奥から飛び出したベルタが、ついにこちらを捕捉したのだ。
「……それはわたしのことか?」
「当たり前でしょ、他に誰いると思ってんの。ほらさっさと帰るよ!」
「嫌だ」
言うが早いか、全力で走り出す。不意を突ければ撒けると思ったがそんなわけはなく、いつの間にか回り込んでいたベルタに足を引っかけられ顔面からぶっ倒れる寸前で首根っこを掴まれた。
「あっ、おい、放せ! わたしは森の向こうに行くんだ!」
「なーに言ってんだか、よわよわのくせに。武器まで勝手に持ち出しちゃってさ。後でナガツキに説教してもらお」
こうなるともう逃げる手立てはない。いくらじたばたしても彼の拘束を振りほどけたためしはなく、これまで何度も繰り返したように、学園までずるずる連れ戻されるだけだった。
「えーと今日教えることはあれとあれと……そうだ、あれもあったか。時間があったら花園の仕事も教えるからね! アルファ、わかった?」
振り返り、ベルタは朗らかに笑う。
彼こそが、アルファの名付け親だった。
具体的にどういう奴だったかというと、まず「変な奴」と言わざるをえない。
いつものほほんとしていて、妙なところで抜けている。こっちが注意しないと道端の石ころにも躓くくせに、肝心なところは絶対に見逃さない鋭さがある。どこからどう見ても隙だらけなのに、こっちが抜け出そうとして逃げおおせたことは一度も無いのが気に入らなかった。
「――わかる? で、こっちをやったら、次はね」
「…………」
「はいダメー。手すりから飛び降りて逃げようとすんなー」
「う」
アルファからしてみれば、動きも喋りもしない花々の世話のどこが楽しいのかわからなかった。
来る日も来る日も同じ場所で、同じ作業。ろくな変化も発見もありはしない。ナガツキなどは未開の森を切り開く「探索班」の総隊長として、今も冒険を続けているそうではないか。あいつだけずるい。不公平だ。
「……今からでも
「残念でした。役割分担ってのがあんの。ナガツキたちがいない間こっちを放っておくわけにもいかないでしょー?」
「わたしじゃなくていいだろ。というかお前だけで充分なんじゃないのか?」
「あ、そういうこと言う。あのねー、花園って広いんだよ? あたしだけじゃ手が足りないんだから、せめてアルファだけでも手伝ってくれないと。同期のよしみってことでさぁ」
「たまたま同じタイミングで咲いただけだろ。……それに、わたしの方が早い」
「数分とかそこらの違いでしょ!」
「けど先は先だ。一番早くに咲いたっていうナガツキはみんなのリーダーだろ。じゃあわたしだってお前より数分だけは上のはずなのに、どうしてお前がわたしに名前を付けるんだ」
「それはアルファが名前に全然興味なかったからでーす。てか話を混ぜっ返さない! 花のお世話の話してんだからね今! 先輩面したかったらもうちょっとしっかりしてよね、もうっ」
強引に軌道修正された。やっぱり抜け目のない奴だ。
「おーい! ベルター!」
と、花園の外周から声がかかった。ベルタはそちらに目をやって、
「ウォルクじゃん! なに?」
「こないだ咲いた新入り知らねーか? どっか行っちまってさ」
「ああ、あの黄色い子? 演習場の辺りうろついてたよー」
「演習場か! わりい!」
何か約束でもあったのだろう。場所を聞くなり、ウォルクは礼もそこそこに地上付近の演習場へと急ぐ。ベルタはふと思い立って、その背中に声をかけた。
「その新人ちゃん名前なんてんだっけー!?」
「キウ! オレが付けた! 悪くねー名前だろ!」
肩越しに振り返り、ウォルクは誇らしげに笑った。
そんな彼に手を振りながら、ベルタは黄色いチューリップの花人の名を諳んじてみる。
「キウ。――うん、いい名前。ウォルクの奴め、いい言葉拾ったなぁ」
言って笑う彼の顔は、いつどんな時も朗らかで。
それでも、いざ武器を持てばベルタは無双だった。
アルファに戦闘の訓練を付けたのはベルタだ。花々の世話が落ち着き、他に仕事が無い時などは、ずっと演習場で模擬戦闘に明け暮れたものだ。しかし、アルファがベルタに勝てたことは一度も無かった。
「終わり?」
「……まだまだ」
倒れるアルファに、見下ろすベルタ。何度も立ち上がるアルファに、ベルタがにんまり笑って――そんな光景が演習場における一種の風物詩にもなっていた。
あるいは、降って湧いた緊急事態などにも。
警鐘が鳴り響く。「襲撃」を意味するそれに、ベルタとアルファはいつも最初に反応した。武器を取って飛び出し、学園の敷地にまで踏み込んできたモノと対峙する。
「
両手に持った二刀一対の鋸が、高速で回転を始める。ベルタ以外には決して使いこなせない、高性能な専用武器。研究班が開発し、初めて実用化に至った『高純度古代兵装』の第一号だ。
彼がそれを振るう時は常に舞うようで、蒼い軌跡と重なって原型を留めていた敵は一体といなかった。敵陣の真っただ中を突き抜けていながら、ベルタが傷付くことは一度も無かったことを覚えている。
プラントの樹海で花人の生活圏を維持できたのは、ベルタの尽力によるところが大きい。
そもそも最初から彼らの領地が決まっていたわけではなく、花人たちも同じところから咲き生まれたわけではない。居住区を作り、花人を集め、施設を揃えて――長い時間をかけて学園というテリトリーを作ってきたのだ。実のところ、最初の頃は剪定者からこちら側に攻め込んできたことの方が多い。その全てを退けることこそ、生存する上で必要不可欠だった。
外を探索し、プラントのどこかにいる花人を発見・保護するのがナガツキ。
拠点を守り、プラントの一角に『学園』という場を維持するのがベルタ。
この二人を中心として役割を分担し、今日に至るまでの花人の生活様式を作り上げていった。
こんなことがあった。
ある夜、学園を剪定者の群れが襲った。これまでに無い大規模な襲撃だ。巨木の前に絶対防衛ラインを定めた戦闘は熾烈を極め、最後の一体を破壊する頃には日が昇っていた。
折り重なる瓦礫の山から、アルファは苦労して這い出る。濛々と立ち込める黒煙を貫通し、朝の日差しが白い筋を作っていた。綺麗だった。
見ればすぐ近く、折れた木の幹にベルタが座っている。目が合うなり彼は何か言おうとして、たまらず咽る。
「けほ」
ぽっ、と口からも煙が出た。気を取り直して、
「アルファ、生きてる?」
「ギリギリな。……ナガツキはどこだ?」
「あっちでひっくり返ってる」
見れば赤い奴が敵の残骸の上で伸びている。いつも余裕綽々なナガツキも、この時ばかりは精魂尽き果てたと見える。
奇跡的に犠牲者は出なかった。探索組と常駐組が両方とも学園にいたことが大きい。全員の花人が迎え撃つことで、誰も失うことなく撃退できたのだ。
それは、偶然ではない。
「どうしてわかった?」
「んー?」
「今日の探索計画を中止させたのはお前だ。いつもは絶対あんなこと言わないのに、今日だけ違ったのは、こいつらが来ることを見越してなんじゃないか?」
ベルタが珍しく返答に詰まる。図星のようだ。
どうやら信じられるとは思っていないらしい。変な話だからなぁ――とまごつくベルタに、いいから話せと促す。変な奴なのは今に始まった話じゃないし、ベルタの話を信じないわけがない。
ようやく踏ん切りがついたようで、ベルタは空の向こうを見ながら言った。
「北の果てに赤い流星が落ちた」
「なに?」
「正体はわからない。見に行ったわけじゃないしね。けどあんなの今まで見たこともなかったから、なんとなく胸騒ぎがしたんだ。それだけ」
「空から落ちたのか? 『世界樹』の播種じゃなくて?」
「どうなんだろう。『世界樹』の活動だったら何か前兆があると思うけど。でも、なんとなく――」
視線の果てには、朝霧に霞む世界樹。ぼんやりとしたシルエットしか見えないそれは、花人たちが目覚めるずっと前からプラントの中心にある。目を細め見上げるベルタの表情には、ある種の畏怖の気配があった。
「あれを調べたら、いけない気がする」
ベルタは結局、アルファ以外に『赤い流星』について話すことはなかった。
また、これを機に、学園への直接的な襲撃は途絶えることとなる。
以降は学外での散発的な遭遇戦がある程度で、花人側も剪定者への対策を確立させていったため大きな脅威とはならなかった。向こうも花人の縄張りを認識したのかもしれない。この時点では皆、剪定者とは野生動物の亜種のような認識でいた。
こうして、花人たちの生活は盤石のものとなっていく。生き残った日数を指折り数える必要もなくなり、長い時が経って、花人は増え、学園は日を追うごとに賑やかになっていった。
ベルタについてもうひとつ、確実に言えることがあるとすれば――
いい奴だった。
いつも自分より仲間のことを考えていた。
それは、間違いない。
もしかしたら、それがいけなかったのかもしれないけれど。
✿✿✿
最初に目覚めて長い時が経ち、学園も随分立派になってきた。
アルファとベルタの追いかけっこは、そうなってもしばらくは続いた。
脱走を試みるアルファと、手早くとっ捕まえるベルタ。手を変え品を変えて遠出しようとするこちらを、しかしあちらは確実に見つける。その光景はもはや学園の恒例行事とさえなっていた。ならばと、アルファが正式に探索班への同行を願い出ても、受理されることは無かった。ベルタが許可しないせいかと考えていたが、どうやら「勝手にルートを逸れて単独行動しそうだから」という理由らしい。悔しいことに大当たりだった。
生活は順調だ。何の不満もない。
だが――いや、だからこそと言うべきか。アルファの中にはずっと、うっすらとした不安があった。
「思うんだ。いつまで、こうしてられる?」
「こうしてちゃいけないの?」
「駄目なんじゃない。わからないんだ。『世界樹』や、プラントそのもののことだってそうだ。何もわからないまま、なんとなく暮らしてる」
ある時『月の花園』で、そう話したことがある。二人きりだからこそ話せた、アルファの本音だった。
「そりゃ、今の生活は安定してるさ。けどこれがずっと続くなんて言い切れるか? もしかしたらまた剪定者の襲撃があるかもしれないし、もっと酷いことが起こるかもしれない。今のわたしたちは……たまたま運良く生き永らえてるだけなのかもしれないんだ」
「…………」
「――そもそも。わたしたちは、どこから来て、どこへ行くんだ?」
花人はこの森に咲き、意思と言葉を持って活動している。それは何故で、何のためなのか。
答えが得られないまま生きているのは、何かずっと、濃い霧の中を歩いているような気にさえなる。
「……あたしはさ。みんなが幸せなら、それでいいかなって思うよ」
「呑気なことを……。その幸せとやらが、いつ終わるかわからないって話をしてるんだ」
「終わらせないために、毎日必死に生きてる。学園を作って、武器や装備を整えて、周囲を探索して安全を確保して。そうやってみんな安心して暮らせる場所が、やっとできたんだよ」
「これまでは運が良かったんだ! この先何があるかわからない以上、こっちから何もしないわけにはいかないだろ! 今までのやり方じゃどうにもならないことが起こったらどうする!?」
「その時が来たら、またみんなで考える。そうやって乗り越えるよ。何度でも、あたしたちがやってきたみたいに」
話にならない。アルファは舌打ちとともに会話を打ち切る。
――お前ほどの奴が、何をそんなに怖がっているんだ。
ベルタは誰が相手だろうと勝ってきた。学園で彼より強い花人はいない。ベルタが陣頭に立てば、花人は緑深い樹海の闇にだって果敢に切り込んでいけるはずだ。アルファの苛立ちは、ベルタのことを強く信頼するが故のものでもあった。
「アルファ」
立ち去ろうとする背に、落ち着いた声がかかる。
「どうしても、この状況を変えたいの? そうしなくちゃアルファは幸せになれない?」
「……わたしはそう思ってる。この世界のことを、少しでも知らなくちゃいけないんだ。……生きるために」
「そか」
それ以上の追及は無く、ベルタはただ小さく頷いた。アルファは振り返りもせず花園を去る。
それが、二人が交わした最後の会話だ。
この先の出来事について、アルファの記憶はあいまいだ。あまりにもショックが大きいため、出来事を断片的にしか覚えていない。
だから、事実だけを記す。
翌日からベルタは姿を消した。学園のどこにもおらず、誰にも行き場所を告げなかった。
最初のうちは誰も心配しなかった。なにしろ学園最強の花人のこと、何があっても問題あるまい。
しかし、一日、また一日と過ぎていくにつれ、ベルタのことを案ずる声が増えてくる。そもそも彼が『月の花園』にいなかったことなど無く、学園を数日離れるなどということはそれ自体が異常だった。
学外に向けた捜索隊が組まれ、そこからまた数日をかけてベルタを探し回った。いつもの探索ルート、発見済みの遺跡、あるいはコースから離れた森の奥地にまで。
そして、彼らはそれを見つけた。
場所は学園から遥か北の森の奥地。花人たちがまだ名前さえ付けていない未踏査地区に彼はいた。いや、「あった」という方が正しいだろう。
発見されたのは、ただ一輪のワスレナグサだった。
「剪定者の武器によるものじゃない」
その夜のことはろくに覚えていないはずなのに、回収された装備に関する分析だけが、アルファの記憶にこびりついていた。
言ったのは確か初代の研究班長だったように思う。これまで無かった事例に、彼は知的好奇心も忘れ、ただ戦慄していた。
「切れ口が鋭利すぎる。剪定者が装備してる大型のブレードじゃ、こんなことにはならない。いや、他のどんな武器だって、高純度古代兵装をここまで綺麗に切り分けられるはずが無いんだ。――ベルタほどの奴が、どうしてここまで……」
作業台に並んでいたのは、衣服や装備などの、ベルタが身に着けていたと思しきものだ。
それら全てが、形や硬度に関わらずバラバラに切断されていた。
例外は無い。愛用だった武器までもが同じ有様だ。まるで元通りに並べたら、そのままくっつきそうなほど綺麗な断面だった。
結局、ベルタを
アルファだけが例外だった。
恐れを知らなかったわけではない。それを上回る激情に支配されていた。
ただ、森の果てへ。あの日ベルタが行った方角へ。見たこともない伐採者の痕跡を求めて、勝算も何も無いまま、量産型の武器を持って。数人がかりで抑え込まなければ、アルファは本当にどこまでも行ってしまっていただろう――死ぬために。結局ナガツキが抑え込み、ほとんど監禁状態のようにしてまで行動を制限しなければ、アルファが落ち着くことはなかった。
やがて生き残った花人の間で、ある共通の認識が出来上がる。
――樹海の果てには「何か」がいる。
ベルタさえ勝てなかった、恐るべき何か。とりもなおさず花人にとっての「死」そのものが。
今となっては、当時を知る花人はほとんどいなくなった。しかし事実は逸話となり、逸話は噂となり、噂は迷信となり、迷信は掟となって今なお命脈を保っている。綿密に組み上げられた探索ルートは、そのどれもが決して森の果てには行かないように作られている。
安全が確保された巡回ルート。不確定要素は起こりようがない。その外には、絶対に出てはならない。
花人たちが生きているのは、そのような限定された楽園だった。
緑豊かな牢獄の中にいて、アルファはゆっくり、ゆっくりと全てを諦めていった。
変化には喪失を伴う。それは誰かの大切なものかもしれない。あるいは、自分の。ならばもう、余計なことは望むべきではない。ただ生きていればいい。「死なないだけ」の毎日も、それが続くのならば幸せだろう。ベルタはそのことを、身をもって教えたのだ。
何も忘れない。だから、何も変わらなくていい。
いつまでも。
✿✿✿
道すがら、ハルはその話を黙って聞いていた。
長く細い通路が続いている。曲がり角を何度も経由し、薄暗いトンネルをただ進む。
「昔の話だ。もう、悲しいわけじゃない。……けど、たまに考えることがある」
「何を?」
「あの時、あいつがどうして一人で出て行ったのか。わたしにも伝えずに。もしかしたら、わたしが余計なことを言わなければ、ベルタはあんなことをしなかったのかもしれない。……なんにせよ無謀すぎる行動だ。わたしがしようとしてたことが、いかに馬鹿だったか思い知らされたんだ」
アルファにとっては、とうに折り合いをつけた過去の出来事だったのだろう。淀みなく話していたが、最後の出来事について話す時、彼の声がほんの少し揺らいで聞こえた。
自分を責めているのだろうか。
そう思えたからではないが、ハルは話を聞いた上で、自分の解釈を口にした。
「――ベルタは多分、『赤い流星』を探しに行ったんじゃないかな」
「ん……?」
「言ってたよね。襲撃の時に見たって。ベルタはずっとそれを気にしてたんじゃないかなって思うの。あれを調べれば、何か変わるかもしれない。アルファが知りたがっていたことについて、何かの手掛かりになるかしれない……って」
アルファは戸惑いの表情を見せた。
「そうだとしたら、どうしてわたしに何も言わなかった?」
「それは――」
ハルには、ベルタの気持ちがわかるような気がした。同じ状況になったなら、自分だってそうしたかもしれないからだ。
「アルファを、がっかりさせたくなかったんだと思う」
「がっかりだって……?」
「だってそうでしょ? 行ったって何も無いかもしれない。もしそうだとしても、自分一人なら自分が諦めるだけで済むよ。けどアルファに教えちゃってて、それで何もありませんでしたなんて凄くがっかりさせちゃう。変に期待させた分だけ余計にね。だから、自分だけ先に行って、それが何なのか調べようとしたんじゃないかな」
「……そう、か」
もちろん、これはただの推測に過ぎない。ベルタが本当は何を思っていたのかなんて本人以外には知りようがないし、それが語られることはきっともう永遠に無い。
しかしアルファは異論を挟まなかった。前に向き直り、噛み締めるように呟いた。
「だとしても、わたしは、あいつに話してほしかったよ」
「……うん。そうだね」
長く細く、薄暗い通路を行く。幾度もの角を曲がり、分岐を経て、時には階段を上っては下りて。
そうしているうちに、出口のようなものが見つかる。
錆び付いた梯子の上に、四角形のハッチがあった。アルファが上ってごんごん叩いてみるが、ビクともしない。
「ハッチが閉じてる。どうだ?」
「ちょっと見せて」
ハルが代わり、ハッチをロックするシステムを確認する。紋様蝶が反応している。
大丈夫だ。これなら問題なく開くことができる。
「【開放/メンテナンスハッチ】」
がこんっ。
紋様蝶がちかりと光るが早いか、いともあっさりハッチが開く。塵と埃に咳き込みながら顔を出すと、懐かしくすらある陽光に照らされた。順番に這い出て辺りを見渡すと、そこは見覚えがある遺跡の入り口付近だったことに気付く。
「『シェルター』!? ここに出るんだ……!」
「だとすると結構歩いたな。……まさか、遺跡同士が地下で繋がってたなんて」
紋様蝶が近くの群れと合流し、自由気ままに飛び去っていく。導いてくれたことに礼を言い、ハルは彼らを見送った。
「あのさ」
そして、改めてアルファに向き合った。
「少しずつ、色んなこと知っていこうよ。あたしは、あたしが考えたことや見つけたことは、アルファやみんなにちゃんと話す。もしかしたら失敗したり、立ち止まったりもするかもだけど……あたしなりにやってみるから。アルファも、なんでも話してほしいな」
アルファは驚いたような顔をした。
決意に満ちたハルを正面から見て、それから、ほんの少しだけ――
「そうだな」
笑った。
ハルの見間違いでなければ、だが。
「まことに!! 申ッッッッし訳ありませんでしたァッッッ!!!!」
土下座というのは古代から続く伝統的な謝罪方法であるらしい。
なんでも相手より遥か低い位置に頭を置くことで、上下関係の違いを示すのだとか。頭を地面に擦り付けることで大地と一体化し、「自分は咲き誇る価値も無い痴れ者です」という意思表示も兼ねているとかいないとか。
ともあれ、大柄なクドリャフカの土下座にはそれ自体に妙な迫力があった。圧倒されたのはむしろアルファの方である。
「いやわたしは、」
「この度の不手際は自分一人の判断ミスッ! アルファ殿がいることにも気付かず水門を開くなど決して許されることではありません!!」
「だから別に、」
「しかしハカセや他の皆は無関係であり、あくまで自分が先走ったまでのこと!! かくなる上は太古より伝わる謝罪方法にて自分一人が腹をばカッ捌いて」
「話を聞け!!」
アルファはクドリャフカの首根っこを掴み、片手で無理やり引き上げて自分と目線を合わせた。
「……そりゃ水門を開いたのはお前だ。けど、あそこで馬鹿みたいに突っ立ってたのはわたしだ。どっちもどっちってことだ」
「そうでありましょうか……!?」
「不注意はあったかもしれないが、お互い様でもある。だからお前が謝る必要は無い」
「い……言われてみれば、そうかもしれないような気がしなくも……!?」
「そうだ。次からはわたしも気を付ける。それで話は終わりだ」
「なるほど!!!」
手を離され、クドリャフカの背筋がピンと伸びた。
「では今後、互いにこのようなことが無いよう細心の注意をもって作業に当たりましょう! ご安全に!!」
「…………ああ」
頷くアルファはさっきよりよほど疲れているように見え、つい笑いそうになってしまうハルだった。
それから地下施設や碧晄流体の循環経路について報告し、簡単な身体検査を行って、学園に帰投する運びとなった。結果的には、資源・情報ともに過去に類を見ない大収穫だったと言える。スメラヤは大興奮しており、一気に見通しが広がった遺跡探索について早くも計画を組み直している。フライデーもまた、紋様蝶の生態について大きな資料的価値を感じており、今後の調査に高揚しているのが見て取れた。
ああでもないこうでもないと話し合いながら進む一団。その最後尾を、ハルとアルファがゆっくり歩いている。流石に疲れて、しかしどこかすっきりした様子で、のんびりと。
「お前、これから大変だぞ」
「かもね」
「かもね、じゃないだろ。資料班からも研究班からも引っ張りだこだ。前の方じゃ今頃順番待ちの話でもしてるんじゃないか?」
「だと思う。言われた通りにするよ。――でも」
「ん?」
「まずは、花のお世話のことを教えてほしいかな。みんなにはちょっとだけ待ってもらうつもり」
「……そうか」
アルファの反応は淡白なものだった。喜びも嫌がりもせず、「今朝は軽く散歩した」とでも言われた時と変わらぬテンションで頷く。多分、ハルがどういう結論を出してもそうなのだろう。ハルにとってはそれが逆に嬉しかった。
やがて学園が見えてくる。うっすら白んだ巨木の化石は相変わらず微動だにせず、住民の帰還を待っている。ハルはその又のあたりを見上げてみる。ここからでも花園の色彩は見えるだろうか。
そんなハルの横顔に声がかかる。
「おい、ハル」
固まった。
かろうじて返事はできた。
「はい」
「『はい』じゃなくて。花の世話の前にもやることがあるから、先にそっちを教えるって話だ。……何やってる?」
見てわからないか。驚いているのだ。
……などと懇切丁寧に説明できる余裕もなく、ハルはただぽかんとしている。今。アルファの方から。「人間」ではなく。
ハルの驚きをようやく察して、アルファはなにやらバツが悪そうな、照れくさそうな顔をした。
「……変な顔するな。名前ってのは、呼ばれるためにあるんだろ」
そう言い残して踵を返し、先頭集団を追い抜く勢いでずんずん進む。
「あっ、ちょっと! 待ってよ! アルファー!」
慌てて追いかけるハル。追い抜かれた花人が驚いてこちらを見送る。
近付いてくる学園の姿は、いつもよりも懐かしく、頼もしく見えた。
焦燥と共に戻った、襲撃の夜より。まだ何も知らなかった、目覚めの日より、ずっと。
✿✿✿
ある日、花園に見覚えのある花人が訪れていた。
ハルは紋様蝶を用いた実験を終え、研究班にレポートを提出したところだった。アルファは図書館で少し作業があるというので、彼が戻るまで自分が花の世話をしなければならない。そんな折のことだった。
「――ウォルク? ネーベル?」
探索班「キウ班」のメンバーだった、二人の花人。
彼らは花園の片隅にしゃがみ込み、ある花を見下ろしていた。
「……ん、ああ。お前か」
「こんにちはです、ハル」
「う、うん」
正直、ハルは少しだけ緊張した。キウが命を落としてからというもの、二人とはろくに会話をしたことがなかったからだ。
二人は、自分を恨んでいるかもしれない。いつかちゃんと話をしなくてはと思っていたのに、向き合うのが怖くて今までコンタクトを取れなかった。
「え、と。……花、見てるの?」
「ああ。たまには挨拶しなきゃって思ってさ」
二人と並び、視線を追ってみると、思った通りの花があった。
黄色いチューリップ。
芽からまた育ち、もう随分と背が高くなっている。蕾に色が付き始める頃だった。ウォルクとネーベルが彼を見に来たのは、これが初めてのことだ。
また少し沈黙が降りた。気まずい、などと言ってはいられない。ハルは意を決して、
「あのさ」
「なあ」
声が重なった。
お互いにまごついて、「お先にどうぞ」「いえいえ」的な謎の譲り合いが発生する。そこからネーベルが促し、先にウォルクから話すことになった。
「――悪い。オレ、今までお前のこと避けちゃってた」
「……うん。無理もないと思うよ」
「変な顔するな。お前のことが嫌いになったんじゃない。ただ……何を話せばいいのか、わからなかったんだよな。色んなことがありすぎてさ」
それを言うならお互い様だった。
ずっと一緒にいた仲間を失う辛さは、ハルには想像するしかできない。アルファのようなケースもあるし、キウ班に関してはまだ一月と経っていないのだ。
「……あたしも似たような感じだった。どんな顔して話しかければいいかわかんなくて。でも、それで遠ざけちゃってたら意味無いよね」
「お互い様、ですね」
「だな」
言って、少し笑う。
ネーベルが、チューリップの葉を指先で撫でる。
「――それに、キウがどこに咲いてるのかもちゃんと知っておかないとですし。この先のことを考えると」
「この先……?」
「聞いたことはあってさ。花になった仲間が、その後どうなるのか」
花人の命は、いずれ終わる。
死んだ花人は人としての形を失い、ただの花として再び咲く。だから『月の花園』は死んでいった花人たちの墓であり、最後に眠る揺りかごだ。
ハルも知っていることだ。だが、「この先」とか「その後」とはどういう意味なのだろう。
「知らないか? 花になった奴も、その後、もう一度花人として咲くかもしれないんだ」
「え」
一瞬、頭が真っ白になった。
花は、また咲く。
キウが死んだ時、ナガツキが言ったことだ。あの時は花園の一部になることを指していると思っていた。だが、それだけではないとしたら。
――じゃあ、
「キウとまた会えるかもしれないの!?」
「うわっ、と……! きゅ、急に乗り出してくるな! 転んじゃうだろ!」
「あ、ごめん!」
体当たりのような勢いで迫ってしまった。ウォルクは気を取り直して、
「絶対にそうなるわけじゃないけどな。時期とか、花の状態とか、あとは……気候とか? それに『世界樹』の活動も関係あるって聞いたことある。とにかく色んな条件が重なれば、また咲く花人が出るかもしれないって。オレはあんまり詳しくないけど、過去にもそういうケースはあったらしいんだ」
「はい。『花守』がここを守るのは、その瞬間のためでもあるって聞きました。ここにいるみんなは……言い過ぎかもですけど、全員、また咲く可能性があるんです」
「……!!!」
ハルはたまらなくなった。
こんなに嬉しいことはない。紋様蝶を読めた時よりも、遺跡の秘密を暴いたことよりも嬉しい。許されるなら、この場で飛び上がって大声を出したいくらいだ。
「ん~~~……」
しかし、ウォルクたちの表情はそれでも浮かない。
「へっ? ……どうしたの? 嬉しくないの?」
「――色々考えてたんだけど、オレたち、どんな顔してアイツに会えばいいのかな」
助けられなかったこと。
逆に、守られてしまったこと。
キウが自らを犠牲にしてウォルクたちの命を繋いだのは事実だ。彼らの心には、そのことへの罪悪感や後悔が残っているのだろう。
「なんだ。だったら、そんなの決まってるよ」
「そう、か?」
だけど、また会えるのなら。
言うべきこともあるかもしれないが、何よりもまず。
「おかえり。これからもよろしくねって。――それでいいんじゃないかな」
ウォルクとネーベルは、目を丸くしてハルを見ていた。
ややあって目を見合わせ、笑う。
「……そうだな」
「ですね」
花はまた咲く。そうしたら、また会える。
少なくとも可能性はある。それは希望だった。
黄色いチューリップの蕾は、じきに花開くだろう。
✿✿✿
【起動】
【各部駆動状況確認/……/…………/完了】
【記憶領域の整合性をチェック/完了/問題なし】
【光学神経及び量子演算装置稼働/第1302番ビオトープとのシステムリンクを開始】
【――以降、管理権限は本機に譲渡される】
廃墟の奥底だった。
花人たちが『遺跡』と呼ぶ場所と似通っているが、それよりも冷たく、全体に生気が乏しい。花人はおろか紋様蝶もあらゆる蟲も動物も、およそ生物と言えるものの気配もありはしない。
そんな中、ある者が目覚めた。
姿は少女に見える。しかし体表面に血の気は無く、顔は能面のように表情が無い。生き物というより人形のようで、裸足で歩くたびにかつんかつんと硬質な足音がした。
少女は蒼い瞳を明滅させ、言葉もなく何かのコマンドを飛ばした。
瞬間、廃墟のまだ生きていたシステムが一斉に反応し、全体に通電して全ての隔壁を開く。埃っぽい風が吹き込み、少女はその中を無言で突き進む。
やがて外が見えてくる。
少女の眼前に広がるのは、緑豊かなプラントの樹海ではない。
見渡す限りの荒野。草ひとつ生えていない砂漠。倒壊し、半ば土に埋もれた何らかの建築物――かつてそこにあったであろう文明の残滓。獣も鳥も、蟲も魚も人も、花も存在しない。この世界を支配するのは、死の静寂そのものだ。
少女はその光景に眉ひとつ動かさず、視線をついと上げて、地平線の果てを見通した。
何かに反応している。肉ならぬ体で観測を続け、双眸は妖しく光り、彼女にしか認識できない「何か」を確実に掴んだ。
そして、時が止まったかのような無表情が、ようやく動く。
「いた」
笑ったのだ。
彼女の体を構成する物質は、その全てが剪定者のものと同じだった。
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます