第6話 少しずつ
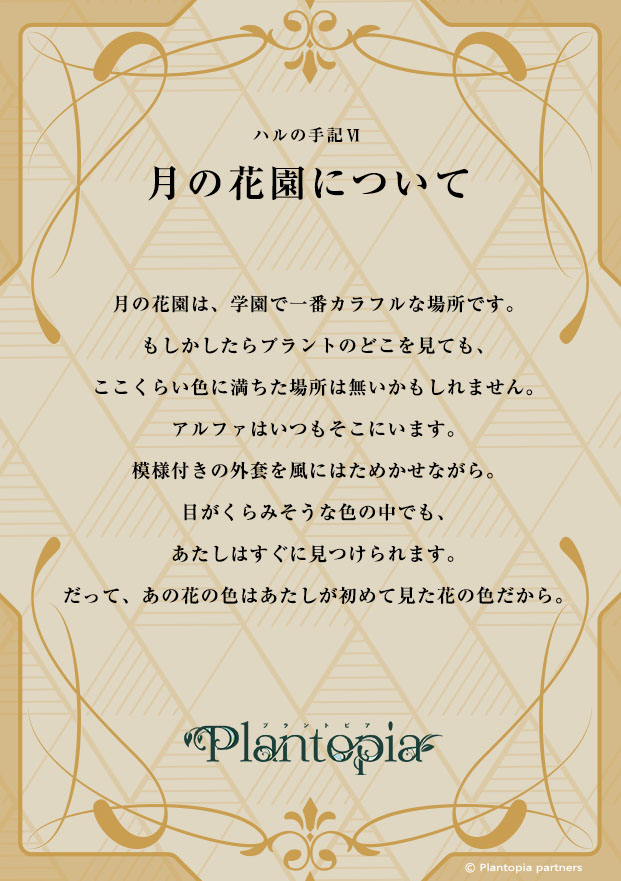
花人たちの間で『第一の指』と呼ばれる遺跡は、学園から徒歩圏の森の中にある。
外に出始めた若い花人は、大体ここを最初の目的地とする。そこから活動圏を広げ、プラントの広大な樹海に慣れていくというから、「第一の」という呼び名も言ってしまえばそのまんまである。横着な奴が中に荷物や装備を置きっぱなしにしていることもあって、実質的に学園の一部みたいな扱いになっている。
「――という場所だが、もう何も残ってないわけじゃない。もちろん目ぼしい機材は漁り尽くしたが、定期的に『湧く』資源もあってね。今回はそれが目的だ」
ハルは朝靄のけぶる森を進みながら、先頭を歩くナガツキの説明を聞いている。とはいえ、内容の半分も頭に入ってこなかった。
気まずい。
すぐ隣をアルファが歩いている。今回は抜き身の剣を無造作に担いでいる。「あの夜」に使った大斧ではなく、全員に支給される汎用装備のようだった。見た感じいつも通りのように思えるが、どう声をかけていいのかハルにはわからなかった。
「ハル。君はちゃんと休んだかな?」
「え、あ。はい、なんとか」
花園での一件の後、ハルはフライデーらの手で自室まで担がれ、問答無用でベッドに放り込まれた。張り詰めていたものが切れたのだろう、そうなると泥のように眠りに落ちて、今朝目覚めてやっと空腹を思い出したほどだ。
「で――なんでしたっけ、そのアレ」
「碧晄流体。名前の通り液状の資源で、用途は様々だ。遺跡でしか採取できない」
「なるほど……。アルファは知ってる?」
「知ってる」
一言。それ以上会話が続かない。
ハルはもう一度、挑戦してみる。
「実際に見たことある?」
「ある」
やはり、一言。こっちの質問が良くなかったかもしれない。
「えっと……どんなのだった?」
「光る水」
ばっさり一言である。
やっぱり、気まずい。
かといって黙っているとそれはそれで息苦しく、今度はナガツキに声をかけた。
「にしても、学園長。どうしてあたしも連れてきてくれたんですか?」
そもそも彼が学外に出るなんて思いもしなかった。今回のこともお忍びらしく、学長室に窓から見える同サイズのカカシを立てての出発だった。そんなことしていいのかと思ったものが、「内緒だ」と微笑むナガツキには普段と違う童心めいたものを感じた。
「なに、大した理由じゃない。君も何かしていないと暇なのではと思ってね。それに――」
木々が開けた、明るい場所に出る。
「遺跡に触れてみれば、新たな発見もあるかもしれない。さあ、着いたよ」
湖のほとりにある『第一の指』は、指と言うより大きな墓標のようでもある。
表面は錆と蔦に覆われ、誰にも管理されないまま半ば自然と一体化している。高さは十数メートル。わずかに湖側に傾いており、波紋ひとつ立てない水面の鑑に映って遠目には「く」の字に見えた。
近くで水を飲んでいた鹿たちが、こちらに気付いて逃げていく。遺跡の扉は開け放たれていて、花人が用意したであろう立札やメモ書きがあちこちにあった。
「ここが……」
「後は流体を採取するだけだ。気になるものがあったら、好きに見ていてくれて構わない」
一抱えほどもある保存用のタンクを手に、ナガツキはさっさと中に入っていく。ハルが慌てて追い、アルファもそれに続いた。
「うわぁ……!」
中は、意外なほどに明るかった。
通路には蛍の蟲籠や蓄光性の苔玉が配置されており、ランタンが無くても奥まで見通せる。入口付近にもあったメモ書き、伝言板らしきもの、探索計画を記した地図などが壁に貼られていかにも賑やかだが、整備中らしき武器や装備がそこらに放置されているのはどうなのだろう。研究班が見たら何と言うか。
「なんか……ほんとに、前線基地って感じなんですね」
「出入りが頻繁だからね。何度片付けろとの通達があっても改善されないから、もう諦められてる」
以前入った『シェルター』のような、半ば打ち捨てられた場所とは大違いだ。学園と遺跡が混ざり合ったかのような、奇妙な風情があった。
アルファはさっきから何も言わず、数歩後ろの最後尾にいた。徹頭徹尾興味なさげだが、口元の覆いをしっかり外しているあたり、護衛としての警戒は欠かしていないようだ。
「――あ」
紋様蝶。
薄ぼんやりと光る白い蝶がちらほら見られる。花人の用意した蜜溜まりに留まっていたり、左右の薄暗い小部屋の中を飛んでいたりと、気ままな様子だ。
紋様蝶は、花人とは別の連絡手段を持っているらしい。つまりは独自の知覚能力を持っていることになる。遺跡を好むのも、そうした生態によるものなのだろうか。
「よそ見するなよ。転ぶぞ」
「あっ、うん」
反射的に返事をした後、すぐ驚いて振り返った。
が、アルファはもうそっぽを向いていて、つまらなそうに壁の落書きを見ている。全身から「話しかけんな」オーラが出ていた。そっちから声をかけてきたのに。
そうこうしているうちに目的の部屋に着いた。一階突き当たりの大部屋は意外と広く、学園の教室くらいはありそうだ。
碧晄流体の「ポンプ」は、部屋の中心にあった。
「ここには、定期的に一定量の流体が充填される。大した量ではないものの、その補充という意味でも『第一の指』は重要な場所と言える」
ポンプは太い柱のような形をしている。植物の根にも似た幾本ものパイプが伸びて、用途もわからない機材に繋がれていた。中心に分厚いガラスの覗き窓があり、そこから淡い光が漏れ出ているのが見える。
「用途は様々、って言ってましたけど……たとえばどんなことに使うんです?」
「薬だよ。この流体には、
思い出した。あの夜、キウたちが応急処置に使っていたのが、この流体というわけか。
「他にも、遺跡由来の装置には、これを燃料とするものも多い。一部の装備の動力源として使う上に、研究室の各種機材を稼働させる上で不可欠だ」
「はぁ~……すごく便利なんですねぇ」
と、気になることがあった。
「じゃあ、これってどうやって供給されてるんですか? このポンプに補充されるって言ってましたけど、そもそもの大元は……?」
「わからない」
言って、ナガツキは鋼鉄のポンプの表面を撫でる。
「この種のポンプは各所の遺跡にあり、採取後も時間を置けば再補充される。我々は経験則としてその現象と流体の効果を知り、有効に活用しているが、これがどういう原理の何物でどこからどう来ているのかは誰も知らないんだ」
ハルはナガツキの横に並び、覗き窓から中を見てみた。確かに中で、仄かに光る液体が循環している気配がある。アルファは壁に背を預け、そんな二人を黙って見守っていた。
ナガツキがタンクをセットすると、ポンプ全体が一瞬小さく唸り、自動で流体の注入を開始した。
「しかし、事実としてこの流体はきわめて有用で、今や我々にとって無くてはならないものとなっている。そういうものだと受け入れているよ。ある意味、森の自然と同じものかもしれないな」
「自然……ですか」
「木々も水も空気も、太陽の光さえ、我々はその原理と成り立ちを理解できていない。ただ、その恵みを享受している。でなければ生きていけないからだ。――ふむ」
注入が終わった。ナガツキはタンクを取り出し、軽く揺すってみる。ハルならば両手で抱えなければならないサイズの代物だが、ナガツキはまるで小石を弄るかのようだった。
「少ないな。やはり早すぎたか。これでは量が足りない」
「いきなり採るからだ。本当ならもう三、四日は開けないとタンクいっぱいにはならないぞ」
「取り急ぎ必要になってしまったからな、致し方ないさ。アルファ、お前も使うんだろう?」
「……使える分があればな」
二人の会話を聞きながら、ハルは考えてみる。
逆に言えば、数日開ければ勝手に必要充分な量が供給されるということだ。
ポンプへの補充は、遺跡の機能か。だとすれば流体周りのシステムはまだ生きていることになる。
そもそも流体とは独自に生成しているのか? 自然発生したものを汲み上げているのか? その仕組みは、各遺跡ごとに独立しているのだろうか。それとも繋がっているのか。元々は何に使われるものだったのか? 誰が、何の目的で?
「気になるかい、ハル」
「正直、すごく。どこかに手がかりって無いんですか? ここの資料とか……」
「君を連れてきた理由もそれだ。まさに、ここに古代文字が記されている。私には半分も解読できないが、君になら読めるのではないかな?」
「!」
見れば、幾つかに項目分けされた小さな文字がポンプに刻印されていた。おそらく簡単に消えないようにするためだろうが、それでも長い年月で表面が掠れ、錆びつき、読めなくなった部分もある。
だが、読める部分はわかる。
「――より……される……。非常の、際には――」
――P.P××循×液、第Ⅰ×補給×。本薬×は×××より生成される××安定環流に×××ものです。施設維持の際には××××、また非常の際は管理者権限のもと××××××。システムリンクを再××し××××――
「読めるのか?」
いつの間にかアルファが傍に来ていた。顔を並べ、目を皿のようにして文字を注視する。しかしアルファには、そのほとんどの意味がわからないようだ。
「消えてないとこは、なんとか」
「意味は? わかるのか?」
「どう、だろ。知らない用語が多すぎていまいち。でも――」
重要と思われる項目にはそれとわかる印が付いてある。途切れ途切れながら、声に出して読み上げてみる。
――管理にあたっては、×××プロトコルに基き、地下××階のメンテナンスレベルを開放のこと。なお必ず××クラス××員同行のもと、指定周波数の量×暗号コマンドを――
「地下?」
二人の声が重なった。
地下とは、この『第一の指』のことを言っているのだろうか?
顔を見合わせる。注意書きに集中しすぎて気付かなかったが、二人ともかなり近い。横を見るなり鼻が当たるような間近にアルファがいた。
「わっ!?」
「っ……!」
お互い後ずさる。
「え、あ、ごめ」
「いや、まあ、その」
お互い言葉が出てこず、なにやら微妙な空気が降りた。そんな二人をナガツキはのほほんと見守っている。アルファの助けを求めるような視線に、ただ一言、
「ああ、構わんよ。続けてくれ」
「何をだ!」
ああびっくりした――胸に手を当てて、どうにか呼吸を整えるハル。
それはともかく、文面だ。ポッドに書かれていた気になる単語。
「学園長。そこに『地下』って書かれてました」
「……ああ、そのようだ。しかしこの遺跡には……」
「地下に続く階段なんて無い。あればとっくに誰かが気付いてる」
「そうだな。もしそんなものがあるとすれば、別のルートから――」
ひらり。
「――へ?」
虚を衝かれて、ハルが間抜けな声を上げる。
紋様蝶がこちらに飛んできていた。
一匹ではない。二匹、三匹、四匹――通路のあちこちを気ままに飛んでいた奴らが集まってきていた。それ以上何をするでもなく、天井付近を漂い始める。
「なんだこいつら? いつもはここまで来ないのに……」
「何か変化があったということだろうか。しかし、何が」
ハルは、その翅の光に目を奪われていた。
思い出すのは『シェルター』での一幕。陰から飛び出た紋様蝶の群れに腰を抜かし、キウたちに笑われたものだ。
あの時。
驚いたのは、単純にいきなり飛び出されたからでもある。けれどそれ以上に、何か感覚に訴えかけるものもあった。
何か、見えたような気が、していたのだ。
「……どうした?」
「ハル? 何か気になることでも?」
二人の声も、今のハルの耳には入らない。
読めそうなのだ。こうして注視していると、あの光る翅に、法則性を持ったパターンのようなものが――
――×××プロトコルに基き、
――量×暗号コマンドを――
「――――【command:rev.001/システム
紋様蝶が、その色を変えた。
色は鮮やかな青。一匹がそうなり、他の個体も応じて変色する。
「……なんだって?」
アルファとナガツキには、その意味がわからない。ハルは次々に集まる紋様蝶のパターンを目で追っていた。そうして拾える断片から、意味が通ると思われるものを直感で口にする。
「【各レベル稼働状況測定/一部リンク
「おい、何言ってる。お前さっきから変だぞ、おい……!」
「待て」
ハルを揺さぶって止めようとしたアルファを、ナガツキが抑えた。集中を通り越して夢を見ているようなハルと、見たことのない発光パターンを展開する紋様蝶に、彼はひとつの確信を得ていた。
「……ハル。紋様蝶の交信方法が、わかるんだな?」
読める。
蝶の動きが規則性を見せた。ハルの「号令」に反応し、沈黙していた各機器にアクセス。
一度手がかりを掴めば早かった。これらの蝶の「紋様」とは、つまりそのまま特定の言語パターンを示している。一語、一句、一節で細かく区切られた言語には固有の意味があり、誰かが解読し、必要なコマンドを飛ばせばそれを実行する。
たとえば、こんな風に――
「【開放/
がこんっっ。
遺跡全体に伝わる振動と共に、何か大きなもののロックが外れる音がした。
次の瞬間、足元が割れた。
ポンプを中心とした半径五メートル範囲の床が、左右にゆっくり開き始めたのだ。
「――あれ?」
「馬鹿っ……!」
よろける。危うく落ちそうなところだった。アルファがハルを引っ張り、部屋の隅まで飛び退いた。
そこでようやく我に返る。蝶を「読む」のに夢中になっていた。
「あ――ありがと」
「そんなのいい。……それよりお前、これは……」
床が開き、下へと続く螺旋階段がそこにあった。
どこに繋がっているのかもわからない。普段使っていたポンプはほんの一部に過ぎず、それは遥か下に長く長く伸びていることが初めてわかった。
「――『地下』、か」
ナガツキが感じ入ったように呟く。コマンドを実行し終えた紋様蝶は元の白色に戻り、何事も無かったかのように自由に飛んでいた。
✿✿✿
ハルたちはまず学園に戻り、専門知識を持つ研究班に報告することにした。
正門前でカカシを片手に仁王立ちしていたフライデーには肝を冷やしたが、ナガツキ本人への一時間強の説教のみで、ハルとアルファにはお咎め無しだった。
その後、急遽『第一の指』地下施設の調査隊が組まれた。
メンバーは、まず発見者であるハルとアルファ。それからスメラヤを中心とした研究班と、まとめ役のフライデーだ。ナガツキはお留守番となった。細心の注意のもと、調査に当たる。
「おおおおっ! これは! 発見でありますなあっ!!」
空のタンクを山と抱え、クドリャフカは無邪気に目を輝かせる。
「ハカセ! どこから取り掛かるでありますか!? ハカセーッ!?」
スメラヤの姿は見えない。どこに行ったのかと思えば物陰からぴゅんと出てきて、
「信じられませんまさかこんな施設がこの場所にあったなんて」右へ、「しかし周辺の地形から鑑みると」左へ、「この場所の役割としては」奥へ、「でも」手前へ、「すごい」とにかく、「わー」
「ハカセ!? お待ちくださいハカセ! どこへ行かれるのかーッ!!」
スメラヤの興奮が落ち着くまでに、また少し時間を要した。
そうなるのも無理のない光景ではある。長い階段を下りた『第一の指』の地下には、信じられないほど広いドーム状の空間が広がっていた。
面積の大部分は、碧晄流体の広大なプール。地上部分まで伸びるポンプを中心として、普段採取できる分のゆうに数百倍にも及ぶ量が溜め込まれていた。それらしき照明器具も無いのに全体が薄ぼんやりと明るいのは、流体が光っているからだ。
まずは施設の調査し、安全を確保する。碧晄流体は一度で採りきれる量では到底ないため、当分はこの場所に通うことになるだろう。
アルファは少し離れた位置から、花人たちがわちゃわちゃするのを見守っていた。
ハルはスメラヤと一緒にいて、この場所についてあれこれ話し合っている。紋様蝶のことについても質問を受けているようだ。
「――驚きました。今まで私たちが見ていたのは、この遺跡のほんの一部分なのですね」
横から声がかかる。目だけ動かして見ると、記録用のファイルを持ったフライデーが立っていた。
「こうして話をするのは初めてですね、アルファ。私は――」
「フライデーか」
先回りすると、彼は目を丸くした。
「私を知っているのですか?」
「花人のことは全員知ってる」
「光栄です。花守のあなたにお見知りおきいただいているとは」
細い指先でファイルにあれこれ記しながら、隣に立つフライデー。アルファも、相変わらず仏頂面ではあるものの、嫌そうな反応は示さなかった。
「この発見は喜ばしいことですが、ある意味、今後が大変かもしれませんね」
「どういう意味だ」
「最も近くの『第一の指』でさえこうなのですから、他でも同じことが考えられます。今まで調査済みだと思っていた全ての遺跡に新たな可能性が浮上したということです。ここと同等かそれ以上の施設だとしたら、一つ増えるだけでも大変ですよ」
大変というのは、当然、嬉しい悲鳴だ。努めて冷静さを保とうとしているが、フライデーの声色には隠しきれない高揚があった。特に今回の一件は「大量の碧晄流体の貯蔵庫」という一点のみにおいても、ここ最近で最も大きな朗報と言える。
「ハルは、お手柄でしたね」
「かもな」
「彼の――ああ、いや。人間の女性は『彼女』と呼ぶのが言葉として正しいんでしたか。とにかく、彼女が来てから、少しずつ変化が起こっているようです」
「……かもな」
良いことにも、悪いことにも、そこには必ずハルが関わっている。
であればやはり、彼女こそが変化の中心にいると考えるべきだろう。
これが終わりではない。今後、また何かの変化が起こるかもしれない。次が良いか悪いかどちらに転ぶかは、誰にもわからない。
「――だから、困るんだ」
「……? 何か言いましたか?」
小さな独り言がフライデーの耳に届くことはなかった。 「なんでもない」とだけ返し、アルファは踵を返す。花人が多く集まるところは、どうも落ち着かない。
「アルファ?」
「考え事がしたい。少し一人にしてくれ」
そうですか――と言いかけ、フライデーはふと思い出したように声をかける。
「ああ、そういえば。ハルは花園の仕事を手伝ったんでしょう?」
アルファは驚いて振り返った。どうしてフライデーが知っているのだろう。
「図書館で連日調べ物をしていましてね。ずっと園芸に関する書物を読み漁っていましたよ。休めと言っても聞かないので、最終的には半ば無理やり寝かせましたが……どうでした? 彼女は成果を発揮できましたか?」
「…………」
「アルファ?」
「……いや、別に。大したことは起こってない。いつも通りだった」
それだけ答えて、今度こそ離れる。後ろでフライデーが首を傾げるのがわかったが、アルファはそれ以上、何も言わなかった。
流体溜まりをぐるっと回り込み、対岸のあたりでアルファは一息ついた。向こう岸ではスメラヤら研究班が調査を続けており、複雑怪奇な機材を慎重に弄っている。
すぐ近くにこれだけの流体があれば、今後当分は在庫に悩まされることもなくなるだろう。ある程度は贅沢に使えそうだ。
脳裏によぎるのは、潰れてしまった蒼い花。ハルの顔。つい今しがた聞かされた、フライデーの話。
―――
そう思った辺りで、すぐ傍の壁から低い音がした。
「ん?」
何か重いものが動くような音だった。試しに触れてみると、分厚い壁越しにわずかな振動を感じる。奥に空間があるのだろうか。
アルファは知らなかった。同じ時、対岸で研究班がある機器を操作していたことに。
それはこの地下施設の制御パネルで、ここに集まる流体を管理するためのものであること。
このプールは独立したものではなく、他所から流れてくる大量の流体を一時貯蔵する施設に過ぎないこと。
そして、今入力されたコマンドが、他区画へと繋がる「水門」を開くスイッチであることに。
「…………んん?」
どばっ!!
突然、碧晄流体の瀑布に晒される。
壁かと思っていたのは巨大なゲートだった。アルファはちょうど、大量の流体が流れ出す門の真ん前に立っていたのだ。
たちまち前後左右がわからなくなる。何も見えず、わけもわからないまま激流に呑み込まれた。
「ちょぉっ!?」
ハルは慌てた。古代文字に集中している間に、水門を開くスイッチが入っていたのだ。
そこまではいいが、アルファが水門の前に立っていたとなると話が変わる。あっという間の出来事だった。
「ぬお!? アルファ殿がいたでありますか!? 何故あんな場所に!?」
スイッチを押したクドリャフカがうろたえている。水門からは今なお新たな流体が注がれ、プール全体に渦を作っていた。アルファがどこにいるのか、ここからではよくわからない。
渦の動きを見ながら、ハルはすぐさま決断した。
「【connect/bt0024-0039-0106
「ハ、ハルさん!?」
「水流のモニターしといて! あたしが合図するから、それまで水門は閉じないで!」
「あ、合図ってどうやって、ちょっ待――ああっ!?」
数匹の紋様蝶をリュックに入れるが早いか、ハルはスメラヤの静止も聞かずに飛び込んだ。
たちまち視界が光に包まれる。流れに身を任せ、奥へ、奥へ――
✿✿✿
もう、自分がどこをどう流されているかもわからない。
アルファに知覚できるのは、360度全方位どこを取っても光、光、光。生まれては弾け、豪速で過ぎ去っていく無数の泡がまるで星のようだった。
焦る気持ちは無かった。
ただ、運が無かったな、と思うだけだ。
これで終わりなら、そんなものかもしれない。驚くほどあっさりと諦めがつく。ただ、間違って水門を開けた奴が、変に気を病まなければいいが。
こうなったらもがいても無駄だ。思えば、どんな状況でもそうだったかもしれない。いくら悪足掻きをしたところで意味は無いのだ。全てはプラントの、この深い森の、変化が無い学園の日常に戻る。誰がいなくなっても、誰が加わっても。
ただ流されるだけ。それでいい。終わるときには終わる。何の不満も無い。
それでいいと、思っていたのに。
(――?)
いきなり誰かに手を掴まれた。
その手は思いのほか力強く、有無を言わさぬ勢いで引き寄せてくる。なんだ、誰だ。諦めきっていたアルファはむしろ困惑した。まさか幻覚? その割には真に迫っていて、光に包まれた視界にぼんやりと、見たことのある顔が――
「大丈夫!?」
気が付けば、濁流から助け出されていた。
ハルが顔を覗き込んでくる。頭からつま先までずぶ濡れになりながら、自分のことよりもこっちを心配しているようだった。
アルファは仰向けになったまま、とりあえず、最初に気になったことを指摘する。
「……お前、頭から液が出てるぞ」
「えっ」
言われて初めて気付いたらしい。どこかにぶつけたのか、ハルの右眉の上あたりがばっくり切れていて、赤い体液――『血液』というらしい――が流れている。
「おわーーーっ!!? めっちゃ切れてる! めっちゃ切れてる!!」
「お、おい暴れるな! 余計酷くなるぞ!」
とはいえ幸い、傷は浅かったようだ。
服の切れ端をハチマキのように巻くことで、なんとか事なきを得た。頭の傷は出血こそ派手だが、止血さえしてしまえばなんてことはない場合が多い。
「――は~びっくりした。こんなに血ぃ出したの初めてかも」
「本当にもういいのか? 流体――は、人間には使えないのかな」
「多分。あたしもあの中泳いだのに、この傷は治ってないし。アルファは? なんともない?」
「わたしは……別に、大丈夫だ」
対するアルファは全身にかすり傷一つ無い。プラントの花にとって、碧晄流体はそれ自体が「薬」のようなものだ。まさかこれほど大量の流体に体ごと突っ込むとは思わなかったが、むしろ流される前よりも体の調子がいいような気がする。
「そっか、よかった!」
「……ああ」
……………………。
「お前馬鹿か!!?」
「えっ!? は!? なに急に!?」
「いきなり飛び込んでどういうつもりだ!? たまたま合流できたからいいものの、お前までどっかに流されるかもしれなかったんだぞ!」
「そんなこと言ったって、ほっとけるわけないでしょ! じゃあ黙って見てればよかったの!?」
「当たり前だ! 誰がこんなこと頼んだ!? 要らん無茶するなって――」
「やだ!!!」
思わぬ剣幕に、アルファは思わず圧倒された。
真正面からこちらを見据えるハルの目には、頑として譲らない強い意思の気配があった。
「……やだ」
「二回言わなくていい」
「目の前でアルファがあんなことになって、それで何もするななんて、やだ。誰がなんて言ってもあたしはこうしたよ」
「……ふん、この前の借りを返したつもりか? あれはわたしが勝手にやっただけだ。いちいち気にするな」
「じゃあこれもあたしが勝手にやったことだもん。そっちだって気にしないでよね」
むう。
流石に反論ができなくなった。むっつり押し黙るアルファ。
続いてハルは背負っていたリュックを下ろす。ゴム質の樹葉を表面加工に使っており、水中でも中に水を通さない高い防水性を備えた代物だ。
「――それに、無茶なんかじゃないよ。この条件なら大丈夫だと思ってた」
「なに?」
「周り見て」
今まで気にする暇こそ無かったが、ここはつい先ほどまでいた流体のプールではなさそうだ。
チューブのように伸びる、長いトンネルの中腹のように思える。学園の回廊にも似ているが、それよりも直径が大きい。二人が今いる場所は壁際の小さな足場で、すぐ下を碧晄流体が川となりどうどうと流れていた。右には滝、左を見ればゆるくカーブしたトンネルがどこまでも伸びている。碧晄流体は、このチューブの中をずっと流れていくのだろう。
「あそこのプールはただの中継点みたいなものだと思う。流体はこのチューブを通って別の施設に流れていくんだよ。多分そんな風にして、ぐるぐる循環してるんじゃないかな」
「じゃあ、あの水門は……」
「別の……つまり、近くの遺跡と繋がるチューブ。あそこから流れてきたのがプールに溜められて、別のとこに送られる。あれが入口だとすれば出口もあるはずで、水流はそっちに向かって動いてた。流れに身を任せれば、アルファのいる方に行けると思ったの。当たってたね」
「どうしてわかる?」
「古代文字を読んでたらわかった。読めないところもいっぱいあったけど、かき集めた情報を総合すれば、そうなんじゃないかなって。だから水門を動かしてみようとしたんだけど……」
そこにたまたま、間抜けな花人が立っていたというわけか。アルファは自分の迂闊さにほとほと嫌気が差した。
リュックが開かれ、中から数匹の紋様蝶がひらひら飛び出てくる。それらはハルのコマンドを受け、アルファの知らないパターンで明滅を続けた。次の瞬間、どこかで何かが開く音がした。
「――これでよし。これだけ長い水路なら、等間隔にメンテナンス用の通路があるはず。スメラヤたちにも位置を伝えてるから、ちゃんと戻れるはずだよ」
びしょ濡れのハルは、心なしか楽しそうだった。
「この地下施設は生きてるんだ。流体の循環システムとか、換気機能がちゃんと動いてる。もしかしたら全部の遺跡が地下で繋がってるかもしれない! 大発見だよアルファ!」
――それにしたって、どんな危険があるかもわからなかったろうに。
流れができていると言っても、その先が安全だという保証など無かった。水路が枝分かれしているかもしれないし、行き止まりだったかもしれないし、異物を排除する装置などあった日には目も当てられない。
なのに、こいつは。
「……アルファ? 聞いてる? どうしたのー?」
「聞いてるよ」
無茶。向こう見ず。お節介。こうと決めたら脇目も振らない。
そういう奴に振り回されるのは、いつも大人しくしている方だ。
けれど、そういう奴がいなければ、変わるものも変わらないのかもしれない。
アルファは立ち上がり、外套の水をざっと払った。身体的には問題無いどころか絶好調だ。むしろハルの方を気遣う必要がある。
「行こう。みんなにはこっちの位置がわかるんだな?」
「大丈夫。
「じゃあまずは見つけられやすい場所に出ないとな。こんなところにいちゃ誰も来られやしない」
ハルの顔が「ぱぁっ」と華やいだ。跳ねるように立ち上がり、リュックを背負い直す。その頭の上あたりを、紋様蝶がひらひら飛んでいる。
どこかから、冷たい空気の流れる気配がある。風を追えばどこかへと出られるはずだ。二人、並んで歩きだした。
✿✿✿
開かれたハッチをくぐると、やはり人が通れる通路に出た。いくつもの鉄の扉に区切られた細い通路は、小型の遺跡にはよくある光景だ。
アルファは振り返り、ハルがちゃんとついて来ていることを確認する。ふと、その頭が気になった。
「……その傷」
「ああ、これ? もう血は止まってるから心配いらないよ」
「そうか。なあ、それ……『痛い』か?」
ハルは即席の包帯に軽く触れ、もう乾き始めた血を指でなぞる。
「んー、どうなんだろ。気にし出したら、まあ、気にはなるけど」
「けど?」
「まあ、そんなにかな。わたわたしてたら、痛いのなんて忘れちゃった」
言って、ハルは照れくさそうに笑った。
そうか――とだけ返して、アルファは歩を進める。うん、と頷き、ハルが続く。一人でいる時よりも歩調を緩める。
「――お前が踏んでしまった、あの花な」
歩きながら切り出す。これも、ちゃんと言わなければならないことだと思ったからだ。
「あ……」
後ろからハルの緊張が伝わる。肩越しに振り返り、しょぼくれた顔を見返した。
「そんな顔するな。……別に、どうしようもないってわけじゃないんだ。碧晄流体を使えば治せる」
「ほんと!?」
「ああ。けど、今はちょうど学園の在庫に余裕が無かった。だからここに採りに来る必要があったんだ。あんなに大量に見つかるとは思わなかったけどな」
「どうやって治すの? 流体に浸けるとか? それとも水の代わりに注ぐの?」
「そういう使い方もするけど、損傷が激しい部分には別のやり方がある。なんというか、こう……一回、封じるんだ」
「『封じる』??」
これに関しては口では説明しづらい。身振り手振りを交えてみるが、具体的な手順は実際に見た方が早いかもしれない。
「琥珀って知ってるか? あれと同じ風にして、樹脂と混ぜた流体を固形化させる。その中に傷付いた花を封じ込める。全体を包み込むことで、傷付いた部分を癒すんだ。終わったらそれごと植えればいい。流体が融けて、花が地面にまた根付く」
「おお……じゃ、じゃあ……!」
「少し時間はかかるけど、元に戻る」
ハルは、心からの安堵を見せた。
笑ったと思えばしょんぼりして、そうかと思ったらまた笑って。表情がころころ変わる奴だ。
人間の相手は初めてのはずだが、どこか懐かしむような気持ちもあった。同じように感情がころころ入れ替わる奴が昔いた。よく笑って、よく怒って、よく喋った。自分とは大違いの奴が。
「そういえばさ。ずっと聞きたかったことがあるんだけど」
「何だ?」
「あの
そう聞かれることはアルファも予想していた。
けれど、その上で、詰まった。
返事をしようとして、言葉に迷う瞬間が確かにあった。
「……あー、もし話したくなかったら、無理にとは言わないけど」
「いや、いい。多分そのうち話さなきゃいけなかったことだ。――ただ、少し、どう言えばいいかわからなかった」
「そっか」
ならばと、ハルは待った。催促も静止もしなかった。
少しの間が空く。嫌な沈黙ではなかった。足音の他には、何も響かない空間。細く長い通路を進み、前を見ながら、アルファは自ら過去を掘り返すことを決断する。
「あいつの名前は、ベルタ」
「『ベルタ』……」
「ワスレナグサだ。
忘れてはいない。だが思い出そうともしなかった。
あいつがいた時といない今とでは、状況に何の変化も無い。日は昇り、森は深く、学園も花園も変わらずあって、花人たちも変わらぬ営みを繰り返していた。ただ、その顔ぶれをほんの少し変えただけで。
同じところを回り続ける時間の中で、置いて行ってしまった花の色を思い出す。
「ベルタは、わたしの相棒だった」
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます