第5話 痛み
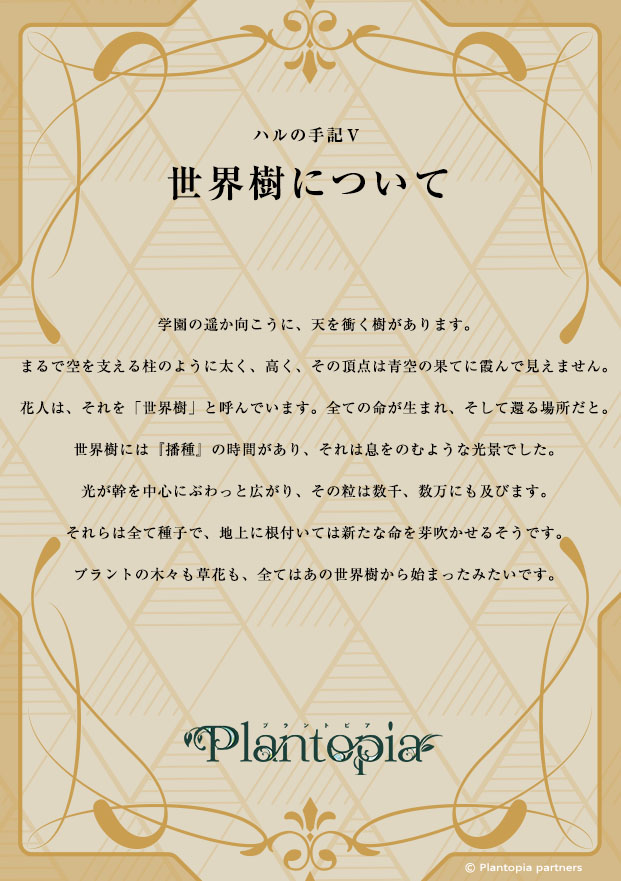
調査に進展があった。
スメラヤら研究班は、あの夜の組織的襲撃に加わった剪定者の残骸を、一体一体つぶさに解析していた。
中でも貴重な存在は、ひときわ大きな「隊長機」だ。
ウォルクやネーベルの報告によれば、鳥にも似たこの個体が他を統率する司令塔となっていたという。肝心の機体はアルファによって真っ二つにされているが、それでも可能な限りの分析を進めたところ、二つのことがわかった。
一つ。隊長機は、内部機関の七割以上が他の個体より高性能なパーツで構成されていること。
これまでの剪定者とは互換性が無い。一体だけならワンオフと言えるが、より恐ろしい推測として、この鳥型と規格を同じくするいわば「同一シリーズ」の存在が考えられる。
一つ。剪定者間の通信手段について。こちらの方がより重要度が高い。
剪定者は高度な連携を見せた。戦闘中も隊長機を中心として常に連絡を取り合っていたと考えるべきだ。声、匂い、動作などといった花人に認識できる伝達手段ではなさそうだった。これについてスメラヤはある仮説を立て、ひとつの実験を行った。
まず、まだ生きているパーツを組み立てる。
次に、そうしてできた「剪定者の一部」に通電し、起動状態にする。と言っても、電気を流して無理やり動かしているだけだ。害意も危険もない。
その上で、近くに数匹の紋様蝶を放つ。
結果はすぐに出た。紋様蝶の白い翅が、変色したのだ。
色は赤、青、緑、黄とばらばらで、意味する信号も全て違う。剪定者のパーツを停止させれば白に戻り、また動かせば色を変える。紋様蝶は混乱したように研究室の天井付近を飛び回り、籠の中の蜜溜まりに留まるまで落ち着くことが無かった。
剪定者に反応していることは、疑いようもなかった。
「お、おそらく――」
スメラヤは調査結果をまとめる。
「剪定者の通信手段は、紋様蝶同士が連絡し合うものと同じです。ま、まだ具体的にどういうものかは、わかりませんが……も、紋様蝶の研究を並行すれば、その秘密の一旦は、つ、掴めると思い……ます」
更に、隊長機から興味深いパーツが採取できた。
これも恐らく同様の原理で動くのだろうが、かえって不可解なものだった。剪定者同士が無言のままに連絡し合うのなら、今更こんなものを搭載する必要はなさそうなものだが。
音声をやり取りする、通信装置である。
✿✿✿
雑草をむしる。
できる限り丁寧に、ひたすら、むしる。
そういえばこの草にも由来はあるのだろうか。花のために抜いているが、「彼ら」にもかつての姿があったらどうしよう。などと益体のないことを考えていると、どこかからテントウムシが飛んできてハルの頭に留まった。
「何やってる」
と、後ろから呆れきった声がした。
「あ――」
「……お前、いつからここにいるんだ?」
早朝だった。ハルは日が昇る前にベッドを出て、アルファよりも早く『月の花園』に来ていた。
早起きしたのではない。ただ単に眠れなかったのだ。アルファが来たことにさえ、声をかけられるまで気付かなかった。
「まだ明るくなる前だから……二時間前、くらいかな」
「その間ずっとそんなことしてるのか」
「うん」
「どうして」
言葉を探したが、もっともらしい理由なんて出てこなかった。
そもそも花の世話のやり方も知らない。道具だって持ってない。全ては見様見真似だ。
相手に説明するというより自分に言い聞かせるような声色で、ハルは答える。
「……あたしも、ここで眠るみんなのためにできること無いかなって」
この花園には、花人だったものたちが咲いている。全てに固有の名前があり、意思を持ち、歩き、言葉を話す時があった。
キウも、その中の一輪としてここで咲いている。
アルファは土に汚れたハルの両手と、それなりにはすっきりしたらしい花園の一部を見比べ、微妙な顔をした。
「……誰がそんなこと頼んだ?」
「誰にも。……けど、それでもなんか――」
「『みんなのために』って? はっ」
首根っこでも掴んで放り出されるのかと思ったが、アルファはそうしなかった。いつも通りのしかめっ面で吐き捨て、ふいとそっぽを向く。そうして、ハルなどいないもののように自分の作業を始めた。
「言っとくが」と、背中越しに付け加える。「適当に草抜いてればいいわけじゃないからな」
言うだけ言って、今度こそむっつり押し黙ってしまう。
アドバイス、なのだろうか。
「……うん」
ずれたタイミングで思い出したように返事をしてみるが、もちろん反応は無い。
それから会話も無いまま作業が続く。アルファはてきぱきと作業を進めているようだが、ハルには何をどうすればいいのかわからない。園芸のことなんてほとんど全く知らないのだ。ならアルファに聞くべきかと思ったが、彼は自分の仕事に没頭して全身から「話しかけんな」オーラを放ちまくっていた。
とりあえず今は、目につく雑草を抜くことに集中しよう。それなら間違えることはなさそうだ。
と、思っていたのだが――
「待て」
「わあ!」
いつの間にかアルファが後ろにいた。
「それは抜くな。花の一部だ」
「え!? でもこれ、ただの草なんじゃ」
「違う。よく見ろ。それにはもう触るな」
言うだけ言って去っていくアルファ。自分が抜こうとしていた「草」を指でなぞってみると、それはある花の一部だったことに気付く。止められなければ、もろとも抜いてしまうところだったのだ。
間違えてしまった。次は気を付けなければ。
しかし――
「そこに水を撒くな。わたしがもうやった。それ以上は花が溺れる」
「ご、ごめん!」
間違えて、
「その蟲は追い払わなくていい。むしろいないと困る」
「そうなの!?」
また間違えて、
「肥料に触るな。種類ごとに分けてる。余計なことはしなくていい」
「う、うん……」
間違えて――
何かしようとしても、全て余計なことだった。アルファは釘を刺してはどこかへ行って、自分のペースで花々の世話を続ける。
ずっと空回りしている。
思いつくままの行動で花を世話できるわけがない。こちらから聞こうとしても、アルファは答えないだろう。色とりどりの花園の中心にぽつんと立ち、ハルは自分で自分の両頬を張った。
やるからには、ちゃんとしなければいけないのだ。
✿✿✿
トレードマークはてっぺんの時計塔。内部機関の歯車により進む大きな針は、見ているだけでも迫力があった。
大きな特徴は、樹上にも関わらず水上にあるということだった。奇妙な話だが、巨木の上層部に湖があり、そこが学園全体の主な水源になっているのだという。
最上部に位置する、大きな湖。その只中に聳える立派な図書館。樹のてっぺんにこんなものがあるのが信じがたく、入口に続く桟橋を渡るだけでもどきどきした。初見時は水面を跳ねる魚にもビビったものだが、いざ入ってみると存外どうということもなかった。
ハルは図書館の一角に陣取り、目についた資料をひたすら読み漁っていた。
天上のステンドグラスから差し込む自然光が、館内を柔らかく照らしている。机にはそれぞれ蛍の入った蟲籠があって、時間を問わず手元の文献が読めるようにしてある。
「それにしても、園芸の本、ですか」
フライデーは意外そうな顔で、ハルと書物の山を見比べる。
「急に言われた時は驚きましたが、ひとまずこんなものでよろしいですか?」
「うん、ありがとう。色々ありすぎて、どこに何があるかわからなかったんだ」
「お気になさらず。書架の中からお望みのものを探し出すのは、資料班の業務のうちです。とはいえ――」
言葉を切り、フライデーはずらりと並ぶ書架を見上げた。そのどれもが天井に達するほど高く、上から下まで多種多様な書物を収めている。
「多くの花人は、古代文字からなる書物を読むことはできませんが。大抵のものは『宝の持ち腐れ』で――ああ、ちなみにこれは古いことわざだそうです」
「そうなんだ……こんなにたくさんの本があるのに」
「私たちよりずっと前の世代は、全員これらを読むことができたそうです。最近はあれですね、字のたくさんある本はあまり好まれない傾向にあります」
「どんな本が人気なの?」
「絵がいっぱいあるやつです」
絵がいっぱいあるやつか。
ともあれ、これだけ資料が豊富なのはありがたい話だ。フライデーに改めて礼を言い、園芸――花の世話をする上で必要な情報を、しっかり頭に叩き込むべく書面に没頭した。
それから数時間が経ち、ハルは椅子から一歩も動かないまま頭を抱えていた。
「…………う~ん」
目が滑る。どうしてこうも頭に入ってこないのだろう。
資料とメモを何度見比べても腑に落ちづらい。理屈としてはわかるのだが、そもそも想定すべき不確定要素が多すぎやしないだろうか?
様子を見に来たフライデーが目を丸くする。
「随分渋い顔をしていますね」
「花のお世話って難しい……生き物相手にするのって、こんなに気にしなきゃいけないことが多いんだ」
「そのようですね。私は門外漢なのでなんとも言えませんが……まあ、誰にでも向き不向きはありますから」
「……なのかな」
たとえばこれが研究班の取り扱う分野なら、よっぽどすらすら覚えられる自信がある。研究に開発、技術、工学、そういったものだ。なのにこちらはどうにも馴染まない。もしかして苦手なのだろうか。
苦手意識。
そういったものがあるとして、では、どこで根付いたものなのか。自分の中で得意と不得意を区別するのは何か? 思索するも答えは出ない。
「――しかし、どうして突然、花のお世話をしようと?」
続く質問に、ハルは少し返答に迷った。
しかしやはり、考えをそのまま言うのが一番いいと思い至る。
「あたしにも何かできないかと思って」
「何か、ですか」
「ほら、今んとこ役に立ててないじゃん。みんなにおんぶに抱っこっていうか……だから、学園の仕事の中で、少しでも手伝えることは無いかって考えたんだ」
ならばどうして苦手分野と思われる園芸に手を出すのかは、言わずにおいた。そこを上手く説明できる気がしなかったからだ。
頭の中に、キウの最期の顔がこびりついている。
「……そうですか」
フライデーはそれ以上は詮索せず、最後に言い添える。
「何にせよ、あまり根を詰めすぎないように。休息は必要です。見たところあなたは、ずっと机に齧り付いているようですので」
「それなら大丈夫だよ、あたしまだまだ」
ぐぅ。
フライデーは意外そうな顔をした。彼にとっては普段あまり聞き慣れない音だったからだろう。
鳴ったのはハルの腹だった。
硬直するハルに対し、フライデーはあくまで冷静に続けた。
「――
「……うん」
「
「はい」
「食事は摂るように」
「ウス」
半ば追い出される形で食堂に急ぐ。この日の調べ物は、それでおしまいだった。
ハルはそれからも、図書館に通い詰めた。吸収したものが自分の血肉になりきるまで、より知識が必要だと思った。
実際のところ、ハルの没入度はかなりのものだった。苦手なら苦手なりに量で補おうとした。図書館にある文献は手当たり次第に読み漁り、手帳に書き留めて自分なりに噛み砕いた。
どうやら机に向かう才能はあったらしい。寝る間も惜しんで、ハルはそればかりを続けた。会ったこともない「誰か」に向けた手紙を書く暇も無くなっていた。いつしか「根を詰めすぎるな」というフライデーの進言も忘れ、図書館に居辛くなってからは、自室で勉強を続けた。
来る日も、来る日も。
そうでなければアルファにも、誰の役にも立てない。
何のためにもならないから。
✿✿✿
「おはよう!」
芽の季節、二十三日の朝。ハルはしばらくぶりに『月の花園』を訪れる。アルファは相変わらず居て、ハルの来訪に迷惑そうな――それでいて妙にほっとしたような――しかめ面を見せた。
「……また来たのか、人間。顔を見なくてせいせいしてたんだがな」
「へへ、おあいにく様。ただ引っ込んでたわけじゃないし。あと、あたしハルね! ちゃんと呼ぶまで何度でも言うから!」
空元気だ。自分でもわかる。無理をしている。
だけどそうでもしないとまともに喋る自信が無い。連日連夜の無理をそのままに、何かに突き動かされるようにここまで来た。
「そりゃご苦労なことで。気が済んだら早くどっか行け」
当然ハルも無策で来たわけではない。花の世話に関する情報は頭に叩き込んでいる。道具だって持ってきた。
「あたしにも、みんなのお世話を手伝わせてほしいんだ」
「言ったろ、誰も頼んでなんか――」
「あたしがやりたいの!」
自分でも、驚くほどの大声が出た。
アルファが目を丸くしている。「あ」と間の抜けた声を上げ、ハルは回転の鈍い頭で必死に取り繕おうとした。駄目だ。いきなり躓いてしまった。取り返しは、つくだろうか。
「あの――あたし、ここのみんなのためになりたくて。アルファにもキウにも、何かしてもらってばっかりで。せめて恩返しっていうか、その」
「……要らない。恩を売ったつもりも、借りを作る気も無い。余計なことばっかり気にするな」
「待って!」
背を向けるアルファに、ハルは縋るように叫んだ。
「――待ってよ」
アルファは振り返ろうともしない。彼がどんな顔をしているのか、想像するだけで恐ろしくなる。
キウのこと。
ウォルクとネーベルのこと。
あの夜のこと。
アルファと、花人たちが眠る花園のこと。
思考が堂々巡りして、あらかじめ用意していた建前がこぼれ落ちていく。取り繕うための言葉が何もかも空疎に思える。
空元気は燃料切れだった。次に搾り出されるのは、血の滲むような本音だった。
「……考えると痛いんだ。何か、してないと」
「『痛い』……?」
「痛いよ。胸のところがずっと。せめてあたしも意味のあることがしたい。少しでも、変わりたくて……!」
その言葉の「何か」が、アルファの癪に障った。
背中に苛立ちの気配があり、返す言葉には棘があった。
「……軽々しく、そんな言葉を吐くな」
吐き捨て、今度こそ彼は会話を打ち切る。ついぞ一度も振り返らぬまま歩み去ろうとするアルファを、ハルは追おうとした。
「……! 待っ……!」
ぐらり。
体が傾ぐ。よろける程度のものだった。それでも、連日の不眠不休は自身に想像以上の負担を強いていたらしい。視界がちらつき、両脚に力が入らず、気が付けばその場に膝を追っていた。
いけない。アルファを追わないと。
這い上がる疲労と眠気を追い払う。顔を上げると、アルファが硬直した表情でこちらを見下ろしていた。
「――――お前」
「ご……ごめん、大じょ――」
アルファはハルではなく、その足元を見ていた。花園には管理用に石畳の通路が敷かれており、普通はそこを通るのだが、今ハルの片足が通路からはみ出てしまっていて。
膝の、下に。
アルファが飛びついて、ハルの脚を乱暴にどけた。そこにある、無残にひしゃげたものが目に焼き付いて離れない。頭が真っ白になっていた。自分は今、何をした?
「あ、」
花。色は、蒼。
潰れている。何の花で、どういう名前なのか、ハルは何も知らない。
アルファはしゃがみ込んで両手を伸ばし、潰れた花の状況を確かめていた。すぐ近くに顔がある。ハルは何かを言おうとして、
「――ここは、お前の逃げ場所じゃない」
肩が跳ねた。
額が触れ合いそうなほどの距離、こちらを睨み上げる桜色の目には、静かだが抑えきれぬ激情があった。
「
「ご、ごめ……あたしっ……」
言い切る前に、アルファは立ち上がっていた。手にはあの潰れた花があった。根の周りを掘り起こし、土塊ごと持っている。両手を泥だらけにしてまで、まるでハルから救い出すように。
「――何もするな。どうせ、変わることなんて何も無いんだ」
立ち去る彼を、今度は追おうともできなかった。
残ったのはハルと、何事も無かったかのような花園。唯一足元の地面だけが抉れて、ぽっかりと口を開けている。
膝の下に残る感覚が、生々しく尾を引いている。
自分は、何をしたかったのだろう。
それは何のためだったのだろう。
その結果が今の状況なのだとしたら、自分がやってきたことに何の意味があったのだろう。
「――ごめんなさい」
ただ、口をついて出た。
「ごめんなさい……ごめん、なさい……っ」
地面の穴が、ひとつふたつ落ちる雫を受け止めた。
ただそれだけで、応える者は誰もいなかった。
「…………」
木陰に立ち、アルファは風にかき消えそうな細い声を聞いている。
人間の感情は「匂い」に乗らない。だから、彼女のころころ変わる表情や声色はどこまでも奇妙に映る。
手の中の土塊を見下ろしてみる。いくつかの花弁が連なって咲く花は半分ほどが潰れ、長めの茎も折れてしまっている。その、空にも似た蒼い色に、我知らず語りかける。
「……お前は、どう思う?」
問いかけに意味は無い。
それはただの花で、喋る口も、笑う顔も無いのだから。
✿✿✿
夜に差し掛かる頃、アルファは学長室に呼ばれた。
ノックも何もしない。来るなり無言で扉を開け、前置き抜きで話に入る。
「何の用だ、ナガツキ」
「学園長を、」言いかけ、ナガツキは止める。「――いや、いいか。他に誰がいるわけでもない」
「学園長、ね……。いちいちそんなポーズが必要なんて、学園長ってのは相変わらず大変らしいな。わたしだったら絶対ごめんだ」
「褒め言葉にしては遠回しだな。確かに大変と言えば大変だが、苦ではないよ。心配いらない」
余裕の態度で返されると、アルファはむっつり押し黙る。こいつのこういう、手の内を知り尽くしたかのような態度は好きではない。こちらの調子が狂う。
「おれは慣れているからいいものの、すぐに皮肉を吐くのは悪い癖だぞ。それではまるで誤解してくださいと言っているようなものだ」
「言いたいことがそれだけなら戻るぞ」
「呼び出したのはこっちの用じゃない。お前こそ、そろそろ溜め込んでいるものがあるんじゃないかと思ってな」
「……はぁ?」
ベッド脇のチェアで脚を組むナガツキは、皆に向ける「学園長」の顔をしてはいない。どこか気だるげで遠慮の無い、けれど腹立たしいまでに鷹揚な、一人の花人だった。
ナガツキのそんな態度に、アルファも察するものがあった。彼は朝方の『月の花園』での一件を知っているのだろう。
「他の場所では吐き出せないこともあるだろう。――お前の『独り言』に付き合えるのは、もうおれくらいのものだ」
それからまた、沈黙が降りた。
アルファは何も言わない。ナガツキも、それ以上何も言おうとしない。
「………………わかってはいるんだ」
先に口火を切ったのは、アルファだった。
ナガツキは反応しない。あくまでも「独り言」であるからだ。
「あの人間に当たったって意味なんか無い。……
「こっちも独り言だが、」ナガツキは敢えて目も合わさずに、「ハルは謝ったのか?」
「……ああ。聞いてた」
「
「鉢に移し替えて、わたしの部屋に置いてる。……最初は驚いたけど、どうしようもないってことは無い」
「ならばいいさ。あいつはいつまでも気にするような奴じゃない。お前も知っているだろう?」
「それはまあ、そうだが」
また、アルファは黙り込んだ。
何か考えることがあった時、彼は頻繁に押し黙る。頭の中で充分に考えをまとめてから口を開く。確証の無いことを口にできない癖は、自分の発言に責任を持ちすぎるがゆえについた習慣だった。だからこれは会話ではなく、独り言のやり取りに過ぎず、ナガツキも続きを急かさない。
許せないものがあるとすれば、花園での一件ではない。
耐え難いものがあるとすれば、ハルがいることでも、一連の事件のことでもない。
何かもっと、大きな枠組みのことだ。
「――いつもそうだ。何かが変わりそうなら、必ず何かが蓋をする。森はどこまでも広がっていて、
「そうだな。もう、随分長い。……最初からここにいるのは、もうおれとお前くらいだ」
花人の世代は移り変わる。咲いては散り、また咲いては散っていく。
若い花人もベテランの花人も数多い。それでも、この学園の移り変わりを最初から見守っていた世代は、今となっては二人だけだ。
「不満か?」
「今の暮らしが嫌なわけじゃない。ただ、この先のことを考える時がある。たまに昔のこともな。そうしてたら、今でもまだ――」
脳裏によぎるものがあった。
こちらに訴えかけようとしていた、ハルの顔。その時の言葉。耳馴染みの無い単語。
「――ナガツキ。『痛い』っていうのは何だ?」
赤い目がこちらを向く。意外な質問だ、と表情が物語っている。
「知識としては知っているな。怪我をした時などの動物の生理的反応を差すが、どうしてそんなことが気になる?」
「あの人間が言ってた。どこも怪我をしていないのに、辛そうだった」
「……そうか。『痛み』には、種類があると聞いた。ならばハルは、今もその痛みをずっと抱えているのかもしれないな」
そんなことがあるのだろうか。だとしたら、その『痛み』とはどんなものなのだろうか。
時たまアルファの胸に去来する、この重みと似ているのだろうか。
「百も承知だとは思うが、ハルにも悪気は無かったはずだ。あまり突き放してやるな」
「わかってる。けど、あいつがああしてるのを見るのは……目に毒だ」
「そう感じるのは、お前があの子を意識しているからだよ」
まさか、と首を振るアルファに、ナガツキは穏やかな視線を注ぐ。妙に居心地が悪くなった。
この「独り言」を聞いているのはナガツキだけ。吐き出したいことはもう言い終えた。それが目的で呼び出したのなら、こっちが満足した時点で立ち去ってもいいはずだ。これ以上いると変なところにまで突っ込まれるような気がして、挨拶もなくドアノブを掴むアルファだったが、
「ああ、ちょっと待て。最後にひとつ頼みたいことがある」
嫌な予感が当たった気がする。
「面倒事ならごめんだ」
「そう難しいことじゃない。護衛をしてほしいんだ、おれの」
「お前の?」アルファは眉をひそめ、「……いちいち必要か?」
「おれだって昔のようにはいかないさ。力の大半をこの学園に注いでる。おかげで一週間の半分以上は寝ていなくちゃいけないんだ。――近くの遺跡に用がある。ここから南の、午睡の森だ」
遺跡、という単語からピンと来るものがあった。
遺跡の深部から採掘できるものは森とはまったく別種だ。研究班垂涎の古代文明の遺物もあれば、花人たちの生活に必要な各種機材や資源の類もある。
「
目的地は、学園から最寄り――つまり花人たちが最初に見つけた小さな遺跡だった。もう何度も調べ尽くしているため採れる資材も無く、たまに探索班がサボって寝ているくらいだ。
「それこそ、お前だけで行けるだろ。あんなところ朝のうちに二往復できるぞ」
「ところが、立場上一人でふらつけなくてな。お前が無理ならフライデーや常駐組の花人がぞろぞろついて来る羽目になりそうだ。いやはやまったく、『学園長ってのは相変わらず大変』だよ」
――やれやれ。
変に騒ぎになっても面倒だ。アルファは大きなため息をついて、
「……夜が明けたらでいいな?」
「助かる。それともう一人、連れていきたい子がいるんだが」
「誰だよ」
ナガツキは、こともなげに答えた。
「ハルだ」
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます