第4話 花を守る人
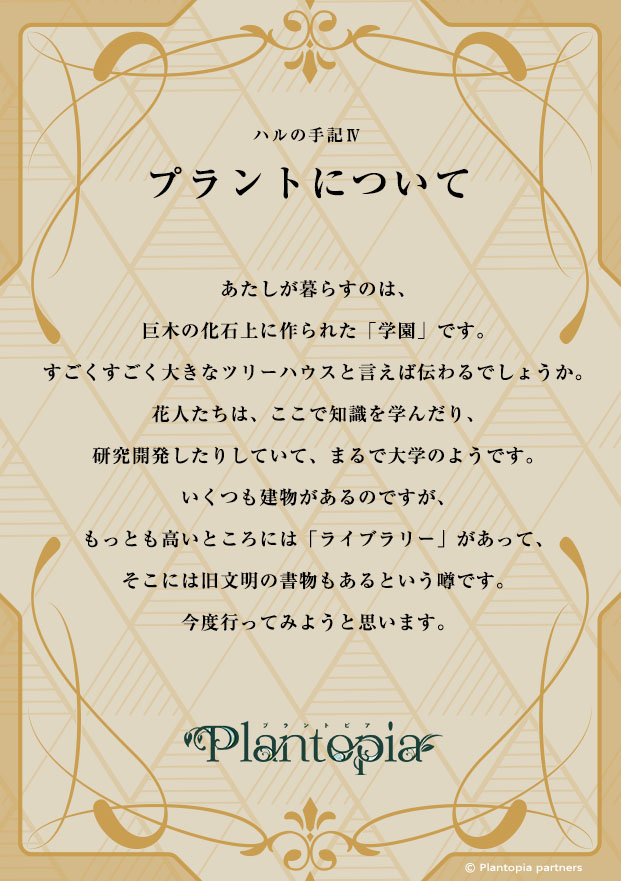
鋼鉄の腕が、遠慮会釈もなくハルに肉薄した。
こちらの頭など片手で覆える大きさだった。力任せに握られれば、小娘の体などどうなるか。
「どおりゃァッ!!」
横からミサイルのように飛んできた何かが腕を弾き飛ばす。
見開かれたハルの目と、爛々と燃える黄色の目がかち合った。
「キウ!!」
「頭下げてろ!」
彼の手には一振りのメイス。Ⅰ式打甲鎚【Pd-03】、硬い装甲を真っ向から打ち据える力任せの重装備だ。振り上げるなり遠心力をたっぷり乗せ、キウは中型の剪定者を一体ぶっ飛ばして遥か後方の木立に叩きつけた。
「おいハル! 大丈夫かよお前!」
遅れて追いついたウォルクとネーベルも、既に戦闘態勢に入っている。
しかし彼らの表情に浮かぶのは、明らかに当惑の色だった。
「――なんなんですか、こいつら。さっきの声は?」
「わ……わかんない。何かスピーカーみたいなものがあって、そこから『助けて』って……」
「スピーカー?」ウォルクが信じられないといった顔をして、「なんだよそれ。オレたちの言葉を真似したってのか? そんなことするなんて聞いたこともないぞ!」
すぐ傍に転がったままのスピーカーは、すっかり沈黙していた。もはやガラクタも同然で、月の光を鈍く跳ね返す様は、こちらを嘲笑っているようにも見えた。
「……罠……」
呟くネーベル。そんなもの想像だにしなかった、と表情が物語る。
「ちょっとヤバいかもしんねーなコレ」
「どうする? ケツまくって逃げるか?」
「無理だと思う、です。囲まれてますし」
包囲が狭まる。三人の花人が武器を構え、口元の覆いを外す。
――芽の季、十四日。卵の刻。西部探索担当「キウ班」、突発的な遭遇戦を開始。
静まり返った夜の淵で、激しい火花が咲いた。
✿✿✿
同じ頃、アルファは『月の花園』にいた。
正直、せいせいしていた。
面倒な人間がどこかへ行ってからというもの、肩の荷が下りた気持ちでいた。これでもう余計な仕事が無くなったわけだ。ナガツキには後から適当に伝えておこう。来る日も来る日も花々を世話し、守る日々が戻る。本来、ここにはもう誰が来るべきでも、どこへ出ていくべきでもないのだ。
だから、アルファの心境はまったくもって平静なのだった。
――ほんとに?
不意に浮かんだ疑問に、咄嗟に首を振る。「誰か」の姿を借りた唐突な問いかけは、その実、自分自身の内なる声に過ぎない。
奴がどこかへ探索に出たことは知っている。別に気にならない。人間の世話なんて他の奴がすればいい。自分などより、もっと馬の合う相手はいるだろう。どうせ軽く学園周辺を回ってくるだけだ。
なので、全然まったく気になどならない。
――そうかなぁ。あんまり意地張んない方がいいと思いますけど?
「……馬鹿馬鹿しい。わたしは何を思い出してるんだ」
幻聴を聴くほど耄碌しているつもりは無い。
あいつならそう言うだろう。
あいつなら、自分の尻を蹴ってそう笑うだろう。
そんな記憶の残滓が、この期に及んで脳裏に浮かび上がっただけのこと。今まではわざわざそんなこと考える暇も無かった。と考えれば、やはり多少の意識の変化はあったのかもしれないが、断じて
こんな夜中なのに眠ろうともしなかったのは、やはり花の世話のためだ。このところ、非常に不本意ながら別のことに時間を取られていたため、 あまり見てやれなかった。
どっかに行った人間のことなど、当然、気にしているわけではない。
――そう突っ張んないでいいじゃん。ほんとは優しいんだから。みんなだってわかってくれるよ。
記憶に蘇るその言葉は、以前実際に言われたことだ。
いつも花園に寄り添うように咲いていた、あの蒼い花の名を思い出す。
やめろ。わたしはそんなに大層な奴じゃない。本当言うと、花守の仕事だって最初は乗り気じゃなかったんだ。それをお前が――
記憶は常に疼くような痛みをもたらす。忘れたくはないのに、思い出したくもないこと。
あるいは覚えているからこそ、あの人間のことが引っかかるのだろうか。
似ているから?
人間が、あいつに?
まさか。うるさいところは似ていなくもないが、まったくの別物だ。それこそ馬鹿馬鹿しい。
――と。
「うん……?」
星明かりと違う薄ぼんやりした光が、アルファの肩に留まった。
一匹の紋様蝶が、翅をゆったりと扇いでいる。
彼らはその一匹一匹の翅が、それぞれ異なる「紋様」に見えることからそう名付けられた。紋様は古代文字のようにも思えるが、見えるだけで読めるわけではない。主な生息域は遺跡やその周辺。静かで冷たい闇を好み、若い花人が驚かされる「謎の怪光」の正体はこいつらであることが多い。
それだけならただ無害なだけのよくいる蟲だが、紋様蝶にはある特性がある。
距離を隔て、別々の個体と連絡を取り合うことができる、という点だ。
紋様蝶は他の個体と互いにリンクしている。原理は不明だが、匂いも届かないような遥か遠隔からでも、常にリンクした個体の場所と状態を認識しているらしい。そうして相手に何らかの変化があった場合は、その状態に応じて光の色を変える。花人はこの習性を「遠く離れた仲間同士の連絡手段」として利用している。紋様蝶は香りである程度操作でき、餌として蜜を与えているため、一種の共生関係と言える。
今アルファの肩に留まった一匹もやはり、学園から離れた個体とリンクしている。片割れの一匹は、ハルが背負っていったリュックに忍ばせてある。
紋様蝶の翅が、放つ光の色をゆっくり変えた。
平常時の白に朱が混ざり、徐々にその濃さを増して、赤く、赤く――
「……!」
それは、危険信号を意味する。
✿✿✿
一体、二体、三体――
十体から先は数えるのを止めた。
あちらこちらに、剪定者だったガラクタが転がっている。三人は武器を杖に立ち、乱れた呼吸を必死に整えていた。
「だ、大丈夫!?」
「……おー。そっちは、どうだ? なんともないか?」
「あたしはなんともないけど、みんな、傷が……!」
ああ――気の抜けたような声を漏らして、キウは自身の傷をまじまじと見下ろす。
彼だけではない。辛うじて退けられたが、ウォルクとネーベルも無傷ではなかった。防御性能にも優れた外套はあちこちが破れ、傷だらけの身体は立っているだけでも不思議に思えてくる。
ハルは最初に見た戦闘のことを思い出していた。あの時は、腕が取れそうな傷でさえ見る間に回復したはずだ。
「これ、治らないの? 前に戦った時みたいに……」
「……ん、今は無理。夜だもんな」
当然のことのような口ぶりに、ピンと来るものがあった。
花人は、日光を主な活力源とするらしい。
夜も動けなくはないが、派手な活動は基本的に避ける。であれば、あの常軌を逸した回復能力は、太陽光を受けてこそのものだったのではないか。
知らなかったのはハルだけだ。花人は、夜に戦ってはいけなかったのだ。
「ごめん。あたしが先走ったせいで……」
「気にすんな、朝にはどうにかなる。つかそれより、ワケわかんねーのは
言いながら、キウたちはポーチから取り出した薬剤を傷口に塗布し、樹皮から作った包帯を巻く。応急処置だろう。
「……報告、しないとです。あれは『罠』でした。あんなの初めてです」
「探索は打ち切りだな。荷物まとめて、朝になったら出ようぜ」
誰も反論を差し挟まなかった。戦闘を終えても、体中にまとわりつく不気味さは拭い去りようもなかった。倒した相手からパーツを剥ぎ取る余裕なんてあるはずもない。四人、踵を返したところで――
もぞ。
横たわるガラクタたちが、動き出した。
「な――」
ある者は胴体を叩き潰され、ある者は手足を斬り飛ばされ、またある者は中心から両断され。そのようにして機能停止した剪定者たちが、全て、破壊されたままの機体で立つ。這いずる。のたうち、蠢く。それは花人でさえ初めて見る光景だった。ここまで叩きのめされてなお動く剪定者などいなかった。ありえないことだ。
ありえないことが起こっているということは、そもそもの前提から違っていたということになる。
塗り潰された森の闇で、新たな目が光る。
現れたその一体は、これまでとは明らかに違う。今までどこに潜んでいたのか、見上げるほど大きなそのフォルムは「鳥」に似ている。ただし体の端々まで無機質な合金で出来ており、左右に大きく広げられた翼は、それぞれ刃渡り五メートルはくだらないであろう長大なブレードだ。
毒虫のような色鮮やかな光を明滅させ、そいつの頭部がガタガタと震える。応じるように、死にかけの剪定者が蠢く。
『た』
鳥が、甲高く耳障りな音を放つ。
『sケ』
それは言葉のようでいて、意味を持たない。
まるで音の響きだけを真似した、全く異種の何らかの信号で。
『――/*$て』
ガラクタたちが一斉にこちらを向いた。
「逃げるぞ!!」
キウが叫ぶやいなや、全員弾かれたように走り出した。
決して後ろを振り返らない。もう休むだの朝を待つだのと言っている暇もなく、とにかく奴らを撒いて、どこか安全な場所へ、早く、早く、早く!
「ちゃんとついて来てっかハル! 足止めんなよ!!」
「あ、あたしは平気! そっちは!?」
「な、なんとか、です。野営地に戻れば、馬がいるから……そこまで……!」
そうだ、
木々の間を走り抜ける。すぐ背後から草を蹴散らし、木々を薙ぎ倒し、土を獰猛に踏み荒らす破壊の気配が迫る。あれは――頭の隅でハルは思う。
あれは、きっと司令塔だ。隊長みたいな存在だ。
あの鳥型が他の剪定者に命令し、操作しているのだ。機体が半壊してもなお及ぶ強制力によって、無理やりに。奴らには奴らの指揮系統があるのだ。では、何故、何を目的に。
みしり。
すぐ隣で、何かがひしゃげるような嫌な音。
「っ……!」
ウォルクが崩れ落ちた。治癒しないままでいた右脚が限界を迎え、ついに折れたのだ。
「ウォルク!!」
足を止め、彼に駆け寄るハル。そこに小型剪定者の一体が躍りかかった。丸みを帯びたボディに、身の丈ほどもある鋸を装備した個体。今やその鋸は半ばから断ち折れ、半壊した機体は火花を散らしているが、止まる気配は無い。
「やめろ、つってんだろッ!!」
返す刀に、メイスがめり込んだ。
剥き出しの内蔵機関に鉄塊をぶち込まれ、ひとたまりもなく砕け散る小型個体。その隙にハルがウォルクを助け起こし、肩を貸した。
「ウォルク、大丈夫!?」
「――悪い。くそ、足が……!」
「ハル、ウォルク、こっちに!」
ネーベルにも助けられ、ハルは必死に前へ進んだ。肩にウォルクの体重がかかる。「花」であるからか、彼は驚くほど軽かった。そのことにハルは、何故か胸をかきむしられるような思いがした。
「あーーーもうめんどくせえっ!! 絶っっ対逃げ切ってやるっ! ウォルク、ネーベル、ハル! 気ぃ抜くなよ!! 絶対諦めんな!!」
噛み付くようなキウの啖呵に、発破をかけられたような思いだった。胸に迫る不気味さも、暗闇がもたらす不安も恐怖も無理やりに捻じ伏せる。鮮やかな花の色と、その香りを信じる。
「――うん……!!」
馬が待つ場所はもうすぐの筈だ。逃げる、逃げる、逃げる――
それでも。
どうしても、目的地に着かなかった。
もう、どれほど走り続けたのかさえわからない。ほんの数分な気もするし、何時間も経った気もする。
走れども走れども、暗黒の樹海。耐えずつきまとう追っ手の気配。方向感覚などとうに失っている。敵により巧みに追い込まれていたと知ったのは、完全に囲まれてからだった。
半ば崩れかけた個体、体の一部が炎上してなお動く個体。無機物の屍のようなそれらが、辺りを不気味に照らしている。
「大丈夫だ」
言って、キウは笑う。その表情にも色濃い疲弊がある。
「絶対、帰れる」
崩れた機体がにじり寄る。率いるのは、あの巨大な鳥型の隊長機。キウは傷付いた体でメイスを握り直す。
「……キウ?」
ネーベルが何かを「嗅いだ」。花人にしか伝わらない意思の伝達を受けて、ネーベルは何故か目に見えて狼狽した。
「そんな。でも。だって、それじゃ」
キウは何も言わない。どういう意味なのか、ハルはおろかウォルクにもわからないようだった。剪定者の包囲が狭まる。がちり――隊長機のブレードが開き、端々にまで凶暴な力がこもる。
「そんなこと、したら……」
「……おい、なんだ? ネーベル? 何を嗅いだ? キウ、お前何を、」
キウはただ一言、ぽつりと呟く。
普段の賑やかさからは考えられない、静かで重々しい、願うような声色だった。
「早く」
「っ……!!」
ネーベルが信じられない行動に出た。
武器を捨て、ハルとウォルクを抱えて一目散に走り出したのだ。
目指すは隊長機のいる反対側、包囲が一番薄いポイント。ハルもネーベルも、抵抗する暇すら与えられなかった。
「えっ!? ちょ、ネーベルっ!!」
「おま、何してんだよ!? 離せって! おい!!」
先んじたキウが、渾身の一振りで隊列の一角を吹き飛ばす。そこを突き、ネーベルが包囲を突破した。
キウは、後に続こうとはしなかった。
「キウ!!」
ハルはただもがくだけで、他にどうすることもできない。ネーベルの足取りは断固としていて、何があっても止まらないという悲壮な決意に満ちている。惨めに揺れた、浅い息遣いが伝わる。自分の息か、ネーベルか、それともウォルクの息か。
そして、ハルは見た。
もはや「戦闘」などではなく、それはほんのささやかな抵抗だった。最初から時間稼ぎ以上の意味などありはしなかった。キウはきっと、そこまで織り込み済みで。
最後の瞬間、距離を隔てて目が合う。
炎に照らされて、彼が何かを言った。香りでは伝えられない、声も届かないような距離で、刻むように動いた口は、こう言っているように見えた。
アタシの、なまえは、
ばつん!!
翼状のブレードが、キウの体を真っ二つに切断する。
何が起こったのか、一瞬わからなかった。
理解が及んだ途端、頭の中で何かが弾けた。
「キっっ――――」
「――ぅぁああああああああッ!!」
血を吐くような叫びが、すぐ傍で聞こえた。
傷だらけで脚が折れ、武器さえも失ったウォルクが、火でも着いたかのように暴れもがいている。
「ウォルク! あ、暴れないでっ……!」
「あいつ!! あいつ、あいつッ!! キウを……!! 殺す!! 殺してやるッ絶対ぶっ殺してやる!!」
「だ、駄目です、ってば……! 逃げなきゃ! わ、私たちだけでも、逃げないと! キウのしたことが……!!」
キウ。
キウが。
ハルの全身から、嘘みたいに力が消え失せていた。眦だけが張り裂けんばかりに見開かれ、もう何も見えない木々の向こうに釘付けのまま。ウォルクとネーベルが言い合う内容すらも頭に入らない。
――大丈夫だ。
――絶対、帰れる。
励ますように笑ったあの顔が、頭から離れない。
だから、ネーベルにもとうとう限界が来たことに、最初気付かなかった。
走りはやがて歩みとなり、歩みはやがて、這うにも等しい懸命な進みとなる。応急処置をしてなお止まらない体液が滴り落ち、彼の全身から、どうしようもなく力が抜けていく。
目の前にはもう、剪定者の群れがいた。
「…………ごめん、なさい。私も……無理、でした」
「上等だよ」
折れた脚で無理やり立ち上がり、ウォルクは敵の群れを睨みつける。
「……誰に喧嘩売ったのか、思い知らせてやる」
武器は、どこにも無い。
ハルには、そもそも何もできない。
傷付いた花人二人と、無力な人間一人。傷も痛みも無いように動き続ける機械人形の群れ。隊長機の頭部に、柄の折れたメイスが突き刺さり、玩具みたいに飛び出ていた。
剪定――そう名付けられた通り、奴らはごく作業的な動作で、伐採対象に刃を向け、
流星が落ちた。
少なくとも、最初はそう見えた。
流星は、花の形をしている。
激甚な振動や轟音と共に、真上から落ちてきた「何か」が立ちはだかった。
二つに結った髪が揺れている。沸き立つように舞う花弁は桜のそれで、一つ一つが異様な熱気を孕んでいた。
空気が歪んで見える。誰もが言葉を失っていた。慈悲なき剪定者すら、突然の闖入者に淀みない連携を停止させた。最大限の警戒。次の瞬間全機に叩き込まれた命令は、きっとそんな感じだっただろう。
何もかも静止した時間の中で、一人だけが自由意志を持って動いているように見える。
その者はハルとウォルクとネーベルを見て、次いで剪定者を見る。そしてもうずっと後ろに置き去りにした「彼」の方を向き、その残り香を一度だけ嗅いだ。
そしてアルファは、右手の装備を展開する。
「
端から端まで頑健な蔦と茨で覆われた、繭のような物体だった。それが合図を受け、解け、開いていく。
月光の下に晒されたのは、主の身の丈ほどもある、巨大な機械仕掛けの戦斧だ。
ハルも、ウォルクやネーベルさえその存在を知らない。遺跡から発掘された装置をふんだんに用いた結果、使用そのものに多大なリスクを伴う危険物だからだ。専用の技能を持つ花人向けにチューンされ、事実上、学園の最高戦力にのみ所持を許された工房の特殊武装。
アルファはその数少ない一つを、仲間の前で初めて手に取った。
「Ⅳ式火焔加速型断甲斧【トゥールビヨン】、起動……!!」
剪定者が戦闘行動に入る。
これより以降、アルファは一切の言葉を発さない。
全ては目が物語っていた。周囲に炎が産まれ、灼熱の朱を写し取る瞳には、極低温の氷のように徹底的な怒りだけがある。
まず一体が斬られた。
ハルには見えなかった。ウォルクとネーベルにも同じだった。圧縮した空気が炸裂し、何か短い爆音がしたと思えば、残るは光の軌跡。そして、敵の残骸のみ。
次に二体が斬られた。
一度解き放たれた閃光は停滞を知らず、淀みなく螺旋に駆動し、休むどころか加速を続ける。
更に四体が斬られた。
八体。
十六体。
「なに、あれ」
知らず零れた言葉は、ウォルクとネーベルの言葉でもあったかもしれない。
目の前で踊る「それ」はアルファではなく、似た形の火焔なのではないかと思った。誰も彼を捉えることができない。燃える桜が標的を次々に喰い破り、「反撃」や「防御」などといったまともな戦闘のやり取りを完全に否定する。
最後の一閃。
斧を大きく振りかぶる一瞬、アルファの顔が見える。
初めて自分を見つけた、あの時と、同じ目をしていた。
ずん! ――と、一際大きな振動が地面を揺らし、そこで初めてアルファが静止する。
一拍置いて、剪定者の隊長機が崩れ落ちる。もう鳥の形はしていない。上から下まで一直線に斬割され、二つに分かれて、そこら中に転がるスクラップの一部となった。
ふっ、と、アルファの背から只ならぬ気配が抜ける。
「な、なあ。あんた……」
「――――キウは?」
質問ではなく、確認の意味を持つ問いかけだった。ウォルクは、傷口を抉られたような顔をした。ネーベルは俯いて何も言えない。それが答えとなる。
振り向いたアルファには、何の感情の色も無かった。責めるでも哀しむでもなく、ただあったことを受け入れるように頷き、ハルに視線を向ける。
「……アル、ファ」
視線はすぐに逸れる。アルファは、キウが「いる」であろう場所に目を向け、ただ一言。
「……帰ろう。みんなで」
✿✿✿
どこをどうやって帰ったのか、ハルはよく覚えていない。
気付けば夜は明けていて、朝方の学園は只ならぬ雰囲気に包まれていた。
ウォルクとネーベルが何かを叫んでいたように思う。沈痛な面持ちのフライデーがいた。朝日と共に、慌ただしく現場へ向かう別の探索班がいた。その夜にあった起こるはずのなかったことについて、必死に情報をかき集め分析を試みるスメラヤがいた。
緊急の治療を受け、ウォルクとネーベルはどうにか持ち直したようだった。誰より先に駆け付けたハルだったが、そこにウォルクの姿はもう無かった。ネーベルはハルを見やり、困ったように笑おうとして、ぎこちない顔のまま言った。
――ごめんなさい。今はまだ、ちゃんとお話できない、です。
何もかもが目まぐるしく推移し、その全てにハルが入り込む余地は無かった。
何もできないまま時が過ぎる中で、ある光景だけが頭に焼き付いて離れなかった。
回収された「彼」の、手で持つことができるほどの小ささが。
ナガツキが目覚めた。きっかり予定通り、三日後の朝のことだ。
報告に向かったのは、フライデーとスメラヤ。それにハルが同行した。
希望したのはハル自身だ。「現場」に居合わせた者として証言するため――という理由もあるが、実際にはもっと大きな目的がある。
確かめたいことがあった。今の今まで、恐ろしすぎて誰にも聞けなかったことが。
学長室の重い扉が開く。赤い花の咲き誇る室内で、ナガツキはもう目覚めていた。大きなベッドから身を起こし、窓の外を見ていた目が、こちらに向けられる。
おはよう――そう言おうとしたであろう口が止まり、代わりに別の言葉が出てくる。
「何か、あったんだね?」
彼は一目でハルたちの様子が違うことに気付いていた。いや、あるいは、一嗅ぎか。
「学園長、 ――」
最初にほんの一瞬、言葉に詰まりはしたものの、フライデーが報告する。淀みがなく、抑揚もない語調は、半ば無理に絞り出したようでもあった。努めて押し殺した、言い知れぬ感情があった。
ハルと、キウ班の探索記録。
深夜に起こった突発的な戦闘。
そして、その顛末について。
途中促されて、ハルも当時の状況を報告した。その時のことを伝えるたびに何か小さな血の塊を吐くような感覚があった。ナガツキはただ、黙って聞いていた。
中でも特筆すべき出来事について、スメラヤが緊張の面持ちで告げる。
「せ……剪定者が、キウ班を罠に嵌めました」
花人にとって、それは怖気をふるう出来事だった。
彼らにとっての「罠」とは常に、こちらがあちらに用意するもの。剪定者だとか、狩りの獲物だとかをおびき寄せ、花人側に有利をもたらすためのものだ。あちらがこちらに仕掛けたことなど、これまでただの一度として無かった。ましてや「言葉」を巧みに利用するなどと。
「また、こ、これまでに無い特殊な個体も確認されています。アルファさんの報告によると、ほ、他の個体を統率するリーダー的な機能があった、とか。今回の戦闘において、剪定者側は……確固たる作戦立案のもと組織的な活動を取っていた……と見て、間違い、ありません」
「つまり」ナガツキは、静かに確認を取る。「
「そ、そうとしか、お、思えません。これまでに、前例の無いことです。……か、回収できる残骸は全て回収しました。可能な限りの解析を、続けています」
「頼んだよ。――きっと、みんな不安を感じているだろう。私から話をする。フライデー、後でみんなを集めてくれるかな」
「わかりました」
「ウォルクとネーベルは、どうしてる?」
名前を聞いた時、ハルの胸にちくりと刺さるものがあった。
「今は回復し、別の任に就いています。休むべきと言ったのですが、どうしても聞かず……」
「それもいい。何でもいいから、とにかく働いていたいこともあるだろう。ただ、必ず誰かを傍に置いてやってくれ」
「承知の上です。――あの。学園長」
「何かな?」
ナガツキの赤い目を見返し、フライデーはわずかに、喉を鳴らした。伝達事項のために被っていた事務的な仮面に、いよいよ限界が来た瞬間だった。
「探索の許可を出したのは、私です。全ての責任は私にあります。――責めは、私に」
そんなわけがない。
ハルは強く、強くそう思った。
フライデーはただ「いい」と言っただけだ。もとはと言えば、探索に出ることを望んだのは自分だ。
責められるべきなのは――
「誰も悪くはない」
声を上げそうになったハルに、ナガツキが先んじた。
「起こらないはずのことが起こった。それを予測できたのは、誰もいない。君もだハル。今回の件で、責任を負うべき子は誰もいない」
肩が跳ねる。
唇を噛み締めるフライデー。焦燥しきった様子のスメラヤ。ナガツキはただ優しい目をしている。全てを見透かし、受け入れるように。
「……私こそ、悪かったね。大事な時に眠りこけていた。君たちも休息を取ってくれ。やるべきことはあるが、無理は禁物だ」
「――はい」
「わかり、ました」
一礼し、学長室を辞す二人。彼らにも彼らのやるべきことがある。
ハルだけが室内に残っていた。
最後に確かめねばならないことがあった。
「学園長」
「何だい」
変わらず泰然として、ハルの言葉を待つナガツキ。
呼吸を整え、その名を口にする。
「――キウは、」
この世界の法則。普通に考えれば、当然に起こりうること。
それなのに、どこか遠く感じていたこと。
「死んだんですか?」
キウに。花人に。
死ぬ、ということが起こりえるのか。
絞り出した質問に、ナガツキは、はっきりと頷いた。
「永遠に続くものは無い。
誰かの口からはっきりと聞いたのは、それが初めてだった。今の今まで悪い夢のように感じていた部分が、重すぎる現実として腹の底に落ちた。
花人の身体能力と回復力は、人間のそれを大きく上回る。ただしそれは「死ににくい」というだけで、「死なない」というわけではない。ハルがそうだったように、花人にだって死のリスクは常につきまとう。
それを押して、彼らは戦ってくれた。
「ハル。これも
返事は、すぐにはできなかった。
✿✿✿
その日の夕刻、ナガツキから学園全体に通達があった。
過日のキウ班の探索中に起こった出来事。その簡単な顛末。
剪定者の行動パターンの激変と、それについて目下調査を進めていること。
キウが、もういないこと。
「――けれど、どうか悲しまないでほしい。キウは消えてなくなったわけではない」
短い通達を、ナガツキはこう締めくくる。
「我々が彼を覚えている。そして、花はきっと、いつかまた咲く」
日暮れ頃の『月の花園』は、普段とはまた違う雰囲気だった。
昼は陽だまりとなり、夜には月光を受けるこの場所が、今はどちらの光も無い。空が朱から藍に変わるこの刻限だけ、花園は月も星も太陽も届かぬ陰となる。
ただ飛び交う蛍や紋様蝶だけが、唯一の光源となって花々をぼんやり照らしている。全体が静謐さを深め、どことなくこの世ならざる幽玄さに満ちていた。
アルファは、何事も無かったかのように花の世話をしている。ナガツキの通達も聞いていたのかいないのか、その佇まいに変化は無い。
そんな彼の背中を、ハルはなすすべもなく見ている。
アルファは振り向こうともしないが、とっくに気付いているだろう。いい加減に声をかけようと思った。しかし、自分が彼に向ける醜悪な願望を思い、すんでのところでためらってしまう。
「わたしが迂闊だった」
にわかに、アルファの方から口を開いた。背を向けたままで。
「え」
「これまでに無いことが起こった以上、
――違う、
「違うよ。アルファは助けてくれたでしょ。悪いのは、全部あたしだよ!!」
お前のせいだ、と。
一言でいいから、誰かに糾弾してほしかった。
ネーベルは何も言わなかった。ウォルクも会ってくれようとはしなかった。ならアルファなら言ってくれると思っていた。身勝手な期待だ。けれど、外へ行きたいと言い出したのは自分だ。キウたちについて行ったのも自分だ。あの夜、先走って敵の罠に飛び込んでいったのも自分だ。
そのくせ、何もできなかったのも、自分だ。
忠告に耳も貸さずに、あるかもわからない可能性に縋って。実体の無い「約束」などという幻影を追い求めたツケを、よりによってキウたちに払わせてしまったのは、他でもない自分なのだ。
「だったら何だ。お前の責任で、全部元通りにできるのか?」
「それはっ――」
「……行けよ。花の世話で忙しい。これは、わたしの仕事だ」
花園もアルファも、どこまでもいつも通りで。
一人取り残されたハルは、ただ俯いた。
「……じゃあ、あたしは、どうしたらいいの」
全て間違っていたように思う。視界に映る靴先が滲んで見える。縋るべき藁さえ無く、事実だけを心の臓に突き刺され、前にも後ろにも進むことができない。
「――――ならせめて、忘れるな」
しばしの沈黙を置いて、アルファが言った。
反射的に顔を上げると、彼は体ごと振り返って、こちらをひたと見据えていた。
「……あの夜のこと?」
「全部だ。ここで起こったこと。お前が見たこと。ここにある、花のことを」
アルファはふと、ある一輪の花を指差す。鮮やかなオレンジの花だった。
「カフス」
次に、木の枝に連なる白い花。
「シルバー」
小さな池に浮かぶ、天を目指すように咲いた花。
「サン」
下垂した蔓を彩る、青紫の花。
「カザミ」
花の種類ではない。それとはまた違う「何か」を、アルファは告げている。
「レーウィン。スノウ。マリイ。エリシャ。ヒラルダ」
次の花、次の花、次の花――無差別に、目に付くまま、花園に咲くものたちを次々と指差してゆくアルファ。その度に、一言一句を刻むように「それ」を呼ぶ。ハルは徐々に、その意味に気付きつつあった。
名前、ではないか。
それぞれが意味を持つ、図書館で一つ一つ拾った言葉からなる独自の名前。
誰かが、誰かに付けた名前。
最後にアルファは、ある花をぴたりと指差して止まる。ついさっき芽吹いたばかりと思しき、片隅の小さな小さなそれは、まだ何の花かすらもわからない。
けれど、きっと黄色いチューリップだろう。
「キウ」
――あたしの、なまえは、
たちまちハルは、ここがどのような場所なのかを理解した。
『月の花園』とは、色とりどりの花々の墓。
桜の花人、アルファは、その墓守であると。
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます