第2話 機械と樹海
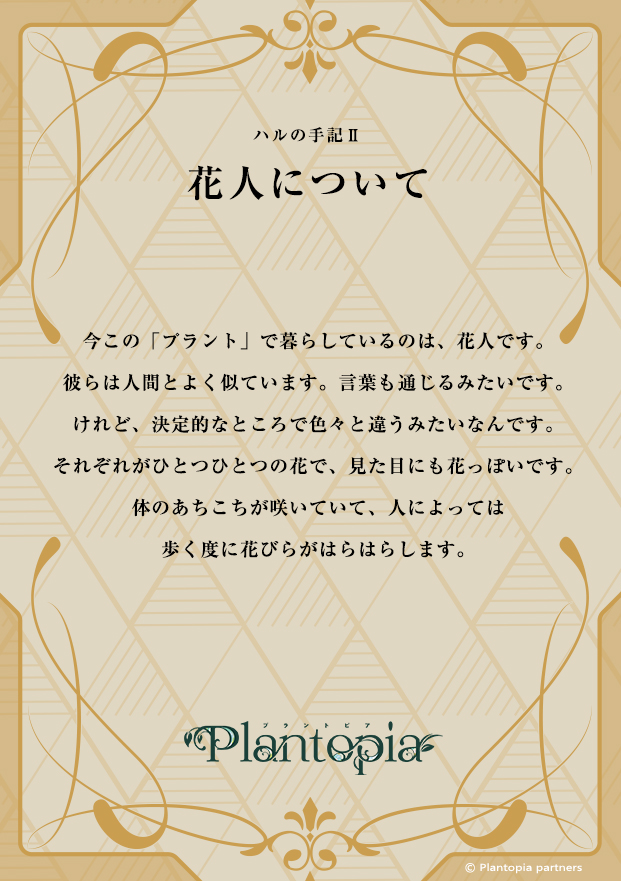
「構成はいかほどでありますか?」
「小さいのが四。中くらいで丸いのが二、ドリルが一ってところ、です」
「めんどくっせえなー。こういうとこにまで出てくるようになったのか」
「なんでもいいじゃんぶっ飛ばせばさ! 軽い軽い!」
黄、白、ピンク、もうひとつ黄――深緑の樹海に、人型の鮮やかな花が在る。
彼らは皆、学外活動用の外套を着けている。これらはプラントの森で採れる「鋼条樹」の蔓からなる特殊繊維で構成されており、軽い上に硬く、優れた防刃・耐衝撃・難燃性を誇る。更に口元までも覆っており、花人によっては目深なフードで顔全体を隠す者もいる。これは有毒な胞子やガスから呼吸器を守る目的もあるが、それ以上の意味もある。
そして彼らは、戦闘時に限り、口元の覆いを外す。
「ぷは。けど、クドリャフカもいるし、大丈夫だと思う、です。お願いします」
「無論であります。では――」
先頭に立つのは長身の花人。担ぐ得物もサイズと重量からして違い、いかにもたくましい。
精悍な顔付きは好奇心旺盛な少年のようでもあり、同時に、歴戦の戦士のような凄味も湛えていた。アーモンド色の瞳が睨む先には森の薄闇があり、その奥で影が蠢いた。数は七つ。どれも花人より大きく、幾何学的で――禍々しい。
赤い光点が生まれる。奴らの目だ。
Ⅰ式斬甲刀【Pd-01】開花。
汎用の近接装備を展開し、白く冴えた刃鋼をその手に取る。向日葵の花人、クドリャフカは、異形の天敵に怯むことなく吠えた。
「始めましょうか。ハカセのもとに帰るまでが、探索といいますからな!!」
芽の季、八日。翅の三刻。日差しに朱色が混ざり始める頃。
西部探索担当「キウ班」、戦闘開始。今回に限り用心棒として、研究室所属の護衛兼新装備テスター、クドリャフカを随伴させている。
❀❀❀
「――なあ。一応聞くんだが……」
「やめてやめて言わないでそっとして」
「……どうやったら、そんな器用にコケられるんだ?」
「うあああ! しょうがないでしょ慣れてないんだから!」
一方ハルはといえば、両脚を上にして派手にひっくり返っていた。
幸い綿毛のようにもふもふの草むらに突っ込んだから怪我はなかったものの、ひっくり返って吹っ飛んで三回転してこうなるのはアルファから見ても珍しいことのようだ。
仕方ない。馬になんて乗ったことがないのだ。
多分これは記憶云々は関係ない。そもそも「
目的地である迷夢の森までは、まだ距離がありそうだ。アルファは自分の幽肢馬から降りて、手元でひらひらしている蟲を一瞥した。
「もう始まってるな」
「え!? うそ!? どこで!?」
「西南西に二キロと少し。始まったばかりだ。まだ激しくはないが、すぐ終わるかもな」
手元の蟲は蝶だろうか。仄明るく発光しており、生物的というより、何かの文字に見えなくもない。その翅らしき部分が、淡いオレンジ色の光を放っていた。
と、アルファがこちらに手を差し伸べる。
「ほら」
「え?」
「見たいんだろ。早く乗れよ。このままじゃ終わっちゃうぞ」
「いや、乗れって――」
アルファの後ろに?
目配せの様子から察するに、どうやらそうらしい。連れてってくれるの? ――と目で聞くと、アルファは急にばつが悪そうな顔をした。
「……お前はろくに馬にも乗れないだろ。見学もさせられなかったら、ナガツキにねちねち言われるのはわたしなんだ。もう一匹の方なら呼べばついてくる、いいからさっさとするぞ」
「あ……うん、ありが」
「飛ばすからな」
「ぶわっ!?」
手を掴むと、思いのほか強い力で引き上げられた。そのまま担ぎ上げられるんじゃないかと思うほどだ。同じくらい細い腕なのに、花人の力は人間よりずっとあるのかもしれない。
あっという間にアルファの馬に乗せられ、そうかと思えば一気に加速する。振り向けば、さっき散々暴れて振り落としてくれたじゃじゃ馬が、驚くほどスムーズに追随してきていた。
風景の緑が高速で流れ去る。走り続けるにつれて樹海の陰は濃さを増し、やがて前方が暗くて見通せなくなってきた頃、激しい金属音のようなものが聞こえてきた。
そして、闇の中にちらつく火花が見えた。
❀❀❀
花人たちが踊っている。
淀みを知らず、声も上げず、一瞬たりとも留まらない。それはあたかも、森の大気を圧縮したが如く激しい渦を形成する人型の風だった。
風は花の色をしている。火花、轟音、振動。ハルの動体視力ではろくに動きも追えないが、あれが戦闘だということはわかる。束の間、方向転換に立ち止まるなどする際、花人たちの姿を見ることができた。彼らは各々の手に武骨な得物を握って、その動きに残像のような花弁を舞わせ、留まるどころか更に加速さえしていく。
その包囲の只中に、異形があった。
獣とも蟲とも言えない。小さなものでも花人より二回りは大きく、大きなものでは周辺の樹木をも上回る。体を構成する物体は、森にあるものとは全く違う。金属、精錬した鋼材、何らかの化学物質――あれは「機械」? プラント由来の存在には思えない。自らの判断で動いているように見える。一体一体が得体の知れない動力によって端々にまで力を漲らせ、その一つ一つに、
悪意がある。
「あれが剪定者だ」
ぽつりと、アルファ。
「こっちが勝手に呼んでるだけだけどな。あいつらは花人を刈りに来る。わたしたちにとっては、このプラントでの一番の脅威だ。ガスや胞子や、暴れる獣や遺跡のトラップより危ない」
「剪定……」
にわかに、背筋が寒くなるのを感じた。
遠目にもわかる、あの異物感。こちらとは違った倫理で動いているらしい「何か」は、間違いなく花人を狙っていた。
「……どうして、そんなことするの?」
「理由は知らん。とにかく向こうから狙ってくる以上、こっちもどうにかしなきゃならない。……黙って刈られるのは、誰だってごめんだ」
理由も知らないまま、明確な敵意だけが向けられる。
そんなものが向こうから来て、否が応でも対処せざるを得ない、など。
『怖い、と思いました』
この件を文にしたためようとするなら、まずはそう書くだろう。
『はっきりとそう思ったのは、目が覚めてから初めてです。
だってあんなものは見たこともなかったから。いつ何度思い返しても、ぞっとすると思います。
みんなは大丈夫なのか。あたし自身は。そんなことで頭がいっぱいでした。
だけどその後で、もっと凄いものを見たんです』
今ハルとアルファは、一帯で最も高い巨木の上に身を潜めている。
離れているため、ここにいれば余波を受ける心配は無いとのことだったが、今やそれとは別の心配を抱かざるをえなかった。そんなハルの心情を読み取ってか、めんどくさそうにアルファが付け加える。
「何の心配してるんだ。お前は余計なこと考えなくていい」
「でも、あんなのどうやって」
「いいから見てろ。見学したかったんだろ」
むん、と、剪定者が動く。ひときわ巨大な個体だ。腕にあたる部位に破壊的な力が漲り、先端の円錐状のパーツ――ドリルが高速回転。ここからでも聞こえる凶悪なモーター音と共に、突き上げられた。
危ない、と叫ぶところだった。狙いは黄色の花人――キウだ。彼は小型の一体を仕留めたばかりで、ちょうど大型に背を向けているところだった。土塊が弾け、進路上の巨岩を砕いてなお勢いを緩めぬ攻撃は、狙いそのまま彼の背中に迫る。
避けようとしたが、一瞬遅かった。鋼の暴威が花人を掠める。
キウの外套の側面が破れ、右腕が大きく抉られた。
「……!! キウっ……!」
体が勝手に動いた。危うく木から転げ落ちそうになるところ、アルファが襟首を掴んで止める。
「馬鹿、頭を出すな。見つかるぞ!」
「だってやられちゃったよ!? あんなに腕が! ぜ、絶対痛い――っていうか痛いとかそんなもんじゃ……!」
遠目にもわかる。体液が飛び散り、キウの右下腕部がほとんど無くなっている。自分の身長ほどもあるドリル相手なら、掠められただけでああなって当たり前だ。
しかし、アルファは平気な顔をしていた。
「『痛い』? なんだそれ」
「え」
古代文字を見るように、「人間」を見るように。そういう時と同じ、アルファの反応は「まるで知らないもの」に対するそれだった。
「お前の言ってることはわからないけどな。どっちにしろ、あの程度は傷のうちに入らない」
次の瞬間、遠目にもわかるほどはっきり、キウは笑った。
――ばァか。
好戦的な瞳で敵を睨みながら、彼の口は、確かにそう動いた。
信じられないことが起こった。飛びのいたその一瞬で、キウの右腕が再生したのだ。あっという間の出来事だった。一秒もすれば振り上げられた腕は完全な形を取り戻し、しかと剣を握りしめている。
ハルは唖然としたまま、ただ見ているしかなかった。
キウは外套を翻し、仲間との陣形に戻る。紙一重の見切りで攻撃を回避。後ろにも目が付いているのかと思った。続く連携も完璧で、何の合図も無いまま巨体への包囲を狭める。
渦巻く旋風の中、楔のような震動が発生した。ひときわ背の高い花人が、ドリル持ちの懐に飛び込み――
「どォっ、せぇええいいいいッ!!!」
猛々しい咆哮と共に、下から上の斬撃を放つ。
半月状の軌道は確かに敵を捉えた。装甲の薄い関節部に切り込み、ものの一撃でドリル部分を切断してのける。
あれほどの巨体を、花人たちは一顧だにしない。
まるで彼ら自体が、森の異物を排除するひとつの自然現象のように。
戦いを見守るうちに、ハルの中にある一抹の心配は、まったく別の感情に取って代わっていた。
――すごい。
すごい、すごい。
すごいすごいすごい。
「だからあんまり乗り出すなって。危ないだろ」
ぐいっと肩を引かれて正気に戻った。とはいえアルファも、自身が言うほどに「危ない」とはまるで思っていないようだ。
「……もう終わるか。クドリャフカがいるからな。やっぱり来るまでもなかった」
「クドリャフカ? あの背が一番高いひと? 強いの?」
「まあまあ」
アルファはあぐらをかいて頬杖を突き、退屈そうに戦局の趨勢を見守っている。心底興味が無さそうに見えるが、澄んだ目は絶えず花人一人一人の動きを観察し続けていた。
「キウもああ見えて冷静だし、ウォルクとネーベルの動きも悪くない。相手も見慣れたようなタイプだしな。もともと負ける戦いじゃなかったんだ」
どこにあれほどの力が宿るのだろう。分厚い鋼板をそのまま研いだかのような長剣で十重二十重の斬線を描き、花人たちは機械仕掛けの巨躯を逆に刈り取ってゆく。何が最も凄まじいかと言われれば、その連携だ。刃と刃のぶつかる軌道でも、ミリ単位の微調整でかち合わせず、互いの最適とする攻撃コースを描いて見えた。
「――どうして、あんなにスムーズに動けるの? なんかみんな、あらかじめわかってるみたい」
「匂いだよ」
「匂い?」
「つまり――」
アルファは、自分の鼻先を指差した。そこで初めて気付いたのだが、戦域に入ってアルファは口元の布を外している。移動中は覆ったままだったのに。最前線で戦っている彼らも同じだった。
「花人には『匂い』がある。一人ひとり、違った匂いだ。花人はその匂いでお互いを識別する。そいつが誰なのかだけじゃなく、そいつが何を感じて、何を考えてるかもな。慣れた奴らなら、鼻さえ利かせれば仲間がどこにいてどう動くのか簡単にわかるんだ。反面――」
「せえええりゃああああああッッ!!」
ここからでも聞こえる裂帛の気迫と共に、最後の一体が両断された。アルファはその様をしかと確かめ、
「――
匂い――
自身が「花」である彼らにとって、それは最大のアイデンティティであるだろうか。この深い森の中にあって、人間の鼻にはあらゆるものが混ざり合った匂いとしか感じられない。けれど花人は、そのひとつひとつを的確に嗅ぎ分けることができるのだ。仲間の個体識別から、小さな異常、異物まで。戦闘時以外には口元を外套で覆っているのも、プラントの
と、ここまで考えたところで、ハルはあることが気にかかった。
敢えて知らんぷりをしていた方がいいような気もするが、思い立ったら聞かずにはいられない。
「…………あたし、どんな匂いする?」
すん。アルファは鼻を一度だけひくつかせて、
「人間臭い」
「『人間臭い』!?」
翅の四刻、戦闘終了。装備・構成員ともに被害なし。
剪定者から分割したパーツは、帰還後、研究室のスメラヤ班に回される。
❀❀❀
「え、と……歩兵型が四と、瘴気妨害型が二。それで、重装突撃型が一体……ですね」
「で、あります」
「回収できたパーツは、右腕部のオートドリルと、中型のファンとプロペラが二基、伐採用のブレード、持ち運べるだけの計器と装甲……」
「であります!」
紫色の花人は、目の前のガラクタの山と目録を見比べ、満足げに頷く。
「……うん。おかげで、装備の不足分が補えそうです。ありがとうございます、クドリャフカ君」
「なんのなんの! ハカセのお役に立つことが、自分の喜びであります!!」
「おひぇっ……は、はい、あの、気持ちは嬉しいんですが、あんまり大きな声は……びっくりするので……」
学園の一角に構えられた「研究室」は、他の部屋とは一味も二味も違った。
まず置かれているものが違う。ハルが知る限りの学内施設は、自室も含めて、ざっくり言えば「木製」といった感じだ。大きな樹の上、あるいはその中に作られているので、自然の中にぽっと生活圏が生えてきたような不思議な統一感がある。
ところがこの部屋には、見たこともない機械や装置が山と積まれている。小さなものは片手に乗る程度、大きなものは見上げるほどで、何をどう使うものかもさっぱりわからない。壁から生えた鋼鉄製のアームは一体何を掴むものなのだろう。
ツールボックスをぶちまけたような部屋の中心、複数ある中で最も大きな作業台の主は、ハルよりも小柄な花人だった。
「と、とにかく、作業を始めましょう。まずは細かいものから。使えるコンパスが少なくなってきたので、この磁力計を改造して……」
「了解であります!! ……おや? 何か忘れているような……」
ハルは研究室の隅っこで事の成り行きを見守っていた。そろそろいいだろうか、声をかけてみよう。
「あの」
「ぴぇえい!!?」
いきなり「ハカセ」の体が数センチ浮いた。かと思えばドタバタひっくり返ってぐるぐる回りながらかろうじて体勢を立て直し、大柄なクドリャフカの後ろに隠れる。今の今までハルの存在自体に気付いていなかったらしい。
「どっどどどどどどど、どちっどちっどどど、どそ、どら」
「ドラ?」
「どどど、どち、どどどちらささささまままでででしょうかかかかかか」
「おお、そうでありました! こちらの御仁は自分が招待したのであります!! ほら、例の人間殿でありますよハカセ!!」
「にんげん」
ぴたり、と一瞬ハカセとやらの動きが止まり、瞳の奥に鋭い知性の光が宿った気がした。
「……に、んに、んにっ、にににんげんげげげ……」
またぶるぶる震えだした。気がしただけかもしれない。
「…………え~っと、あたし出直そうか?」
「お気になさらず!! ハカセは極端にシャイなお方でありましてな!! 顔見知りでないお相手をお見掛けすると、高確率でこうなるのであります!!」
「お、おき、おき、おきに、おきにに……」
そう言われても、と思うハルだった。
結局「ハカセ」が落ち着きを(比較的)取り戻したのは、蟲時計がもう一度鳴いてからのことだ。改めて話をすることになったのだが、
「研……にご用……ょうか」
「いや遠い遠い遠い! なんで入り口のとこいるの!? よく聞こえないんだけど!」
しかも体が半分廊下に出ている。
「ハカセ! よろしければ、自分がハカセの言葉を通訳いたしましょうか!?」
「…………ぃします」
「『お願いします』だそうであります!!」
それはなんとなくわかる。
ぽつぽつ何か喋る「ハカセ」と、ふんふん頷くクドリャフカ。ハルにはさっぱり聞こえないが、あるいはこのやり取りにも例の「匂い」が介在しているのかもしれない。
「失礼、『まずは自己紹介』でしたな! ――改めまして、自分はクドリャフカ! 向日葵であります! あちらのハカセは、スメラヤという名でいらっしゃいます!! ラベンダーであります!!」
「あたしはハル。知ってるかもだけど、人間です。よろしくね」
「ハル殿ですな!! お噂はかねがね!!」
ラベンダー。向日葵。名前と共に、メモに書き記しておく。
一応、こちらの目的も話しておいた方がいいだろうと思った。
「ええと、ここに連れてきてほしいって頼んだのはあたしなんだ。探索が終わった後、クドリャフカたちは色んなパーツを持ち帰ろうとしてたでしょ? あれってどこに持っていくのか気になって」
「で、ありましたな! アルファ殿はいらっしゃいませんでしたが!」
そうなのだ。アルファは学園に帰るなり、月の花園へさっさと戻ってしまった。学内ならハルをほっぽっても安全だという判断かもしれない。
「――しかしながら、あれですな。近辺に来られていたのであれば、アルファ殿の戦いぶりも是非拝見したかったところなのですが」
「え? アルファって強いの?」
「噂でありますがな。実戦に出たところは誰も見たことがありません。なにしろ、彼には花守という大事な仕事がありますゆえ!」
そういうものなのだろうか。ハルはまだ、彼のことをよく知らない。
また向こうでハカセ改めスメラヤがぽしょぽしょ言って、クドリャフカが通訳を続ける。
「ともかく――『気になるのなら』ということでしたので、軽くここの説明をいたしましょう。この部屋はハカセを室長とする、学内唯一の研究室であります! 学内の設備や我々の各種装備を製造・整備してくださる、いわば戦略上の生命線ですな!」
「それじゃあ、さっきみんなが使ってた武器みたいなのもここで?」
「ええ! 全てハカセが手掛けておりますぞ!」
武器も――なるほど。ハルは山と積まれた剪定者の部品を前に思い出す。当のクドリャフカが最後に放った、素晴らしい斬撃。その切れ味といったら。
「じゃあ、あの武器は
「!」
向こうでスメラヤが目を丸くした。
「おお! 何故おわかりに?」
「だって、あいつらすごく硬そうだった。多分だけど、そこらの岩にぶつかったくらいじゃビクともしないでしょ? そんなのをあれだけ簡単に解体するってことは、同等以上の硬さの素材が無いとダメってことになる」
「!!」
とっとっとっとっ、とスメラヤが寄ってきた。
「わ、わか、わかりますか?」
「パッと見た感じでだけど、あいつらみたいな造りのモノは他のどこにも無かったから。最初はどこかから素材を採ってるのかなと思ってたけど、そうでもなさそうだったし、なんとなく」
伏し目がちだったスメラヤの視線が、今はしっかりハルに注がれている。
「そ、そう、そうなんです。たとえばですが、森の奥の山岳地や洞窟などには、鉄鉱石などが採れる採掘地が存在しますし、学園のもっと下層の施設では小規模ながら製鋼所もあります。もちろんそうやって作った金属類も役に立っていますが、剪定者の装甲を破るには難しいです。よって、彼ら自身の部品を鹵獲して流用する以外に現状手はありません。もっとも、花人の手にも扱いやすいように加工する必要はありますが」
「でもそれっておかしくない? そこまでやらなきゃどうにもできない素材なんて、逆にあいつらの側はどうやって用意してるの?」
「!!!」
今度こそ、ぱぁぁぁっという音が聞こえてきそうなほど彼の表情が華やいだ。
「そうなんです! 彼らには謎が多くそもそも『剪定者』という呼び方自体我々が作った仮称なのですが度重なる遭遇にもかかわらず彼らの出どころは一切不明のままで出没地点も不定なので生息地を逆算することも難しくまた幾度の解析や追跡も空振りと終わりましたが現状の仮説としましては遺跡の建造物に見られるきわめて高度な冶金技術との共通点も見られるため両者には何らかの関連性があるものと見て遺跡調査も急務と」
「ちょ、ちょっと待って待って! メモが間に合わない!」
「はっ」
身を乗り出したスメラヤに押される形で、気が付けば作業台にまで追い詰められていた。ぽわっ、とにわかにラベンダーの香りが濃くなった気がする。
「ごごごごごごめんなさいいいいいい」
「わはは! ハカセが自らここまでお話しになるとは! そう照れることはありませんぞ!!」
あ、これは恥ずかしい時の香りなのか。
圧倒こそされたものの、噛み砕いてみるとスメラヤの言うことは至極もっともだ。
あれほどの――あるいは学園を上回るレベルの――技術の結晶は、一体どこから生まれるのか。そもそも何が目的なのか。何故、花人を刈ろうとしているのか。
さっとメモに書き記し、ペンの尻で頭を掻く。剪定者。花人の戦闘。技術レベルの違いについて。
「――あの、良かったらなんだけど、また詳しく話を聞かせてくれる? 今日は忙しいかもだから、今度時間ができたら」
「……! は、ははは、はい! ぼぼぼボクでよかったら喜んででで」
「おお! ハル殿もこうした話はかなりいける口ですな!? いやはや、かくいう自分はちんぷんかんぷんでしてなわはは!!」
いける口、なのかもしれない。
なくした記憶の補填とするため、とにかく知識を詰め込む段階だというのはある。しかしそれを差し引いても、何かを作るとか、技術がどうとかいう話は、妙に馴染む。
「して、ハカセ! 今後自分はどのように動きましょう!?」
「え、と、そうですね。せ、製造の方は問題ないので、クドリャフカ君は、ほ、他の皆さんの護衛についてあげてください。確か北西方面に、い、遺跡の調査にあたる班がいたはずです」
「廻炉の湖の方面ですな! 当該地区には
「問題は、ない、です。い、今はまだ芽の季で、そ、そちらの
「了解であります!!」
遺跡。廻炉の湖。遺跡歩き。紋様蝶。遺物。
それらも書き留める。この学園の外は、当然ながら、知らないことばかりだ。
「……っ」
人知れず息を呑む。ぶるる、と体が震えるのがわかる。
知らない場所。知らない情報。知らない出来事。正直に言うと、わくわくしていた。あんなにも鮮やかに躍動する花人たちにも。
もっと、知りたい。どんなことでもいい、この世界を、少しでも。
❀❀❀
研究室を出る頃には、日はすっかり西に傾いていた。
見上げる巨木が朱色に染め上げられている。昼よりいくらか冷たさを増した風は、また違った香りを運んできているような気がした。東の彼方に、絵の具を混ぜたような夜の藍がある。
ハルも、実のところ自分の中で結論は出ている。
理解していかなければいけないのだ。少しずつでも。
この時点でハルの好奇心は、既に学外の広い世界に向き始めていた。
もっとも、それを「世話役」のアルファが許すかどうかは、まったくの別問題なのだが。
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます