プラントピア
九岡 望/電撃文庫・電撃の新文芸
第1話 花の世界
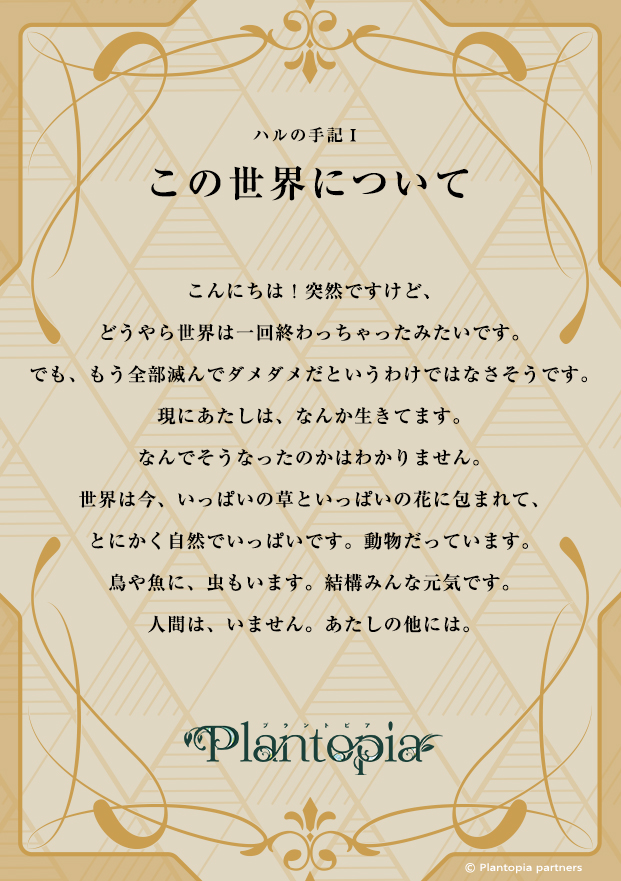
ずっと前に、誰かと大切なことを約束し合ったような気がする。
❀❀❀
『いつか逢うだろう、あなたへ:
こんにちは!
突然ですけど、どうやら世界は一回終わっちゃったみたいです。
でも、もう全部滅んでダメダメだというわけではなさそうです。現にあたしは、なんか生きてます。
なんでそうなったのかはわかりません。世界は今、いっぱいの草といっぱいの花に包まれて、とにかく自然でいっぱいです。動物だっています。鳥や魚に、虫もいます。結構みんな元気です。
人間は、いません。あたしの他には。
ナガツキ学園長が言うには、種としての「人間」はずーっと前にどこにもいなくなっちゃったみたい。理由はわかりません。誰にもわからないみたいです。
今このプラントで暮らしているのは、花人です。
上に書いたナガツキ学園長も、その花人です。学園にいるのは、あたし以外みんなそうです。彼らは人間とよく似ています。言葉も通じるみたいです。けれど、決定的なところで色々と違うみたいなんです。
彼らが、人間に似てるんでしょうか?
それとも人間が彼らに似てるんでしょうか?
今はまだわかりません。もし、あなたや他の人間たちを見つけることができたら、その辺りも話してみたいと思います。だから、あなたにいてほしいです。この文字が読めるあなた。どこかにいるかもしれない、名前も知らないあなたへ。
名前で思い出した。書き忘れてました、ごめんなさい!
あたしの名前はハルっていいます。
学園長が付けてくれました。名前の意味は、「もうこの世に存在しないもの」だそうです。
いつか、あなたの名前も聞かせてもらえたら嬉しいな。
それから、花人についてですけど――』
続く文面を考えているうちに、時間が来てしまった。
壁にかけた蟲時計がりんりんと音を立てる。芽の季、八日。翅の一刻。日が最も高く上る時。
「やばっ! 始まっちゃう!」
窓を開けて身を乗り出すと、色のある風が吹いた。
その色は花、草木、土に獣。あらゆる香りが混然一体となり、風に運ばれたそれらは鼻腔をくすぐる度に豊かな彩りを想起させる。
地平線の彼方まで、碧い樹海が広がっていた。
遥か向こうに、天を衝く樹がある。まるで空を支える柱のように太く、高く、その頂点は青空の果てに霞んで見えない。遠すぎてスケール感が狂ってしまうが、幹の直径は今自分たちが暮らす『学園』よりずっと太いのだという。
花人は、あれを『世界樹』と呼ぶ。全ての命が生まれ、そして還る場所だと。
今日は終日雲ひとつ無い快晴で、だから条件が合っていた。
『播種』の時間だ。
「わぁ……!」
次の瞬間、世界樹が光を撒いた。
それは幹を中心にぶわっと広がり、晴天の中でもなお鮮烈にハルの目に焼き付く。光の粒は数千、数万にも及ぶだろうか。輝きながら地表へ落ちていくそれらは全て種子で、地上に根付いては新たな命を芽吹かせると言われている。プラントを構成する木々も草花も、全てはあの世界樹から始まったのだ。
あれが見たかった。鉛筆を走らせ、播種の様子をざっとスケッチしながら、ぽつりと。
「――あたし、あそこから来たんだよね」
少なくとも、そう言われている。
ハルは、学園から遥かに離れた南の森の奥深くで拾われた。見つけてくれたのは、学園周辺をパトロールする巡回班ではなく、ただ一人。今にして思えば一体全体どうしてあんなところに、しかもたった一人でいたのかわからない、ある「桜」の花人だ。
播種が終わった。ハルは窓を閉め、被服班に作ってもらった人間用の上着を羽織る。文面の続きは、頭の中でまとめておくとしよう。
学園長に、今日の予定を伝えに行かなければならない。
❀❀❀
スミレ。
シオン。
デイジー。
ヒヤシンス。
「あ、新顔」
「新顔って、あの『人間』の?」
アザミ。
ダリア。
マリーゴールド。
「ほんとだ。匂いが違う」
「あれが例の……」
「ちょっと怖いかも……」
「外のドーブツと何が違うの?」
サフラン。
スイセン。
キンギョソウ。
カルミア――
すれ違う相手全てから、別々の香りがする。ハルはびっしり書き込んだ手帳を片手に、彼らがそれぞれ何の花なのか意識しながら進む。
巨木をくり抜いた回廊はゆるやかにカーブして、数階層も下まで続いている。高低差に富んだ学園の敷地は、目覚めたてのハルにはなかなかにきついのだが、道行く花人たちの足取りはみな軽やかだ。彼ら全員に固有の香りがあり、そして色があった。
『花人は、名前の通り、花の人です。それとも人の花なのかな?
それぞれがひとつひとつの花で、見た目にも花っぽいです。体のあちこちが咲いていて、人によっては歩く度に花びらがはらはらします。彼らの中で生活してると、なんにも咲いてない自分がちょっと恥ずかしくなります。
あっちにとっても、人間は珍しいみたいです。だって初めて見る動物だから。今のところ、ちょっと遠巻き気味です。無理もないかなぁと思います』
手紙の文面をつらつら考えてみる。ハルに対する花人の反応は様々だ。じろじろ見てくる奴、逆に見ないふりをする奴、妙に怖がる奴、顔をしかめて外套で鼻を隠す奴。
『・花人は一人一種。たくさん種類があっても、同じ花は一人だけ。
・性別は無いみたい。どっちでもある? どっちでもない? 二つに差は無いのかも。
・食事の必要もなさそう。食べてもいいけど、最悪日光と水さえあればどうにでもなるんだとか』
ゼラニウム、ハナズオウ、アルストロメリア――すれ違う花々。それぞれから意味ありげな視線を感じる。その誰もが、自分からハルに話しかけてくることはないが――
「いよう!」
「わっ」
いきなり、後ろから背中をばしーんと叩かれた。
「あてて……えっと。確か……」
「キウな。何やってんの新入り? どっか行くの?」
チューリップ。色は黄色。名前の意味は「待ちわびていたもの」。
中には、こうやって積極的に絡んでくる花人もいる。彼はとても好奇心旺盛な性格のようで、目覚めたばかりのハルを質問攻めに遭わせたことは記憶に新しい。
「学園長のとこ行くの。色々と報告。キウは?」
「あそっか、学園長まだ起きてる時期か。アタシはなー巡回! なんか西んとこの遺跡にガチャガチャしたのがいんだって! まあなんとかなるっしょ!」
「巡回かぁ……。あたし、まだ外出たことないんだよね。気を付けてね」
「おう! でさでさ、それ何持ってんのー?」
「手帳。見る?」
「みるみるみる!」
いつも好奇心にきらきらしている目が、ハルの手帳に留まる。渡してみると急いでパラパラめくり、色々なスケッチに目を輝かせるも、やはり文字で躓いた。
「うげっ、古代文字! 読めねー!」
これがハルにはよくわからないのだが、今自分が当たり前に使っている文字は「古代文字」といって、ほとんどの花人には読めるものではないらしい。解読できるのは学園長と、ライブラリにいる資料班の花人くらいのもの。言葉は通じるのに不思議だ。彼らはどこで言語を学んでいるのだろうか。
「今度教えようか? そんな難しいもんじゃないと思うけど」
「えー、いいよぉ。そーゆーのは委員長とかスメラヤ室長に任すってば。アタシあんま頭よくねーし」
「――キウ! 早く!」
と、向こうから別の花人の呼ぶ声。キウは慌てて、
「あヤベ、もう行かなきゃ! じゃな新入り!」
「うん、ばいばい」
笑いながら去っていくキウを見送り、手帳を閉じる。もう学長室の前だ。
重く分厚い壁を開けると、眼前に鮮やかな赤が広がっていた。
学長室の中心には大きなベッドが鎮座している。削り出した木のベッドには夥しい数の花が根付いており、半ば以上はその茎に支えられているようにすら見える。花の色は全て赤。一輪残らず、燃えるようなヒガンバナだった。
ナガツキはベッドの前に立っている。周りのどの花よりも赤い、足先まで届くほど長い髪を垂らして、彼は何かの報告書を「読んで」いた。ハルが使う文字ではない。彼らが指先で触れる板に何が「書かれ」てあるのか、ハルに読み取ることはできない。
「こんにちは、ハル。調子はどうかな」
「こんにちは学園長! まあ、ぼちぼちって感じですかね」
少し眠たげな、優しい視線がこちらに注がれる。案山子のように細身で、見上げるほどに背が高い。彼自身が茎の長いヒガンバナのようだ。
「手紙は、まだ書いているのかい?」
「はい。今、四十九通目を書いてるとこです。もうすぐできそうかも」
「それはいいことだ。五十までいったら食堂のニハチに伝えてみなさい。ご褒美にデザートをおまけしてくれるかもしれない」
ニハチというのは学園の食堂をたった一人で切り盛りしている花人だ。古代より続く「料理」という文化を重要視しているが、そもそも花人は食事自体あまりしないため空回りし続けていた。そこへ毎日の食事が必要なハルがやってきて、毎日物凄く張り切っている。
何かのご褒美になるくらいには手紙を書いた。
けれど、そのどれも、誰にも渡す宛ては無い。
「……他の人間、やっぱり見つかりそうにないですか?」
「――そうだな。どの探索班から上げられる報告書も、結果は『異常無し』だ。君が突然現れたような、過日の異例の播種も起こっていない。現状ではあれがイレギュラーだったと言わざるをえないね。なにしろ何の予兆も無かったものだから」
てっきり同じことが続くのだと思っていたが、そうではないらしい。
唐突に始まったものは、やはり唐突に終わるものか。
……だけど、それでは困ってしまう。
「ハル。君は今のところ、この世界で唯一の人間だ。我々花人の歴史もそれなりに長いが、君のような存在と遭遇した前例は無い。したがって、君が何者なのか。どのように、どうして現れたのかについては、君自身の記憶が必要不可欠な情報になるわけだが……」
記憶。
どこから、どうやって来たのか。
「まだ、新たに思い出すことはできないかな?」
「……なんにも。あのこと以外は……」
それはまだ、空白のままで。
「そうか。いや、気長にやるといい。幸い多くの花人は君の存在に対して肯定的だ。遥か過去に存在していたらしい種族に対して、我々の興味は尽きないからな。それに、花人は若ければ若いほど――まあ、楽観的だ」
お決まりの現状確認をする度にもどかしい気持ちになる。自分が何者なのか、一番知りたいのはハル自身だ。靄がかかった記憶の中に、望むべき真実があるかどうかさえわからない。
であれば当面必要なのは、ハルが今何をすべきかなのだが――
「――それで。アルファは傍にいないのかな?」
「あ。それは~……あはは……」
「うん?」
言葉を濁すハルに、ナガツキはすぐさま察したようで、
「……ああ、やっぱり勝手に離れてるのか。あいつにも困ったものだな。いつも君の近くにいろと言ったのだが……」
「正直、気付いたらいなくなっちゃってて。どこにいるんだかわかりますか?」
「それなら、まず間違いなく『月の花園』だな。アルファはいつもあそこにいるし、滅多に出ることはない。遠慮なく頼るといい。あいつは嫌がってるかもしれないが、そういう決まりだ」
「わかりました! 行ってみます。今日どうするのかは、それから話し合おうと思います」
「それがいい。――ハル」
その場を辞そうとしたハルの背に声がかかる。
「君の『ともだち』が、見つかることを祈っているよ」
「はい!」
扉を閉じ、回廊に飛び出す。『月の花園』は、ここから更に下の階層だ。
❀❀❀
思い返してみる。
記憶の始まりは、空と桜だった。
何か大きく分厚いものがほどけて、閉じた瞼に光が刺さった。
土と草の匂いに包まれて、ハルは仰向けに横たわっていた。
呆然としていた。何も思い出せなかったからだ。自分が何者なのかもわからず、ただ青空だけが映る視界に、ひらひらと舞う桜の花びらが入った。
そちらを目で追ってみると、桜の主は案外すぐ傍にいた。立ち尽くし、ハルを見下ろす少女――少なくともそう見えた――その長い髪から散る、美しい花びら。それでハルはぼんやりと、ああ、彼女が花なんだと、何の疑いもなく思った。
そしてこの花びらは、きっとそのひとの涙なんだと思った。
桜の子は、何故か泣きそうな顔をしていたから。
目が合い、心のままに発した一言が、偶然にもまったく重なったことを覚えている。
――あなたは、誰?
――お前は、誰だ?
「アルファ!」
月の花園は、学園で最もカラフルな場所だ。ことによるとプラント全域を探しても、ここほど色彩に満ちた場所は無いのかもしれない。
さして広くもない敷地内には、多種多様な花がある。
時期や生息域に関係なく、同じ時・同じ場所に、ありとあらゆる花々が咲いているのだ。
目当ての相手はその真ん中にいた。風に膨らむ、模様付きの外套。一切の音を発さない異様に物静かな所作。目がくらむような極彩色の空間でも、最初に見た花の色を見逃すハルではなかった。
桜の花人は、呼び声を受けて反射的に振り返る。目が合った。ハルはもう一度その名を呼ぼうとして、
「アル――」
ぷいっ。
「え゛!?」
思いっきり無視された。
「ちょっとー! 今あたし呼んだんだけど!? 反応したよね! おーい!!」
その花人はギリギリまで見なかったことにしようとしていたが、駆け寄って目の前でわちゃわちゃされると流石に観念したらしい。心底嫌そうな顔で、応じる。
「…………何か用か、人間」
「また人間って言う! あたしハルって名前があるんだけど!?」
「名前ってのは、同族の中で誰が誰かを識別するために使うもんだ。わたしたちの中で人間はお前だけだから『人間』でいい」
「う……無駄に理論的な……」
「話は終わりだ。とっととどっか行け。わたしは忙しいんだ」
「むぐぐ……!」
『それからもうひとつ、大事なことがあります。
アルファっていう花人です。
こいつは変なやつです。無愛想で、口が悪くて、何を考えてるのかわかりません。見た目的にはあたしと同い年くらいの女の子に見えて、すごく綺麗。だけどいつもぶすっとしています。
あたしを学園に連れ帰ったくせに、そこからは関わろうともしてくれません。あたしが嫌いなのかも。人間だから?
あなたも人間なら、アルファに嫌われちゃうかも。もし学園に来ることがあったら気を付けてください。その日までにできる限りなんとかしたいけど、間に合わなかったらごめんね』
アルファはいつも、この花畑を管理している。
昼も夜も、雨の日も晴れの日も。水をやり、雑草を抜き、鳥や虫から守る。花が花の世話をするというのは不思議な構図だ。特にやることが無い日は、外周のベンチに座り、ただ花を見ているのだという。
ハルはそんなアルファの作業を、ベンチに座ってじっと見守っていた。
じろりと、アルファが横目にこちらを睨んだ。
「……なんだよ」
「べっつに」
「どっか行けってば。お前なんかに構ってる暇無いって言ったろ」
「そんなこと言われたって。あたしだって、いつもアルファと一緒にいろって学園長に言われたもん」
アルファは大きく溜め息をついて、
「それがおかしいんだ。何が『世話役』だ。ナガツキの奴、勝手に決めやがって……」
「あたしを最初に見つけたのがアルファだからなんじゃないの?」
「あんなのただの偶然だろ。それだけの理由で面倒を押し付けられてたまるか」
むう。
取り付く島もない。とはいえ、はいそうですかと一人でふらふら行動もできない。第一、学園のどこに何があるかもまだ把握しきれていないのだ。宛がわれた自室と学長室、それから月の花園、あとは食堂への行き方くらいしかわからない。敷地外などもっての外。話したことのある花人さえまだ極端に少なく、たちまち迷子になる自信さえある。
そういう時、アルファは見つけに来てくれるだろうか。
最初の時みたいに。
「――じゃあ、なんであたしを見つけてくれたの?」
「……なに?」
「だって。アルファ、いつもは滅多にここから出ないって聞いたよ。なのにあんな遠い森まで来るのって、どう考えても理由があるじゃん」
――――――。
束の間、息を呑むくらいの長さの沈黙が、確かにあった。
アルファは何も答えない。「うるさい」と言わんばかりに目を反らし、自分の作業に没頭する。
『――ただ、ひとつ確かなのは、アルファがいないと私は危なかったってことです。
あたしは学園からずっと離れたところで目覚めました。周りは、どっちがどことも知れない深い森の中です。たった一人で目覚めたとしても、きっと何もできなかったでしょう。今頃どうなっていたかさえもわかりません。
だからアルファは、あたしの命の恩人です。
もっと仲良くなりたいなと、正直、思います』
「ねえアルファ、あのさ――」
その時、鐘が鳴った。
高い位置にある鐘楼のうち、西側のひとつ。耳に残るような甲高い音。
聞いたことがある。あの鐘の意味は「警報」だ。
『第二探索班が「剪定者」の群れと遭遇しました。場所は西、迷夢の森付近とのこと。敵集団は小規模の模様。戦力に問題はないかと思われますが、念のため手の空いている花人は増援に向かってください』
事務的な報告が、伝声枝から樹上の学園に伝わる。
アルファは一瞬険しい顔になったが、続く「敵集団は小規模」の報告にふっと興味を失ったようですぐに自分の作業に戻った。
「行かなくていいの?」
「いい。あのくらいなら、いつものことだ」
「けど危ないんじゃ――」
「――見に行ってみればどうだい?」
横から、第三者の声が入り込んできた。見れば背の高い、歩くヒガンバナのようなシルエットがそこにいた。彼と目が合い、アルファは露骨に顔を顰める。
「学園長!」
「お前、ナガツキ……」
「『学園長』を付けなさい、アルファ」
こほん、とナガツキは咳払いをして、
「いい機会ではある。今回の『剪定者』は大した戦力じゃない。クドリャフカもいるようだし、戦闘面での問題はなさそうだ」
「だったら放っとけばいいだろ。行かせてどうするんだよ」
「見学だよ。ハルはまだ奴らを見たことがない。――我々の唯一の天敵がどんなものなのか、一度その目で見ておいた方がいい」
剪定者。
敵勢力。
漏れ聞こえるそれらの言葉が、具体的にどういうものを指しているのかハルは知らない。
「どうだろう、ハル。気にはならないか?」
「え……。それは――」
この森の奥には「何か」がいる。ハルの知らない何かが。
それは、自らの正体に繋がる「何か」でありはしないだろうか。
「――なる。なります! あたしそれ、見てみたい!」
「お前な……!」
「決まりだ。連れていってあげなさい、アルファ。確かに相手は危険だが、お前が付いていれば何の心配も要らないだろう?」
「勝手に決めるなって言ってるだろ! わたしは全然納得してないんだぞ! なんで人間のお守りなんか……!」
「これは正式な決定だよ、アルファ。お前のためでもある。『花守』以外のことを、お前も少しはするべきだ。――いいな?」
「っ……」
有無を言わさぬ口調だった。言葉に詰まるアルファの態度を合意と見て、ナガツキはふっと微笑む。
「あのなぁ、ナガツキ……!」
「『学園長』を付けなさい。麓に足を用意した。ハル、ついでにアレの乗り方も教えてもらうといい。のちのち便利だ」
「あ! おいっ!」
言うが早いか踵を返し、さっさと引っ込んでしまうナガツキ。アルファは中途半端に伸ばしかけた手をそのままに、呆然としていた。
「え~~っと……アルファ? どうしよっか?」
「……………………」
数秒の間。アルファは頭に手を当て、長い長いため息を吐いた。
どうやら彼は、ナガツキには頭が上がらないようだった。
「……さっさと行くぞ。先に言っとくけど、わたしから離れて勝手なことしても知らないからな」
「……! わ、わかった! 早く行こ!」
決めるなり足早に歩きだすアルファを、ハルは慌てて追った。歩く軌跡に数枚の桜が舞い、ハルはそれを、やはり綺麗だと思った。
記憶も無いまま目覚めて、数日。これがハルの初めての外出だ。
つづく
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます