第一巻 第二章 魔女狩り編
ごきげんよう はじめまして 前編
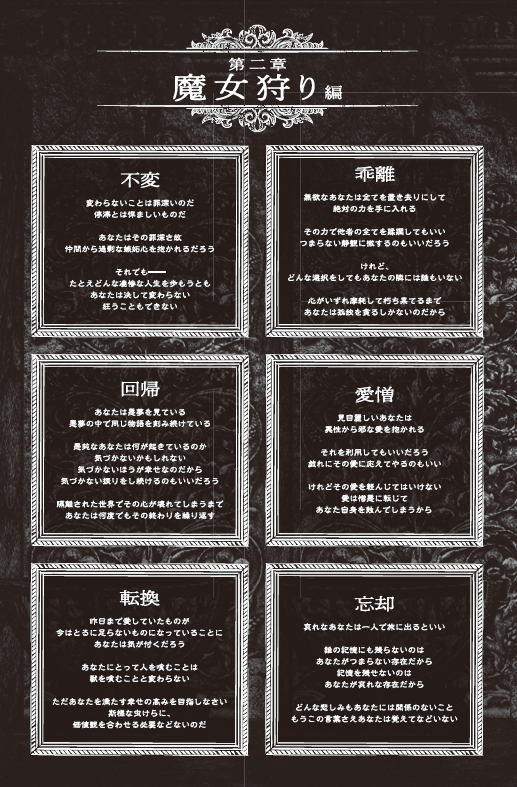

白白明
麗らかな朝の陽ざしが厨房の小窓からも入り込んでいる。静かだ……とアルバは思った。
非日常を乗り越えた後の平穏な空気を噛みしめる。有難みが深い。だが――
ぎゃあという悲鳴と共に家が揺れて、身構える。
その直後に激しい地鳴りがして、階段を滑り降りる音が近づいてくる。平和が遠くに行ってしまう予感がした。
「最悪だ!」居間の扉をぶち開けたリナリアが、開口一番にそう叫んだ。
「起きたらあいつが私の髪を食べて……唾でベトベトなのぉ!」
「お、落ち着いてください……」
「これが落ち着いてなどいられますか! だいたいあいつ今日も私のベッドにもぐりこんでッ!」
「顔、洗いましょう。すっきりしますよ」
「アルバはあいつに甘い!」
どうどう、と彼女をなだめつつ、居間の外へと追いやる。
「洗面所はこっちですよー」「だいたいなんなのよあいつ! 居候のくせに!」終始ぷりぷりとしているリナリアの背中を押して別室に促した。扉を閉めても「最悪、信じられない!」壁の向こうでも彼女の声は良く通る。
「それで、何したんだよ」
すぐ背後に立つ……というより、いつの間にやら足に抱き着いていた少女に尋ねると、
「あの子おおげさよ」つぶらな瞳をこちらに向けてルピーは答えた。
「私はベッドから突き落とされたもん、おあいこでしょ」
「あんたがベッドにもぐりこんでこなかったらこうはならなかったわよ……」
「だからって突き飛ばすことないよねー、アルちゃん?」
料理中のアルバに白羽の矢が立つ。早朝から、勘弁してくれ。
「二人の仲がいいのは、僕としてはうれしいんですけどね」
「なんでこんな奴と!」
「そうだ!」
またぎゃーぎゃーと言い争いが始まる。とげとげしい空気を背中に感じつつ、動かす手を休めることはしない。
「そもそもなんで私だけ別室なのよっ、おかしい!」
リナリアとアルバが同室の時点でおかしい。そこにルピーが加わったことで更にアルバの安眠が妨げられている。この場でこの事実を叫びたかった。
「新参がわがまま言わないで」
「横暴!」
「つまみ出すわよ!」
「あの、お師匠分のご飯、できました」
二人の元に駆け寄り、焼いた目玉焼きとホットケーキを彼女の目の前に並べる。
「お、ありがと」
これでしばらくは大人しくしてくれるといいのだけど。
「ご飯の用意って、いつもアルちゃんがやってるの?」
「え?」ルピーに突然声をかけられ「まあ……」と目を泳がせながら答える。
というより、料理だけに止まらず家事全般を請け負っているのだが。
リナリアを見ると、彼女は食事に夢中のようでこちらには反応しない。
「お師匠はあんまり家事ができないんだ」アルバはルピーの耳に顔を近づけて言う。
「生活能力ないんだ」ルピーが小声で返す。思ってても言ってはいけない。
「私はなんでもこなせるよ。お菓子作りが趣味なの」
へぇ、いつか食べてみたいものだ。
「私の旦那さんになる人は幸せだと思うなぁ」体を揺らしながら言う。
「アルバー、おかわりある?」
そんな最中でも、リナリアは平らげた皿を前に、物欲しそうな目をこちらに向けていた。
はいはい……。
「違う違う、もっと縫い目にそってやらないと」
派手な髪色のマダムが野太い声で破けた衣類を指さして言う。
ロウフ――森と山に愛されたド田舎村。
あのフィサリスの一件から僅か一週間後のことだ。
アルバはリナリアの服の修繕も兼ねて村に舞い戻って来ていた。
村に仕立て屋のような便利な店はないので、おのずと人伝てで詳しい人を頼ることになる。そしてたどり着いたのが、人懐っこい笑顔て応対してくれるマダムなおばさんだ。突然の訪問でも嫌な顔一つしなかった。優しげなタレ目の瞳からは人の良さが垣間見える。背後からの殺気がなければ極めて有意義な時間だっただろうな。
「それにしても可愛い服だけどだいぶ傷んでるわね。新調したほうがはやい気もするけど」
「ですよねぇ……」
背後に控えるリナリアに目を向ける。彼女は物陰から顔だけ出してこちらを睨みつけている。どうやら聞き耳を立てているようで、あまり下手なことは言えない。
「そういえばさっきの話、やっぱり本当なんですか?」話題を切り替え、尋ねる。おばさんは難しい表情になってきょろきょろと周囲を気にする仕草をした。
「カイトさんとこの奥さんの話? もう一週間もたつし、心配よねぇ」
フィサリスは村から姿を消した。というのが、この村での共通認識のようだった。
「他の男と出ていったとか、いつもの放浪癖だろうとか、まあ勝手な噂が独り歩きしてるけどね。あんな可愛い娘さんに、いい旦那さんだもの。ちょっと考えにくいわよねぇ」
考えにくい。確かにそうだろう。フィサリスとはあんな一件があったが、イルやカイトとはうまく過ごしているように見えた。偽りの家族、というわけでもなかったのだろう。――であれば何故に消えたのか。
直接、カイトに聞けば何かわかるかもしれない。だけど、何か言いようもない不安が、胸の内に湧き上がってくる。「本当はわかってるんだろ?」と、内なる誰かが囁いている。不死身の魔女なら死ぬはずがない、現に、二度も目の前で復活してみせたのに。彼女の胸を貫いたあの生々しい感触が、容易に思い出されて、嫌な気分になる。
おばさんから修繕の細かな手順と、必要な裁縫道具を一式譲ってもらう。丁寧にお礼を述べてその場を去ろうとしたのだが、
「ところであちらにいる子はだあれ? 見慣れない子だけど」
物陰に身を潜めるリナリアを指差す。恋人さん? と興味津々にマダムが顔を近づけてくる。得も言われぬ迫力にドキリとするが、
「妹みたいなものです」真顔で答える。
「妹ってなに?」
リナリアの元に戻るといきなり恨めしそうな顔をされた。
「聞こえてましたか」
はた目には人前に恥ずかしがって出てこられない年若い少女という印象なので、妹が妥当だと思ったのだけど。
「そこは正直に師匠って言っておきなさいよ」
「師匠って見た目でもないですし」
「なぁにそれ、馬鹿にしてんのっ?」
すぐ怒らないでほしい……。
「それで、どうだった?」
「お洋服なら修繕の目途が立ちましたよ。道具も貸してもらえましたし、僕でもなんとかできそうです」
「いや、そうじゃなくて……」呆れた顔をされた。仕方ないので真面目に答えるとする。
「フィサリスは、いなくなってるみたいですね」
あの廃城で遭遇したフィサリス。その行方を知るため、今日は引きこもりのリナリアも珍しく同行している。
「なるほどね……」
彼女は少し考えに耽っていたが、「まあいいわ」と言ってすぐに視線をアルバに移した。
「じゃあ今日はもう用事は済んだわよね。戻りましょ」
自然な動作で手をつかんでくる。その手はしっとりとしていて赤ちゃんの手みたいに熱い。
「あの、恥ずかしいんですけど」
「だってあなた、目を離すとすぐに迷子になるし」
あれは拉致されたのであって道に迷っていたわけではない。アルバは不満げに鼻を膨らませるが「ほら、いくわよ」と同行者に手を引かれ、それ以上の異論は認められなかった。
歩く。歩きながら、フィサリスが消えたという事実を、うまい具合に受け入れられないでいた。少なからず衝撃を受けていた。何度も交わした彼女の声音も、表情も、鮮明に思い出すことができる。
周りの景色が、人気のない森の中に変わったころ。
「フィサリスみたいな魔法使いって、他にもいるんですか」
戦々恐々とした面持ちで、尋ねる。リナリアは視線を前に向けたまま、難しそうに顔を歪めた。
「いるよ。もっと速く人を殺せる魔法使いだって――」
「そいつらも、不死身なんですか?」
彼女の肩が僅かに震えた。なにかに怯えるみたいに。
「そうとは限らない。不死身っていうのは、ただの特性でしかないからね。ルピーだって、不死身だけど、使い魔を使役する魔法に特化してる。本来は戦闘向きじゃないのよ」
「お師匠は、不死身なんですよね」
片時も離れない彼女の手の体温を感じながら、尋ねる。少女は前を向いたまま「そうね」とそっけなく肯定した。
「そういう魔法もあるってだけよ。不老不死の魔法。ありがちな話でしょ? 童話にも似たようなものはあるし」
彼女は早口で、どこかよそよそしい。だからそれ以上の追及はしなかった。ありがち、ということにして欲しいのだろう。
まあそれにしたって……。
「百才超えのおばあちゃんかぁ……」
「ぶつわよっ!」
「いだぁあああ゛あっ! つねらないで!」
何も変わることはない。この人が不死身でも、恩人であることは変わらない。廃墟に近づくにつれて、見慣れた石造建築が現れてくる。その煙突からは今ももくもくと白い煙が漏れ出ている。
きっとルピーが夕食に何か作っているのだろう。
二人は手をつないだまま走り出した。
カチ、カチ。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます