第6話
「それでは先輩! 判定をどうぞ!」
「……大町花楽さんの勝利です」
店を後にした俺たちは、ショッピングモールの外で勝負の判定を下す。
結果はまあ、いま言ったとおり。
なんというか、圧勝でございました。
「翔ちゃんのばかぁ――――っ!」
敗北を突きつけられた凛珠はそんな捨て台詞を叫び、駆け出していった。
花楽はそんな凛珠の背中を見ながら、額の汗を拭うポーズ。
「ふう、厳しい戦いでした」
「やりきったスポーツマンみたいに清々しい顔してんな、おまえ」
「では先輩。戦勝の喜びを分かち合うため、デートの続きとまいりましょう」
「え? もういい時間だと思うけど、まだ続けるのか?」
「恋人同士のデートなんですよ? むしろこれからの時間こそが本番です」
まだ恋人同士ではないのだが。
いや交際を認めなかった凛珠が去ったのだから、もう恋人同士か?
時刻は午後六時。
日はまだ落ちていないが、さすがにそろそろ暗くなるよな。
花楽って物腰や言葉遣いがお嬢様っぽいけど、門限とか大丈夫なんだろうか?
そんなことを考えながらしばらく歩いていると――
「あの……花楽さん?」
「なんですか、先輩?」
「あんまりこのへんを歩くのは感心しないなー……と、年上の男からご意見を」
「頂戴しました。しかし、なぜでしょう? 理由を求めます」
「理由って」
繁華街からは少し外れたところに来ていた。
このあたりに立ち並ぶ建物は、一見するとマンションとかお城とか?
だがそのマンションとかお城っぽい建物はどれも看板付きで……要するに。
ラブホテルだこれ。
「なぜですか? ほらほら先輩、無知なわたくしにぜひとも教えてください」
嬉々とした様子で答えをせがんでくる花楽。
何が無知だよ。こいつ、絶対わかっててやってる。
そうは思っても言い出せないでいるチキンな俺。
自分でも顔が赤くなっているのがわかる。
そうしていたら――
「ふふふ……あはははっ!」
さっきまでにまにましていた花楽が、突然笑いだした。
「ごめんなさい。本音を言うと、先輩の反応が楽しくて、ついふざけてしまいました」
「お、おまえやっぱり」
「ご安心ください。わたくし、先輩が思っているほど子供じゃありませんので」
どういう意味での安心なんだ、それは。とも訊けず。
花楽は心底楽しそうに、そして心底幸せそうに、俺に抱きついてくる。
「男の人と過ごしてこんなにも楽しいと感じられたのは、生まれて初めてです」
「花楽――」
「本当に、探し続けてよかった。巡り会えてよかったです」
俺は花楽に言葉をかけようとして、しかし。
「エルステは偉大です。先輩は本当に、相性度97%の――運命の人」
何を言おうとしたか、その一言で忘れてしまった。
俺は、花楽の目を見る。
でも花楽は、俺を見ていなかった。
視線はこちらを向いているのに、俺のことを見ていない。
最初に会ったときからずっと、花楽は友柳翔ではなく『運命の人』を見ていた。
不意にその事実に気付かされた。
……ああ。
さっきランジェリーショップで覚えた違和感は、これだったんだ。
バイタリティ全振りである花楽は相性抜群の『異性』を求めている。
それは、攻撃力全振りの凛珠が俺という『個人』を求めているのとは意味が違った。
最大の違いは――俺でなくてもいい、ということ。
花楽が見ているのはエルステの相性度であり、そしてその数値が高い異性。
エルステの信頼度は疑うべくもない。
だが、はたしてそれは――本当の恋と呼べるのか?
もし俺より相性度の高い相手が現れたら、花楽はどうするんだ?
「で、真面目な話この後どうします? 先輩が興味おありなら下見だけでも――」
「……花楽。ちょっとこっち来い」
「え?」
衝動的に、花楽の手を引いた。
このままじゃいけないと思った。
一度花楽を落ち着かせ、考え直させる必要がある。
「ちょ、ちょっとセンパ――」
「あんまり調子に乗るなよ」
狭く薄暗い路地裏に、花楽を連れ込む。
そのまま小さな身体を壁に押しやり、距離を詰めた。
腕を伸ばして退路を塞ぎ、緊張感を演出する。よく言う壁ドンだ。
「安い言葉で男をそんな風に挑発するな」
「え? ええ? 何を――」
「言ってわからないようなら」
外界から隔絶された路地裏。隣の建物はラブホテル。夜も間近な時間。人目はなし。
女子なら危機感を覚えてしかるべきシチュエーションで、俺は顔を近づける。
「本気で食っちまうぞ」
――花楽を落ち着かせ、考え直させる必要がある。そのためにはどうするべきか?
ヒントは俺の幼なじみにあった。
凛珠と同様に、ヘタレさせてしまえばいいのだ。
花楽のステータスはバイタリティ100。しかし、防御力は0。つまり積極的ではあるが打たれ弱い。こうやって挑発し返してやれば、逆に尻込みしてしまうはずだ。
日頃から頭を悩まされている幼なじみと欠点が同じ。だからこそ気づけた。
強引かもしれない。誤解されるかもしれない。あるいは幻滅されるかも。
それでもいい。
とにかく花楽には一度冷静に――
「っ、はいっ」
冷静に考えて――うん?
「ま、まだ早いと、思っていましたけど。先輩が、望むなら……っ!」
……お、おい。
なんかこの子、おもむろに胸元のスクールリボンをほどき始めたんだけど。
上から順番に二つほどボタンを外して、下着がチラッと見えてるんだけど。
「ちょ、ちょちょちょ! なにやってんだ花楽!」
「あ、すいません。別にここで、という話ではありませんよね。入れるところはすぐ近くにあるわけですし」
「いやそうじゃなくて!」
「安心してください先輩! 花楽は初めてです!」
「そりゃそうだろうけどね!?」
「そして先ほど選んでいただいた下着も身につけています! ほら!」
「こんなところで見せるな!」
予想に反し、花楽は俺の挑発に乗ってきた。
恥ずかしさはあるようで顔は赤くなっているが、その表情に不安や戸惑いはなく、なんというか「期待しています!」「楽しみです!」といった感情が伝わってくる笑顔だった。
な、なんで……花楽は凛珠と同じで防御力が0のはずだ。なんでヘタレない!?
あれ? いや、そうか違うぞ! 俺の勘違いだ!
エルステの防御力は、異性への警戒心を表すステータス。防御力の低い女の子は、言ってしまえば『ちょろい』。男の挑発にもなびきやすいし、さらに花楽はバイタリティが高いから、こういうこと――エロいことにも興味津々なんだ!
要するに、逆効果。
凛珠のヘタレ癖は、防御力が0だからというよりはバイタリティが0だから。
謎が解けてスッキリしたところで、さて花楽がやる気になっている現状をどうしよう。
「――謎が解けたよ、翔ちゃん!」
俺が困惑していると、聞き慣れた幼なじみの声が。
往来から路地裏の俺たちを覗く、凛珠の姿があった。
凛珠は俺と花楽――ラブホテルの脇で壁ドンする俺と、制服脱ぎかけの花楽を見て声を上げる。
「こんなところで何やってるのぉ!?」
「誤解だぁ!」
「誤解じゃありません! わたくしは今日ようやく、運命の人と結ばれるんです!」
「っ! やっぱりだ! 戻ってきて正解だった!」
大胆発言をする花楽に、しかし凛珠は怯まない。
俺でも見たことのないような強い眼差しで、暴走する花楽と向き合う。
「凛珠さんは先刻、わたくしとの勝負に負けたじゃないですか! なのにまた邪魔しに来るだなんて、往生際が悪いにもほどがあります!」
「確かに私は負けたよ。それでもやっぱり、あなたと翔ちゃんの交際を認めるわけにはいかないって思い直したの。あとになって、重要なことに気づいたから」
だから舞い戻ってきて、俺たちを探し回っていたのか。よく見ると凛珠の額には汗が浮かんでいる。きっと繁華街を中心に大捜索していたのだろう。
「不愉快なことを言う人ですね。いったいなんなんですか? その重要なこととは」
「……あなたは翔ちゃんを見ていない」
「は?」
「あなたが見ているのは、翔ちゃんじゃなくてエルステの相性度だけ! 翔ちゃんじゃなくて、相性度が示す恋に恋してるんだよ!」
凛珠が言い放ち――花楽は何を思ったか、俺の身体に縋り付いてきた。
その姿は、怖いものを前にした子供のようにも見える。
「い、意味がわかりません。わたくしはちゃんと先輩をお慕いしています」
「それは翔ちゃんが運命の人だからでしょ? ただエルステの相性度が高いから――」
「それの何がいけないんですか? エルステの相性診断は絶対です。それをきっかけにした恋が恋と言えないとでも?」
「出会いのきっかけとしてならいいよ。相性度が高いからっていう理由で知り合って、そこからその人のことを好きになるんなら。でも、あなたは違う」
「なっ、何を根拠に!」
「じゃあ訊くけど! 翔ちゃんとの相性度、97%って言ったよね? もしこの場に98%以上の人が現れたら、あなたはどうするの?」
「…………っ!」
花楽が口ごもる。
俺の腕を掴むその手は、微かに震えていた。
「きっと、あなたは一途に翔ちゃんを想うことができなくなる。そういう風に思ったから、私は戻ってきたの。幼なじみのおせっかいだけど……翔ちゃんには、翔ちゃんのことを一途に想ってくれる人と付き合ってほしいから」
「凛珠……」
俺は、かけるべき言葉を見失った。
胸中にある感情は、ただただ「すごい」だった。
この幼なじみは、俺とまったく同じことを思い、指摘したのである。
そしてその指摘は花楽にとっても正鵠を射たものだったらしく、結果がこの閉口だ。
やがて花楽は俺から手を離し、制服のボタンも留め直す。
「……すいません先輩。少し、考える時間をください」
俯いて言う花楽。
横顔からは、酷くショックを受けている様子が窺えた。
俺の返答を待たず、走り出す。
咄嗟に追いかけようとして――すぐに思いとどまった。
「あの……ごめんね、翔ちゃん。私、余計なこと……」
「いや、いいんだよ。ちょうど俺も、花楽に同じこと言おうとしてたから。きっとあいつも俺と同じで……運命の相手と出会えて舞い上がってたんだ」
頭が冷えた。
これでよかったんだ。
相性度が高いとはいえ、それだけに依存した恋愛は危うい。
少なくとも花楽に限って言えば、いつまでも「もし、もっと相性度の高い人が現れたら――」という仮定がつきまとう。
俺だって、数値だけ見られてもっと相性度の高い奴に乗り換えられるのは嫌だ。
でもそれ以上に、花楽だってそんなことはしたくないだろう。
「……けっきょく、凛珠の言うとおりだったのかもな」
「え?」
「恋愛初心者の俺には、彼女っていうか……男女交際なんて早かったのかもしれない」
運命の出会いに舞い上がらず、もっと冷静に花楽を見ることができていれば。
あいつは走り去ることなんてなく、笑ってデートを終えられたのかもしれない。
つまり相性度に依存しすぎていたのは、俺も同じ。
花楽はああ言っていたが、答えを待つだけでなく、俺自身もきちんと考え直そう。
花楽のことが好きなのかどうか、付き合いたいのかどうか。
答えが出るまでにどれだけの時間がかかるのか、恋愛初心者の俺にはまったく見当がつかなかった。
◇ ◇ ◇
そして、翌日のことである。
「おはようございます。先輩、凛珠さん」
凛珠と一緒に登校した俺は、文樹坂学園の校門で待ち構えていた花楽と出会った。
「昨日は見苦しいところをお見せしました。さっそくですが、昨日の凛珠さんの質問に対して回答を」
「もう!?」
隣で驚く凛珠。俺も同じ気持ちだった。
正直、このまま喧嘩別れみたいになることも覚悟していたのだが、まさか一日で答えを用意してくるとは。俺のほうは深夜までうだうだ悩んでけっきょく寝落ちしたというのに。
花楽は俺と正面から向き合い、深呼吸をしてから言葉を紡ぐ。
「先輩よりも相性度の高い相手が現れたらどうするのか。きっとわたくしは、その人とお付き合いしたくなると思います。だって、わたくしが探していたのは先輩ではなく運命の人なのですから」
「花楽……」
「凛珠さんのご指摘はごもっともでした。ですので、一晩考えた上で結論を出しました。ごめんなさい。交際の申し込みは、撤回させていただきます」
ああ。
……これって要するにフラれたんだろうか?
面と向かって言われると予想以上のダメージがある。
俺は傷心した様子を見せないよう努力し、花楽に伝えるべき言葉を選ぶ。
「そしてあらためて、意思表明をします」
しかし花楽の答えには続きがあった。
「い、意思表明?」
「先輩への交際のお申し込みは撤回しましたが……先輩のことは諦めません。いつか必ず、再告白をします。具体的には、わたくしと先輩の相性度が100%になったら」
耳を疑うような宣言。
告白は取り消すが……いつかまた告白するって? なんだそれ?
「お二人もご存知でしょう? エルステの相性度は100%が最高値です。つまりそれ以上の相手はいないということです。わたくしにつきまとう不安は『もし先輩以上の相手が現れたらどうしよう』というものですから、相性マックスならその心配もありません」
「た、確かにそうだ」
「はいっ! それなら自信を持って先輩に恋できます!」
そう言った花楽の笑顔が――やばい可愛い。
いやもう運命の相手、それも相性度98%以上の相手なんてそうそう現れるわけないんだから、心配とか気にせずこのまま俺たち付き合っちゃえばいいのでは? むしろ俺から告白をすればそれで幸せになれるのでは? と思わされた。
花楽だって、俺が諸々了承済みなら受け入れてくれるはず――
「や、ダメでしょ!」
異を唱えたのが凛珠だった。
花楽の発言が予想外すぎたのか、俺以上に混乱した様子で身振り手振りを繰り返す。
しまいには大の字のポーズで俺の前に立ち塞がったりして。親衛隊か何かかおまえは。
「なぜですか? エルステの相性度は上げることができます。知ってますよね?」
「知ってるけれども!」
「しかも凛珠さんから、先輩はもっとバストの大きい方が好みという情報も入手していますので。案外あと数センチ成長するだけで100%になるんじゃないかと愚考します」
「だ、ダメ! ダメです! 今後あなたは牛乳を飲むことを禁止します!」
「なるほど、牛乳がいいと。その豊かさを見るに、風評はあながち間違いではないのですね。そういえば先輩、気になる男の人に揉んでもらうのも近道だと――」
そんな感じで。
幼なじみと後輩の言い争いは、朝の予鈴が鳴るまで続いた。
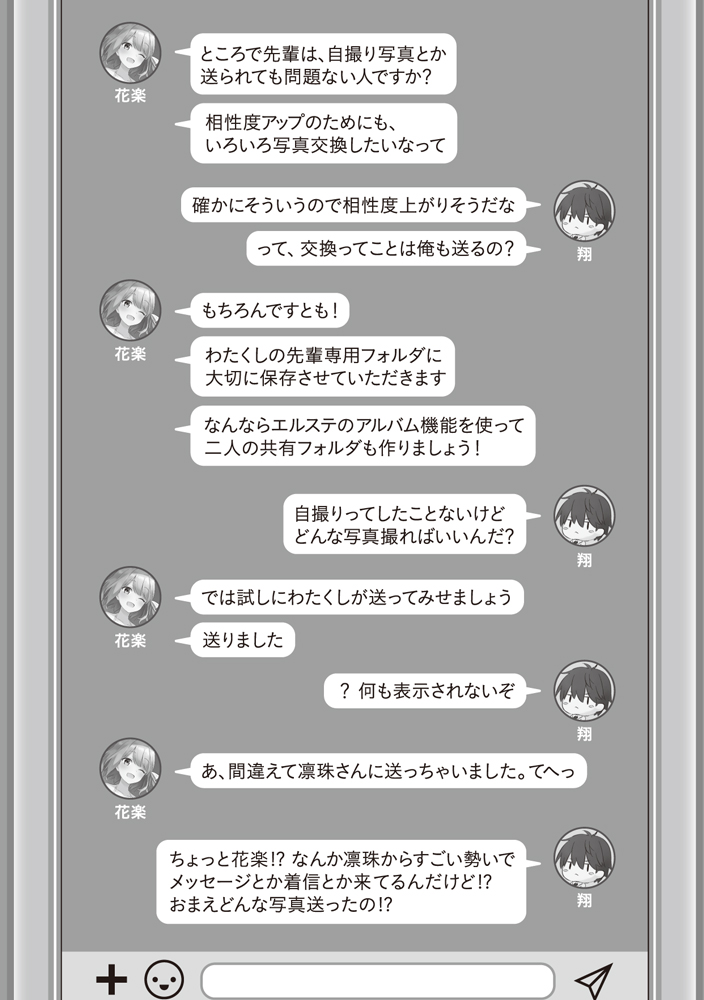
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます