三杯目 勇気を与える紫キャベツのポタージュ
三杯目 勇気を与える紫キャベツのポタージュ①
種まきを待つ耕された麦畑が、秋の訪れを知らせている。
空は高く澄み渡り、風に吹かれた雲がたなびいていた。
町の広場はいつになく賑やかで、麦畑にまで様々な音が響いてくる。
楽器が奏でる旋律や美しい歌声に、浮かれて跳ね回る子どもたちの笑い声。
収穫祭の準備がはじまった町は、活気に溢れていた。
「シーナ、ここに置いておくわね」
店先から声をかけるのは、ご近所の奥さんだ。
シーナが向かうと、すでに紫キャベツが積まれていた。
「たくさん採れたからおすそわけよ」
「いつもありがとうございます」
「紫キャベツはスープには向かないでしょうね。煮込むと色が出るもの。だけど、酢漬けにするといいわよ」
農家の奥さんは、野菜を分けてくれるときは必ず、親切に簡単な調理法まで教えてくれた。
「良かったらパンを持っていってください」
シーナが焼きたてのパンをお返しするのも、もはや当たり前の光景である。
「こちらこそ、いつも悪いわね。お店にも食べに行くからね」
藁紙に包まれた熱々のくるみパンを抱え、奥さんは笑顔で帰っていった。
シーナはそっと自分の頬に触れる。
私も、ちゃんと笑顔を返せたかしら。
思いきり口を横に開いてみるが、依然ぎこちなく感じられた。
「少しずつ慣れていけばいいわよね」
この町のゆっくりと流れる時間が好きだと、シーナはしみじみ思う。
ご近所さんとは顔見知りになり、店には新たな常連客も増えはじめた。
町の人たちはいつしかシーナの名前を覚え、気さくに呼びかけてくれるようになった。
パンとスープの店とともに、この町に溶け込みたいと願っているシーナには、嬉しいことばかりだ。
いつまでもここにいられたらいいのに……。
スープを作り続けることは大変ではあるが、そのぶん、やりがいと楽しさに満ちていた。
今日はどんなスープがいいかしら――シーナは紫キャベツを持ち上げる。
「ああ、確かあれは……」
何気なく、懐かしい料理が頭に浮かんだ。
それは、修道院で子どもたちと食べた、緑色のキャベツと腸詰めの煮込み。
湯気の温もりや香ばしい香り、キャベツの甘みと腸詰めの旨味まで、はっきりと思い出せる。
素朴だけど奥深い味で、日々の憂いを忘れさせてくれる優しさがあった。
ヴァレリアとして生きていた頃は料理をしたことはなく、食事の時間に広間で待っていれば、豪華な料理が運ばれてくるのが日常だった。
ただし、どんなごちそうよりも、修道院の質素な食事のほうが心に残っている。
食前の祈り、シスターたちの厳しくも優しいまなざし、小さな子どもの汚れた口元をふいてやったこと。記憶の断片が、いくつも頭に浮かんではすぐさま消えていった。
静かで厳かな食事の時間は、生きることと向き合うための時間でもあったように思う。
「主よ、今日も我らに糧を与え、共に食する喜びをありがとうございます」
自然と、シーナは祈りの言葉を口にする。
修道院の温かな料理が、命を実感させ寂しさを和らげてくれていたことに、改めて感謝するのだ。
「みんな、元気かしら」
振り返ればすぐそこにある景色のようにも、二度と戻れない遠い場所のようにも感じられるあの頃。
『ヴァレリア様、お待ちしていました。たくさん練習したので見てください』
記憶に焼き付いているのは、三つ編みを揺らしながら駆け寄ってくる少女の姿だ。
シーナがヴァレリアだった頃、修道院で家庭教師をしていた時の記憶である。
少女は、蝋板に書かれたジュアナという文字を、嬉しそうにヴァレリアへ見せてきた。
学びはじめたばかりの文字は、震えた手で書かれたかのように波打っている。
そこに記されたジュアナという文字は彼女の名で、両親からの唯一の贈り物だった。
綴りの間違いを正してやると、ジュアナは屈託のない笑顔を向けてくる。
『ヴァレリア様とお勉強するのが、楽しみでなりません。また来てくださいね』
しかし、もう二度と、ジュアナの顔を見ることすら叶わないだろう。
果たせなかった約束は、心の奥底に沈んだままだ。
姉のように自分を慕ってくれていたジュアナが、今ごろ寂しくしていないか気がかりで仕方ない。
もっと、そばにいてやりたかった。もっと、いろんなことを教えてあげたかった。
シーナはジュアナだけでなく、たくさんの子どもたちの顔を次々と思い浮かべ、苦い思いになる。
私は、あまりにも非力だったのね……。
ジュアナたちをもう一歩先へと導いてやれなかった後悔や、自分だけが自由を手に入れたことへの後ろめたさで、シーナの心は重くなった。
「こんなことでは、誰のことも笑顔にできないわ……」
小さくため息をついたところで、隣家から斧で薪を割る音が聞こえてきた。
「……そうだわ。アルバにも紫キャベツをおすそわけすべきね」
紫キャベツを抱えたまま、シーナはアルバの家の裏手へまわる。
「おはようございます」
シーナは、薪割りをするアルバの背中に向かって声をかけた。
「おはよう。早朝からどうした?」
声だけでシーナと分かったアルバは、振り返ることなく薪を薪割り台に乗せる。
「紫キャベツをたくさんわけてもらったので、持ってきました」
「ありがとう。そのへんに転がしておいていいから」
「分かりました」
「危ないから、下がってて」
アルバは斧を振り上げると、狙いを定めてから勢いよく振り下ろした。
鋭い音を立て、薪は真っ二つに割れる。
「すごいわ」
シーナは思わず声をあげてしまった。
斧を構えた立ち姿は安定しているし、一連の動きにも無駄がない。刃は正確に木の割れ目を捉え、薪はまっすぐに割れている。
「慣れれば誰にでもできる。たいしたことじゃない」
気まずそうに言いながら、アルバはシーナを振り返った。
「邪魔してごめんなさい」
「いいや。これは、来年の収穫祭で使う薪だから急いでない」
「来年のぶんを今から?」
「たくさん必要だし、忘れないうちにやっておいたほうがいいだろ」
シーナは、はたと気付く。
寒くなると木の水分量が減ると言われており、乾燥させて使う薪を準備するのには、今がちょうどいい時期だということに。
「私にもできるかしら……」
シーナはぽつりと言う。
「やってみるか?」
試すような口調で、アルバが斧を差し出してきた。
「やってみます」
町の人のために何かできることはないかと、常々考えているのは本当だ。
「冗談だよ。無理しなくていいから」
「無理はしていません」
シーナが斧を受け取ると、アルバは愉快そうに唇の端を上げた。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




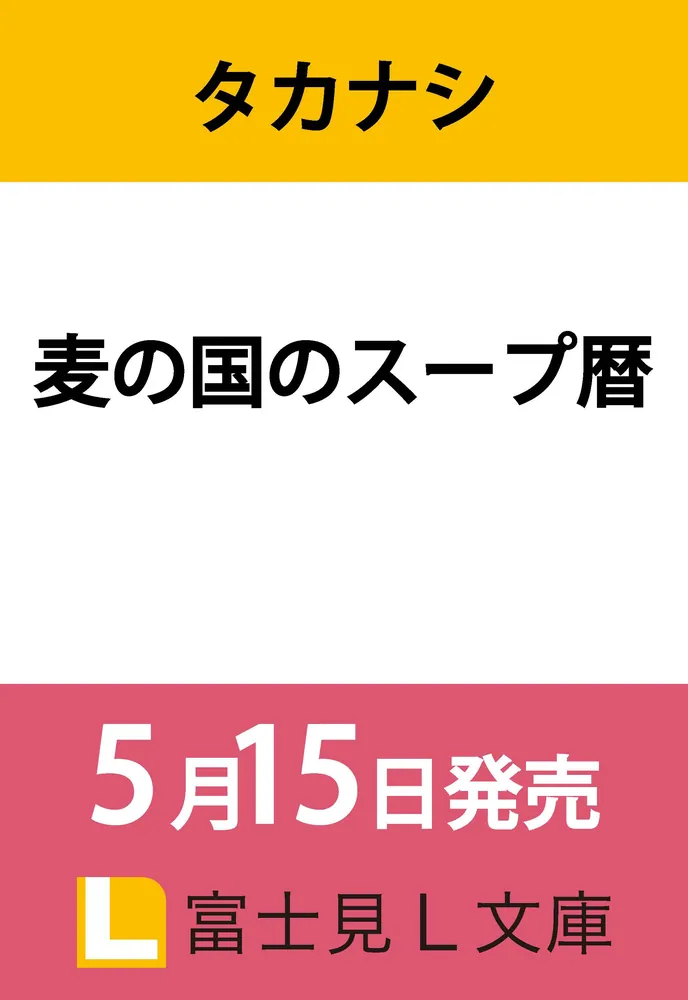
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます