三杯目 勇気を与える紫キャベツのポタージュ②
「よし。じゃあ、薪の割り方を教えるよ。まず、ここに薪を置くだろ」
きめ細やかに、アルバは薪割り台の上に安定して薪を乗せる方法から教えてくれる。
「次は、斧の握り方だな。こことここを持って」
口頭で指示しながら、シーナに斧の柄を握らせた。
「足は肩幅に開いて、力は抜いて」
「は、はい」
「薪の割れ目を狙って、垂直に振り下ろすんだ」
「分かりました」
シーナは思いきって斧を振り下ろすが、薪は割れずに弾け飛んだ。
「惜しい!」
アルバが悔しそうに膝を打つ。
「すみません、上手にできなくて」
じんじんとして、手の感覚がおかしい。
たった一度斧を振り下ろしただけで、シーナの手は痺れてしまったようだ。
「誰だって最初はそうだよ。まだ続ける?」
「この辺にしておきます。あっ……」
痺れた手から斧の柄がずるりと滑り、シーナは足元をふらつかせる。
「どうした? 大丈夫か?」
アルバは慌てたように、シーナから斧を受け取って地面へ置いた。
「どこか痛めたのなら、見せてくれ」
「大丈夫です。そろそろ店の準備があるので……」
差し出されたアルバの手を無下にはできず、シーナはそっと押し返そうとするが。
感覚が鈍っているせいか、思いのほか強くつかんでしまった。
「本当に、平気か?」
「少し手が痺れているだけで、なんともありません」
「だったらいいが」
「ええ、大丈夫です」
シーナとアルバは手を握りあったまま、しばらくの間まごまごしてしまった。
そこで予期せず、馬屋からブランシェの嘶きが響く。
「きゃあ!」
「わっ!」
驚いた二人は、反発しあうようにぱっと手を離した。
「言っておくが、この野菜はお前のじゃないからな」
ブランシェに向かって不服そうに言いながら、アルバは紫キャベツを拾い上げた。
「……じゃ、また」
くるりと背を向け軽く片手をあげると、そのまま馬屋へと消えていく。
シーナは胸の前で両手を握りしめ、がっかりしたように肩を落とした。
少しも役に立てなかったわ……。
薪割りがうまくできなかったことを申し訳なく思いながら、シーナはとぼとぼと店に戻るのだった。
「紫キャベツはスープに不向きだと言われたけれど……」
ぽこぽこと泡が立つ鍋を、シーナはゆっくりとかき混ぜていた。
鍋の中には、薄明の空のような神秘的な色をしたスープがたっぷりと入っている。
「思った通り、綺麗な紫色のスープができたわ」
くたくたになるまで煮込んだ紫キャベツをすり鉢ですりおろし、牛乳を加えて塩と少しの胡椒で味を整えると、まろやかで甘味たっぷりのスープができあがった。
鍋から漂う豊かな香りが、シーナをうっとりとさせる。
エルザのバターを隠し味に入れたことで、スープはコクのある贅沢な味となった。
「せっかくだから、酢漬けも作りましょう」
手早く紫キャベツを千切りにし、塩を振ってしんなりさせてから絞る。
味付けは酢と砂糖だけだが、味を引き締めるために、月桂樹の葉と赤胡椒を一緒に漬け込んだ。
赤胡椒は、赤くて小さな丸い実を乾燥させたもので、胡椒と呼ばれているが辛味はなく、ほんのり甘い果実のような味がする。
「そろそろ馴染んだはず」
できあがった紫キャベツの酢漬けは、鮮やかな赤色に染まっていた。
色が変わる科学現象ね。
紫キャベツの成分と酸性の酢が反応したことによって、紫色から赤色へと変化したのである。
ひと口味見して、シーナは小さく唸った。
「おいしい……それぞれの味がうまく混ざり合ってるわ」
月桂樹の葉と赤胡椒は、異国の特産品を扱う町の商店で手に入れた。
町の商店には、珍しい調味料や香辛料がたくさんあり、どれも試してみたいものばかりだ。
「ヴィセンテさんのお店は、サラさんが言うように重宝しそう」
くるみパンが焼けたところで店を開けると、すでにちらほらと町の人たちが待っている。
今日は、忙しくなりそう。
嬉しい予感に、シーナの胸は高鳴った。
高い空にゆっくりと流れる雲。
慌ただしく働くうちに混み合う時間は過ぎ、やがて静かな午後のひとときがやってくる。
そこへ、一人のあやしげな男が店を訪れた。
男は、マントのフードを深くかぶり、人目を避けるように席につく。大きな布袋に鍋や天幕と、大量の荷物を軽々と運ぶ大柄な男だった。
さすがのシーナも用心しながら男に近づく。
「あの、ご注文ですが」
声をかけると、男はびくりと肩を震わせた。
「は、はい。ええと、麦のスープを……」
見かけによらず声はか細い。
「麦のスープはご用意がなくて。日替わりスープのみとなっています」
「えっ……あの、この店の店主って?」
男は慌てたようにフードを脱いだ。男の太く濃い眉や、角張った顎があらわとなる。顎にはうっすらと無精ひげが生えていた。
「エルザさんでしたら、もう店をやめられました」
「ええっ! そ、そうなんですか!」
男はひどく驚いた様子で、「まさか、そんな」とつぶやく。
外見こそ落ち着いて見えるけれど、その言動には頼りなさが感じられた。
「す、すみません。じゃあ、その日替わりスープをお願いします」
男は大きな体を丸めて、ぺこぺこと頭を下げる。
「かしこまりました」
悪い人ではなさそうだわ。
男の謙虚な態度に安心したシーナは、気を利かせてスープを大盛りにして運んだ。
「ありがとうございます」
男はそう言ったきり、なぜか、スープを口にすることもなくぼんやりとしている。
どうしたのかしら?
かなりの時間そのままだったため、シーナは心配になってきた。
「もしかして、麦のスープをご希望でしたか?」
おそるおそる、男に訊ねてみる。
「あ、いえ……いや、はい……」
男の返事は、まったくもって曖昧だった。
「お口に合わないようでしたら、お代はけっこうですので。どうか、気になさらないでくださいね」
紫色をした珍しいスープに食が進まないのかもしれないと、シーナは男を気遣う。
「そうではなくて! すみません、考え事をしていて」
再び、男は繰り返し何度も頭を下げた。
「ええと、俺はロイと言います。この町で生まれましたが、今は王都で騎士見習いをしています。いい年してまだ見習いなんです。いい年してというのは、実は今年で二十六歳になります」
ロイと名乗る男は、堰を切ったように話し出す。
「すみません、べらべらと。お嬢さんに警戒させてはいけないと思って」
そう言って、また頭を下げるのだ。
「あの、大丈夫です。そんな頭を下げなくても」
「いえいえ、こんなおいしそうなスープを前に考え事なんて、本当にすみません。でも、それだけ切羽詰まっていまして……実は、入団試験から逃げ出して来たところなんです」
切羽詰まっているというわりには、ロイはへらへらと笑っている。
「入団試験……?」
「王都で大人気の第三騎士団の入団試験です」
今度は、自信満々に胸を張った。
「第三騎士団……?」
「ご存じありませんか? 王都周辺を警備する騎士団なんですが、他の騎士団とは訳が違うんです」
ロイの目がみるみる輝き出し、シーナは興味深く耳を傾ける。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




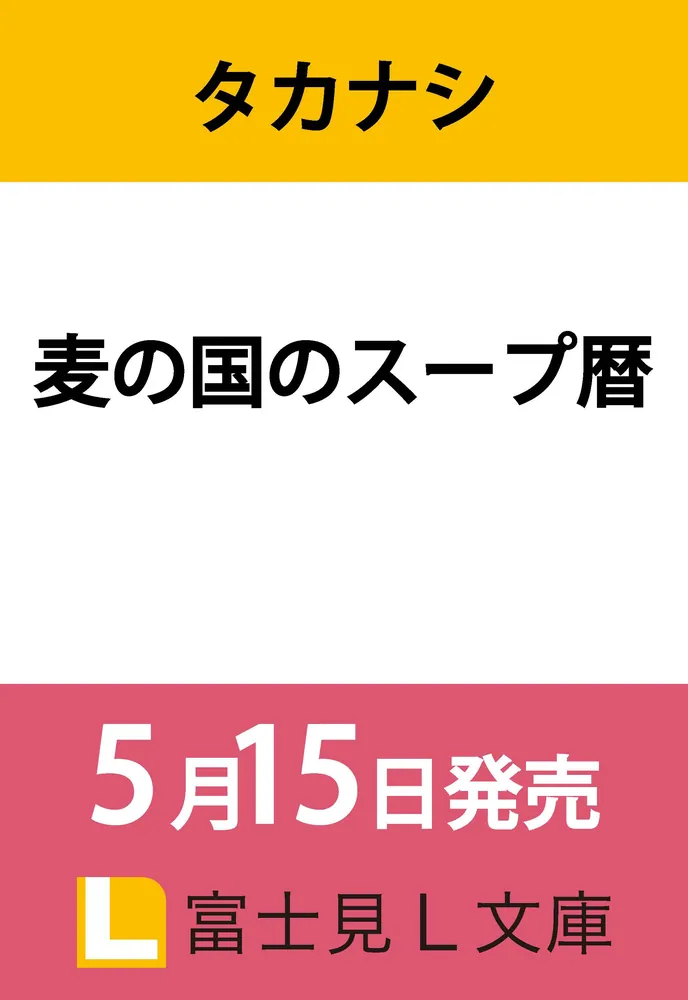
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます