二杯目 幸せをもたらす夏いちごのガスパチョ⑧
「そうだよ。僕はただの臆病者だ」
「違うわ……私もヴィセンテのことならよく知っているもの。頭が良くて努力家なだけでなく、正義感も強くて頼りになる人だって。子どもの頃は、いじめっ子たちを追い払ってくれたこともあったわね。それも一度や二度じゃない。困ったことがあると、よく助けてもらったわ」
「誰にでもそうしていたわけじゃない」
ヴィセンテはむすりとしたように言った。
「商売がうまくいってせっかく店が大きくなったのに、私と結婚してこの町に残ってもいいの?」
「家業は兄が継ぐことになっている。サラが心配することじゃない」
「まさか、一人娘の私に同情しているの? なかなか婿養子が見つからなくて困っていると思った?」
「同情だって? 馬鹿馬鹿しい。君のほうこそ、親の言いなりになって僕と結婚してもいいのか? 僕なんか、そもそも……ああ、もういい」
執拗なサラの質問に、ヴィセンテは音を上げたように天を仰いだ。
「じゃあ、何だって言うの?」
「…………」
「言ってくれないと分からないわ」
「…………」
ヴィセンテは、再び口を閉ざしてしまった。
「シーナ、そう言えば、麦の国には〝寡黙は信頼を得るが、沈黙は愛を失う〟という、古いことわざがあるんだ」
我慢ならなくなったのか、アルバはいきなりそんなことを言い出した。
ぎくりとしたように、ヴィセンテが調理場を振り返る。
「まあ! そんなことわざが!」
シーナはわざと、大げさに言ってみせた。
シーナとアルバは、そっとうなずき合う。
「やはり愛の言葉は口にしてこそ、ですものね。どんなに素敵な贈り物……たとえば、素晴らしい指輪をいただいたとしても、心のこもった愛の言葉にはかないません」
シーナは、あくまでもアルバに向かってそう言った。
「えっ、指輪……? あ、ああ、そうだな」
シーナの芝居に、アルバは戸惑いつつもなんとか合わせる。
「シーナさん……」
芝居の意図を読み取ったサラは、シーナに向かって強くうなずいた。
サラさん、私がついているから大丈夫……。
シーナは励ましの意味で、サラへとうなずき返す。
心を奮い立たせるかのように、サラは表情を引き締めると、ヴィセンテへと向き直った。
「私、あなたから指輪をもらって、涙がこぼれるほど嬉しかったの。とても大事な指輪だったから、ずっと指にはめたまま一度も外さずにいたわ。だけど、指輪だけじゃ、ヴィセンテの思いは分からない。ちゃんと聞かせてほしいの。あなたの気持ちを」
「一度も外さずに? まさか……僕が贈った言葉に、気付いていないのか?」
ヴィセンテは唖然としている。
「ヴィセンテが贈った言葉?」
「……そうか、そういうことか。ここに呼ばれた理由がやっと分かったよ」
サラの目の前で、ヴィセンテは手のひらを上に向けて広げた。
「サラ、僕が贈った指輪を外してくれないか」
「えっ……そんな……」
「頼むから」
「……分かったわ」
サラは悲しみを耐えるように口元を引き結び、渋々と指輪を外す。
「サラ、よく見てくれ」
ヴィセンテは指輪をつまんで、内側が見えるようにサラに示した。
『プルクラ・エス、アミカ・メア』
「これは……?」
指輪の内側に刻まれた異国語が読めずに、サラは不安げな表情になる。
「君は美しい、僕の愛する人、という意味だ」
「それが、ヴィセンテの本当の気持ちなの?」
サラの切迫した表情を見て、覚悟を決めたように、ヴィセンテはごくりと息を呑んだ。
「ああ、本当だよ……僕はサラをずっと愛している……だけど、言葉にするのが怖かったんだ。僕は、他人と会話をするのが怖い。正しい発音か、言葉を間違っていないか、気がかりでしょうがないんだ。誰かの視線を感じるたび、笑われているんじゃないかといつも怯えている」
「そんな……知らなかったわ」
ヴィセンテの思いがけない告白に、サラは驚きを隠せない。
「だから、僕は臆病者なんだよ。そのうえ、親の財力がなければ、君に結婚の申込みもできない情けない男だ。そんな僕が夫となることで、君まで奇異の目で見られるんじゃないかと思うと余計に怖くなる。だけど……それでも、君を愛する気持ちは本当だ」
「ヴィセンテ……」
ヴィセンテの思いをしっかりと受け止めながら、サラは震える手をそっと胸元に当てた。
「ありがとう。私も同じ気持ちよ」
「まさか……本当に……?」
「あなただから、結婚を承諾したのよ」
「サラ……嬉しいよ……」
「もう、怖がる必要はないわ。今度は、私があなたを守るから」
そこから先は、互いの思いを噛みしめるかのように、二人は黙り込むのだ。
二人なら、大丈夫ね……。
様子をうかがっていたシーナは、ほっと一息つく。
プルクラ・エス、アミカ・メア――君は美しい、僕の愛する人。
あの日、指輪に刻まれた愛の言葉に気付いたシーナは、言葉の意味は告げずに、もう一度二人で話をすべきだとサラに持ちかけた。
愛の言葉は、本人から直接聞いたほうがいいはず……。
しかし、拒絶されたらと思うと二人きりになるのが怖い、とサラは言う。そんなサラの気持ちを汲み取って、シーナは二人を店に招待することにしたのだ。
「二人のところへ、スープを運んできますね」
シーナが告げると、アルバは無言でうなずく。
「冷たいとうもろこしのスープです。それから、くるみパンにあんずジャムを添えました」
乾煎りしたくるみを混ぜて焼いたパンは、でこぼことした見た目をしていた。
個性的な見た目ではあるが、くるみの香ばしい風味とこりこりとした食感がやみつきになる、おいしいパンに焼き上がっている。
料理を載せた皿に飾ったのは、森の入口で摘んだチャイブの花だ。
「まあ、素敵! シーナさん、ありがとう」
薄紫色の小さな花を見て、サラは嬉しそうにする。
「懐かしいな……子どもの頃に熱を出した時、すりつぶしたとうもろこしのスープを作ってもらったことがある。麦の国にも、体を労るスープがあるんだな」
ヴィセンテの表情が、一段と柔らかくなった。
「いただこうか」
ヴィセンテが言い、二人はそっと見つめ合って笑みを浮かべる。
「どうぞ、召し上がってください」
それだけ言うと、シーナは静かに調理場へと戻っていった。
「うまくいったな。シーナのスープが最後のひと押しとなって、二人の心の鎧を剥ぎ取った」
アルバの言葉に、シーナは「いいえ」と遠慮がちに返す。
「私はただ、私のスープを作っただけですから」
それでも、二人のために、このスープを作って良かった……。
言いようのない充実感が、シーナの中に広がっていった。
これからも、人々を笑顔にできるスープを作りたい……。
スープを口に含み、微笑み合う二人の姿が、シーナに未来への希望を与えてくれるようだった。
再び、二人の話し声が聞こえはじめ、シーナとアルバは咄嗟に耳を澄ませた。
「だけど、ヴィセンテは誤解しているわ。町の人たちは恥ずかしがり屋ではあるけれど、よそ者だからというだけで、笑ったり避けたりする人ばかりじゃないと思うの」
サラは切々と、ヴィセンテに語った。
「確かに……町の人たちには、僕たち家族も助けられてきたんだった……」
ヴィセンテは深くうなずいている。
「あなたは、臆病者でもないし、情けなくもない。ヴィセンテが、家族と一丸になって必死に働いてきたのを、町の人たちはよく知っている。今となっては、あなたを笑う人なんてどこにもいないはずだわ」
サラの言葉に、ヴィセンテは控えめながらも喜びを滲ませる。
「それから、私は無理なんかしていない。この町や町の人たちが好きなだけ。今の私は、好きな人たちと会って、楽しくおしゃべりがしたいだけなの。内気な女の子は、あれからずいぶんと成長したのよ」
「そうか……要するに、もっと僕が君と話をすべきだったんだな」
サラはにっこりと微笑んだ。
「これからいくらでも語り合いましょう。旦那様」
「なっ…………ここのスープは本当においしい」
サラから旦那様と呼ばれて照れくさくなったのか、ヴィセンテは白々しく話をそらす。
そんな初々しい二人の様子に、シーナは優しく微笑んだ。
「いつまでも、自分から逃げてはいられないんだよな……」
アルバがつぶやくように言う。
「アルバ……?」
シーナは、アルバの顔を見上げた。
「あ、いや、だから……彼は臆病者なんかじゃないだろ。本当の自分を見せることは、とても勇気がいることだ」
「ええ、そうですね……」
「その勇気が持てたのも、受け止めてくれる相手がいたからか……」
しみじみと言うアルバに、シーナも感じ入る。
「サラさんとヴィセンテさんは、お互いがいたからこそ救われたんですね」
本心を見せ合うことが、これほど二人の今を変えるなんて……。
穏やかな空気の中で、楽しげに食事をする、サラとヴィセンテ。
固く絆を結んだ二人のまばゆさに、シーナは目を細めるのだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




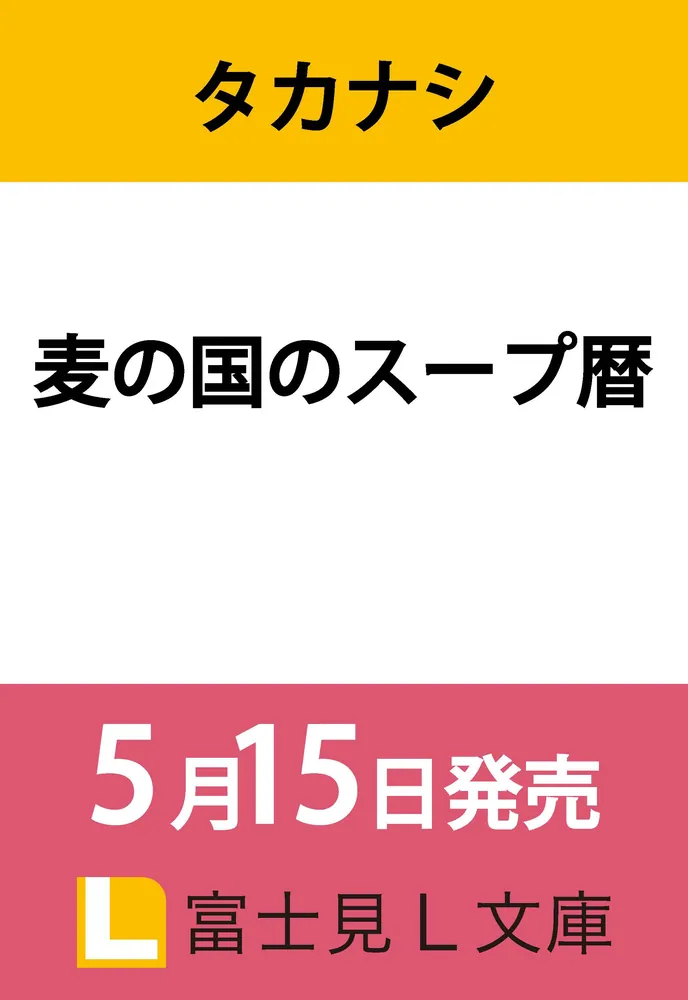
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます