二杯目 幸せをもたらす夏いちごのガスパチョ⑦
「いらっしゃいませ。お待ちしていました」
すれ違う二人のために、この場を用意したのはシーナである。
「彼が婚約者のヴィセンテよ。彼も、シーナさんのスープを楽しみにしているわ。ヴィセンテ、そうよね?」
サラはぎこちなく、ヴィセンテを見上げた。
「シーナさん、はじめまして。お招きありがとうございます」
ヴィセンテは被っていた帽子を取る。表情は硬いが、態度は極めて紳士的だった。
「はじめまして。足を運んでいただき嬉しく思います。こちらへどうぞ」
シーナは二人を奥の席へと案内した。
「シーナさんにヴィセンテを紹介しなくちゃね……ええと、何から話せばいいのかしら」
サラはそわそわしながら早口で言った。
「ヴィセンテは、家族と一緒に色々な大陸を旅してきたのよ。だから、知識が豊富でいくつもの言語を話すことができるの。ご両親は商店を営んでいて、食料や日用品だけでなく珍しい特産品も扱っているから、町の人たちに重宝がられているわ。ヴィセンテも幼い頃から家業を手伝ってきたのよ。何日もかけて、遠方まで仕入れに出かけることもあるんだから」
ヴィセンテを語るサラは、とても誇らしげである。
当のヴィセンテは、サラの話に相槌を打つこともせず、終始無言だった。
「そうでしたか。では、そろそろ料理を……」
シーナはスープの準備をしに調理場へ戻ろうとするが、サラの話は止まらない。
「シーナさんのとうもろこしのスープ、楽しみでしょうがなかったの」
おそらく、二人きりになるのを怖がっているのだろう。
シーナには心当たりがあった。
「もちろん、ヴィセンテも楽しみにしているわよね。そうでしょう?」
ヴィセンテの故郷ではとうもろこしが主食と聞き、この日のために腕によりをかけて作った、とうもろこしのスープだ。ところが。
「あ、ああ」
ヴィセンテは、たいして興味がなさそうである。
「私、シーナさんのスープがどれだけ素晴らしいか、町の人たちにも話して回ったわ。だって、一人でも多くの人に知ってほしかったんだもの」
客がちらほら増えはじめたのは、サラのおかげだったようだ。
「サラさん、ありがとうございます」
サラの親切心を、シーナは心から嬉しく思ったが。
やはり、ヴィセンテは小さく首を振り苦笑するだけだった。
「なっ……」
ヴィセンテの態度に気付いたサラは、不服そうに頬を膨らませる。
「言いたいことがあるのなら、はっきり言ってくださらない? 私たち、これから夫婦になるというのに、こんなことでいいのでしょうか」
「…………」
「私の話、聞いています?」
「…………」
聞いているのかいないのか、ヴィセンテは押し黙ったままだ。
「もういいわ」
返事のないことに呆れたのかサラまで黙り込み、少々険悪な空気が立ち込める。
だが、シーナにさほど心配はなかった。
「他にお客様もいらっしゃいませんし、ゆっくりしていってくださいね」
サラの指輪にちらりと目をやり、そっとその場を離れる。
本人たちが気付いていないだけで、二人は互いを思い合っていると、すでにシーナは知っていた。
二人にそれぞれの思いを伝えれば、簡単な話かもしれない。しかし、互いが相手を理解しようと努力することのほうが、ずっと大切なはずだ。
二人なら乗り越えられる……。
シーナは、二人が会話をしやすいように奥へ引っ込み、食事の準備を進めることにした。
愛し合う二人のために、心を込めて……。
とろりとした黄色いスープを、器に流し込む。
黄色いスープは、茹でたとうもろこしを丁寧に裏ごしし、野菜の出汁と牛乳で伸ばした、冷たいスープだ。
ヴィセンテの故郷のとうもろこしスープは、鶏肉からとった出汁で作る濃厚なスープで、裏ごしせず粒感を残すのが特徴だと知ってはいたものの。
シーナはあえて、夏の暑さに疲れ気味の町の人たちに合わせ、喉越しの良い冷たいスープに仕上げてみた。
「味もちょうどいい」
口に含めば、とうもろこしの甘さとほのかな塩味が、舌の上でゆっくりとほどけていく。とろけるように滑らかな食感の、優しいスープだ。
仕上げに香草を飾り、オイルを垂らせば、爽やかで豊かな香りがふわりと漂う。
二人がこの味を気に入ってくれるといいけれど。
「シーナ、さっきは……」
大きな麻袋をかかえやってきたのは、アルバだ。
「すまない。まだお客さんがいたのか」
アルバは身をかがめながら、こそこそと調理場に回り込んでくる。
「いつもの、採れたて野菜だ」
小声で言いながら、アルバは麻袋をどさりと床へ置いた。
「こんなにたくさん……いいのですか?」
「今年は特に豊作なんだ。それに、いつも大盛りにしてもらっているだろ。世話になりっぱなしだから」
世話になっているのは自分のほうだと、シーナは怪訝に思う。
「ところで……何かあったのか?」
重い空気を感じ取ったアルバが、そっとシーナに耳打ちした。
静まった店内に、ヴィセンテが深く息を吸い込む音が響く。
「僕の前で、無理をする必要はない。君が町の人たちの前で、わざわざいい人を演じているのを、僕は知っている」
「えっ…………」
サラは驚いたように目を丸くしていた。
サラさんが演じている?
ヴィセンテの言葉に違和感を覚え、シーナは調理の手を止める。
シーナには、サラの人の良さは演じたものではなく、彼女の本質だと思われた。
「地主の娘として、社交的であるよう求められてきたことも、もちろん知っている。だから、僕といる時は、無理しておしゃべりをする必要はない」
どうやら、ヴィセンテにも思うところがありそうだ。
シーナが考え込んでいると、アルバも同じように思案している様子だった。
「いったい、どうしたの……今日は、あなたのほうがおしゃべりね」
サラはきまずそうにうつむく。
「おしゃべりな私は嫌い?」
頼りなくつぶやいた。
「ノン・イータ!」
ヴィセンテは声を張り上げたあと、しまった、という具合に頭を抱える。
聞き慣れない言葉にアルバは眉間に皺を寄せ、シーナはその言葉が別の大陸の言語だと気付いた。
「す、すまない……そうじゃないんだ」
「私なら、大丈夫よ」
サラは平然としている。
「……君のおしゃべりのおかげで、僕たち家族は救われた。麦の国にやってきたばかりで、この国の言葉をまだうまく話せなかった頃から、サラは気さくに僕たちに話しかけてくれただろ。他の人たちのように、よそ者の僕たちを陰で笑ったり、あからさまに避けたりすることもなかった」
ヴィセンテはすでに落ち着いていたが、言葉には強く訴えかけるものがあった。
「僕たちはいつも、サラが遊びにきてくれるのを心待ちにしていたんだ」
サラは咄嗟に顔をあげる。
「だけど昔から、ヴィセンテは私と話をしてくれなかったじゃない」
「何を話せばいいのか分からなかったんだ。それに……あの頃は、今よりずっと言葉も上手じゃなかったし」
「私のこと、よく知っているのね。興味がないのかと思ってたのに」
「サラの家の庭は通りに面していて、外からよく見えるんだ。だから、木陰で静かに本を読むことや、編み物をするのが好きな女の子だって知っていたよ。家に閉じこもっていないで友達と遊ぶようにと、いつも注意されていたこともね」
ヴィセンテはほんの少し声を弱める。
「あなたの言う通りよ。私、親に言われて、ヴィセンテの家に遊びに行っていたの。私の父は、いずれあなたたちがこの町を潤してくれると分かっていたのよ。だから、私を使ってあなたたちと親しくなろうとしたのね……ごめんなさい」
過去を悔いているかのように、サラの瞳はわずかに潤んでいた。
「だとしても、君が気にすることじゃない。そもそも僕たちは、この町の質の良い麦を扱いたくてここへやってきたんだから、お互いにとって有益な関係でしかないだろ。それに、あの頃の僕はただ、おしゃべりな女の子のことを……いい子だなと思っていただけで……」
ヴィセンテの声は、ますます小さくなっていく。サラの様子に、動揺しているのだろう。
「ヴィセンテはやっぱり、昔のままだったのね」
サラは泣きそうな顔で微笑んだ。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




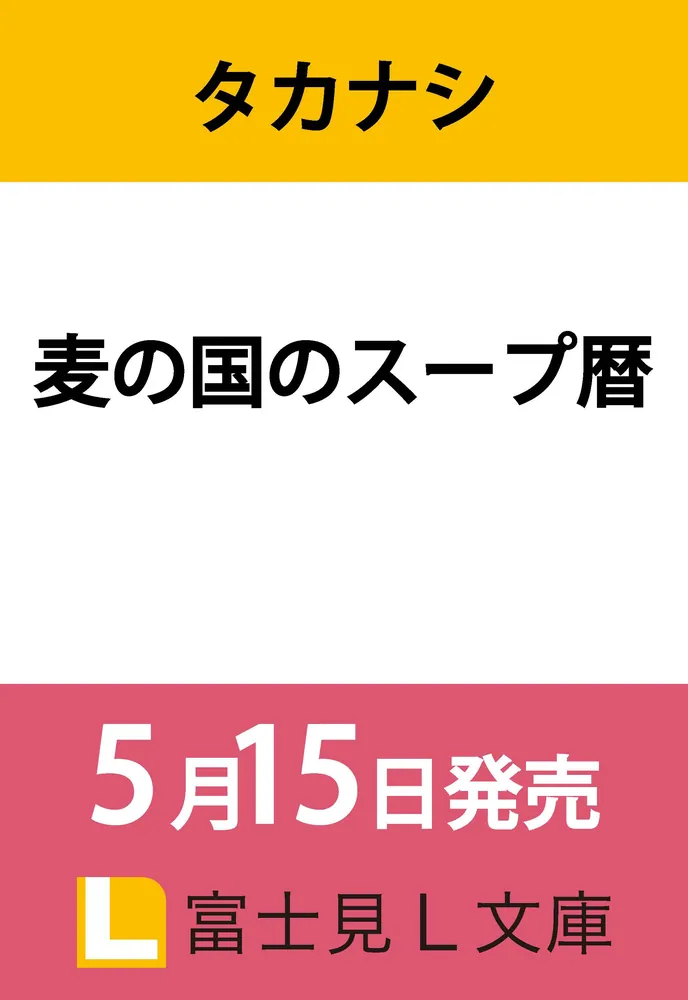
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます