第10話
扉をくぐり抜けた先は、雑然とした空間となっていた。
洗剤、ブラシ、ワックスなどがぎっしりと詰まった棚に、積み上げられた椅子や箱。その隣では白エプロンと黒のロングドレスを身につけた女性たちが、身支度をしながらおしゃべりに興じている。けれども
見回しても人間の姿はない。ここでもラヴィニアは、異質な存在であるらしい。
「この部屋が清掃部門の事務所だよ。仕事を始める前に、まずここにみんなで集合するの。あ、出勤したら名前を台帳に書いてね。それから制服に着替えて、朝礼が終わったら持ち場につくよ」
周囲の視線をものともせず、マルルカは早口に説明しながら室内を突っ切って行く。さらには部屋奥の『主任室』と書かれた扉のドアノブに手をかけて、勢いよく中へと足を進めた。
「主任! 入ります!」
扉の先にいたのは、襟つめの制服を着た老婦人だった。年は六十半ばといったところで、灰色混じりの白髪を緩みなく結い上げている。
容姿だけを見るならば、いかにも家政婦長といった風体だ。だが魔素で輝く錆色の虹彩が、彼女に魔女めいた威圧感を醸していた。
話の流れから察するに、この老婦人が清掃部門の長なのだろう。仕事中だったのか、彼女が向かう机の上には書類が積み重なっている。
「……マルルカか。部屋に入る時にはノックをしてくれと、いつも言っているだろう」
至極もっともな苦言を吐きながら、老婦人が顔を上げた。だがマルルカの背後に見慣れぬ人影を認めると、目元の眼鏡を下にずらす。
「誰だい。ここは部外者立ち入り禁止だよ」
「新人ですよ。ほら、客室清掃で募集をかけていたでしょう」
老婦人の睨みを軽く受け流すと、マルルカはラヴィニアの背中をぐいと押す。
「ラヴィニア。この人が客室部門の主任、バーシャさんだよ。さ、挨拶して」
「挨拶って。そんな、いきなり――」
心の準備もないままバーシャの前に立たされて、流石のラヴィニアもまごついてしまう。
だがこういう場面では、最初の印象が肝心となる。高圧的な相手に初手で舐められると、その後の人間関係に不利が生じかねない。
ラヴィニアはドレスの裾をふわりとつまむと、軽く膝を折って一礼した。
「突然のご挨拶となり失礼いたします。本日より清掃部門で働くことになりました、ラヴィニアと申します」
令嬢教育で鍛え上げた、宮廷風の挨拶である。こうしたさりげない所作一つに、気品や教養が滲み出るものだ。
「一日でも早くお役に立てるよう、精一杯頑張ります。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします」
そして完璧なお辞儀の最後には、控えめな笑みを添える。隣で見ていたマルルカが、「わあ」と感嘆の声を上げた。
「素敵。ラヴィニア、お姫様みたい」
――この娘には優しくしてやろう。ラヴィニアは胸の奥で密かに誓った。
だが相対するバーシャが漏らしたのは、不満のため息である。
「はぁ。人手を寄越せとは言ったが、よりによってこんなお荷物が送り込まれるとはね」
「……お荷物、ですって」
聞き捨てならぬ単語を耳にして、ラヴィニアは表情を強張らせた。
そうだお荷物だよ、とバーシャは丁寧に肯定する。
「手足は細っこくて頼りないし、肌は病人みたいに生っ白い。おまけに混ざりもののない人間で、立ち振る舞いは上流貴族そのものときた。――これがお荷物じゃなくて、なんだと言うんだい」
次々と問題点を
「いいかい、ここはホテル・アルハイムだ。世界最高峰のこのホテルで、中途半端な仕事は許されない。指にあかぎれ一つない箱入りのお嬢様が、ごっこ遊びをしていい場所じゃないんだよ」
「ですが総支配人は」
「お黙り。どんな事情があるのかは知らないが、ここはあんたの場所じゃない。荷物をまとめてとっとと帰りな」
反論を封じると、バーシャは尖った顎をくいっと動かし扉を示す。出ていけ、と言いたいらしい。
ラヴィニアは愛想笑いを凍りつかせたまま、しばらくその場に立ち尽くした。
ゴミを掃いて捨てる程度の仕事など、そこらの子供にだってできるはず。それなのに、どうしてこの自分が侮られなければならないのか。
他人の挑発に乗ってはならない。売られた喧嘩は速やかに転売すべしというのがバースタイン家の教えである。だが今のラヴィニアにとって、〝役立たず扱い〟は何にも耐え難い屈辱だった。
「お言葉ですが、私は」
「もう! どうしてそんな意地悪言うんですか!」
だが舌戦開始寸前のところで、思わぬ援護があった。マルルカがやや間延びした口調で、怒りの声をあげたのだ。
「せっかく新入りが来てくれたのに、働く前から追い出そうとするなんて。いま客室清掃は空前の人手不足なんですよ!」
「だからって、いかにも訳ありなお姫様を働かせる馬鹿がどこにいるんだい」
お姫様、の部分に皮肉を込めてバーシャが言うが、マルルカは引き下がらない。
「私がラヴィニアに仕事を教えます。彼女が働けるかどうかは、今後の成長を見てからでも遅くないはずです。それに――」
マルルカは胸を張ると、ラヴィニアの腕を取る。
「お姫様がいると心強いよね。なにせうちのホテルには、色んな国のお姫様がお泊まりになることだってあるんだから」
「……わかった、好きにしな」
とうとうバーシャが降参の旗を振った。これ以上の面倒はごめんだと言わんばかりに、勢いよく立ち上がる。
「ただし使えないと判断したらすぐに首を切るからね。嫌ならさっさと仕事を覚えな」
「あ、ありがとうございます!」
反射的に礼を言ってしまい、ラヴィニアは自分の口を押さえ込んだ。これではまるで、バーシャに許しを乞うていたようではないか。
当のバーシャは苛立たしげに懐中時計を取り出すと、「チッ」と大きく舌打ちした。
「始業時間が三分遅れちまった。ほら、さっさと出るよ」
ラヴィニアを押し退けるようにして、バーシャは事務室の扉を開け放つ。
外ではルームメイドたちが、こそこそと語らいながら主任室の様子をうかがっていた。
「朝礼を始めるよ! 整列しな!」
ガラガラと錆びたハンドベルを響かせながら、バーシャが部屋全体に呼びかけた。たちまちお喋りの声が鳴りやんで、数十名のメイドたちが事務所中央に整列する。
「はじめに、今日から新人が一人増えることになった。名前はラヴィニアという。マルルカが指導役につくが、他の者も気づいたことがあったら遠慮なく指導するように」
「よろしくお願いしま――」
「続いて昨日の反省点だ。シーリン!」
ラヴィニアの挨拶は、荒々しい声にかき消される。
いつもこの調子なのだろうか。名を呼ばれた黒髪のメイドは特に戸惑う様子もなく、澄ました顔で前に進み出た。
「303号室、浴室ゴミ箱の処理忘れ。407号室、掃除用布巾の置き忘れ。410号室、使用済みティーカップの交換忘れ。また509号室のお客様からは、『隣室の掃除の音が響く』との苦情があり――」
黒髪のメイドが、手元の用紙を読み上げていく。次いで他のメイドが夜番からの引き継ぎ、さらに他のメイドがフロントからの引き継ぎ事項を読み終えたところで、バーシャが内容を総括した。
「このところ掃除の抜けや失敗が増えているね。それぞれ清掃終了前に、必ず定められた順番で抜けがないか確認をするように。人手不足は手抜きの理由にならないよ!」
「はい!」
メイドたちが一斉に応答する。重なり合った声が反響して、じりじりと壁を揺らした。バーシャは満足そうにうなずいて、再びベルを打ち鳴らす。
「いい返事だ。――ではこれにて、朝礼を終了とする。気を引き締めて行ってきな!」
いつしか事務所には、戦場さながらの空気が流れていた。きゃっきゃと談笑していたはずのメイドたちは、すっかり戦士の顔となって各々持ち場へと向かって行く。気づけばラヴィニアだけが私服のまま、その場にぽつねんと取り残された。
「あの。私はどうすれば――」
「じゃ、行こうか」
手持ち無沙汰に視線を惑わすラヴィニアの肩を、誰かがぽんと叩く。
振り向けばやはり戦士の顔をしたマルルカが、にかりと逞しい笑みを浮かべていた。
「働かざるもの食うべからずだよ」
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




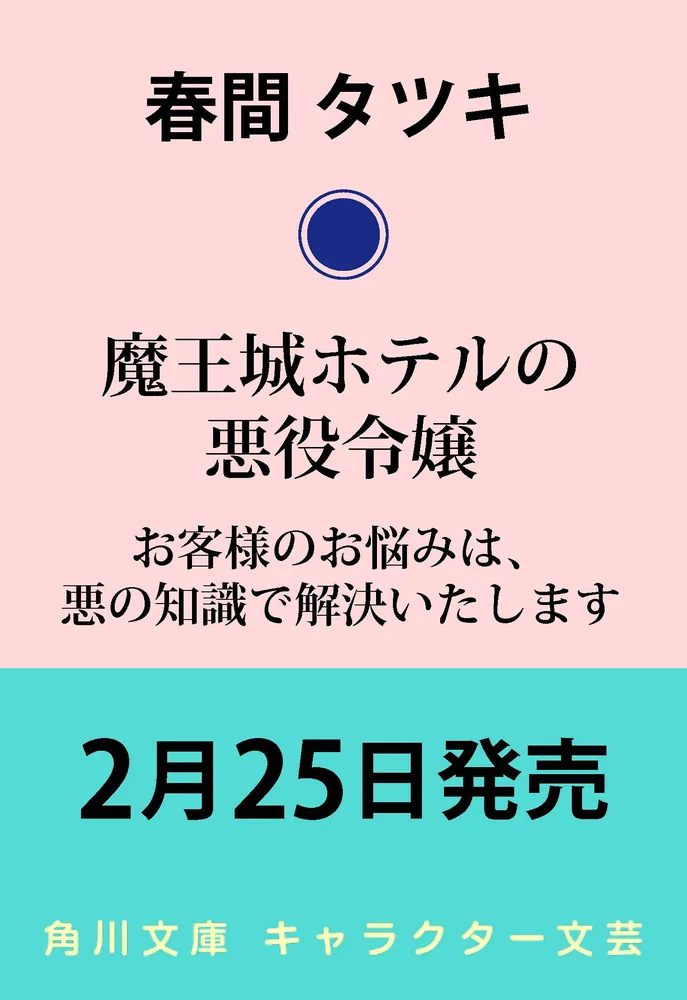
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます