第3話 のろけのような愚痴のような
「はいはい、もうすぐ終わるよー。がんばれゆうじくーん」
「んぶぅふぇふびー!」
「もうちょっとだー」
歯科クリニックの診察室から聞こえてくるのは、器具が歯を削る音と先生のかけ声、そしてたまにお子様の泣き声。
きゅいいいいいいん。
「ぴぎゃー」
子供特有の超音波と、ドリルの高音が交互に響く。
歯の治療はクライマックスを迎え、しばらくすると顔を真っ赤にして涙まみれのお子様と、それ以上にげっそりした顔のお母様が連れ立って待合室に戻ってきた。
受付の椅子に座るひばりは、まずお子様を目一杯ねぎらった。
「ゆうじくーん、がんばったねー。えらいよー」
「ん」
間を置いてお母様には診察券と保険証の返還、そして次回のご予約についてのお話をする。見送る時は「ありがとうございます」ではなく、「どうぞお大事に」と言う。
思えば『ときとう』のお客様は、自分からおいしいものを買いに店を訪れ、ほくほく顔で出ていく人ばかりだったなと思う。あれはかなり幸せな奇跡のもとに成り立っていたわけだ。
伊吹と結婚するため東京に越してきたのが、二月の半ば。今は年度も明けて四月だ。仕事はどうせなら飲食以外の仕事をしてみようと、築地の歯科医院で受付のパートを始めてみた。
ここで『ときとう』二号店の開店資金を貯めようと思っているが、色々気づきも多いのだ。
「三輪さーん、今ので午前の患者さん最後だったよね。お昼入っていいよ」
「あ、はいっ。ありがとうございます」
背後からこの『築地ひまわり歯科クリニック』の院長、
本人は名前に影があるのを気にしているらしいが、院内の雰囲気もご本人も明るくなるよう心がけて立派だと思うのだ。
お昼は院内のスタッフ休憩室でいただく。
(やれやれ、やっとご飯にありつけますわ)
パートのために新しく奮発して買った曲げわっぱの弁当箱の蓋を開けると、現れるのは黄色い薄焼き卵で包んだチキンライスだ。
リーフレタスで隙間を埋めつつ、副菜にミニトマトと唐揚げも入れた、いわゆる鶏×鶏オムライス弁当だ。ここまで自転車をこいで来るため、移動中にケチャップでおかずが汚れる危険を加味して卵の上にかけるのは乾燥パセリだけにしたが、ご飯にも薄焼き卵にもしっかり味をつけたので、物足りない印象はないはずだ。一見プレーンな卵焼きと思わせて、箸を入れるとケチャップ色のご飯と人参やグリンピースが出てくるご機嫌な仕掛けである。
(ん、冷めてもおいしい。塩加減ばっちり)
もぐもぐ食べながら、同じものを食べているであろう伊吹のことを考える。
全部自分で作ったので今さら驚きもないが、伊吹には少しでも楽しんでもらえたらいいと思うのだ。
「わー、三輪さんのお弁当、相変わらずおいしそう」
一緒に休憩に入った
彼女はひばりと同年代の歯科衛生士だ。本日のランチは、コンビニの新作サラダとサンドイッチのようである。
「いぶき……旦那のぶんを作るついでですから」
「そうだよねー、新婚さんなんだもんねー。私には未知の領域すぎてさっぱりだわ。ぶっちゃけどんな感じ? 結婚してみて」
まるでインタビュアーのように、ストローを挿す前のオレンジジュースパックをつきつけてきた。
最近彼氏と別れたばかりだという菊花嬢は、婚活にも興味があるらしい。
──どう、と言われても。
「良かったなーって思いますよ。一緒に暮らしてみないと、わからないことってありましたし」
「へえ、たとえばどんな?」
「テレビでお笑い番組見てると、やたら顔怖くなるんですよね。つまらないのかなって思ったら、むしろツボにはまると際限なく笑っちゃうから、顔面に力入れてたみたいで」
「……写真見せて貰ってもいい?」
「こんなんで」
「このさわやかそうなイケメンが!?」
「しかもすごい時間差で思い出し笑いするんです」
「ご職業ってなんだっけ」
「なんか、どっかの財団法人の職員らしいです。『MKL』ってご存じですか? 非営利で国際交流とかフェアトレードとかやってるって話で」
「ごめん知らない」
「わかんないですよね、NTTとかPTAとかFBIとかいっぱいあって。私もいまいちよくわかってなくて」
ひばりは苦笑した。
とりあえず、旧姓の時任ではなく三輪と呼ばれることに関しては、だいぶ慣れた。方向感覚の手がかりに、山を使わず歩くことも修業中だ。
しかし同じ家に住んでいても伊吹は相変わらず忙しく、たまに電話で知らない土地の話をしている。急な出張や休日出勤も多く、言うほど二人の時間があるわけでもないのは予想外だった。
それでも新幹線の距離にいた頃に比べれば、何もかもずっとましだろう。
「あ、でも、ありました一個。困ったこと」
「なに、なに。教えて」
目を輝かせて迫ってこないでほしいと思う。
「別にすごく
「えー、何それ。夜中につまみとか作らされるってこと!? 最悪!」
憤慨するのとブリックパックにストローを突き刺すのがほぼ同時で、オレンジジュースが休憩室の壁まで噴出された。院長に見つかるとことなので、ひばりたちは慌てて痕跡を雑巾で拭いた。
「そっかー。やっぱ色々あるわよねー。いくらイケメンで高収入でもね。うん。気をつけよう」
「そこまで嫌ってわけじゃ」
「注意一秒怪我一生。目先のおいしい餌に飛びついちゃ駄目よ菊花」
菊花は一人ぶつぶつと、己に言い聞かせている。
ひばりとしては、料理を作ること自体は唯一の取り柄と言ってもいいので、前述の通りそこまで苦でもないのである。
ただ、ただだ。
これを菊花に言っていいものかわからないが──どうも伊吹が連れてくるお客様は『変』な気がするのだ。
***
『ごめん。これから三人連れていきたいんだけど、なんとかなる?』
パートが終わって先に夕飯を食べていたら、伊吹から連絡が来て目をむいた。
(待って待って、急に言わないで伊吹)
慌てて胸を叩いてご飯を飲み込み、ダイニングテーブルに置いたスマホに返信を打ち込んだ。
『いいけど、もうちょっと早く言って』
『ほんとごめん』
ほんとだよ。
伊吹の職場は東銀座にあり、佃のこちらまで歩こうと思えば歩けるし、電車やタクシーを使ってもすぐだ。つまりあまり時間的猶予はない。旦那の職場が近いというのも、こうなると考え物かもしれなかった。
とりあえず急いで自分の食事をかきこんで終えると、皿は流しへ移動させた。
伊吹に出すつもりだったハンバーグと付け合わせは、潔く明日の弁当に回すことにした。
炊飯器のご飯は、みんな握っておにぎりにしてしまおう。三つに分けて一つは米酢とゆかり、もう一つはごま油と塩昆布、もう一つは枝豆とプロセスチーズを混ぜ込み、三色おむすびにすれば見栄えもいい。
弁当用に卵だけは沢山買ってあるので、出汁をきかせて分厚い出汁巻きを焼く。あとは旬の春キャベツを塩麹で揉んで浅漬けにし、ご近所の佃煮屋さんで買った『いかあられ』でも出せば上出来だろう。
(──よし。もうなんにもしないぞ)
超特急で主要な料理を作り終え、ひばりは額の汗をぬぐった。
どれもこれも時間がたって味が落ちるものでもないので、おにぎりの皿にラップだけかけて終了とする。
後は台所でダイニングセットの椅子に座って、出汁巻きの切れ端や混ぜ込まなかったチーズや枝豆の余り──作り手の特権だ──をつまみながらビールを飲んでいたら、玄関の呼び鈴が鳴る音がした。
「帰ってきたなー、伊吹のやつめ」
口の端についた泡をぬぐい、ひばりは立ち上がった。
玄関の引き戸を開けると、スーツ姿の伊吹が客人を連れて立っていた。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




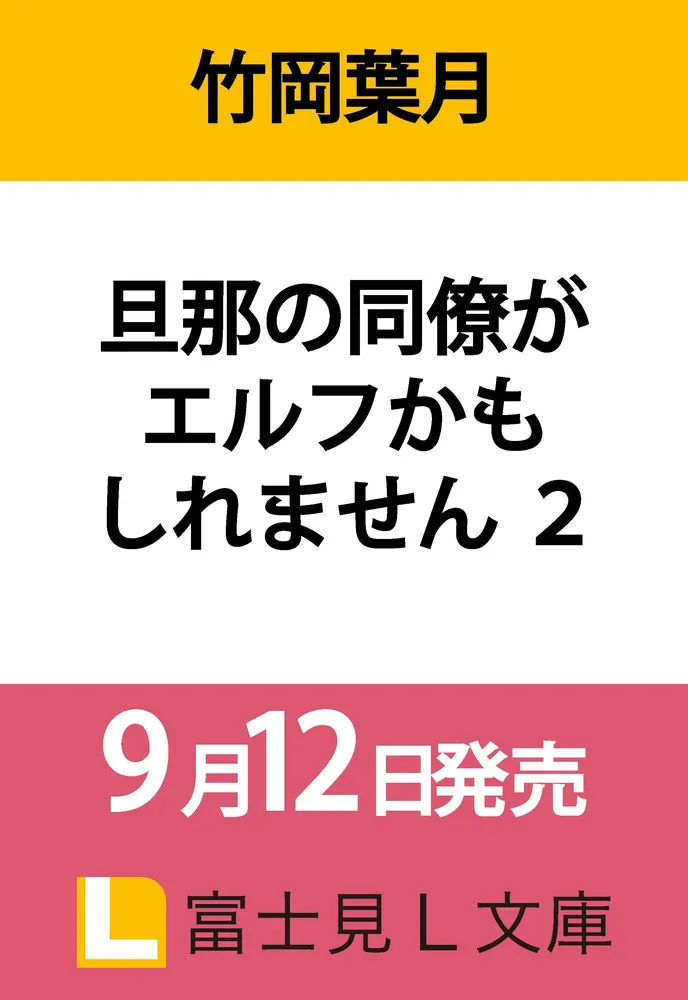
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます