第5節 別れ
異変は突然だった。
「おはよう、ルクス」
「おはようヤミ……」
朝、いつものようにリビングに立つルクスを見て驚いた。
彼の顔色は真っ青で、目の下には酷い隈が浮かんでいた。
昨日までは元気そうだったのに、生気が失われている。
「大丈夫? 体調悪そうだけれど」
「これくらいどうってことないさ……」
ルクスは弱々しい笑みを浮かべると、フラフラとした足取りで自室へと向かった。
部屋の中に入った後すぐに大きな物音がして、私は慌てて彼の部屋へと飛び込む。
地面に倒れ込んだルクスの姿がそこにあった。
「ルクス!」
そこから、ルクスは目に見えて衰弱していった。
体調は日に日に悪化し、一週間もしないうちにベッドの上から動けなくなった。
「私、医者を呼んでくる」
「ダメだ……。ここを離れてはいけない」
ルクスは私の手を掴む。
だがその力はあまりに弱く、かつて魔王城で掴まれた時とは比べ物にならなかった。
「でも、このままじゃルクスが……」
「良いんだ」
ルクスは切実な表情で私を見つめる。
「傍にいて欲しい」
私は、彼の願いを無視することが出来なかった。
ルクスは医者を呼ぶことを頑なに拒んだ。
それはまるで、最初から治らないことを知っているかのようでもあった。
私は彼のために付きっきりで看病をした。
けれど、彼の容態が良くなることはなかった。
祈るように彼の手を握っても、まるで氷のように冷たくて。
刻一刻と、彼が死に向かっていることだけが分かった。
その日、私はルクスのすぐ傍で目を覚ました。
眼の前にはベッドに横たわるルクスの姿があり、自分が看病中に疲れてそのまま寝てしまったらしいと気がつく。
穏やかな朝だった。
森から聞こえる自然の歌声が緩やかに時の流れを告げている。
窓からは温かな日差しが射し込んでいた。
「ヤミ、おはよう」
ルクスは息も絶え絶えに言葉を紡ぐ。
頬がこけ、体はやせ細り、かつての面影はすっかり消えてしまっていた。
その姿を見て泣きそうになったが、無理矢理笑顔で誤魔化す。
「今、御飯作るね。何が食べたい?」
「すまない、ヤミ」
私の言葉には答えず、ルクスは言葉を紡ぐ。
「傍にいるって言ったのに、君を一人にしてしまう……」
それは話しかけるというよりは、独り言を呟いているように見えた。
「変なこと言わないで。きっと良くなるから」
「君と過ごした時間は、まるで夢のようだった……」
「ルクス、喋っちゃダメ」
ルクスの視線は遠く、ここではないどこかを見つめているようだった。
「長い長い争いの先でようやく平穏を感じられた。君と過ごす日々は、きっと女神様からの贈り物だった」
ルクスは穏やかに目を細めた。
「ヤミ、僕は君のことが好きだった」
「好き……?」
「君と一緒にいると、不思議と心が落ち着いた。君が笑うと安心できたんだ。静かに癒やされるようだった。それは、君が僕に与えてくれたものだ」
「そんなの、私も同じだよ……」
ルクスは力の入らない両手で、私の手をそっと包み込んだ。
氷のように冷たくなってしまった彼の手にはもう、ほとんど血が通っていない。
「ヤミ、君を愛せて良かった……」
そして彼は目を閉じ、はっきりと言った。
「生きろ」
それきり、彼が再び目を開くことは無かった。
呼吸で上下していた胸は動かなくなり、腕の力が抜け落ちている。
穏やかな眠りについたようにも見えた。
「ルクス?」
声をかけるも、返事はない。
「起きてよルクス。ねぇ、もう一度私の名前を呼んで」
しかし、言葉は静かに空間へ溶けた。
「嫌だよ。お願い、目を覚まして……」
私は何度も懇願するように呟いた。
「私を一人にしないで……」
生まれて今まで、ずっと諦めて生きてきた。
辛いことがあっても、何も考えずにいれば受け止められると思っていた。
父が死んだ時だって、悲しかったけど涙は流れなかった。
もう、何があっても平気だと思っていたのに。
私の瞳からは、壊れたように涙が溢れ続けた。
世界は私からルクスまで奪ってしまった。
◯
ルクスの遺体を見つめたまま、私はその場に三日三晩座り続けた。
徐々に腐敗が始まったのを見て、私はようやく彼の遺体を焼く決心をした。
誰も来ない山奥で、私は炎の魔法を用いてルクスの遺体を焼いた。
抜け殻のようになった私は、灰になっていく彼をただ漠然と眺めた。
すべてが終わった時、私の元にはルクスの骨と、ルクスの指輪だけが残った。
私は残された彼の骨を壺に入れ、そこに蓋をした。
胸に大きな穴が空いたようだった。
自分の中から大切な何かが消えてしまって、それがルクスだったのだと悟る。
「……何をするんだっけ」
自分が何の為に生きているのか、既に分からなくなっていた。
苦しい。
どうしようもなく胸が痛かった。
心と体が締め付けられるようだ。
この胸の穴はもう、二度と塞がらないような気がする。
「そうか、死ねば良いんだ……」
不意に、そのようなことを思いついた。
ルクスと生きることだけが、私の最後の生きる意味だった。
生きる意味を失った今、私がこの世界にいる理由は無い。
それなら、さっさと死んでしまえば良い。
本来ならばこの命は勇者の手によって奪われるはずだった。
私が死んでも、あるべき形に戻るだけだ。
キッチンにあるナイフを手に取り、喉元に突きつけた。
後は思い切り喉を突けば、私は死ぬだろう。
簡単なことだ。
いくら私が魔王と言えども、魔法で保護もせずに致命傷を受ければ簡単に死ぬ。
「ルクス……今、会いに行くね」
ナイフを刺そうとしたその時。
『生きろ』
ルクスの言葉が脳裏に蘇った。
彼が死ぬ前に遺した、最期の言葉が。
私は手に持っていたナイフをその場に置く。
「……死ねない」
それは呪いだった。
勇者ルクスが魔王ヤミに遺した最大の呪い。
皮肉にも、その呪いだけが私にとって唯一の生きる意味となった。
一瞬だけ手元で何かが輝いた気がした。
ルクスの指輪だった。
指輪に嵌められた鉱石が光に反射したらしい。
「そう言えばこの指輪、ルクスの弟が作ったって言ってたっけ」
ルクスは私のせいで故郷に帰れなかった。
なら、せめて遺骨だけでも帰らせてあげるべきじゃないだろうか。
私は立ち上がると、ルクスの骨壺を持って山小屋を出た。
ルクスを故郷に送り届けることが、私に残された唯一の目標だった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




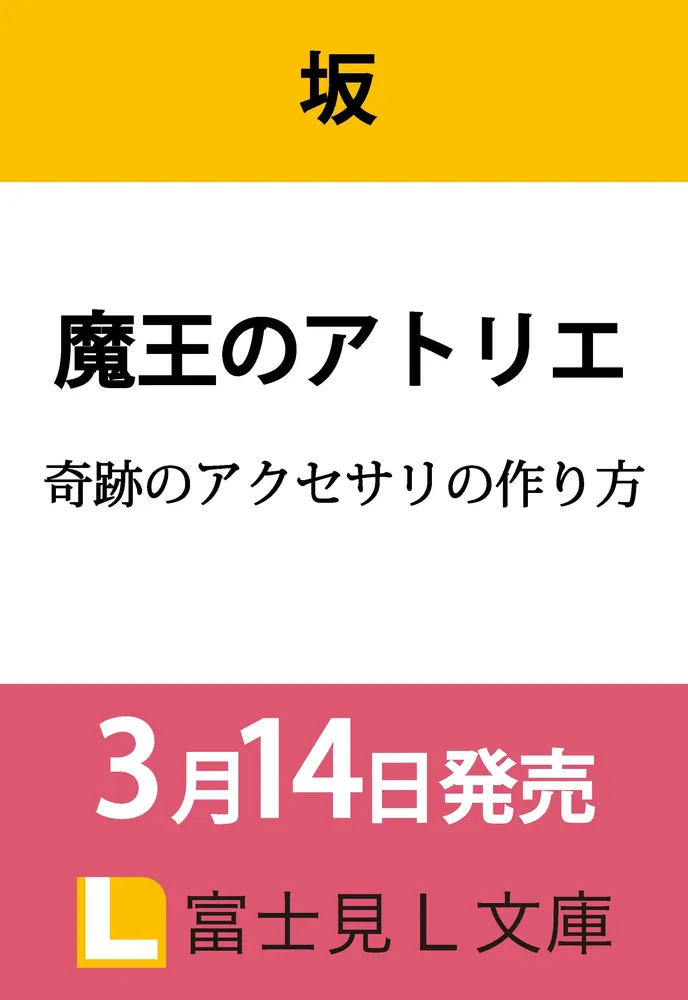
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます