第6節 勇者の故郷
ルクスの故郷であるトリトの街は、王都リディアより更に三日ほど南へ下った場所にあるらしい。
馬車を乗り継ぎ、山を越えて更に平原を進み。
いくつかの村を経由した後、ようやくたどり着くことが出来た。
「ここが、ルクスの生まれた街……」
王都ほど大都市ではないものの、市場が開かれ、活気があり、農地や牧場も存在している。
自然と調和した住みやすそうな街だと思った。
田舎と都会が一緒になったような独特な雰囲気が漂っている。
王都に行った時のように、魔法で人間の姿に外見を変えて街に入った。
街の外から来る人間は珍しくないのか、悪目立ちしている様子はない。
この街のどこかに、ルクスの実家というアクセサリ工房があるのだろう。
ルクスの話では、弟が職人として店を切り盛りしているとのことだった。
街自体が広く、見て回るだけでも骨が折れる。
一通り街を巡ったが、件の店を見つけることはできなかった。
足が疲れたので近くの広場で少し休むことにする。
商売をしていたり、誰かが歌っていたり、子供たちが遊んでいたり。
まるで戦争なんて無かったかのように、街は平穏そのものだった。
ルクスはこの街の光景を守ろうとして戦争に身を投じたのだろうか。
「ルクスの家はどこなんだろう……」
失敗した。
アクセサリ工房くらいすぐに見つかると思っていたけれど、この広大な街からたった一件の店を見つけるのはかなり難しいことなのだと今更実感する。
とは言え、戦争を終結に導いた勇者の実家だ。
街の人に聞けばすぐに見つかるのだろうが、あまり目立ちたくなくてどうしても躊躇してしまう。
「あの、大丈夫ですか?」
噴水の前で座っていると声をかけられた。
顔を上げると、青い瞳の青年が心配そうな顔で私の前に立っている。
金色の短髪が印象的な、優しそうな人だ。
私と同年代か、少し上かもしれない。
私が困惑していると彼は頬を掻いた。
「ごめんなさい。困っているように見えたので気になってしまって」
青年は困ったように笑みを浮かべる。
その笑顔に、一瞬ルクスの姿が重なった。
「ルクス……」
思わずその名前を口にしてしまう。
髪型が違っていたから気が付かなかったけれど、よく見たら彼はかなりルクスに似ていた。
すると青年は「えっ?」と驚いたように目を丸くした。
「もしかして、兄に何かご用ですか?」
「兄?」
彼は頷く。
「勇者ルクスは、僕の兄ですから」
◯
青年に案内されたのは、市場の奥にある小さなお店だった。
小さな看板が出ているがあまり目立っていない。
店の前は一度通っていたのだが、見落としてしまっていたらしい。
「『ルーステン』……」
看板に書かれた文字を読み上げる。
聞いたことない言葉だ。
どういう意味だろう。
「すいません。汚いですけど、気にしないでください」
青年がドアを開くとカランカランとカウベルが鳴り響いた。
中に入ると店内の色んなところに埃が目立った。
清掃が行き届いていないのだろう。
ただ、店に飾られている商品や棚は綺麗にされているから、最低限のメンテナンスはしているらしい。
指輪やブローチ、ブレスレットにネックレス。
色んなアクセサリが飾られており、それぞれ違う色の鉱石が装飾に用いられていた。
どれも精巧なデザインのものばかりで、かなり丁寧な仕事であることが素人目でも分かる。
思わず魅了された。
「これ、全部あなたが作ったの?」
「はい。ここの工房は僕が一人で切り盛りしているんで」
両親はいないのだろうか。
そう言えば、ルクスから弟以外の家族の話は聞いたことが無い。
いや、それ以前にそもそもルクスの素性を私はあまり知らないのだ。
私が知っているルクスの姿は、ほんの一部でしかない。
「カウンターの奥にリビングがあるんで、どうぞ入って下さい。今、お茶入れますね」
「気を使わなくてもいい。長居はしないから」
リビングのテーブルを挟み、青年と向かい合って座る。
「それで、兄に用というのは?」
どう切り出したものか分からず、しばらく考える。
青年は私が話すまで黙って待ってくれていた。
「私がここを訪ねたのは、あなたに会いに来たの」
「僕に?」
私はルクスの骨壺を机に置く。
彼は最初、それが何か分からないでいるようだった。
「これは……?」
「ルクスの遺骨」
私が言うと彼は一瞬目を見開き、静かに息を呑んだ。
「私は、勇者ルクスの遺骨をあなたに届けに来た」
しばらく沈黙があった。
どこか遠くで時計の秒針が聞こえてくる。
「兄は……死んだんですか」
私が首肯すると、彼はやがて諦めたように視線を落とした。
気落ちはしているが、狼狽している様子はない。
どこか納得しているようにも見えた。
まるで、兄の死を悟っていたかのように。
「ルクスは私の命を救ってくれた。それがきっかけで、一緒に暮らしていたの」
なるべく嘘にならないように、私は慎重に言葉を紡ぐ。
「……兄は最期、どうなりましたか」
「病死……だと思う。急に弱り始めて、動けなくなった」
「苦しみましたか」
「分からない……」
私は、死に際のルクスの顔を思い出す。
「でも、最期は笑ってた」
「そうですか……」
私の言葉を咀嚼するように、彼は小刻みに何度も首肯した。
「変だと思ったんです。戦争が終わったのに便りの一つも無かったから。てっきり王都で英雄として奉られているんだと思っていました」
泣きそうになるのを堪えるためか、青年は寂しそうな笑みを浮かべる。
その仕草が、記憶の中のルクスと重なった。
私の胸に空いた穴がジクジクと痛む。
苦しくなって、私は気付かれないように静かに深呼吸した。
「どうしてあなたは笑顔でいられるの。大切な家族が死んだのに」
「辛くないわけじゃないです。兄が戦争に出てから一度も会っていないので、実感がまだ湧いていないだけだと思います。それに、兄は昔から自分の信じたことを貫き通す人でしたから。兄が戦地に出た時、こうなることは覚悟していました」
青年はゆっくりと顔を上げ、まっすぐ私に目を向ける。
「長い戦いを終わらせて笑顔で死ねたなら、兄はきっと幸せだったと思うんです」
「幸せ……? ルクスが?」
「はい。兄はきっと、あなたとの生活に幸せを感じていたんじゃないでしょうか。それに、その指輪……」
彼は私の指に嵌められたルクスの指輪を指し示す。
「僕が兄さんに上げたアイオライトの指輪です」
「アイオライト?」
「その指輪に用いられてる鉱石の名前ですよ」
「ルクスが私にくれたの。あなたに作ってもらったって嬉しそうに話してた。これもあなたに返さないと……」
指輪を取ろうと右手の薬指に手をやる。
しかし何故か指輪を取ることができなかった。
嵌める時はあれほどスムーズに
サイズがきついわけでもないのに、どうしてだろうか。
私が指輪と格闘していると「大丈夫ですよ」と青年が言った。
「その指輪を兄さんがあなたに渡したことには、理由がある気がしますから」
「理由?」
「ヤミさん、アイオライトが持つ意味を知っていますか?」
「鉱石の意味は知らないけど、迷った時に導いてくれる指輪だってルクスは言ってた……」
「はい。アイオライトが持つ意味は『人生の道標』。迷った時に進むべき道を指し示してくれる鉱石なんです。兄さんはきっと自分がいなくなった後、この石があなたを導くことを願ったのかもしれません」
「ルクスが……願った?」
私は指輪を見つめる。指輪に嵌った青い鉱石は美しく輝いて見えた。
『魔王は死んだ。だから君にはもう苦しみのない、ヤミとしての幸せを見つけて欲しい』
ルクスの言葉が思い浮かぶ。
彼は私の幸せを願ってこの指輪を渡したのだろうか。
でもそれはもう叶わない願いだ。
ルクスが死んだ今、私が幸せになることはなくなった。
彼のいない世界で生きる私は、これから孤独の中で罪に苛まれ続ける。
私は、自分だけが生き残ったことに負い目を感じていた。
死ぬべきは魔王であり、生き残るのは勇者であるべきだった。
なのに結果は逆になっている。現実は上手く行かない。
私が自分の幸せを見つけることなんてできるわけがない。
指輪を見つめながら考えていると、ルクスの弟は深々と頭を下げた。
「兄と一緒に居てくれて、本当にありがとうございます」
「……やめて」
思わずそう言った。
手を握りしめると、爪がぐっと食い込む。
「誰かに感謝される筋合いはない」
私のせいで戦争は激化し多くの人が死んだ。
私と暮らしていたからルクスは病院にも行けず死んでしまった。
私がいたから、みんな不幸になった。
「私は誰かに幸せを願われるべきではない存在なの」
「それは、どういう……?」
青年の疑問を私は無視し、立ち上がる。
もう用事は済んだ。早く立ち去ろう。
「もう行かないと」
「せっかく来たんだから、もう少しゆっくりして行ってください」
「大丈夫、気にしないで」
足早に店の入口へ向かう。
ドアに手をかけて外に出ようとすると――
「あの、お名前だけでも教えてもらえませんか」
背後から、彼がそう声をかけてきた。
一瞬自分の名前を告げるべきか逡巡する。
魔王の名を知るものは魔族ですらほとんどいない。
勇者の弟とは言え、彼が魔王の名を知ることはまずないだろう。
どうせもう会うこともないのだ。
名前くらい教えても問題ない。
私は立ち止まり、少し考えた後「ヤミ」と答えた。
「私の名前はヤミ」
「僕はルクスの弟のレイです。ヤミさん、また良かったらいつでもここに来てください」
「……さようなら、レイ」
私は彼を振り切るように、店の外へ出た。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




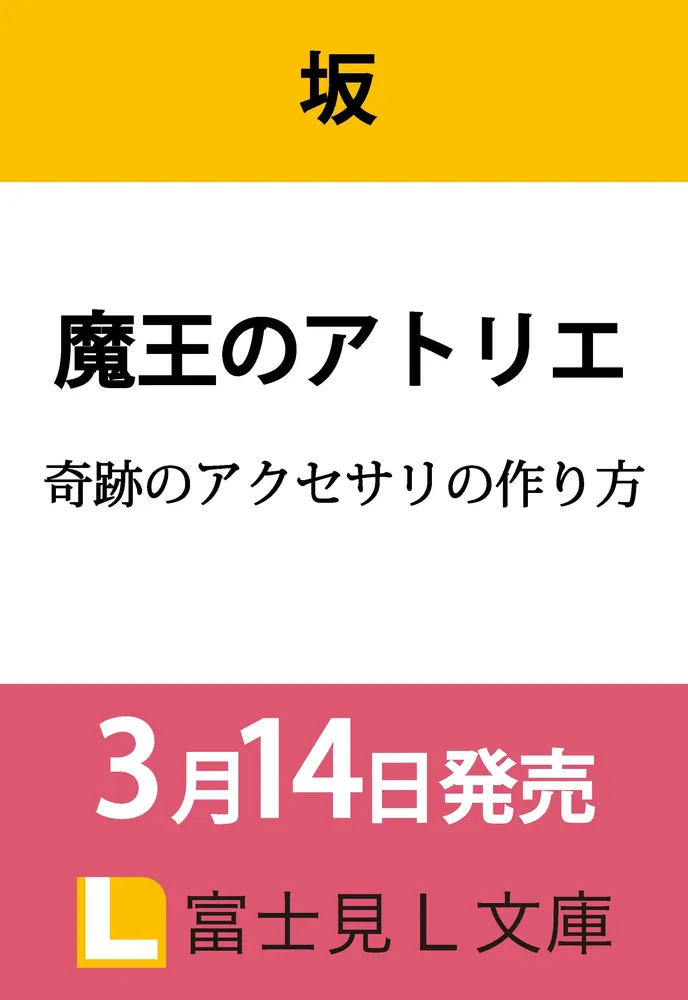
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます