つるぎのかなた/第4巻今冬発売!
渋谷瑞也/電撃文庫・電撃の新文芸
つるぎのこなた ――番外短編集
一本目:二束三文の挑戦者(チャレンジャー)

その挑戦を、黒瀬誠は後ろに立って腕を組んで見守っていた。
まるで、他人が遊ぶゲームの筐体を覗き込むように。
『なあ、悠』
『……ん?』
レベル上げをサボってきた奴の細い腕が、いきなりラスボスの肩を叩く。結末は誰にでもすぐ分かる。二本でゲームオーバーだ。無駄なんだからやめておけ、誰も得なんかしないだろ。そんな風に止める気が、しかしそのとき起きなかった。
『一回ちゃんと、オレと喧嘩しねえ?』
挑戦者が、身銭を切ってコインを入れる。
もうこのゲームに飽きることはないのだという雄弁な笑顔が少し、そのとき眩しかった。
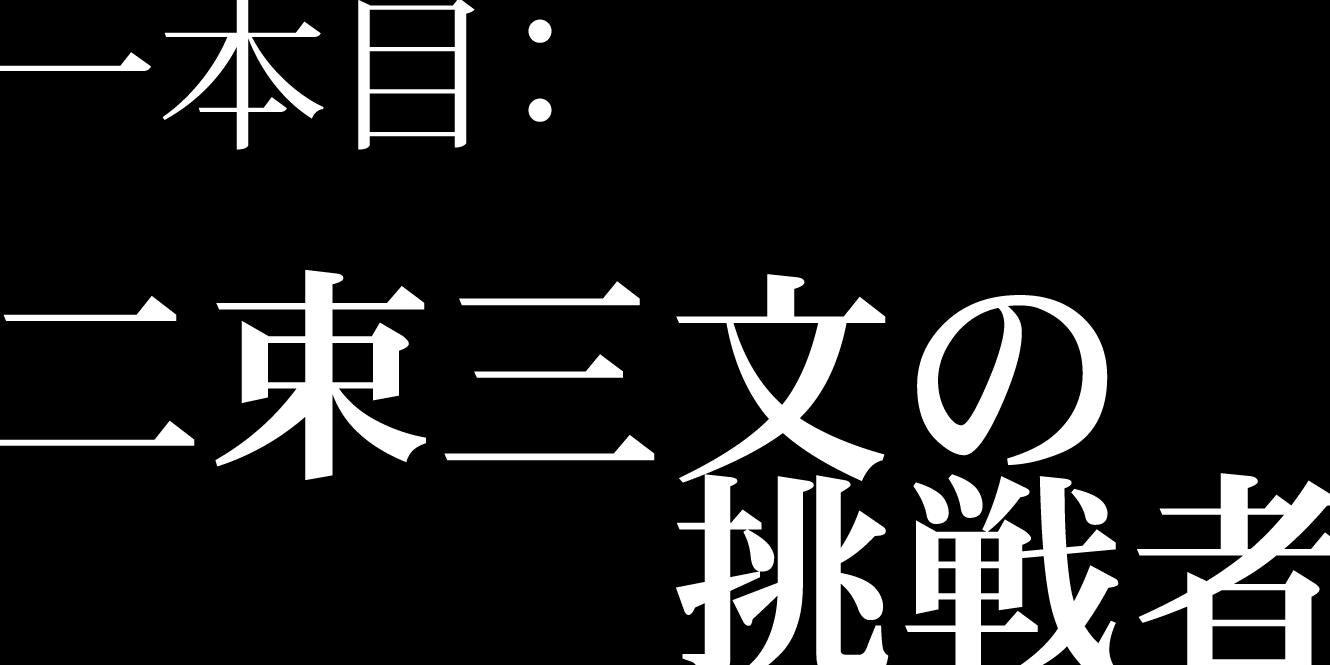
「わりーな、クロ。付き合わせちゃって」
「謝るくらいなら最初から頼むんじゃねぇよ。……あぁ、疲れた。毎回、最後の地稽古がいらねぇんだよなぁ」
五月、連休。武人錬成会帰りの電車の中で、黒瀬は城崎とドア横の両サイドに陣取って、背中を座席の壁にだらっと預けた。竹刀袋と防具袋は床に置く。剣道具は場所を取るので、連休夕方の混雑時に電車の中に入っていこうものなら、舌打ちのシャワーを浴びること間違いなし。だからドア脇だ。ガラスから差し込んでくる夕陽が、インドアの民には辛かった。
黒瀬は辟易しながら携帯を制服ズボンのポケットから取り出す。
時計を見ると、まだ十七時と意外に時間が浅かった。
「そうかなー。オレ、今日の地稽古だけは、あって良かったと思ったけどな」
そして、この反応はもう意外でもない。携帯から視線を上げると、城崎はカチューシャの上から両手で頭を押さえにかりと笑っている。
「クロは見てなかったの? 悠と乾の地稽古」
「……見てたよ。つーか全員見てただろ。気付いてねぇのはあいつらだけだ」
「ははっ、だよなー。……凄かったなあ。なんかもう、怪獣大戦争って感じだったよな」
いつだったか暗殺でしか殺せないと愚痴った乾快晴を、本当に倒せてしまいそうな奴がいる。そしてそれは、同じく城崎が部室で語った「六大道場からやってきた強い奴」だった。
他人がそんなに都合良い訳がないだろ、と奴は言う。
しかし絵空事は、都合良く本当になってくれた。
その段で、隣に立つ軽薄を形にしたような奴がいきなり自分に問い始めた。
このままがいいのか、それとも、このままでいいのかと。
「……で。お前はその怪獣と戦うんだろ、一般人」
意外なことに、奴は悩まず選んで自分を誘った。このままで終わりたくないからと。
「おー。文句言ってきてやんよ。簡単に踏み潰してんじゃねーぞって」
同じ一般人だったはずの奴が、楽しそうに笑う。
逃げずに怪獣と戦う人間は、たとえ最初に簡単に敗れ去るのだとしても、もう立派に役割を持った脇役だ。残された一般人はほんの少しだけ寂しくて、窓の外を見て笑った。
「お前だって、これからおれの休みを踏み潰しやがる予定なんだけどなぁ」
「それはごめんって言ってんじゃんよー。ほんと悪いって、この通り」
ぱん、と両手を合わせて城崎は苦笑する。相変わらず、「悪い」が軽い奴だと思う。
「……今回だけだからな」
だが、「やっぱりやめた」を言わないところだけは評価してやってもいい。
黒瀬は鼻を鳴らして笑い、眼鏡を外してブレザーのポケットに入れていたハンカチで拭く。ふと、電車が止まった。慣性に抗っていると上手く電車のアナウンスが聞き取れなかったため、眼鏡を付け直して目を細める。
藤宮高校最寄り駅の、ひとつ隣駅だった。
「なぁ、降りねぇか? 俊」
「……え? なんで? 防具置きに行くんじゃねーの?」
「今行くと、水上と深瀬に鉢合うかもしんねぇぞ。せっかくズラしたのにいいんだな?」
気を遣ってやる。振りをする。
なぜなら今日は連休で、まだ時間は早くて、明日は昼まで寝ることができるのだ。
「ゲーセン行こうぜ。久々に」
「おー、いいぜ!」
神様だって一仕事の後は休んだ。試合後に一般人が遊んだって、誰も文句はないだろう。
× × ×
薄暗い店内に入ると、レースゲームやらメダルゲームやら音ゲーやら、あらゆるゲーム音が混ざったカオスな音がうるさい。が、問題ない。剣道のほうがよっぽどうるさい。その上臭い。
誰が入っているのか分からない二階のカラオケ、点滅しているのに一向に替わらない蛍光灯、筐体に放置された飲みかけの空き缶、ヤニ臭い淀んだ空気。そして、どいつもこいつも目が死んでいる客。
黒瀬は深呼吸して、しみじみ言った。
「あぁ、実家だ。落ち着くんだよなぁ」
「荒廃しすぎだろクロんち……」
防具袋を改めて肩にかけて、目を細めて引いている城崎に相談を持ちかける。
「何からやる? おれは何でもいいぞ」
「じゃあ音ゲー以外で。あれやってるときクロ怖えんだもん……」
「ゲームであっても遊びじゃねぇからな、あれは。じゃあ、何か対戦できるやつにすっか」
城崎の目が妖しく光り出す。藤宮の剣道場では一度も見たことがない顔だった。
「じゃー何か賭けようぜ。晩飯前だしオレはアイスがいい!」
「ああ、まぁいいんじゃねぇの? しかしありがてぇな」
「ん? 何が?」
眼鏡を、右手中指でかちゃっと上げる。表情を消し、蛍光灯を照り返して真っ白に光った。
「そんなにおれに奢りてぇとはな。ご馳走様」
「……驕ってんじゃねーぞ、このクソメガネ。ご愁傷様」
城崎が、剣道場にいるときのようにカチューシャを外す。そのせいか毛が逆立っていた。
蛍光灯の点滅に合わせて、ばちりと火花が二人の間に弾ける。
やがて竹刀袋の柄側を持って突きつけて、城崎が舌を鳴らした。
「剣道部ルールな。二本先取だぞ」
「よし。残念だなぁ、二回しかゲームできなくて」
「……うるせー、見てろよ。じゃあ最初はクロからゲーム選べばいいじゃん。二回ともお前が負けたときかわいそうだし!」
混沌とした店内の音の中に、はっきりと血管がぶち切れる音が二つ聞こえた。
「……クイズゲーからやんぞ」
「っしゃこいや! オレだって藤宮入ったんだからな! 偏差値六十八を舐めんなよ!」
「……いるんだよなぁ、過去の栄光にすがるやつ。お前、前回赤点何個あったよ?」
「…………わっ、忘れちまったよ! んなの覚えてねー!」
とりあえず、一勝は間違いなさそうだった。
× × ×
そしてやっぱり、戦況は一方的だった。
横並びの筐体二つにそれぞれ座って、早押しクイズに興じる。
『鼻血』
ぴぽん!
「ちょっと! 早すぎだろクロ!? 読んでねーだろそれ!」
「読む必要はねぇ。二文字で終わりだ」
黒板に綴られた文字を回答ボタンですぐさま止め、画面上に現れたキーボードを高速でタッチする。身体がキーの場所を覚えていた。
『キーゼルバッハ部位』
正解、の赤丸と共にマッチポイント表示が自キャラの下に出てくる。城崎は零点だった。
「もうこれクイズじゃねーじゃん!? 暗記ゲーだろただの!」
「奇遇だな。勉強も同じらしいぞ」
「く、く……。うるせぇ、こっからオレの逆転劇が!」
『なぜ山』
ぴぽん!
「おぉおおおおおい!?」
隣で聞こえる悲鳴が快感だった。
画面を見ず、城崎の顔を見ながらにやにやと答えを入力する。
『ジョージ・マロリー』
正解! YOU WIN! の表示が画面に躍る。両手を広げてかぶりを振った。
「ごめんな? 頭良すぎて。あーあ、何ゲンダッツのアイスにすっかなぁ」
煽ると、ゆらりと城崎が立ち上がる。その動きにどこか見覚えがある。
やがて機械的に直角に動き出した城崎の指が、とあるコーナーを指した。
「次はUFOキャッチャーで勝負だ」
「……上等だ。てめーの防具棚にキッティちゃん飾ってやんよ」
× × ×
「クソがっ、アーム緩すぎなんだよなぁ! 二宮の頭か? お前は!」
完全に厄介クレーマーと化した黒瀬が、数多の百円を呑まれた憤怒で台を叩く。店員に睨まれてしまったのでそれ以上は自重するが、釣果ゼロで憤懣やる方なかった。
舌打ちと共に、隣の台に立っているはずの城崎の方を見る。
獲った人形の山で姿が見えなかった。
「お前それどうなってんだよ……。引くんだが……」
「女子受けのテクなら誰にも負けねー。……あっ、店員さーん。これ動かしてもらえますぅ?」
「おい、てめぇずりぃぞ! プライドねぇのか!?」
「バーカ、真っ向勝負なんてアホのやることなんだよ! あれっ、もしかして黒瀬さんはそんなのも分からない感じ? いやー、さっすが頭いい奴は違うなあ!」
くの字に曲がった右のアームが、キッティちゃんをずらして穴へと華麗に落とす。城崎はにやにやしながら屈んで取り出し口からそれを取ると、両の手のひらに乗せて黒瀬に差し出した。
「はーいクロちゃん、プレゼント♪ 遠慮すんなよ。防具棚に飾ってもいーんだぜー?」
黒瀬が剣道部の握力を最大限に発揮し、左手で人形の頭を握りつぶす。
そして城崎に突きつけて笑った。
「これが、五分後のお前の姿だ」
しかし握力が全然ないので、途中でふにゃんと元の姿に戻ってしまった。
「何も変わってねーんすけど……。え、何? 降伏っすか?」
「うるせぇ、これは潰しすぎて逆に戻って見えてんだよ」
「意味わかんねえ……。しっかし認めねえ奴だなー、お前も!」
デコがぶつかり合うくらいの距離で睨み合った後、城崎が左の親指でとあるコーナーを指す。
練習帰り、何度も寄ってきた戦場を。
「殴り合って決めようぜ。手っ取り早えし」
「ああ。やっぱ暴力ってのが最高のソリューションなんだよなぁ」
いそいそと竹刀袋と防具袋を持ち上げ、並んで歩いて行く。が、試合帰りの身体にこのセットはやはり重い。二人の肩がどんどん下がっていき、しまいに腹の虫が共鳴した。
「……オレたち、何やってんのかなあ」
「虚無だろ」
「それな」
だが、戦いをやめるという選択肢だけはなかった。
× × ×
格闘ゲーム。
それは剣道と同じく初心者殺し満載のゲームで、かけた時間と吸い込まれた金の分しか絶対に強くならないシビアなジャンルだ。黒瀬は城崎を引き連れ、いつもの筐体へと向かった。
ちょうど、二つ対面が空いている。
「しかし、相変わらず誰もいねぇな。このゲーム」
「地味だし流行ってねーもんなー。でもいいじゃん、安いんだし!」
「だな」
大して熱中している訳でもないこのゲームに入り浸っている理由は一つ。圧倒的な安さだ。
一クレジット、五十円。
常に金欠の高校生にとってこの値段は破格だった。しかも、勝ち続ければ何時間でも五十円で居座ることができる。練習帰り、よく二人して不毛な時間を溶かしたものだった。
それで得た教訓はひとつだけ。現実世界の強さとゲームの強さは反比例する。以上。
二人して防具袋を下ろし、深呼吸してパイプ椅子に座る。筐体の横から互いに顔を出して睨み合った。
「一回きりだ。コンティニューは聞かねぇからな」
「おーいいぜ。男に二言はねえ」
先に五十円を入れてスタート画面で待っていると、間もなく画面にカットインが入る。
『
すぐにキャラ選択の画面に切り替わる。
さてどれにするか、と青い正方形のカーソルを動かさずに腕を組んで考えていると、城崎の赤いカーソルが一直線にとあるキャラを目指した。
ぴろん、と選択音が響いて美青年剣士のキャラが決めポーズを取る。思わず舌打ちした。
「相変わらずためらうことなく強キャラばっか使うよな。流石おれたちの城崎俊介さんだ……」
「うっせーなあ! 勝てばジャスティス!」
城崎が選んだキャラは、壊れ性能と呼ばれていて使うとまず良い顔をされない。間合いが広い上に攻撃力も高く、ボタンを連打するだけで素人でも簡単に勝ててしまうからだ。
息を漏らし、黒瀬は目を瞑って数秒考える。
そして頷いてから、そのキャラを選んだ。
「……い? そいつでいいの?」
「あぁ。さぁ、やろうぜ」
選んだキャラは、一番弱いと言われている鈍重な筋肉の塊キャラだった。見た目ほど防御力も高くないし、動きも遅い。ただ難しいコマンド入力を要する特殊投げが強く、それが当たったらデカいというだけのキャラだ。
誰も選ばない。
だからこそ、選ぶのだ。
ワイングラスを持つように左手の人差し指と中指をスティックに差し込み、黒瀬は笑う。
『ROUND1、FIGHT!』
始まった瞬間、向こうからがちゃがちゃとボタンを押したりスティックを動かす音が聞こえてくる。それを全て無視して、静かにボタンを運ぶ。
おそらく、一分もなかっただろう。
美剣士は巨体のキャラにがっしりと掴んで空から投げ落とされ、無様に地面に埋まっていた。
「くー!」
「……あと一本な」
二本目が始まる。奴は焦ったように雷の飛び道具や遠間からの斬撃、それからゲージが溜まったことによる必殺の一閃を繰り出してくる。それらを冷静に読んで、たまに外されて、しかし頭を使うことをやめずに近間に寄ってぶん投げる。唇が、思わずつり上がった。
『YOU WIN!』
試合が終わって、画面が暗転する。筐体に不意に映り込んだ自分の目は、輝いていた。
勝ったので、またキャラ選択になる。向こう側の筐体からカウントが減っていく音がするが、とうとうコンティニューはしなかった。
がたっ、と音がする。
防具袋と竹刀袋を持ってこちらにやって来た城崎は、苦々しい顔でため息をついていた。
「だーめだ。やっぱクロさんには勝てねーな。めちゃくちゃ強えわホント……」
「……分かってて何でやるかね、お前は」
「うっせーなー。だって引っ込みつかないじゃんかよー」
がくっ、と肩を落として、城崎は一緒に地べたに荷物を置いていく。
その表情は、負けたくせにどこかすっきりとしている笑顔だった。
「ダッツがいい? やっぱ。オレさっきのUFOで金ギリギリなんだけど……」
「ばかやろ、そこまで鬼じゃねぇよ。自販機のやつでいいって」
はいよ、と自販機コーナーに歩いて行く城崎に背を向けて、ひとり用ゲームが始まった筐体に笑いかける。何も考えなくとも、両指は勝手に動いた。
最初から分かっていた。どんなゲームが選ばれようとも、結局自分が負けることはない。つまらないなといつもの自分なら言うだろうが、しかし今回はそうではなかった。
楽しかった。こんなに人気のないゲームでも。
結局何をやるのかではなく、誰とやるのかに落ち着くのかもしれない。そんならしくないことを考えていると、視界の橋からプラスチックの棒に刺さったクッキー&クリームが現れた。
まずぱくっと食べてから、その棒を受け取る。隣の筐体の椅子に城崎が座った。
「ひょく、わぁったな。おれが、これ好きだっての」
「いつも食ってんじゃん。言わなくたって分かるよー。……なあ、クロってさー。なんでいっつもあーいう弱くて難しいキャラばっか使うの?」
最後の金で買ってきたであろうコーラを呷りながら、城崎が人差し指で頬を掻く。情けなさそうに笑った。
「せめて、ゲームくらいさあ。強くてカッコいいキャラ使いたくね?」
「……でもみんなが使うしな。それで勝っても、おれの力じゃねぇみたいで嫌なんだ」
ぱくりとアイスを食べていく。冷たいものは得意だった。
一気に平らげて、さっきまでアイスが刺さっていたプラスチックの部分を噛む。
「強え奴が勝って、何が面白えんだ? 弱い奴がどうやって勝つか、考えてひっくり返すから面白えんじゃねぇか。……おれはなんか、負けそうな奴に肩入れしたくなんだよ」
顔を逸らす。放置して敵キャラに倒されそうになっている自分のキャラを操り、鮮やかに逆転していった。
ゲームに集中して、ついぽつりと言葉が漏れる。
「せめてゲームくらい、弱い奴が勝ったっていいだろ」
色んなことを、よく諦める。無理なものは無理だとすぐ切って捨てる。
現実は厳しい。そういう風に行動できる自分のことだって嫌いじゃない。
だが、どこかで寂しい気持ちも持ち合わせているのも事実だった。
「……クロは、熱いのか冷たいのかよく分かんねーなあ」
「あぁ? めっちゃ冷えてるわ。つーかエアコン効き過ぎなんだよなここ……」
「いや、そーいう意味じゃなくて……って、お?」
だべっていると、画面が暗転する。ひとりプレイが中断された。
『
珍しいこともあるものだ、と思う。歓待するように、さっきと同じ投げキャラを選んだ。
すると、相手も先程の城崎と同じキャラを選ぶ。
腕が鳴った。
「やってやんよ」
「んー? 誰だろなー? オレ、ちょっと見てくるわ」
城崎が隣の席を立つ。その間に勝負は始まった。
そして二分後に奴が戻ってくるころには、勝負は終わっていた。
「な、なあ……。向こうの子、女の子だったんだけど……」
「……別に性別関係ねぇだろ。こんだけ強けりゃ」
完敗だった。
二本通して相手の体力ゲージは一割も減っていない。
強い人が強いキャラを使ったらこうなります、といったお手本のような立ち回りだった。
「なにもんだ……? こんな奴いたら噂になるレベルだぞ」
「顔分かんなかったんだよなー。黒い帽子深く被ってて。でもなんかインドアって感じの色白の子だったぞ? ちょっと可愛かった。あと服も全部真っ黒だった」
「誰が容姿の話を聞いたよ……」
うんざりしながら、財布からもう一枚五十円を出す。
挑戦する、のボタンを押した。
「おっ、男だねー」
「うるせぇ。舐められっぱなしで終われるか」
相手が選ぶキャラは同じ。
そして、こっちが選ぶキャラもまた同じだった。
「いっ? また? クロ、他の使えば全然つえーんだから――」
「黙ってろ。これでいい」
集中する。百パーセントの力を出せるように。
相性最悪でも、性能が弱くても、腕さえあればひっくり返せる。それを見せつけたかった。
「……くそ」
だが、非情な現実は変わらない。相変わらず近づけないままだった。
ムキになって何度も五十円を入れて挑戦する。しかし、結果は何度やっても変わらなかった。
「ちっ。無理、か」
十連戦はしていたと思う。最後、体力は三割削れた。何かコツを掴んだような気がする。
「……終わり、だな」
だが、財布の方は底を突いてしまった。残りは定期外のため、一駅分残した運賃のみ。
これを使い果たせば、防具をかついで夜の町を歩くことになる。
それは愚か、だった。
「帰んぞ、俊」
「やーだ、よっと」
立ち上がろうとする自分の両肩を城崎が押さえてきて、立ち上がれない。
そのまま奴は、コイン投入口に五十円を入れてしまった。「やれよ、クロ。もっかいだ!」
「……お前、金ねぇって」
「おう、最後の電車賃逝ったー。まあいいのいいの、若えしオレは歩くから!」
にかりと歯を見せて笑い、城崎は肩から手を離して背後に立った。
「これで二人分のパワーだ。ぜってー勝てるぞー」
「……馬鹿だな。んなわけねぇだろ。待ってろ、今返す――」
「んなもんいらねー。勝ってチャラにしろよ。……こんままで、終わっていいのか?」
高みの見物、というように奴は腕を組む。唇を尖らせていた。
「オレならぜってー、ヤダ。むかつくもん。……行け、クロ! ぶっ飛ばしてやれ!」
檄を飛ばす仲間を見て、眼鏡を外して思わず笑う。
本当にいつも通りすぎて。
「そこまで言うんならお前がやれよ。男なら自分の力でじゃねぇの?」
「い……いや! そうだけど! 確かにそうなんだけどさあ!」
いつもいつも、そこだけは相容れないなと思ってきた。
他力本願なんて理解ができない。
全部自分の力でやり遂げられたら、それに越したことはないと。
「……でも、オレ勝ちてえもん。使えるもんは、使ったほうが良くね?」
だが、どうしようもない奴の苦笑を見ながら、今は少しだけ思う。
こういうやり方を通す奴も、隣にひとりくらいなら居てもいい。
「救えねぇ奴だな、お前も」
ゲームの画面に向き合い、挑戦するのボタンを押す。画面が、一瞬暗転する。
「あと二クレ付き合いな。おれ、最近ダイエットしてんだよ」
「ははっ。どこに脂肪があんだよクロに!」
そこには、夜道を死体となって歩くであろう、二束三文の馬鹿たちの笑顔が映っていた。
× × ×
一日経って、夜。
黒瀬がリビングのソファでひとり携帯ゲーム機で遊んでいると、丁度風呂を上がった六つ下の弟が水を飲みながら話しかけてきた。
「マコ兄、いっつもそのゲームやってるねー。飽きないの?」
「まぁ、何年も惰性でやってんな。正直、面白いとか面白くねぇとかもうよく分かんね」
膝の上に置いていた携帯の電源ボタンをタッチする。
ロック画面には、五月の剣道部の予定表が出てきている。
明日は、部内戦だった。
「……でも最近、新キャラが出てきてよ」
「えっ!? 何年もやってるのに!? そんなことある!?」
「おれもねぇと思ってたよ。でも何年も遊び続けたら、出るもんは出てくるらしい」
苦笑しながら、セーブして電源を落とす。きょとんとしながら弟は聞いてきた。
「そのキャラ、強いの?」
「強え。アホみたいに。……だからやっぱり、おれはあっちの味方じゃねぇ」
もう一度携帯を見て、時刻を確認する。こくりと頷き立ち上がった。
「やっぱり、勝って欲しいのは弱ぇ方だよな。……おやすみ」
「えっ、もう寝るの?」
「ああ。明日はすげぇ早いんだ」
寝室に向かう背に、声がかかる。
そんなに楽しそうな顔して、一体明日は何しにいくの? と。
その問いに、小さく笑うだけで答えなかった。
自室の電気を消し、眼鏡を外す前に目覚ましのアラームを確認した。
ドがつく早起き。だから、金儲けが大好きな自分は笑うのだ。
「早起きは、三文の得だよな」
今の貨幣価値で大体六十円。安いが、これだけあれば十分だ。
「一クレ分、返してやんよ。
さあ、明日は自分が後ろで腕を組んで見ていよう。
新キャラが出たくらいで、この黒瀬誠が熱くなることはない。だがまあ万が一、もしも間違いが起こるとしたら、それはきっとこのクソゲーを毎日続けたご褒美に、新武器が貰えるくらいのことがあったらだろう。
「くく。……寝言は、寝て言え」
眼鏡を外し、布団を被る。
二束三文の挑戦者たちが、笑顔で夢を見に行った。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます