第3話-1 すみれ合唱サークル
東京都東部…荒川と隅田川に挟まれた下町の風情が残る地域に、
千両ふれあい館は四十年ほど前に建設されて以来、地元の公民館として、様々な活動や催し事などで利用されて来た。毎年、十一月にはその敷地と隣接する公園を利用し、「千両ふれあいフェスタ」というお祭りが開かれる。
地区の有志が中心となり、二十年ほど前から始まった千両ふれあいフェスタ…通称、ふれフェスは、親子で遊べる体験コーナーやバザー、地元商店による出店、スタンプラリーなど、多様な催しが目白押しの人気イベントだ。
当日は駐車場にステージが設けられ、カラオケ大会も開かれる。そして、その前座として「すみれ合唱サークル」が合唱を披露する。
すみれ合唱サークルは地元で音楽教室を開いている
老若男女、歌が好きな地域住人が二十名ほど参加しており、千両ふれあい館の会議室を借りて、毎週木曜日の夜に練習を行っている。
練習時間は七時から九時までと決まっているが、メンバーの多くは社会人なので、なかなか開始時間に全員は揃わない。練習が始まるのは大抵、七時半過ぎだ。
すみれ合唱サークルに一昨年から参加している
ショートボブの黒髪を揺らし、自転車置き場に自転車を停める。走って正面出入り口へ向かおうとすると、背後から「文ちゃん」と呼ばれた。
振り返れば、同じ合唱サークルのメンバーである
「久恵ちゃん、今日、遅くない?」
「保護者対応に手間取っちゃって」
地元の保育園で保育士として働く久恵の勤務は六時までだが、時間通りに終わった試しがないといつも嘆いている。今日も色々あったのだと話しかけた久恵は、「それより!」と言って真面目な顔付きになった。
「聞いた?」
「何を?」
「
久恵が「大平さん」と言うのは、同じすみれ合唱サークルで活動しているメンバーだと分かったが、話というのに心当たりはない。文は首を振り、「どうしたの?」と聞く。
「大変なことになってるらしい」
「大変なことって?」
大変なことってなんだろう。想像がつかなくて繰り返した文に、久恵は声を潜めて「痴漢」と口にする。
「え?」
「大平さんが痴漢してるって話がSNSに出てて、保護者の間で騒ぎになって、学校休んでるんだって。私の友達、大平さんと同じ小学校で先生してるじゃない。その子からの情報だから、確かだよ」
「嘘でしょ…」
大平は隣の区の小学校で教師をしている。高校までサッカーに明け暮れ、体育大学で学んで教師になったという大平は、合唱だけでなく、他の地域活動にも積極的に参加していると聞いていた。
イケメン…というほどではないけれど、爽やかな青年というイメージだっただけに、痴漢というのは意外で衝撃が大きい。
先週の練習に参加していた大平は、いつも通り、快活でにこやかだったのに。
「えー…そんな感じじゃなかったよね。なんかショックー」
「だよね。でもさ。これでとうとう
「あ、そうか」
これまで、すみれ合唱サークルには男性メンバーが三名いた。その一人だった
その福本に続いて、大平もいなくなったとなると、残る男性は黒田一人になってしまうのだ。
「合唱だけ来る…とかないかな」
「ないでしょ。さすがに」
痴漢というのはかなり外聞が悪い。自転車を停めた久恵と共にふれあい館の正面出入り口へ回りながら、文は「どうなるんだろう」と呟いた。
すみれ合唱サークルにとって、年に一度の大舞台である千両ふれあいフェスタは来週末に迫っている。ふれフェスの為に、来週はいつもより練習回数を増やしているというのに。
困ったね…と久恵が返した時、「こんばんは」と挨拶する声が聞こえた。二人で振り返った先には、男性メンバーの最後の一人である黒田が立っていた。
「こんばんは。黒田さん。聞きました?」
久恵は黒田を見ると、挨拶もそこそこに大平の件を確認した。黒田は神妙に頷き、「大変みたいですね」と続ける。
「ふれフェス、来週だし、黒田さん一人になっちゃって、どうするんだろうって話してたんです」
千両ふれあいフェスタでは、「紅葉」を男女混声で歌う練習を重ねてきた。男性三名に対し、女性が十五名という偏った比率だったものの、合唱経験者である黒田の歌声は存在感のあるものだったので、何とかなりそうだったのだが。
さすがに一人では難しいのではないか。心配そうな久恵と文に、黒田は笑みを浮かべて「大丈夫ですよ」と返す。
「僕一人でも」
「そうですか?」
どんなに黒田の歌がうまくても、無理がある気がする。文は内心でそう思いつつも、口には出さなかった。合唱サークルでは黒田は先輩だし、年上でもある。それに決めるのは指導者であるすみれ先生だ。
三人で会議室へ移動すると、すみれ先生が古参メンバーである年長の女性数名と深刻な表情で話し込んでいた。すみれ先生は品のいい美人で、いつも可愛らしいワンピースを着ている。年齢は不詳だが、六十歳は過ぎているという話だ。
部屋に入って来た文たち三人を見ると、すみれ先生は「皆さん」と呼びかけ、練習前に話があると切り出した。
「千両ふれあいフェスタが来週に迫っていますが、大平さんからお仕事の都合で、しばらく休みたいという連絡がありました。なので、曲の構成を変えようと…」
思います、とすみれ先生が最後まで話す前に、黒田が声を上げる。黒田は文たちに言ったのと同じく「大丈夫です」とすみれ先生にも言い切った。
「僕一人でもいけますよ。今になって変えるのも、皆さんが戸惑われるでしょう」
「ですが…」
黒田は自信満々だったが、すみれ先生は頷かなかった。長い睫が印象的な瞳に憂いの色を浮かべ、しばし沈黙した後、「やはり」と懸念を示す。
「お一人では心許ないと思いますので…そうだ。皆さん。来週だけでもいいので、どなたか参加出来る男性の方をご存じありませんか?お声がけ頂けたら嬉しいのですが」
すみれ先生の提案に、文と久恵だけでなく、他のメンバーたちも少し困ったように顔を見合わせた。歌が歌える男性の知り合いなんて、すぐに思いつくはずもない。
けれど、ふれフェスの舞台を成功させたいという思いは全員にある。来週は臨時の練習を予定しているので、それまでに探してみようという話にまとまった。一人も見つからなかったら、混声合唱は諦めて構成を変えます…とすみれ先生は話し、練習を開始した。
練習後、帰路に就いた文は自転車を漕ぎながら、「歌が歌える男性」について考えていた。歌が歌える…かどうかは微妙だが、「男性」なら身近に一人いる。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




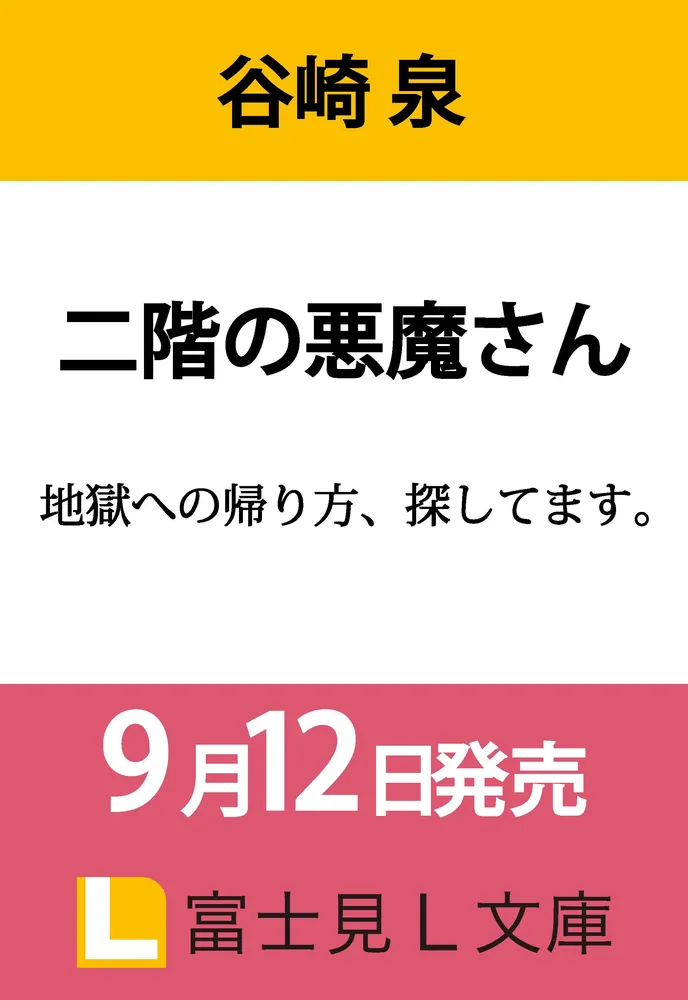
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます