二杯目 幸せをもたらす夏いちごのガスパチョ⑤
夏の盛りを超えたものの、まだ暑さは厳しい。
シーナが店をはじめて半月が経つというのに、いまだに客足はまばらだった。
店の様子が気になるようで、ハルタはたびたび顔をのぞかせる。
「隣町の知り合いから、夏いちごを分けてもらったよ。店で使うといい」
今朝は、夏いちごがたっぷり盛られた籠を抱えていた。
「夏いちごですか。珍しいですね」
シーナは鮮やかな赤い果実を、ひと粒つまみあげる。
「隣町は高地になっていて、ここよりずいぶんと涼しいんだ。だから、夏いちごの栽培に向いているのさ」
いちごを食したことがあまりないシーナは、味を想像して期待を高めた。
「こんなにたくさん……ありがたく使わせていただきます」
「料理が余ったら、いつものように夕食に持っておいで。楽しみにしているよ」
ハルタはそう言い残して、店を出ていった。
夏いちごの清々しい香りに、シーナの心は躍る。
今日はどんなスープがいいかしら?
夏いちごのスープにしてみようかしら?
夏いちごは、オレンジと合わせてもいいし、牛乳で煮込んでもおいしそう。
心ときめく食材を前にすると、色々なスープが浮かんでくるから不思議である。
とびきりおいしい、私のスープができますように。
アルバの助言を受け、シーナは〝私のスープ〟を作りはじめた。
それは、シーナなりに工夫を凝らしたスープのことである。
シーナのスープは麦のスープだけではなく、その日手に入った野菜や果物でお客様を思いながら丁寧に作る、日替わりスープとなった。
日替わりにすることで、町の人にも飽きずに通ってもらえるかもしれない。
お客様に喜んでもらえることが、シーナにとって何より嬉しいことだ。
人々の笑顔を思い描きながら、そっと夏いちごを手に取った。
可愛らしいいちごを、傷つけないように……。
そこで、店の扉が控えめにこんこんと叩かれる。
夏いちごのへたを取る手を止め、シーナは顔をあげた。
「お店、やっていますか?」
日よけの軽やかなボンネットを被り、麻布に美しい刺繍が施されたドレスを纏う、若い娘があらわれる。
肩からつるりと滑り落ちるのは、手入れの行き届いた栗色の長い髪。
ただ、顔色があまり良くないのが、気になった。
「はい。どうぞお入りください」
「エルザさんの、遠縁の娘さんだって聞いたけど……」
若い娘は用心深くシーナの様子を窺っている。
どうやらシーナは、エルザの親戚ということになっているようだ。
おそらく、エルザたちが親切心で、町の人たちにそう説明しているのだろう。
「シーナと言います。はじめまして」
「はじめまして。私はサラ。ロセリウス家の長女よ」
ロセリウス家といえば、この町の大地主である。
たびたびハルタたちの会話にものぼるため、町に来て日の浅いシーナでも耳にしたことがある名前だった。
「シーナさんにお願いがあるの。私がここに来たことは、家族には秘密にして」
「はい。分かりました」
「ありがとう」
サラは一番奥の席まで行くと、扉を背にして腰をおろした。
「お料理のことですが……」
シーナはその背中に向かって、控えめに声をかける。
「ああ、注文ね。いつもの麦のスープとパンを。ジャムは適当に」
「実は、本日は麦のスープのご用意がなく、日替わりスープのみとなっています」
「なんでもいいわ。あまり食欲がないから、少なめでお願いします」
サラは振り向きもせずにそう言った。
それは、すべてを拒絶するような、冷ややかな声だった。
何か事情がありそうだが、そっとしておくほうがいいだろう。
そう考えたシーナは速やかに調理場へ戻り、スープの準備に取り掛かることにした。
顔色が悪く、食欲がない……。
「連日の暑さで、体が疲れているのかも」
そこでシーナは、サラの体調に合わせて、スープを作ることにした。
まずは、すりつぶした夏いちごに白チーズを加えて、よくかき混ぜる。エルザが手作りした滑らかでさっぱりとした白チーズは、夏いちごにも合うはずだ。
さらに、レモン汁とはちみつで味を整えれば、完成まであと一歩。
「氷が溶けてないといいけれど……」
床板の一部を剥がし、土を掘って麦わらをしきつめた貯蔵庫から、壺を取り出した。
地下水が流れるこの周辺は、夏でも地中はひんやりと冷たい。この冷たい地中を利用して、町の人々は地下に氷室を作り、家の床下に貯蔵庫を設けた。
壺の中には、布に幾重にもくるまれた氷がおさまっている。
数日前より氷はいくらか小さくなっていたが、まだ形をとどめていた。
「念の為、準備しておいて良かった」
町の氷室を教えてくれた、アルバのおかげだわ……。
冬に切り出した大きな氷を貯蔵する町の氷室から、わけてもらった氷だった。
「これで、スープを冷たくできる」
シーナは氷水を張った桶に、静かにスープの器を沈める。
スープを冷やすことで、夏日でも口にしやすいはずだ。
仕上げには香草の葉を飾り、豊かな香りを足す。
「あとは、盛り付けるだけ」
大きめの木皿を取り出し、スープの器とパンを載せて、今朝摘んできたばかりのラベンダーの花を添えた。
少しでもサラさんの表情が、明るくなればいい……。
そう願って、シーナは料理を彼女の元へ運んだ。
「お待たせいたしました。夏いちごの冷たいスープです」
「…………」
サラは何も言わず食事をはじめる。ときおり、涙を拭っているようにも見えた。
しばらくすると、嗚咽のようなものが聞こえはじめる。
サラの背中は、小さく上下するように震えていた。
「どうされました? 大丈夫ですか?」
これ以上黙っていられずに、シーナは声をかけてしまう。
「ご、ごめんなさい。ずっと食欲がなかったのに……とてもおいしくて」
とうとうサラは大きな声をあげて泣き出した。
シーナは優しくサラの肩を撫でてやる。
「落ち着いたら、話を聞かせてくれませんか」
「ええ……」
サラは真っ赤な目でシーナを見上げてきた。
シーナはそっとサラの隣に腰を下ろす。
「夏いちごの甘酸っぱいスープなんて、はじめて口にしたわ。喉越しが良くて、するすると入っていく。昨日まで、何も食べられなかったのが嘘みたいよ。ラベンダーの花も、良い香りで可愛らしくて、とても心が和んだの。本当にありがとう」
瞳に涙をためながらも、サラは微笑んでみせた。
「さっきは、嫌な態度をとってごめんなさい。なのに、シーナさんはこんなにおいしい料理を出してくれて。私、自分がとても恥ずかしい。店主が代わってから繁盛していないと聞いて、一人で泣くのにちょうどいいと思ったの。こんなに素敵なお店に対して、失礼だったわ」
サラは、自分の気持ちに正直な人なのだろう。
シーナは、苦しげな表情を見せるサラのことを、どうしても悪くは思えなかった。
「いいえ。何かお辛いことがあったんですね」
「実は私、もうすぐ結婚するの。親が決めた相手だけど幼い頃から知っている人で、私は彼とだったら幸せになれると信じて結婚を決めたわ。だけど、今は不安で仕方ない。結婚なんてやめてしまいたいくらいよ。だけど、そんなの無理。親に顔向けできないし、町の人たちにもどう思われるか……」
サラは再び感情が昂ったようで、慌ててハンカチを目元に当てる。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




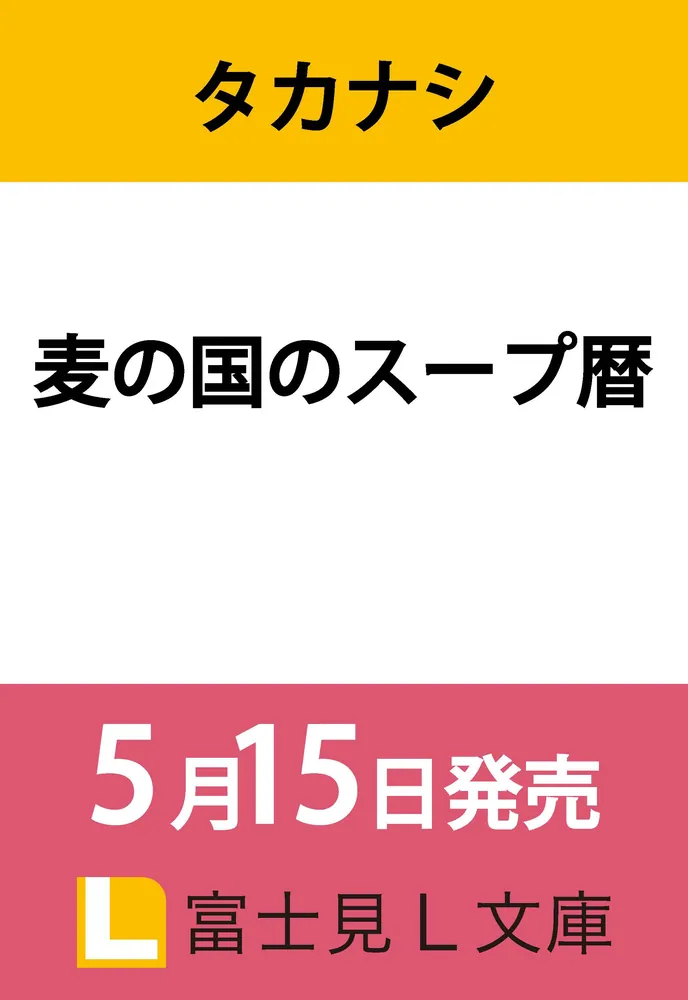
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます