二杯目 幸せをもたらす夏いちごのガスパチョ④
「確かに、病人の世話をするのは若くて元気な私の役目だわ」
エルザの企みに気付くことなく、シーナは勝手に納得してアルバの家へ向かった。
「こんばんは。シーナです」
明かりは灯っているが、アルバからの返事はない。
弱っていて、起きられないのかもしれないわ。
余計に心配になったシーナは、扉の取っ手に手をかける。幸いにも、鍵はかかっていないようだ。
シーナはそっと扉を開け、家の中へ向かって声をかけた。
「食べ物を持ってきました」
やはり応答がないため、仕方なしに籠を土間へ下ろした。
さすがに、許可なく中に入るわけには……。
「またあとで、様子を見に来ますね」
そこで、どん、と物音がする。
「ま、待ってくれ」
見るからに、立っているのがやっとという状態のアルバがあらわれた。
「何も食べてなくて……力が出ない……」
アルバは壁に背を付けたまま、ずるずると床に座り込む。
「大丈夫ですか?」
シーナは慌ててアルバへと駆け寄った。触れた体はじんわりと熱を帯びている。
「とにかくベッドへ行きましょう」
「……あ、ああ。すまないが肩を貸してくれ」
窓際にあるベッドにアルバを寝かせると、シーナは土間から籠を取ってきた。
「台所を借りますね」
エルザが言っていた通り、籠の中には、食材がぎゅうぎゅうに詰め込まれている。
牛乳に卵、土のついたままの野菜、藁紙で包まれたパン、それからみずみずしいオレンジ。
それらを取り出して、シーナは考え込む。
パンと牛乳はそのままでいいとして、卵は焼いたほうが……。
「いいえ、病人のアルバでも食べられそうなものがいいはず……そうだわ」
まずは、器の中に卵を割り入れた。
そこへ、牛乳と少量のはちみつを入れてかき混ぜ卵液を作り、パンを浸す。
パンに卵液が染みる間に火を起こし、食べやすいようオレンジの皮を剥いて切り分けた。
「料理ができるまで、良かったらオレンジをどうぞ」
アルバは、そろりとオレンジをひと房つまみあげる。
口に含んだあと、ぎゅっと唇をすぼめ、ひどく酸っぱそうにしていた。
「冷たくてうまい……生き返るようだ」
勢いづいたアルバは、貪るようにオレンジを口の中へ放り込む。熱に侵された体が、よほど水分を欲していたのだろう。
「酸っぱいが、うまい……ごほっ」
がっついてむせるアルバの背中を、シーナは優しくさすってやった。
「落ち着いてください。食べすぎると、弱っている胃腸にも負担になるでしょうから」
「大丈夫。普段は、体だけは丈夫なんだ。風邪をひいておいてなんだけど」
そう言って、アルバは苦笑する。
裏を返せば、どれほど頑強な者でも、病の前には無力になるということだ。
だけど、たくさん食べてゆっくり休めば、大丈夫。
エルザがしてくれたように、シーナもアルバを自分の料理で元気にしたいと思った。
「お水を持ってきますね」
その水さえも、あっという間にアルバは飲み干してしまう。
「料理もすぐにできますから」
シーナは台所へ戻ると、卵液に浸したパンを少しのバターで焼いた。
バターの甘く香ばしい香りが部屋中に広がり、ベッドのアルバをもどかしくさせる。
「余計に腹が減ってきた……」
「もうできましたよ」
焼き目がついたやわらかなパンを皿に盛り付け、シーナは急いでベッドまで届ける。
「どうぞ、召し上がってください」
表面の焦げ目とバターのつや、持ち上げればじゅわっと染み出る卵液に、アルバは喉を鳴らした。
「うまそうだ」
やわらかなパンの形を崩さないよう、そっと口へと運ぶ。
「とろけるようだ……とにかく食べやすい。いくらでも入るな」
ひと皿をぺろりとたいらげたアルバは、おかわりまでしてやっと満ち足りたように言った。
「ごちそうさま。本当においしかった」
これだけ食欲があれば大丈夫ね。
元気を取り戻したアルバに、シーナはひと安心する。
「そうだわ、ブランシェは?」
「あいつは、王都の知り合いに預けたままなんだ。早く迎えに行ってやらないとならないが……そもそもブランシェと川遊びをしていてこうなったんだ。暑い日が続いたから水辺で休ませてやるつもりだったのが、半日水につからされることになるとは」
「アルバとブランシェは、本当の兄妹や家族みたいですね」
アルバはどこか不服そうに、再びオレンジを口に含んだが。
やはり酸っぱかったようで、思いきり唇を噛み締めていた。
アルバの愛嬌のある仕草に表情が緩みそうになるのを、シーナはなんとか耐え凌ぐ。
「……シーナ、ありがとう。俺のために料理までしてくれて」
軽く咳払いをすると、少し照れくさそうにアルバは言った。
「支え合うのは当然ですから。それに、食材はエルザさんが用意してくれたものです」
「エルザさんたちにはずいぶんと世話になっているんだ。この家も彼らの家だし」
シーナはアルバの部屋を見回す。
革でできた馬具や鋲のついた腕当てが、どこか誇らしげに壁に飾られていた。いっぽうで、刃こぼれした短剣は軽率に棚の上に放り出されている。
意外だったのは、窓辺に飾られた可憐なラベンダーの花だ。
古びてはいるが手直しされているせいか、明るくて心地よい空間に感じられる。
「あまりじろじろ見ないでくれ。散らかっているだろ」
「たいへん失礼しました」
ぴたりと動きを止め、シーナはかしこまる。
「そうまで真剣に受け取らなくてもいいさ。シーナは真面目なんだな」
アルバは口元に笑みを浮かべながら、後頭部をがしがしとかいた。
「ところで、店はうまくいってるのか?」
シーナは小さく首を横に振る。
「そうか。何か手伝えることがあれば言ってくれ」
「ありがとうございます。実は今日、ランタンを並べてみたら、店先が星空のようにとても綺麗になりました。少しの工夫で、変わるものですね。もしかしたら、お客様を呼べるきっかけを見つけられるかもしれません」
自然を感じることも、きっと調味料になるはず。
たとえば、摘んできた花を飾ってみるのはどうかしら……。
窓辺のラベンダーに目をやり、シーナは何気なく思う。
「面白いな。シーナは色んなことを思いつくんだな」
感心したように言い、再びアルバはオレンジを口に入れた。
「ですが、肝心の麦のスープは、まだまだエルザさんの味には届きません……」
「なるほど。となると、エルザさんの麦のスープにこだわる必要はないんじゃないか?」
「こだわる必要はない?」
「シーナの店なんだから、シーナのスープを出せばいい」
「私のスープ……」
「今日、俺のために料理をしてくれたように、手元にある食材で工夫を凝らしたスープを作るのはどうだろう?」
シーナの料理で満足そうにする、アルバの言葉には説得力があった。
「工夫を凝らしたスープ……それはたいへん良い考えです」
シーナは、霧が晴れて視界が開けるような感覚になる。
すると、ぴたりと、オレンジをつまむアルバの指先が止まった。
「シーナも腹が減ってるんじゃないか?」
思いがけず、顔の前にオレンジを差し出される。
「ほら、口を開けて」
言われるがままにシーナが口を開けると、オレンジが放り込まれた。
「酸っぱい」
口の中いっぱいに酸味が広がり、シーナは思わず唇をすぼめた。
「ははは。ちゃんと食べられて……偉いぞ……いい子だ……」
再び熱があがってきたのか、アルバはぼんやりとした口調になる。
星のない夜空のようだわ……。
ちらりと覗く、アルバの片方の瞳を見て、シーナは思った。
同じように、アルバもシーナの様子をうかがっているようだった。
「それにしても……高貴な髪色だ。まるで……豊穣の女神だな……」
シーナの長い髪をひと房掬うと、アルバはうわ言のように言った。
「え…………」
「だめだ、瞼が重い……」
強い眠気に襲われたようで、アルバはベッドへと沈み込む。
「すまない……シーナ、今夜はありがとう」
ブランシェに語りかけるように優しく言われ、慣れないシーナは戸惑ってしまうのだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




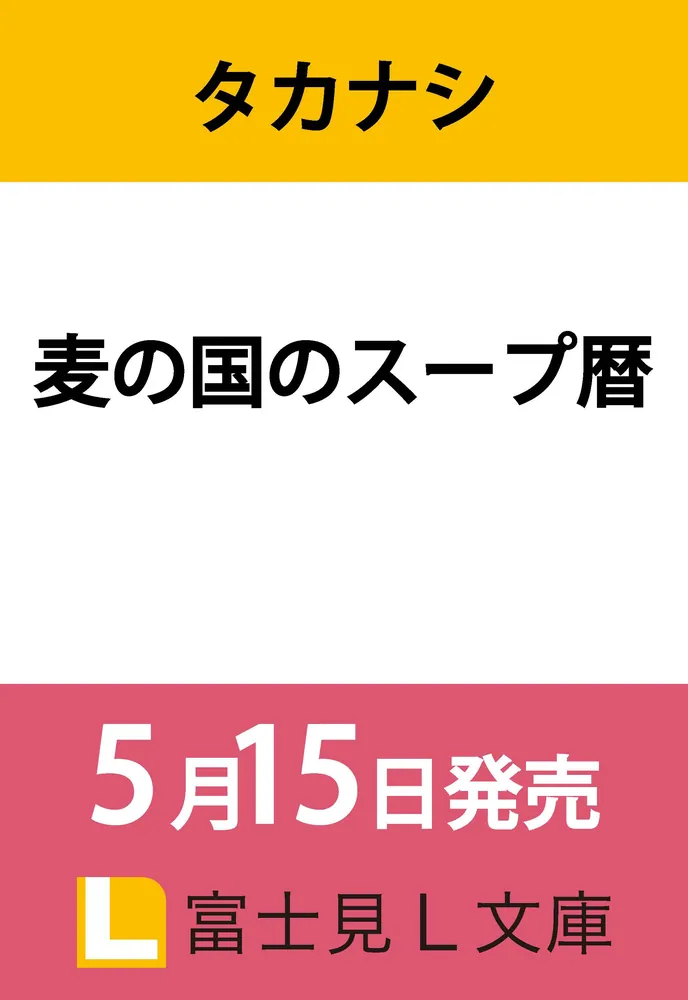
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます