一杯目 涙をぬぐう琥珀色のベジブロス⑤
シーナがエルザの店を手伝うようになり、数日が過ぎた。
夫婦が暮らす母屋に寄り添うように建つ小屋が、エルザのパンとスープの店だ。
狭い店の中には木製のテーブルが三台置かれ、それぞれに椅子が四脚ずつ並べられている。奥が調理場になっており、炎が揺らめく立派な石窯があった。
炉の上には使い込まれた鍋が吊るされ、桶や籠などの道具類は棚に整然と並べられている。
店を彩るのは、鮮やかな野菜や瓶詰めのジャムたちだ。古びたつましい小屋ではあるが、温かみのある店だった。
しかも、店には屋根裏まであり、シーナはここで寝起きをするようになっていた。
「シーナ、朝よ。さあ、起きて」
エルザの朝は早い。まだ薄暗い夜明け前から起き出して、パンを焼きスープを仕込む。
やっと目を覚ましたシーナは、眠たい目をこすりながらつぶやいた。
「もう、朝……急がないと」
シーナの朝ももちろん早い。
シーナなりに、食事や寝床を与えてくれたエルザとハルタの厚意に報いるべく、一日も早く一人前になろうとしていた。
「ふふふ。シーナはお寝坊さんね」
エルザの独り言が聞こえてくる。
ヴァレリアだった頃の生活と比べれば、これでもずいぶんと早起きだったが、まだまだのようだ。
「おはようございます」
屋根裏から梯子を伝って階下へ下り、シーナはさっそく湯を沸かす。
エルザの丸パンは風味が良く弾力もあり、町一番のパンだと言われているそうだ。
おいしいパンを作るには、発酵という手順を踏まなければならない。
パン生地を発酵させるには、湯が必要だった。
さらにもうひとつ、重要なのは……。
「良かった。今日も元気そうね」
手にした瓶を眺め、エルザは満足そうに微笑んでいた。
表面に無数の気泡を浮かべ、瓶の中でぷっくりと膨らんでいるものはパン種だ。
麦粉に干し葡萄から作る秘伝の液を混ぜたパン種は、生地をふっくらと膨らませ、旨味や風味をもたらしてくれるという。
食材や料理の知識はあっても、実際に調理をしたことがないシーナにとって、毎日が新鮮な学びだった。
「シーナ、見ていて」
麦粉に塩や水、さらにパン種を加えたものを、エルザは桶の中でくるくるとかき混ぜた。生地がまとまりはじめ粉気がなくなったところで、作業台へと取り出す。
シーナは、エルザの手元をしっかりと見つめていた。
生地を押し広げ、力強く押し込む。
まるで生地と対話しているかのような、熟練した手つきだった。
こねが終わると、エルザは軽く生地に粉をはたき、湯を張った桶と一緒に木箱に入れる。
「シーナもやってみなさい」
「は、はい」
「おいしいパンが焼けるようになれば、きっとこの先も困ることはないでしょうから」
手に職をつけたほうがいい、ということかしら……。
もしかするとこの店に、シーナを養うだけの実入りはないのかもしれない。
迷惑をかけているのかもしれないわ……。
新しい仕事を探し、住む家を見つけて、いずれはここを出ていくべきだろう。
当然、いつまで自分を偽っていられるかも分からない――シーナの表情はみるみる硬くなっていった。
「嫌だ、眉間に皺が寄ってる。可愛い顔が台無しよ」
エルザは、シーナを真似て顔をしかめてみせる。
真面目なシーナは、ひたすら困惑した。
「ただ、パンを焼くだけよ。そんなに難しく考えないで」
お手本のような柔らかな笑顔を、エルザはふわりと浮かべる。
「もっと気楽にやればいいのよ。だから、笑ってちょうだい?」
「ここでは、笑ってもいいのでしょうか」
「もちろんよ」
そこでシーナは、ぎこちないながらも口角を上げてみた。
「笑うと、もっと素敵よ。さあ、続きをやって」
「分かりました」
素敵かどうかは、ともかくとして。
先のことばかり考えていてもしょうがないと、シーナは軽く首を横に振った。
見様見真似ではあるものの、ただ夢中で生地をこねていく。
エルザの手の動きを頭に思い描きながら、生地を広げて伸ばし、畳むのを繰り返した。
ところが、シーナの生地はいつまで経ってもぼそぼそとしていて、なかなかまとまらない。
「ふふふ。生真面目なシーナの前で、生地がよそ行きの顔をしているわ」
エルザはどこか愉快そうである。
「よそ行きの顔、ですか……?」
「もっと肩の力を抜いて、楽にやればいいのよ。代わって」
エルザがこねだすと、生地はしっとりと滑らかになっていった。
見るからに、生地は楽しげな表情をしている。ふっくらとしていてつやつやだ。
「シーナは呑み込みが早いから、すぐに上手になるでしょうね」
エルザの手から、いい具合にまとまった生地を渡される。
「発酵をお願い」
「発酵ですね」
シーナは湯を張った桶と粉をはたいた生地を、手早く木箱へと入れた。
木箱の中の程よい湿気と温度が、生地の発酵を促してくれるそうだ。
「次はスープよ」
エルザは、皮を剥いた芋をざくざくと大きめに切り分けていく。
エルザが店で出すスープは、田舎町の家庭料理である麦のスープだ。
茹でた麦と季節の野菜、たまに燻した肉や腸詰めなどが入る素朴なスープで、塩と香草だけで味付けする。
ぷちぷちとした麦の食感と野菜の旨味が、麦の国に暮らす人々の郷愁を誘うらしい。
中でもエルザの味付けは絶妙で、繰り返し口にしたくなる味だと好評だった。評判を聞きつけ、王都からわざわざやってくる客もいるようだ。
「ふう。ちょっと疲れたみたい。休むわね」
「私が代わります」
エルザを椅子に座らせるとすぐに、シーナは鍋を火にかけた。
教わった通りオイルでにんにくを炒め、香りが出てきたところで角切りの燻した肉を入れる。
さらに、芋や玉ねぎ、トマトなどの野菜を加えて、焦がさないよう軽く炒めた。
「山の国では珍しいでしょうね。トマトに毒があるなんて迷信よ」
トマトの扱いに慣れていないシーナを見て、エルザは微笑む。
「どんな味がするのか、楽しみです」
山の国では、トマトは主に観賞用で、毒性があるからと嫌厭され口にすることはない。
実際には、完熟トマトに毒性はなく、未熟のトマトにおいては量によって用心したほうがいい――という話だが、シーナはこれまで、この知識をただ頭の片隅に置いていただけだった。
「トマトを口にする日が来るなんて……」
交易が盛んな麦の国には珍しい野菜や果物が多くあり、それらを食することにも抵抗がないようだ。
栽培することにも熱心で、ハルタの畑にも様々な野菜が植えられている。
「いい香りね」
エルザが楽しげに言った。
食欲をそそるにんにくの香りが充満する。野菜たちに艶が出る。
あとは、茹でた麦と水を加えて煮込んでいくだけだ。
コツは、煮崩れないよう野菜を大きめに切ること。
シーナは真剣な表情で、いっときも鍋から目を離さなかった。
ぐつぐつと煮立ってきたら、丁寧に灰汁を掬う。
「味付けはどうしましょうか?」
シーナが訊ねると、「よっこらしょ」とエルザが立ち上がった。
「適当でいいのよ。見ていて」
エルザは指先で塩をつまみ上げ、鍋の中にぱらぱらと振りかけた。
小皿に少量のスープを取ると、よく冷ましてから味見する。
納得いかないのか「うーん」と首を傾げ、さらに塩を振った。
「自分の体調によっても、味覚が変わるのよ。だから、適当」
再びスープの味を見て、「こんなものかしら」といったん鍋を火から下ろす。
野菜がたっぷり入ったスープの表面は、コクと旨味できらめいていた。
ふわりと漂う芳醇な香りは、畑から摘んできたばかりの新鮮な香草だ。
香草は香りが飛ばないよう、食べる直前に刻んでスープに加えるそうだ。
「おいしそう……」
自分の手から生まれたとは思えない出来栄えのスープに、思わずため息がこぼれる。
スープの温もりが、心にまで染み渡っていくようだわ……。
シーナは、これまで感じたことのない充実感で満たされた。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




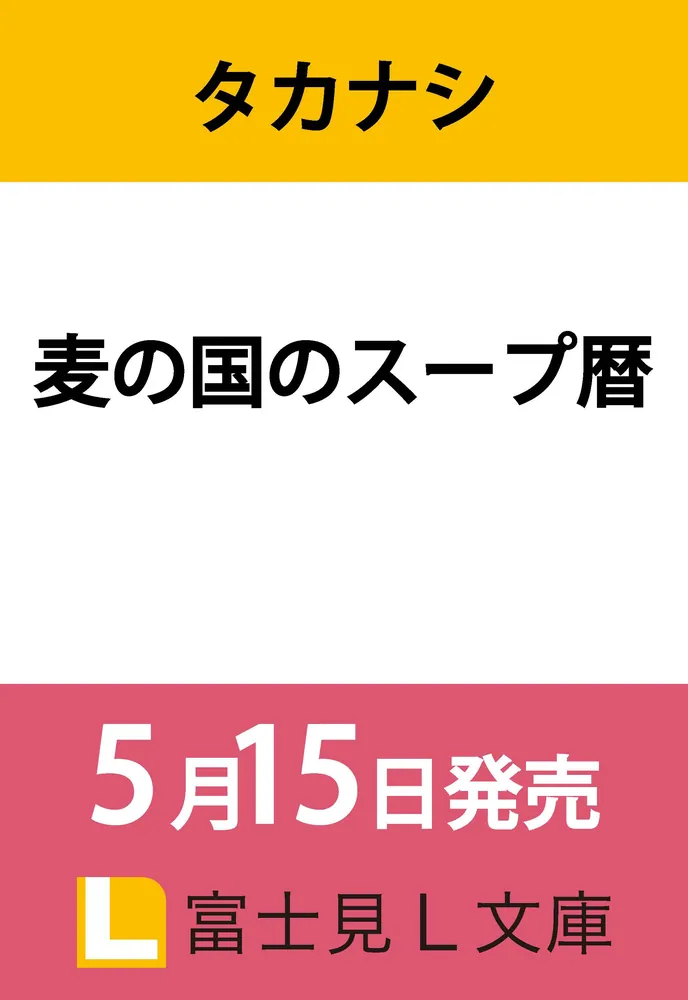
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます