一杯目 涙をぬぐう琥珀色のベジブロス④
「野菜の皮や切れ端からとった
器の上には、食欲を誘うように可愛らしい湯気が揺れていた。
「……いただきます」
何も口にできないと思っていたはずが、不思議とお腹が空いてくる。
ヴァレリアはゆっくりと器を傾け、スープを喉へと流し込んだ。
野菜の旨味が口の中で踊る。体の中に心地よい温もりが広がっていった。
「ああ、おいしい……」
ぽろりと、言葉が口からこぼれ落ちる。
食事中に言葉を発したことで、品がないと咎められるだろうか。
だとしても、かまわない。
滋味深い味わいに、ただ心が満たされていくのをヴァレリアは感じていた。
「昨日焼いたパンだから、スープに浸して食べるといいわ」
手渡された丸パンの表面は少しざらついている。覚えのある懐かしい感触だった。
ふと、修道院で出会った少年の顔が浮かぶ。眉間に力を込めた、悔しげな顔だ。
ひどくお腹を空かせているようだったので、自分のぶんのパンを渡したところ、少年は怒ったように言った。
『あんたにはたった一切れのパンでも、このパンがあれば妹は死なずにすんだ』
ヴァレリアはパン一切れの重みを、今になってやっと理解する。
その重みも知らずに施しを与えようとしていた、傲慢な自分が恥ずかしかった。
このパンは、私の命を繋いでくれる大事なパン……。
また、今まで口にしたどんなパンよりも、優しい味がした。
「あらあら」
エルザが目を見開く。
思いがけず、ヴァレリアの頬を一筋の涙が伝っていった。
「私、泣いて……?」
ヴァレリア自身も驚きを隠せない。人前で泣いたのは、はじめての経験だったからだ。
涙が温かいなんて。
てっきり涙は、冷たいものだと思っていた。
私は、何も知らない――
様々なことを学んだ気になっていただけで、少しも分かっていなかった。
ヴァレリアは、世界の広さと人生の奥深さを、ひしひしと感じるのだ。
「大丈夫よ。泣きたい時は泣いたほうがいいの」
「スープが、とてもおいしくて……」
そう口にするのが精一杯である。
ヴァレリアの涙を、エルザがエプロンの端で拭った。
「おいしいものを食べてぐっすり眠れば、きっと元気になるわ。焦る必要なんてないの。あなたには、まだたっぷり時間はあるんだから」
エルザの気遣いが、ヴァレリアの心を癒やしてくれる。
誰にも必要とされない、未熟な私なのに。
家族に顧みられることなく、婚約者には蔑まれ、人々からは忌避されてきたヴァレリアにとって、エルザの言葉は救いのようにも感じられた。
ヴァレリアは心の中で問いかける。
主よ、私はまだ生きていてもいいのですか?
「さあ、たくさんお食べなさい」
温かなエルザの微笑みが、問いの答えであるかのように、ヴァレリアの瞳には映るのだった。
エルザが言った通り、それから十日も経たずに、ヴァレリアはすっかり元気になった。
この家のもう一人の住人であるハルタは、「かまわんよ」とひと言、見ず知らずのヴァレリアを気軽に家に置いてくれた。
夫婦は、質素な暮らしをしているにもかかわらず、ヴァレリアのために着替えや靴まで買い与えてくれた。
隣人のアルバはあれ以来顔を見せないが、頻繁にエルザの店を訪れては、ヴァレリアの様子を訊ねているらしい。
優しい人ばかり……。
あまりの居心地の良さに、ヴァレリアは、自分の置かれた状況を忘れてしまいそうになった。
だけど、いつまでも甘えてはいられない……。
いつかはここを出ていかねばならないと分かってはいるが、帰る場所のないヴァレリアは困り果てるだけだった。
「お嬢さん、スープができたわよ」
食卓につくヴァレリアへ、エルザがスープを運んできた。
「そうだわ。いつまでもお嬢さんと呼ぶのも他人行儀だし、そろそろ名前を聞いてもいいかしら」
「わ……私の名前は……」
ヴァレリアはごくりと息を呑んだ。
ここで、罪人とされた名を口にするわけにはいかない。
「あ、あの……」
告げる名がないだけで、自分が空っぽの器のように感じられる。
その時ふと、山の国の古語で〝価値のないもの〟という意味の言葉を思い出した。
「私の名前は
名を偽ることが不敬であるのは承知している。
けれども、真実を語ったところで信じてもらえるかも分からないうえ、かえって迷惑をかけることになりかねない。
「いい名前だわ。確か、〝神の恵み〟という意味がある、昔の言葉よね。あまり学がなくて、ごめんなさい」
エルザは恥ずかしそうに笑った。
「麦の国ではそういう意味が……でも、私には不釣り合いです……」
ヴァレリアの名を捨てたシーナはうつむく。
「そんなこと言わないで。シーナはシーナよ」
励ますように、シーナの手をそっとエルザが握った。
働き者だと分かる、やや硬くなった指先だった。
「……ありがとうございます」
「いいのよ。それにしても、ずいぶん顔色が良くなったみたい」
「エルザさんのスープのおかげです。とてもおいしくて……」
今日のスープには、肉のかたまりと大きめの野菜がごろりと入っている。
肉はほろほろと崩れるほど煮込まれ、スープの水面から顔を出した野菜たちはつやつやに輝いていた。
ふっくらとした麦も、ぷかぷかとたくさん浮かんでいる。
「私のスープを気に入ったのなら、店を手伝ってみない?」
「え…………」
「店を手伝いながら、しばらくここにいるといいわ」
そう言って、エルザは明るい笑顔になった。
シーナにとって、ありがたい申し出であることには違いない。
「……はい。お願いします」
人手が足りないわけではなく、それがエルザの優しさであることも、シーナはよく分かっていた。
行く当てのない私のことを思って……。
エルザに感謝しながら、シーナは匙を手にする。
「そうと決まったら、どんどん食べてもっと元気におなりなさい」
器にたっぷりと注がれたスープを見ていると、自分を空っぽだと感じていたシーナでも、不思議と心が満たされていくような気がするのだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




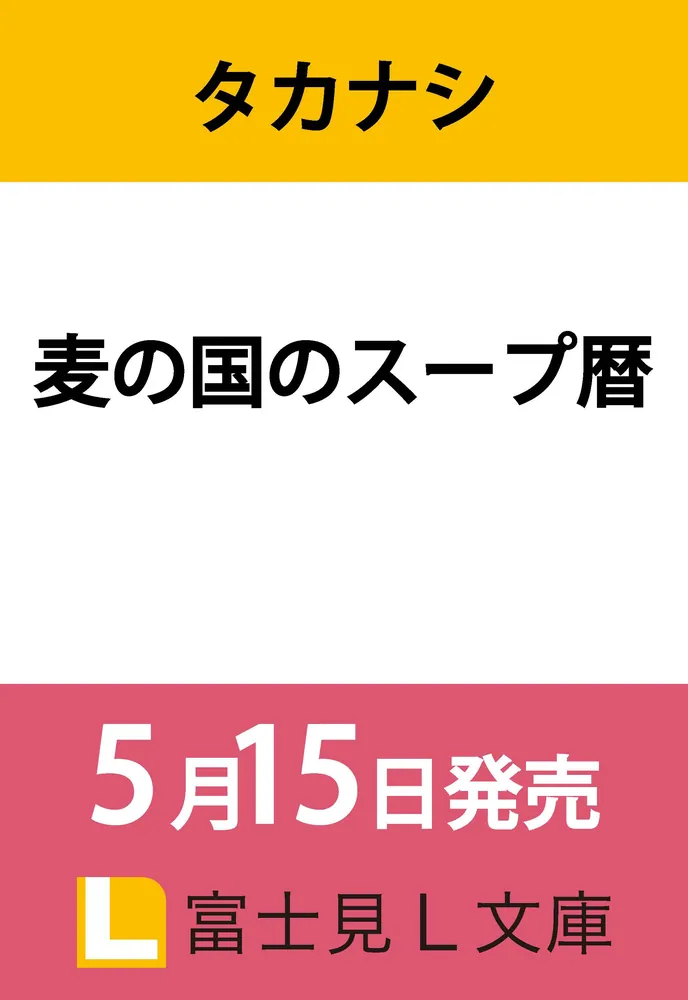
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます