一杯目 涙をぬぐう琥珀色のベジブロス②
それはまだ、若葉が芽吹く春の頃。
去りし年に王太后が亡くなり、しきたり通り喪に服していたヴァレリアは、とうとう未婚のまま二十二歳の誕生日を迎える。星の巡りが悪いからと、婚姻が先延ばしにされていたためだ。
そのような中、王宮の庭で密会する、オスカーとソフィアに出くわしてしまった。
なんてこと……!
抱き合って唇を重ねる二人を見て、逃げ出すようにその場を離れたのは言うまでもない。
オスカーのソフィアを見つめる視線は、ヴァレリアを見る時のような冷めたものではなく甘く熱を帯びていた。
まだまだ子どもだと思っていたソフィアはいつの間にか成熟し、うっとりとした妖艶な表情を浮かべるようになっていた。
二人が愛し合っているのは明々白々である。
しかしながら、ヴァレリアが身を引けばいいという話でもない。
しきたりに則り王が決めた婚約を覆すなど、あってはならないことだからだ。
「誰にも知られてはならないわ……いつか二人が目を覚まして、正しい道に戻ってくれますように……」
傷つきながらもヴァレリアはどうにか心を鎮め、二人を信じて待つことにした。
ところが――
どこから漏れたのか、ほどなくしてオスカーとソフィアの不貞は明るみに出る。よりにもよって、噂を広めたのはヴァレリアであると
飛び交う憶測や流言によって、とうとう王宮だけでなく、民までもが混乱する事態となった。
「お姉様、ひどいわ……私にオスカー様を奪われたからって、こんな仕打ち」
ソフィアは一方的にヴァレリアを責め、オスカーの胸で泣き崩れる。
「いずれ、私から王に進言するつもりだったのを、わざわざこんな騒ぎにするなど、恥知らずにもほどがある!」
オスカーもヴァレリアの仕業だと決めつけ、激しく非難してきた。
「私は、何も知りません!」
身に覚えのないヴァレリアは、断固として否定するが聞き入れられない。
「お姉様がいけないのよ……」
いよいよ追い詰められたソフィアは、どういうつもりか姉に毒を飲まされたと嘘の証言をした。
「ヴァレリア、妹になんてことを!」
両親はソフィアを信じ、ヴァレリアの言葉には耳を貸そうとしない。
知らぬうちに、愛くるしいソフィアに嫉妬したヴァレリアが、オスカーとの関係を邪推し、妹殺害を目論んだという筋書きが作り上げられていた。
集団心理とは恐ろしいもので、個々の判断力を鈍らせた人々を、やすやすと誤った結論へと導いてしまう。
ヴァレリアがいわれのない罪であると訴えようとも、誰一人として信じようとはせず、ついには極刑を宣告されるのだった。
主よ、真実を明らかにしてください――
気付けばヴァレリアは、修道院の聖堂で神に祈りを捧げていた。
深い悲しみが襲ってきたが、涙は流れない。
心は激しく波打っていようとも、殺風景な顔しかできなかった。しかし。
ヴァレリアは、心の中では泣いていた。
僅かな時間を見つけては訪れて、他に行く当てのない子どもたちの家庭教師をしていた、馴染み深い修道院である。ありのままの感情が、無様に溢れそうになるのを必死で耐えた。
修道院には、そんなヴァレリアの隠しきれぬ心に気付いてくれる人もいる。
「珍しいですね。いつも落ち着いているあなたが、心を乱すとは」
マザーの声に顔を上げた途端、ヴァレリアの世界は暗転した。
何も見えない――誰か、誰かいませんか。
耳をそばだてれば、暗闇の中から人の声が聞こえてくる。
『自分の娘なのに、何を考えているのか分からないわ。不気味で末恐ろしい』
それは、扉の隙間から漏れてきた、ため息混じりの母の声。
『堅苦しい女だ。一緒にいると、息が詰まる』
それは、お茶会の席で放たれた、オスカーからの冷淡な一言。
『お姉様に……毒の入った紅茶を飲まされました……』
それは、青白い顔をしたソフィアの、消え入りそうな弱々しい声。
『神の裁きを受けるがいい』
それは、無実の罪だと訴えるヴァレリアが、最後に耳にした言葉。
沈黙が訪れたあとは、深い闇だけが残された。
もう、私には何も聞こえない。
世界から色も音も消え去り、すべてを諦めかけた時だった。
いきなり誰かに体をつかまれ、水面から引き上げられる。
「大丈夫か! しっかりしろ!」
ヴァレリアは激しくむせ返り、口から水を溢れさせるのだ。
ここはどこ?
闇は途切れ、再び音と光がヴァレリアの世界に飛び込んできた。
修道院ではないの?
しばらく考えて、死の淵をさまよいながら記憶の走馬灯を見ていたのだと、ようやく理解する。
ヴァレリアが元いた場所は崖の上で、深い谷底を見下ろしていたのだから。
「ごほっ……ごほごほっ……」
ヴァレリアは苦しい胸を押さえて咳き込む。
まともに息ができない。
初夏とはいえ、寒さに震えが止まらなかった。
死にたくない……!
咄嗟に、冷え切った体をさすってくれる逞しい腕にしがみつく。
「慌てるな。ゆっくり息をしろ」
耳元で若い男の声がした。
浅い呼吸を繰り返すうち、ヴァレリアのぼやけた視界が鮮明になっていく。
「もう大丈夫だ」
男は無造作に、濡れた黒髪をかきあげた。
あらわれたのは、鋭さと気高さを兼ね備えた、彫刻のように端整な男の顔。
「よく頑張った。いい子だ」
男の言葉に安心したヴァレリアは、ゆっくりと瞼を閉じるのだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




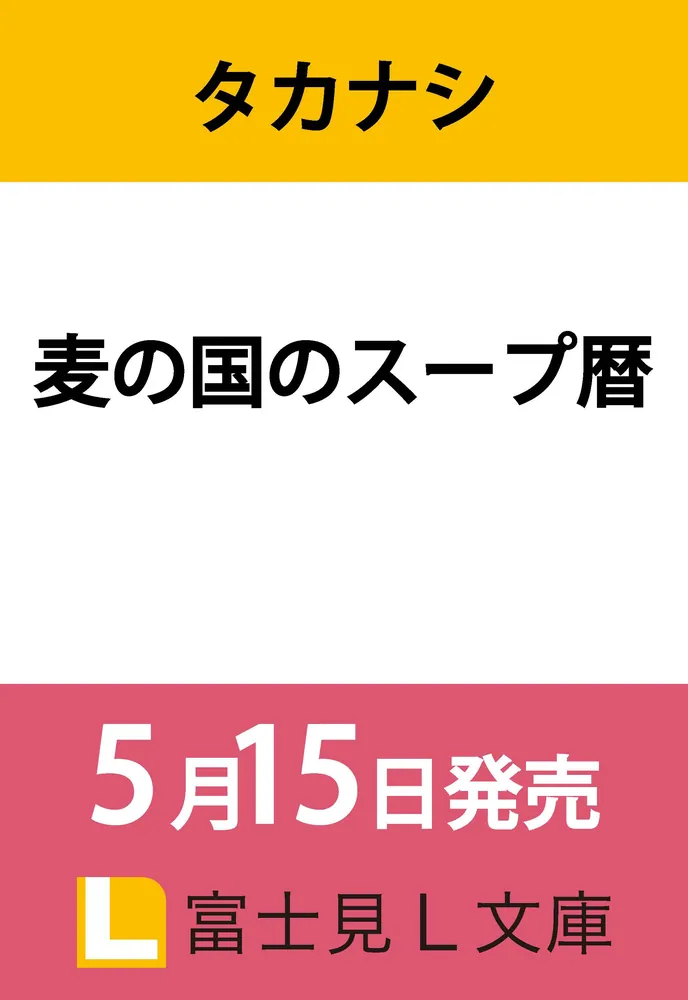
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます