旦那の同僚がエルフかもしれません
竹岡葉月
第1部
1章
第1話 はじまりはじまり、そして
そもそもあまりファンタジーの素養はない人間だったのだ。
『ハリー・ポッター』は二作目で止まっているし、『指輪物語』の映画はエルフ役の人が格好いいという噂だけを頼りに頑張って観た。
だから今目の前で魔法を使って魔物を倒している耳の長い人が、一般にエルフ族と呼ばれているのはなんとなくわかった。
「イブキ、とどめを」
「ああ!」
エルフの魔法使いの呼びかけに応え、刀を携えた勇者が巨大な敵を切り裂く。
魔物は胴体を切断され、迷宮の地面に
勇者がマントの内側で刀を鞘に納め、こちらを振り返った。
「ひばり……!?」
何やら愕然とした様子だが、その
だって私の記憶が確かなら、この人は『ららぽーと豊洲』で買った上下丸洗いできる一万七千八百円のスーツを着て、朝出勤したはずなのだ。
***
後々のことを考えれば、出会いや馴れ初めはきわめて普通だった。
ひばりの祖父が営む弁当屋『ときとう』は、京都市上京区、鴨川デルタ近くの商店街にあった。同志社などの総合大学も近いだけに、ボリュームのある鯵フライ弁当と、各種のお惣菜が人気の店だった。
ひばり自身は市内の高校を卒業した後、祖父を手伝い『ときとう』の店頭に立っていたのである。
「はい、鯵フライ弁当、大盛り一つですね。かしこまりました」
体格のいいジャージ姿の体育会系男子から注文を受け、厨房にいる祖父にオーダーを通す。
「おじいちゃーん、鯵弁大イチ、オーダー入りましたー!」
ひばりの祖父、
『ときとう』の売りは、全て店内調理でできたてを提供することだ。衣をつけた鯵を揚げている間、ひばりは客から料金を受け取り、次の人の注文を聞き、弁当ができあがると箸とおしぼりをつけてビニール袋に入れていく。
「鯵フライ弁当、大盛りお待たせしました。ありがとうございます!」
商品をカウンター越しに手渡し、三角巾とポニーテールでまとめた頭を下げる。
(よしよし。このペースなら、鯵は終わりまでにはけそうだね)
ひばりが祖父と一緒に仕込んだお惣菜も、今日はまずまずの売れ行き。順調だと全てが嬉しい。
ランチタイムと夕方に続き、閉店前のラスト一時間は最後のピークタイムだ。ただ今、一人暮らしの夕飯用の弁当を買いにきた大学生が出ていき、代わりに入ってきたお客様が彼だった。
(──お、
黒っぽいスーツの上に、カジュアルなマウンテンパーカーを着込んだ、二十代半ばほどの青年である。名前は聞いたところによると、三輪
襟足を短くした黒髪は天然なのか人工なのか少し癖があり、顔だちは比例するようにすっきりあっさりしていると思う。身長は平均よりやや低めかもしれないが、姿勢がいいのであまり小さい印象がない。
この近くの会社で働いている人らしく、よく昼食や残業用の弁当を買いにくるのである。
「いらっしゃいませ、三輪さん。いつもの中華丼と豚汁のセットでいいですか?」
「はい。お願いします」
「大変ですよねー、今日も会社居残りですか」
ひばりの質問に、伊吹は人のよさそうな顔をほころばせて苦笑した。やはり図星らしい。
このお兄さんが頼むものは、だいたい一緒だから覚えてしまった。
ちょうど今から一年ぐらい前にふらりと現れ、最初はひばりが勧めた通りに鯵のフライ弁当を買っていった。そこからあまりに同じメニューが続くものだから、たまには気分を変えてと唐揚げ弁当を勧めたらそればかりになり、今は野菜を食べさせようと中華丼と豚汁のセットを定着させたところだ。
食にこだわりがないのかと思うが、「ここのものはみんなおいしいですよ」と伊吹は言う。弁当屋のひばりにも丁寧な物言いで、こうやって待っている間もふらふらしないですっと真っ直ぐ立って、無理がない感じも好ましかった。
パートのおば様などは、伊吹を見て「可愛いじゃない」「体幹いいから、なんか武道でもやってるのかもね」と言うが、ひばりとしては舞踊の方がよほどしっくり来る感じだ。なんにしろ荒事をしている彼が想像つかない。
「外、かなり寒いんですか?」
「え?」
「鼻とほっぺ、真っ赤だから」
できた弁当と箸を袋に詰めながら聞いたら、伊吹は慌てて自分の鼻をおさえた。見ろ、こんなに隙だらけなのだ。ひばりはおかしくて笑ってしまった。
今は京都でも一番冷え込む二月である。商店街にはアーケードがあり、表の天気がどうなっているかわかりにくいが、予報では夜から崩れるとあった気がする。
「……そうですね。雪にはまだなっていないですよ……」
「ごめんなさい。豚汁飲んであったまってください」
持ち手をねじったビニール袋を、彼に差し出す。
すると伊吹が、あらたまった調子で言った。
「
いきなり名前を呼ばれ、どういうことかと顔を上げた。
「僕が今いる京都支部が、三月いっぱいで閉鎖することになりました。四月からは、東京の本部勤務になります」
「閉鎖、ですか……」
「もともとこちらの人員を本部に回すために、僕が派遣されていたようなものなんです。時任さんには短い間ですが、大変お世話になりました」
嘘だろうと思いたかった。けれど、伊吹の精一杯であろう真顔が、冗談ではないと言っていた。
とっさには、きのきいた台詞なんて出てこない。
「そ、そうですか……それは、寂しくなりますね……」
地元の人間でないというのは、ふだんの言動でなんとなくわかっていた。地理に疎そうだったし、イントネーションも癖のない標準語だった。
この放っておけば同じ弁当ばかり食べる、実直で物腰の丁寧な青年は、もうじきいなくなってしまうのか。東京では体に気をつけて、栄養のバランスも考えなさいと言ってくれる人はいるだろうか。残業ばかりで倒れたりしないだろうか。
思ったら胸が痛くて、そんな自分に驚いた。社交辞令のつもりで言った『寂しい』だが、今こうして寂しくてたまらなくなっている。
(あ、やばい。泣きそう)
嫌だ、行かないでよ三輪さん──言えないひばりはとっさにうつむいて、目にゴミが入ったふりをするしかなかった。
「それで、できれば僕としても、ここで終わりになるのを避けたいと言いますか」
「──え?」
「その、連絡先交換しませんか。よろしければなんですが」
もう一度、顔を上げた。
伊吹はどこまでも真剣だった。ただ、外の気温のせいだと思っていた顔の赤さが、決してそれだけではないとわかってしまった。
「……はい。お願いします」
「よかった」
夢ではないだろうか。
終わりではなく続きがある。この人とまた会って、今よりもっと距離を縮めることもできるのか。
「おいこら、おまえさん方! いつまでそうやってるつもりだ。続きはよそでやれ、よそで。後ろで客が詰まってるんだぞ!」
カウンター越しに見つめ合っていたら、業を煮やした新八にどやされた。
後ろにいたお客様にも冷やかされ、ずいぶん前から周りには歯がゆく思われていたと、その時初めて知ったのだ。
*
桜が咲くまでのわずかな時間を一緒に過ごし、それからはずっと遠距離だった。
離れているがゆえのトラブルもあったが、それはどのカップルにも訪れるありがちなものだったと思う。交際から二年がたった今、こうして結婚しようとしているのだから。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




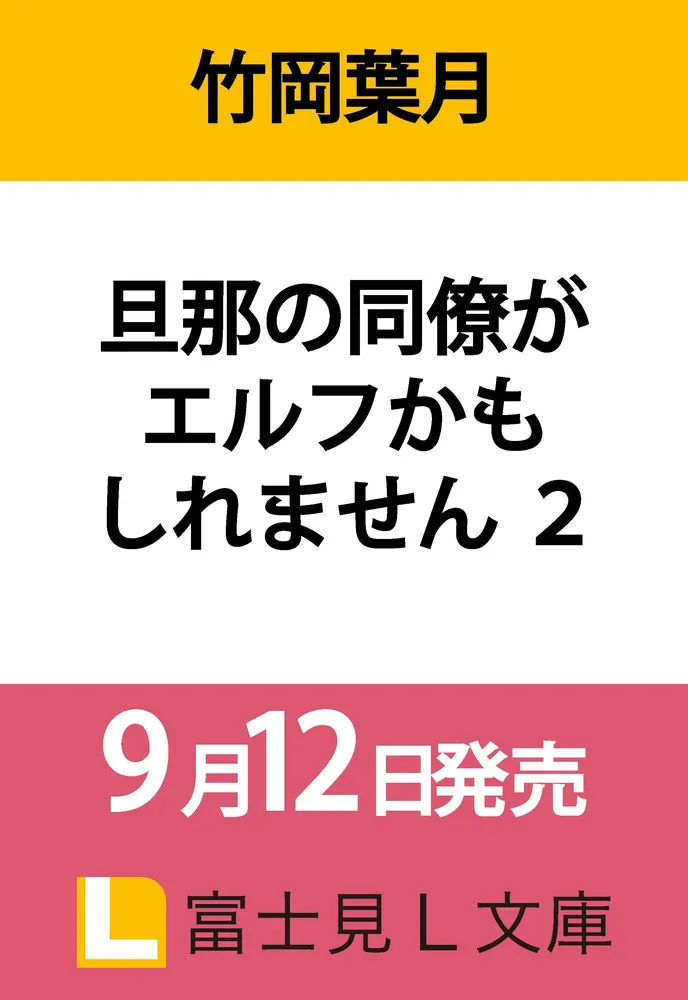
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます