魔王が如く 絶対強者の極道魔王、正体を隠して学園を極める【先行公開】
なめこ印/ファンタジア文庫
1、でくの坊、その正体は 1
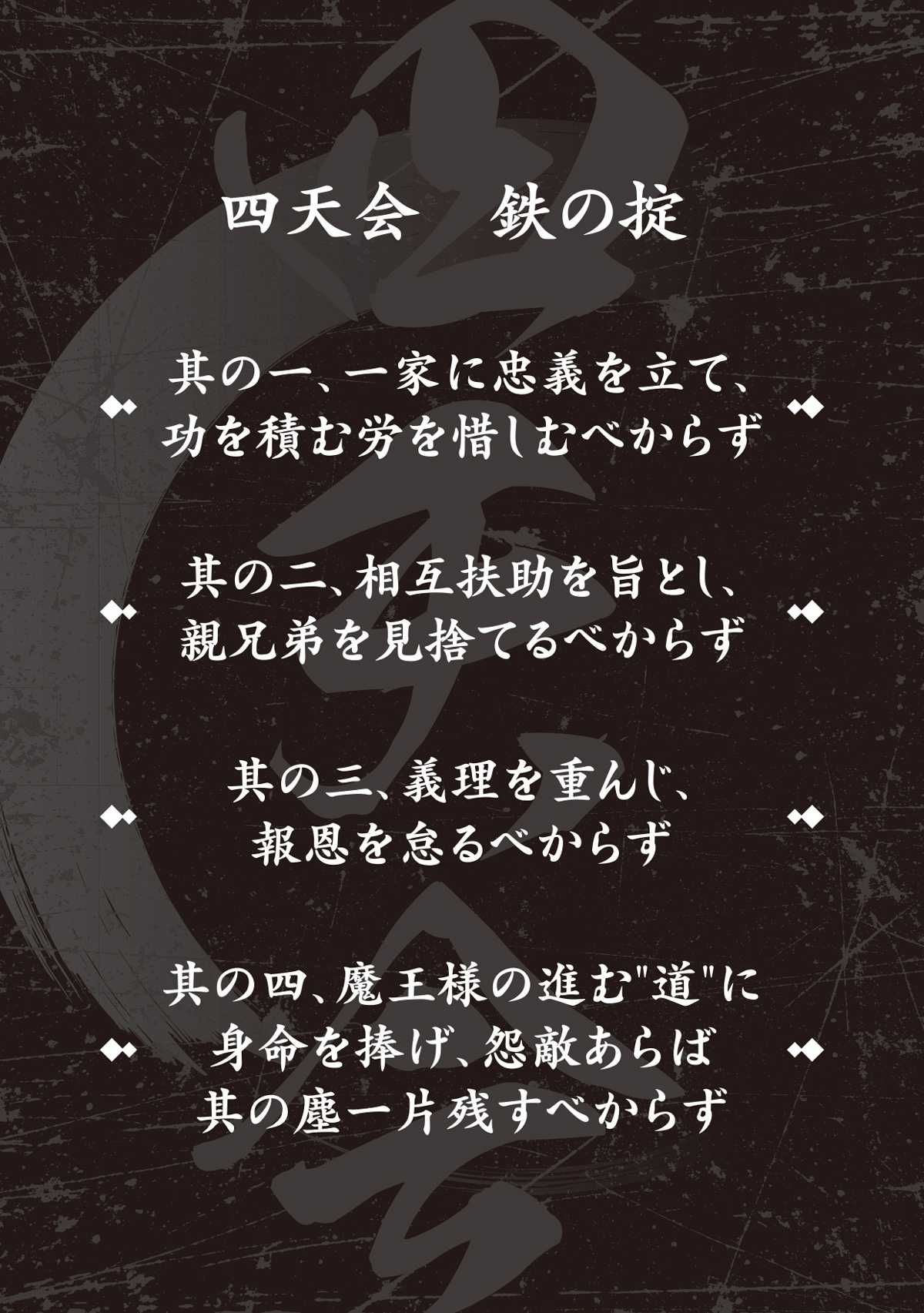
クラウディウス高校。
人類と魔王の「大戦」終結後に大陸東部の首都に建てられた最初の高等学校である。
歴史ある名門校として知られ、かつては王侯貴族のみしか入学できなかった。
が、時代が下って、政治が立憲君主制に移行したのと同時に一般にも門戸を開放した。
とはいえ名門校であることに変わりはない。
今でも名家の子女が多く在籍し、それに相応しい風格を備えていた。
そんな高校における生徒の頂点――生徒会。
この高校の生徒会に所属することはもはや一種のステータスである。
卒業後の進路は言うに及ばず、社会に出てからの人脈という意味でも、ここの生徒であれば誰もが生徒会に入りたいと願うのであった。
が――今年はそんな生徒会に異物がひとり混じっていた。
クラウディウス高校生徒会――通称クラ高生徒会のある日の放課後。
やたら体のデカい一年生オーマ=ローゼンは、生徒会室の隅の机で眉間にシワを寄せていた。
その顔面の圧たるや、気の弱い者なら失禁物の凶悪さ。
人を五人や十人軽く殺してそうな悪魔面をした彼だが、何も生徒会室で大犯罪の計画を立てているわけではない。
「何だ……こりゃ……?」
オーマがやっているのは簡単な書類の確認作業だ。
羅列された数字が正しいかを検算して確認、ただそれだけの簡単なお仕事……なのだが。
「ううん?」
生憎、彼とは相性が悪いようだった。
先程から
それは彼も自覚しているようで、焦りから書類を握る手にも力が入っていた。
書類を睨む眼光は爛々と光り、唸る声は地獄の底から響くようだ。
彼の仕事が進んでいないのに周囲も気づいているが、その背中から放たれる圧が恐ろしすぎて声をかけることができずにいた。
「んー……えーと、これとこっちが同じ数字で……?」
一方、オーマはオーマで与えられた書類仕事を投げ出す様子がなかった。
うんうん唸りながら数字と格闘し続けている。
根はまじめ、ということなのだろう。
そんな風に彼が懸命に仕事をしていると。
「おい、一年坊!」
「……?」
不意に声をかけられ、オーマは書類から顔を上げる。
彼の目に映ったのは生徒会の先輩のブランギだった。
口調の粗雑さもカリカリした様子もいつものこと。
何かにつけてオーマに突っかかってくるのがこの先輩の特徴であった。
「何でしょうか、ブランギ先輩?」
「何でしょうか……じゃない!」
怒鳴るブランギの手には一枚のシャツが握られていた。
「生徒会で行う校外ボランティアのシャツを発注したのはお前だな?」
「はい。確かに俺ですが……」
オーマは頷く。
校外ボランティアとは、再来週から行われる生徒会の活動だ。
この生徒会では度々こうした新規業務が追加される。
また今回は校外でのボランティア活動ということもあり、活動の周知を目的とした生徒会Tシャツを作ることになった。
だが問題はデザインだった。
いや、デザインそのものというより、デザインを決めるための会議が、だ。
クラ高生徒会は男女合わせて二十人以上の大所帯である。
しかもこれがなかなかの個性揃い。
各々こだわりを持っており、デザイン会議は難航した。
やれ袖の丈は何センチだ、色は何色だ、花柄にして、スタイリッシュにしろ、チョイ悪も入れろ、等々。
数時間かけても意見が纏まらず、疲れ果てた彼らはデザインを一年のオーマに一任した。
「皆の意見を参考に上手く作ってくれ」
「安心しろ。どうなっても文句は言わない」
先輩方は口々にそう言った――が、当然そんなのは建前だ。
てんでバラバラな意見を全部まとめるなど無理な話。
要するにオーマは責任だけ押しつけられたのだ。
――で、案の定、この通り文句が怒声となって降ってきたというわけである。
「シャツのサンプルがさっき届いた……これだ!」
ブランギはオーマのデザインしたシャツのサンプルを机に叩きつける。
彼らの話を聞いていた周囲の人間も、どれどれとそのシャツを覗き込む。
で、皆が皆あんぐりと口を開いた。
そのシャツは真っ黒な生地に火を吐く三つ首の黄金竜がプリントされ、さらに仰々しい書体で『クラウディアス生徒会』の文字が書き込まれていた。
「何だこの悪趣味なデザインは!?」
ブランギは両腕をワナワナさせながら問い詰める。
元々、一年生に全責任を押しつけるなど無責任な話だった。
なのにいきなり怒鳴りつけるブランギを止めよう……と、集まってきた中には良心的な者もいたのだが……。
(これはフォローできない)
と、誰もが匙を投げてしまっていた。
「お前はこれが伝統ある我々生徒会が着るべき物と思うのか!?」
「えぇと……」
オーマは頭を掻きながら、悪趣味と詰られたシャツを手に取る。
それから二、三度表裏をひっくり返して眺めてみてから。
「竜のデザインがドスが利いてますね」
オーマは満足そうに答えた。
(えぇぇー!?)
この空気の読めなさに誰もが心の中で総突っ込みする。
「おっっまっっっ……!!」
ブランギは顔を真っ赤にして唇をプルプルと震わせる。
彼はよくオーマに突っかかる先輩だと先程述べたが……実はむしろ振り回されているのは彼の方だったりする。
「このでくの坊! お前なッッ!」
ブランギは思いつく限りの罵声をオーマに浴びせようとした。
が、その罵倒が声になることはなかった。
横から少女の綺麗な声が割って入ったからだ。
「ふたりとも、どうかしたの?」
声の主は生徒会長のツクモ=キサラギだった。
彼女は王家の親戚筋に当たるキサラギ家の長女。
名門校であるこの高校の中でも屈指のお嬢様。しかし、その血筋を鼻にかけない柔和な物腰で、男女問わず人気が高い。
また可憐な顔立ちは白百合のように清楚であり、ヘタに触れたら汚してしまうのでは……と、こちら側が畏れを抱いてしまいそうになるほどである。
まさに高嶺の花という形容詞が似合う美少女が、この高校の生徒会長だった。
「せ、生徒会長!?」
そんな彼女に不意に声をかけられたブランギは、思わずその場でビシッと背筋を伸ばした。
「大声で話していたけど、何かあって?」
そう言ってツクモは軽く小首を傾げてみせる。
その仕草は美人でありながら可愛らしくもあり、綺麗だが親しみやすさも感じる――本人にその気はないだろうが――ある意味、小悪魔的ですらあった。
「オーマ君、どうかしたの?」
ブランギの返事がないので、ツクモは次にオーマへ視線を向けた。
「えぇと、その……」
「なぁに?」
オーマがどう説明しようか頭を掻いていると、ツクモはさらに尋ねてくる。
その拍子に歩幅一歩分、彼女は顔をオーマに近づけた。
「……!」
さすがのオーマもそれには眠そうな目を見開き、一瞬だけビクッとした。
「あ、ごめんなさい」
「いえ」
男子にも距離感の近いツクモに、オーマは少しばかり照れたように頬を掻く。
と、いつの間にか置いてけぼりにされたブランギがそこでハッとした。
「そうだ! 聞いてください生徒会長! このバカ、こんなっ、よりにもよって生徒会のシャツをこんなデザインにしたんですよ!?」
「あら、どんな?」
ツクモはブランギからシャツを受け取って確認する。
彼女はシャツのデザインをゆっくりと眺め、そして……
「ん~、いいんじゃないかしら?」
と、彼女が微笑んだ瞬間、ズコーッとブランギや他数名がその場ですっ転ぶ。
「……って! 何を言ってるんですか会長!?」
「え~ダメかしら?」
「ダメに決まってますよ!
「あらあら、ダメよそんなこと言っちゃ~」
「ですが会長」
「人も魔族も平等よ~。そういう発言をすると~、かえって学校の品格を問われることになるわ~」
魔族とはかつて魔王によって生み出された種族の総称である。
大戦直後は差別や奴隷化などもあったが、現在ではそれらを完全に法で禁じている。
今では人類と友好的に暮らし表社会で商売をする者もいる。
が、歴史的偏見というのはなかなか拭い去れないのもまた事実だ。
ゆえに今でも極一部では魔族を心の中で見下す風潮が存在する。
ツクモの言葉はそれを窘めるものだった。
「……」
彼女の正論の前に、ブランギはそれ以上何も言えなくなる。
「でも~これはちょっと男の子向けすぎるかもしれないわね~」
と、そこでツクモはオーマへも視線を移す。
「生徒会には女の子もいるから、女子用にもうひとつデザインできる?」
「……家に帰って考えてみます」
オーマはこくりと頷く。
「お願いね」
「……ウス」
ツクモは微笑まれ、オーマはもう一度頷いた。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます