第1章 2006年、春へ その4
雑談をしているあいだに、学生も次第に
みんな芸大に入ったことで気分が高揚しているのか、どことなく楽しげな雰囲気で満たされている。
そして9時を示すチャイムが部屋に鳴り響いた。
「それでは
パンフレットでも見た人だ。たしか広告業界の偉い人だったはず。
「映像学科にようこそ。えー、当学科は……」
学科長は淡々と、大芸映像学科について説明をしていった。
元々、映画会社の
まあ、おおむねパンフレットに書かれている内容と同じだ。
「映画制作かぁ、何やるんだろうなあ」
横で
僕も同じく、疑問ばかりが先に立っていた。
「では続きまして、実技担当の
佐々井先生に代わり、やけに若い、スーツ姿の女性の先生が壇上に向かった。
マイクの前に立った瞬間、加納先生はにっこりと
「新入生のみなさぁん、入学おめでとう~! わたしはみなさんの映画制作の実習を担当する加納と申しまぁす。4年間、よろしくお願いしまぁす」
まるで語尾にハートマークでも付いているかのようなポップさで、
(なんだこの先生……)
新作アニメの紹介をする若手声優ばりの甘い声だ。
「えーと、今からアンケート取りまぁす。手を挙げて答えてもらえるかな?」
そして急にアンケートを採り始めた。
なんだか急にフリーダムな空間に変わり始めたぞ。
「この中で、映画監督になりたいと思ってる人~」
結構な数の手が挙がる。
「じゃあ、次は脚本家~」
これも、それなりに挙がる。
「アニメ作家とかはどうかな?」
最初の質問と同じぐらいの手が挙がった。
続けて、ゲームデザイナーや広告プランナー、CGアーティストなどなど、いろんな職業の名前が出る。
みんな私語をしながら、好き勝手に進路について夢を語っていた。
なるほど、そういう職業があるのかと、漠然と考えていた将来像について、具体例が示されたのだ。それは少々夢見がちにもなるだろう。
(ああ、こういうのって、僕が思い描いていた芸大って感じだな……)
僕自身も、改めてゲームを作る仕事について思いを
「ふーん、よしよしよし……」
先生はニヤニヤしながらその様子を見ていたが、いきなりくわっと目を見開くと、
「おーし、みんな心して聞けェ!!」
突然、ドスの利いた声でそう怒鳴った。
「ひぇっ!」
「え、な、なに……?」
生徒もビビったのか、短く悲鳴を上げたりしている。
和やかだった雰囲気が一転して、一気に静まりかえる。
先生はその様子を
「よーし、いいかー? 去年、映像学科の卒業生は、135人いましたー」
今年の入学者とほぼ同じだ。
「その中で、入学時になりたいと思っていた職業に就けた人はー、何人くらいいたと思う……?」
みんな顔を見合わせている。
「よし、そこの金髪の子!」
「え、ええっ、あたし!?」
ナナコが思いっきり指差された。
「40人……ぐら」
「ブ───────────────ッッッッ!! はずれぇぇぇ!!!!」
少々かぶせ気味でのハズレ宣告。
「40人かぁ……うんうん、それぐらいあれば夢のある話なんだけどねえ~うんうん」
わざとらしく悲しげな表情を見せつつ、何度もうなずく。
「正解は……8人。アニメの演出が2人、脚本家が2人。大手のゲーム会社に就職したのが3人。監督にいたってはたったの……1人だ」
一気に会場がどよめいた。
明らかに少なすぎる。そ、そうなの?
「お金の話をしよう」
先生の声のトーンが、さらに低くなる。面持ちも、一気に真剣なものへと変わる。
「人間、腹は減るし眠くなるし、トイレにだって行きたくなる。社会生活を営んでいる以上は服だって着るし、雨風をしのぐためには家もほしくなる」
上着を脱いで、それをマイクスタンドにかけた。
「衣・食・住。人間に必要なものだからこそ、これらは間違いなく金になる。しかし、映画やアニメ、ゲームは……どうだ? 無くても別に困りゃしないだろう?」
演壇に上がるための階段に腰掛け、そこで足を組んだ。スカートが短いので、それどころじゃないのに、ちょっとドキドキしてしまう。
「
場内がすこしざわつく。
「これから君たちは、アホなことを4年もかけて学ぶことになる。学んだからといって、特に資格を得るわけじゃない。何かの保証があるわけでもない。さっきも言った通り、就職が約束されているわけでもない……」
そこで言葉を切って、先生はニヤッと笑った。
「だがな」
「アホだって、極めればそれは売り物になる。特別になれば、それは価値になる。それを目指せ。どうせアホをやるのなら、
「……そこまでいけば、紙一重がひっくり返って、君たちは天才になるかもしれん。そうなる
「以上だ」
場内は相変わらずシーンと静まりかえっている。何ごともなかったかのように、司会進行役の男性が壇上に上がり、事務的に話しはじめた。
「次に授業の採り方について説明をします。履修表と学生便覧を開いてください──」
◇
続く履修についての説明を聞きつつ、僕はさっきの先生の話を頭の中で繰り返していた。
(甘かった、かなあ)
考えてみれば、この業界はとにかく狭き門だ。それは映画だろうがアニメだろうがゲームだろうが関係ない話で、名前が売れて人気者になるのは本当に限られた人間だけだ。いくらこの世代がプラチナと呼ばれたところで、同い年の人間がみんな光り輝くわけじゃない。それは、元の未来の僕が何より証明していたじゃないか。
先生の言ったとおり、
それを学びに来たからには、それこそ衣食住より魅力的なものを作れるくらいの力を得なければならないのだ。
(がんばらなきゃ……な)
初っぱなから落ちこんでいても、何も始まらない。とにかく、先へ進まないと。
ガイダンスは次の項目へと移っていた。再びおじいさんの
「えー、では次に、みなさん一人ずつ自己紹介をしてもらおうと思います。学生番号1番から始めてもらって……そうですね、映像学科らしく、好きな映画監督を挙げてもらいましょうか」
佐々井学科長の言葉に、学生は少しどよめいた。
(え、映画監督って……)
言われて、困ってしまった。
仕事の兼ね合いもあって、映画自体はそこそこ
でも、監督の名前までは、正直言ってそんなに
「はい、じゃあ学生番号1番、
僕が焦っているあいだに、自己紹介が始まってしまう。
「1番、赤城
学生の間から、「あ、俺も好き」とか「スコセッシ、話合いそう」という声が漏れる。
(……
だけど、僕の脳内でははてなマークが飛び交っていた。
「2番、
「5番、
「9番、
(え、マジで誰……? 日本人も外国人も誰もみんなわからないんだけど)
つくづく、入学前に映画監督の名前ぐらいウィキペで見ておくべきだったと後悔した。えーと、うん、ウィキペディアはこの時代もうばんばん使われてるはず。
記憶の中から誰かいないかと探していたところ、
「10番、
僕のすぐ目の前の席から、キリッとしたとおりのいい声がした。
思わず顔を上げる。
しかし、名乗ったところから次の言葉が出てこない。
(あれ? ひょっとして、この子も映画監督知らないんじゃ)
もしそうだとしたら、情けない話だが僕の仲間が増える。
しかし、
「好きな映画監督……多すぎて一人二人には絞れませんが」
彼女はそう口火を切ると、
「昔の邦画では
その後も、これまた聞いたことのない監督とその特徴を羅列していった。
「ああ、詳しいのはわかったからその辺にしとけ。他の
「……はい、失礼しました」
かすかに舌打ちが入ったような気もしたけれど、河瀬川はそこで言葉を切った。
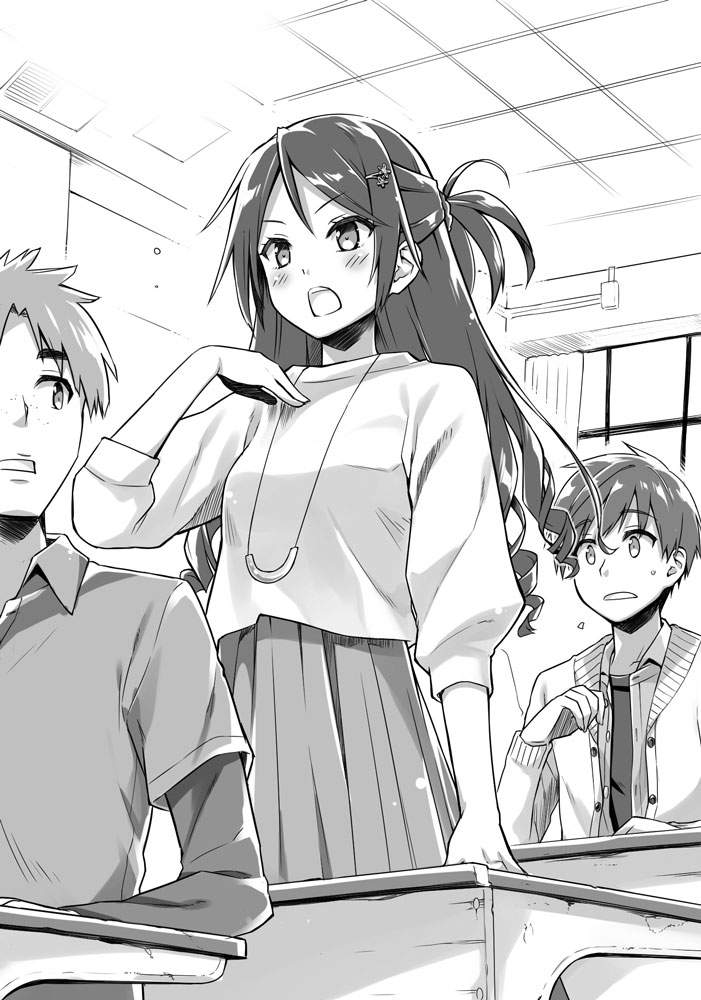
(……一瞬黙ったのはそういう理由だったのかー)
意地の悪い期待をしたバチが、思いっきり当たった気分だ。
「うへーすげえなあ、めちゃくちゃ詳しいなこの子」
隣の
他の席からも、
「15番、
(あ、クッソ、先に言われた!)
残されたわずかな希望だったアニメの巨匠を、ナナコに先んじて言われてしまった。
(ま、まあいい、いざとなったら
もうひとりのストックをなんとか失わないよう、祈りを
「23番、
妙にほわほわした声が響き渡る。
「監督、監督は、え────っっと」
シノアキは首を左右に傾けつつ、明らかに『無』の表情を見せていた。
(あ、これはマジなやつだ)
さっきの
(シノアキ、ここはもう無理せずに「知らない」って言お……)
「えーっと、好きな監督は
シノアキがそう
「あれ? 野球の監督と映画の監督は違うとね?」
シノアキは首をかしげつつ、席に着いた。
一瞬の静寂の後、何事もなかったかのように次の学生が自己紹介を再開して、元の時間が戻ってきた。
だが、先程まで河瀬川への尊敬で埋め尽くされていた会場は、シノアキの発言で一変し、『なんかすごいのがいるぞ』という好奇心で塗り替えられていた。
「……映像学科に入ったというのに、なんなのあの子。ありえないわよ……」
前の席でブツブツとつぶやく河瀬川
どうやらこの学年は、相当にカオスな集団になりそうだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。







応援すると応援コメントも書けます