第20話 罪悪感とアップルパイ
「お腹空いたー」
「最近お前、食べる量が増えたもんな」
「蒼兄、ノンデリ」
「なっ。俺は事実を言ったまでで、単に成長期だからすぐに腹が減るんだろうっていう客観的事実をだな……」
「蒼兄、セクハラ」
「どこが⁉」
蒼司と瑞葉が、仲よく言い合いながら帰ってきた。
彼らは温太とまつりを見て、同時にぎょっとする。
「まつり、髪の毛ぐちゃぐちゃだぞ⁉」
「お姉ちゃん、大丈夫⁉ 鳥の巣みたいになっちゃってるよ⁉」
そんなにひどいのだろうか。
まつりが髪を手櫛で直しはじめると、すかさず瑞葉も手伝う。彼女はそのまま、温太に厳しい視線を送る。
「温太兄はゴリラなんだから、人間の頭を撫でるなんて高度なことに挑戦しないで!」
「言いたい放題だな、瑞葉……」
「いや、ゴリラの握力は五百キロ相当といわれるが、子どもをあやす時などはしっかり加減していると考えられているんだぞ」
「お前もか、蒼司……」
弟妹の暴言を甘んじて受け入れていた温太だが、慌てて台所へ戻っていく。
「まずい、料理の途中だった。とりあえず唐揚げだけはできてるから、お前ら先に食べてていいぞ。あ、手洗いうがいしてすぐにアイス冷やせよ」
そこから彼は、いつもの手際のよさを発揮した。
まつり達が茶碗にご飯をよそい、飲みものの準備をしている内に、味噌汁やレンコンのきんぴらを完成させてみせた。
「いただきます」
全員一緒に食卓について、夕ごはんがはじまる。
まつりはまず、卵を落としたジャガイモと玉ねぎの味噌汁に手を伸ばした。
椀の中央に浮かんでいる半熟卵に、箸を入れる。とろりと黄身が溢れ出し、味噌汁に溶け込んでいく。
これをジャガイモにつけ、口に運んだ。味噌や出汁の旨みが染み込んだホクホクのジャガイモに、黄身がまろやかに絡んでたまらない。
続けざまに玉ねぎも一口。柔らかいけれどシャキっとした食感が残っていて、これもまたおいしい。
味噌汁を食べると、ほっこりした気持ちになる。まつりはこくりと汁を飲んでから、ほっと息をついた。
「うん、おいしい。温まるね」
「お姉ちゃん、唐揚げもおいしいよー」
瑞葉は大きな唐揚げを一口で頬張りながら、満面の笑みを浮かべている。
まつりは頷いて唐揚げを取り皿に載せた。
後のせの白髪ネギをたっぷりとかけてから、かぶり付く。
塩ベースのあんがネギとよく合う。香ばしい衣からじゅわっと肉汁が溢れ、味わいが口いっぱいに広がる。黒胡椒のピリリとしたアクセントも最高だった。
そのあと、ピリ辛に味付けたレンコンのきんぴらを食べる。
ほんの少しの唐辛子とたっぷりの白ごまが絡めてあるため、風味が豊かだ。
レンコンは火を通すとねっとりしたほくほく食感になるが、温太はあえて生のシャキシャキ感を残している。まつりは、その独特の食べ応えも好きだった。
視線を感じてふと顔を上げる。
温太の微笑ましげな眼差しが、まつりに向けられていた。
ばつが悪い。これでは、わざわざ好物を言うまでもないというものだ。
――おばさんとか性格きつそうとか言われる方が、多いのにな……。
温太にかかれば、まるきり子ども扱いだ。
むず痒いと同時に、胸が切なく痛む。
家族で囲む食卓は、いつも温かい。
潤がまだ元気な頃もそうだった。まつりの両親が生きていた頃も。
箸を止めたまつりの隣で、瑞葉が訝しげな声を上げる。
「――ん? 甘い匂いがする」
妹の言葉でまつりも気が付く。
居間には食欲をそそる甘い香りが漂っていた。どうやら、既にアップルパイも焼きはじめていたらしい。
「今日は、デザートにアップルパイも作ってくれてるんだよ」
「アップルパイ。まつりの好物だらけだな」
煮た林檎の食感が苦手な蒼司が、渋い顔をする。
まつりは唇を尖らせて彼を睨んだ。
「作ってくれた人の前でそういう言い方やめなよ。温太くんも分かってるから、蒼司の分はそもそもないし」
「別にいい。自分のアイスも買ってきたから」
「……いいな」
「……お前と温太の分もある」
「え? え、あ、ありがと……」
蒼司は、気恥ずかしそうに目を逸らした。
まつりもまつりでぎこちなさが居たたまれなくて、妙な沈黙が生まれてしまう。
そこで、温太が口を開いた。
「安心しろ。蒼司の分は、チョコレートパイにしてある。しかもアイスは熱々のパイにのせてアレンジ可だ」
それは、想像だけでおいしそうだ。
まつり達は無言で目を合わせると、すぐに食事を再開した。
食べ終わった食器を片付けるため、台所に入る。
ちょうど、温太がトースターからアップルパイを取り出しているところだった。
「アップルパイって、トースターでできるんだね」
「ライスペーパーのアップルパイだからな。元々生でも食べられるものだから、しっかり焼き色さえ付けばいいんだよ」
SNSでアレンジレシピを見かけて、挑戦してみたくなったらしい。
こんがり焼けたアップルパイは、かたちが正方形に近かった。
バターの匂いといい、やはりライスペーパーとは思えない。
「すごいね。これで、本当にパイシートは使ってないんだ」
「ライスペーパーって普通は水で戻すんだけど、これは卵とバターと牛乳、それと砂糖と少しの塩を混ぜたもので戻してるんだ。こうすることでパイ生地みたいになるらしいぞ。ライスペーパーを三枚重ねてあるから、食感もしっかりしてるはずだ」
温太がいつもより饒舌になり、期待に瞳を輝かせている。
一つのアップルパイにつきライスペーパーを三枚も使っていたら、節約料理にならないのではないか。そんな野暮は言わないことにする。
まつりに続いて食器を片付け終えた瑞葉が、自身の席に用意されたアップルパイを眺めてにんまりと笑う。
「今年も、温太兄のアップルパイの季節が来たかー。温太兄が東京に行ってる間は食べられなかったけど、ほとんどこの時期の定番だよね」
「おう。やっぱ林檎は、ぼける前に食べきりたいからな」
温太が頷いて答える。
長野あるあるで、秋になると大量の林檎をもらう。
どこの家も似たようなものなので、他にお裾分けすることも難しい。
林檎は日持ちする果物だが、食べ頃をすぎると食感が悪くなってしまう。こうなると生で食べるには向かないため、林檎を大量消費するカレーやアップルパイが、白河家の食卓に上がるようになるのだ。
――これを食べたら、ちゃんと好きって言おう。
まつりも焼き立てのアップルパイを前に、小さな決意をする。
これからは家族に察してもらうばかりではなく、自分で主張していきたい。
遠慮をしていたって、温太にも蒼司にもどうせ見抜かれてしまうのだから。
「アイスまでのっけたら……さすがにカロリーオーバーかな……」
ただでさえおいしい温太の料理だし、秋はおいしいものが多い。
さつまいもも栗もかぼちゃも、シャインマスカットもシナノパープルもおいしかった。新そばも新米も最高だった。
どれも全力で味わったことは後悔していないけれど、そろそろ体重を戻したいところ。
アイスを控えるべきか思い悩むまつりの横で、温太が少し意地悪げに笑った。
「さすが、まつりは思慮深いな」
「ねぇ、うっすら馬鹿にしてるでしょ」
今日のところは、アイスを買ってきてくれた蒼司を尊重することにしよう。
まつりはそう決めて、アップルパイにアイスをのせた。
絶品だったのは言うまでもない。
「うわー、さつまいものアイス買って正解! 林檎と合うー!」
「瑞葉、私のマカダミアナッツ味もおいしいよ。ちょっとあげるね」
「何で俺はこんな時にまで……チョコ味のアイスを……」
「チョコレートパイにチョコアイスだって、うまくはあるんだけどな。あー……俺のヨーグルト味、食べるか?」
……そう。
まつりは何でも考えすぎるのだ。
一之瀬から翔の現在について聞いた時、【ほしいさま】は自由な人生の記憶を求めたのだろうという結論にいたった。
けれどまつりは、もっと嫌な想像をしてしまった。
【ほしいさま】は、病弱だった当主の生への執着から生まれた呪物。
死者すら出している呪物が……本当に自由な記憶だけで満足するだろうか。
もしも、【ほしいさま】が求めたのが、取り込んだ者の人生そのものだとすれば。
若く健康な体を欲したのだとしたら――保護された翔は、果たして本物なのだろうか。
薄皮一枚剥がした向こうに、あの影のようなものが、日の光を全て吸収するかのような漆黒があるのでは――……。
生きていたことを素直に喜べばいいのに、まつりはどうしても、そんなふうに想像してしまうのだ。
『十一月九日。【ほしいさま】を再封印する。ただここに、病弱だった当主の怨念が本当に残っているのか——不明』
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




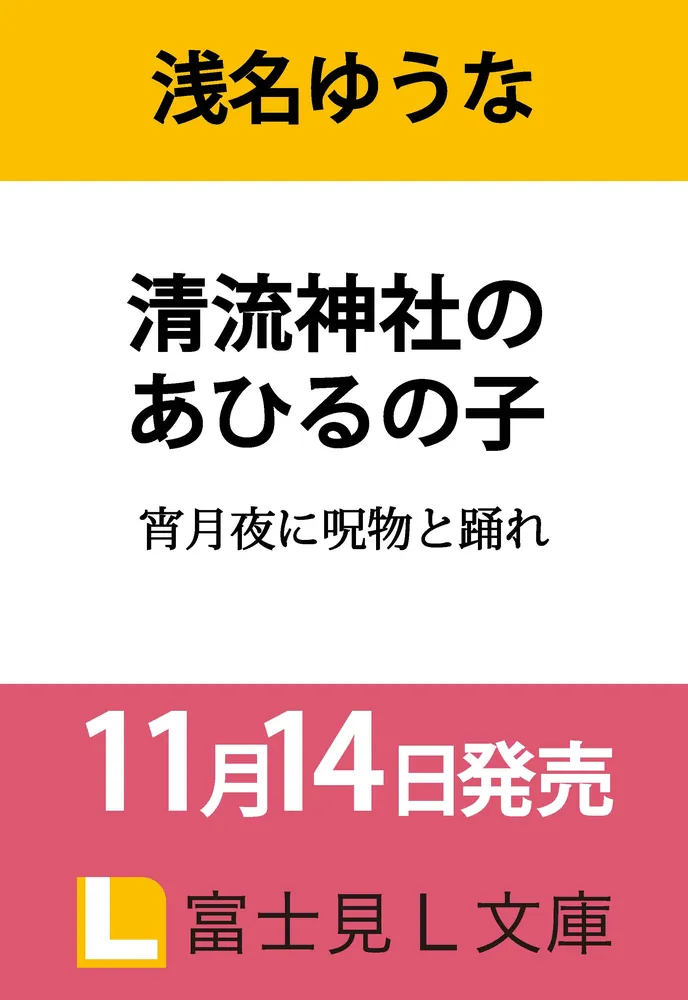
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます