第3話 呪物の来訪
「失礼いたします」
暗い庫内に誰かがいるわけではない。
蔵に入る時に挨拶をするのは、清流神社に代々受け継がれる習慣だった。
この蔵には、やむを得ず預かることとなった呪物がいくつも眠っている。
普段は閉じ切っている格子窓を開け放ち、蔵の中に明るい日差しを取り込む。
整然と並んだ棚には、様々な呪物が置かれていた。
たとえば、死者の顔の皮から作られた【人皮面】。
これは見た目も素材もかなりインパクトがあるけれど、決して恐ろしいものではない。
アユタヤ王朝時代のタイでは、舞踏家など芸術分野で活躍した人が亡くなると、顔の皮を剥ぎ、面にして祀るという信仰があったらしい。これを祀る者は、偉大な師の技術を継承して活躍できるという。
【カパーラ】は、死者の頭蓋骨を加工して作られた盃だ。
チベット製の装飾のないシンプルなものもあれば、ネパールで作られたもののように、鮮やかな彩色が施されたものもある。
智慧や知識の象徴とされる法具であり、『有と無の分別を断つ』シンボルとして儀式に用いられる。チベット密教では、儀式の祭壇で仏に酒を注ぎかける際に、カパーラが使われているらしい。
他にも、人形型の特殊なお守り【フンパヨン】や、【キブ】という悪霊を吸引する壺など。呪物というと人を不幸にするイメージが強いけれど、儀式に使用されるもの、精霊や神の依代となるものなど、神秘的なものも数多くあるのだ。
もちろん、【見たら不幸になる絵画】や【呪いの五寸釘】、【持ち主を死に追いやった市松人形】など、いわくつきの呪物も保管されているのだが。
丁寧に棚のほこりを落とし、濡れた雑巾で床を綺麗にしていく。触れることさえ禁じられたものもあるので、これが精いっぱいの掃除法だ。
一番の目的は、呪物達に異常がないか確認をすること。
見てはいけない絵の封印は解けていないし、呪物が一人でに動いた形跡もない。今日もそれが確認できれば十分だった。
まつりは丁寧に、けれど淡々と蔵内を拭き清めていく。
来客があったのは、紅葉をさらに朱く染める、夕陽が差しはじめる時刻だった。
参拝客ではなく、来客。
それは呪物関係の相談者がやって来た合図に他ならない。
上品な雰囲気の、五十代の男性。ジャケットにスラックスと服装も洗練されている。だが、妙に顔色が悪くやつれていた。
清流神社には社務所がないため、こういった場合は白河家の客間に案内するのが定番の流れだ。まつりは疲れた様子の男性を、すぐに客間に通した。
今は蒼司がお茶の準備をしてくれている。その間まつりは、温太を待つ場繋ぎも兼ねて世間話をしていた。
男性は、上村実と名乗った。
はるばる東北地方からやって来たらしい。
「山形県から、ですか……わざわざ長野県まで来られずとも、地元にも有名な寺社が多くあると思うのですが……」
「この神社は、その……呪物を引き取ってくださると聞きまして」
地方の小さな一神社が、どのようにして全国に名を轟かせているのだろうか。
信じられないし考えたくもないので深く掘り下げることなく、まつりは軽く訂正するにとどめた。
「……ご依頼主様のお話を聞いての判断となりますが、まずは呪物のお祓いなどで対応させていただくのが、通常の流れとなっております」
「そうなんですか? 困ります、私の手には余るもので……」
今にも身の上話がはじまりそうになったところで、ちょうど温太が座敷に顔を出した。緑茶と茶菓子を載せた盆を持つ、蒼司を伴っている。
「たいへんお待たせいたしました。宮司を務めております、白河温太と申します」
外向けの顔をした温太は、普段より貫禄が増す。彼が頭を下げると、実もつられたように辞儀を返した。
けれどすぐに戸惑いを浮かべる。
「いやぁ、こんなにお若い方が宮司をなさっているんですね……」
「先代が帰幽し、跡を継ぎました。若輩なれど、誠心誠意努めさせていただきます」
泰然とした温太の振る舞いは、若い責任者への不安を払拭したらしい。実はほっと表情をゆるめる。
そうして正座をして向かい合い、正式に相談がはじまった。
「改めまして、ご挨拶申し上げます。上村実と申します。本日は、こちらの呪物を引き取っていただきたく参りました」
彼がそう言って畳に置いたのは、竹で編まれた小さめの行李だった。
だが、見た目からしてただの物入れではない。古びた護符が何枚も貼られ、麻紐で何重にも縛られている。厳重な封が、いかにも忌まわしいものをしまい込んでいるようで、見ている者に不安をもたらす。
「これは、【ほしいさま】というものらしいです。かつての大名家に、代々伝わっていたものだそうで」
実はボストンバッグの中から、さらに手帳を取り出した。
松葉色の革張りで、片手に収まるようなサイズ。角がひび割れているが、使い込まれたもの特有の重厚感があった。
「私自身、最近までこの行李の存在を知りませんでした。私のあずかり知らぬところで父が管理していたのですが――その父が亡くなって」
父親の死を告げる声が、やけに暗く重い。
しんと静まり返った客間内、実がゆっくりと続けた。
「この手帳は、父が遺したものです。【ほしいさま】についても、ここに詳しく記してありました」
「……拝見してもよろしいでしょうか?」
「どうぞ」
温太が断りを入れ、実から手帳を受け取る。
まつりもそれを隣から覗き込んだ。
手記は、覚え書きのようだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




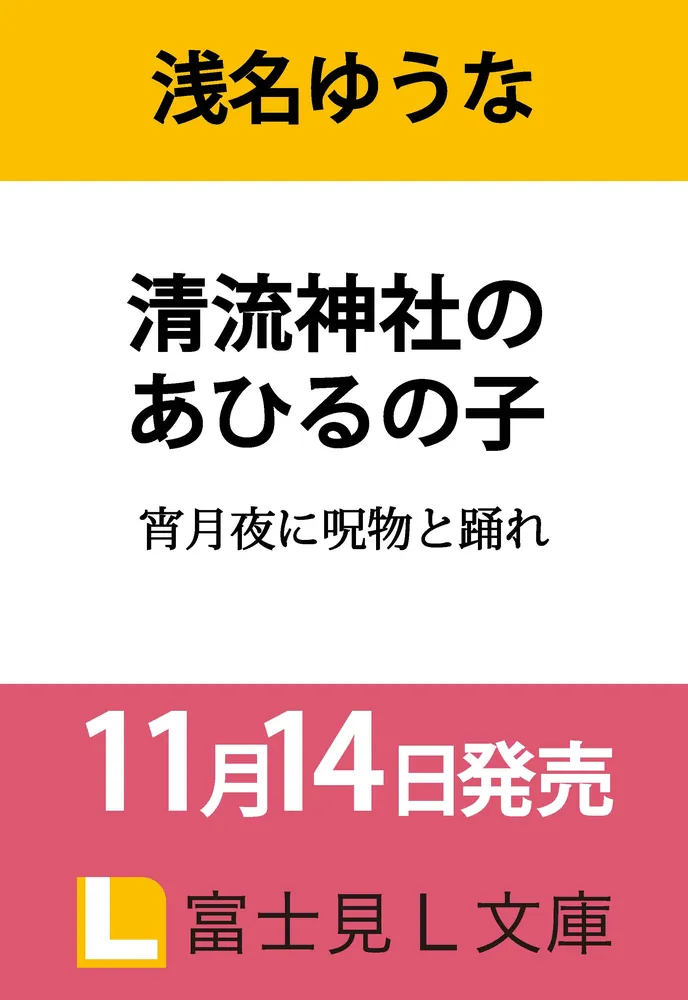
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます