一杯目 涙をぬぐう琥珀色のベジブロス⑦
主よ、命の恵みをありがとうございます――
その日の夕食の席で、そっとシーナは祈りを捧げた。
食卓に並んだ皿へと、エルザが丸パンを載せていく。
麦のスープは売り切れてしまったが、パンの皿にはジャムだけでなく、網焼きした肉や野菜まで添えられていた。野菜は隣のアルバが育てたものらしい。
焼き目のついたかぼちゃは見るからにほくほくとしていて、鮮やかな色をしたオクラはなんともやわらかそうだ。
たった一切れではあるものの、ほどよく脂が滲んだ肉も、いい具合に食欲を刺激してくれた。
「ハルタ、いちじくのジャムを取ってちょうだい」
エルザが手を伸ばす。
「パンのジャムならあるだろ」
ハルタは各自の皿に盛られたりんごのジャムを指差した。
「そうじゃないの。肉のソースにするのよ。シーナも試してみて。いちじくのジャムはこの肉にとても合うの」
「お前の好みだろ」
ハルタは苦笑しながら、いちじくのジャムが入った瓶を手渡す。
「私の舌を信じなさい」
エルザは有無を言わさず、シーナの肉にほんの少しいちじくのジャムを垂らした。
「いただきます」
ごくりと喉を鳴らすと、シーナは用心深く肉を口にした。
ぷちぷちとした、面白い食感がする。
弾力のある肉と一緒にいちじくの粒感を楽しんでいると、塩気とジャムの甘みがちょうどいい塩梅で混ざりあい、極上の旨味を連れてきた。
エルザさんの舌は正しい。
果物の酸味は、肉をさっぱりとさせる効果がある。
いちじくには、肉の消化を助ける成分が含まれている。
シーナの知識に基づけば、いちじくと肉の組み合わせは合理的だと言える。
「すごく……おいしいです」
「ほらね」
エルザは得意げな顔をする。
「どれどれ」
すかさずハルタも肉にジャムを付けて頬張った。
「なかなかだな」
なかなかどころか、とろけそうな表情だ。
「みんなで食べると余計においしいわね。楽しい会話も調味料みたいなものかしら」
会話が調味料……シーナは目を見開く。
食事中の会話が許されていることや、純粋に食事を楽しんでいる自分自身にも、シーナは驚いていた。
「そうかもな」
ハルタがしみじみと言う。
「私たち二人の時はたいした会話もなかったもの。シーナがいてくれるおかげよ」
エルザから優しい眼差しを向けられ、シーナは胸に鈍い痛みを覚えた。
二人には感謝しながらも、罪悪感を覚えるせいだろう。
私には、隠し事がある――シーナは視線をさまよわせる。
「シーナは息子の代わりじゃないんだぞ」
ハルタがエルザに釘を刺すように言った。
「私たちには息子が一人いるの。農家なんかやりたくないって、十年前に家を出ていってそれっきりだけど」
いつもの元気なエルザとは違い、憂いを含む表情だった。
「そうでしたか……」
シーナは励ましの言葉を探すが、簡単には見つからない。
「年を取ってからようやく我が家にやってきた子だったから、可愛くて可愛くて、少し甘やかしすぎたのかも」
気まずそうにエルザが言う。
「だけど、どこかで元気にしていてくれたら、それでいいの」
「あいつなら、元気に違いないさ」
エルザとハルタはうなずきあった。
どこか寂しげな二人に、シーナまでしんみりとしてしまう。
どんな言葉も絵空事のように感じられ、軽々しく口にできない気がした。
気の利いた言葉ひとつ言えない自分がただ、歯がゆい。
「いつかあの子が帰ってきてくれた時に、好物だった麦のスープで迎えてあげたかったけれど……もう、無理みたい。老いてしまったせいね」
エルザは弱々しく笑った。
「近いうちにあの店はたたむつもりよ。私もそろそろのんびりするわ」
「で、ですが……」
麦のスープを口に含み、幸せそうに微笑む人々の顔が次々と頭に浮かぶ。
丸パンをかじる子どもたちの笑顔は、宝石のようにまばゆかった。
エルザの店には一流と言われる高級料理はないけれど、他のどこにもない贅沢な一品がある。並んでも食べたい、思いやり溢れるスープのことだ。
エルザさんの店を失いたくない……。
シーナの心は激しく揺さぶられる。
とはいえ、すでに高齢となったにエルザに、これ以上忙しい店を続けてもらうのも酷だろう。
「安心して。シーナの働き先は、ちゃんと見つけてあげるから」
エルザがそっとシーナの肩を撫でる。
ああ、優しくて温かい……。
生きる気力を失っていたシーナを包んでくれた、琥珀色のスープの温もりそのものだった。
こんな時にまで、私のことを心配してくれるなんて。
『おいしいパンが焼けるようになれば、きっとこの先も困ることはないでしょうから』
あの言葉は、店をたたんだあとのことを考えて、シーナに生きる道筋をつけようとしてくれたエルザの思いやりだったのだ。
そう気付いた時、心の中までじんわりと温かくなる。
これほど親身になって、シーナのことを考えてくれた人はいただろうか。
両親でさえ他人のようであったのに……。
過去を思い出し、シーナは胸を痛める。
エルザさんのために、私にできることはあるかしら。
しかし、シーナは何も言えずに、ただ膝の上でぎゅっと拳を握りしめるだけだった。
翌朝、開いた窓の外から男の声が聞こえ、シーナは瞼を開ける。
使い古した鍋にオイルランタン、たくさんの荷物の隙間から、ゆっくりと体を起こした。
「ブランシェ、今日はご機嫌ななめなのか?」
ふわりと、夜明け前のひんやりと冷やされた風が屋根裏に舞い込む。
「こっちを向いてくれよ。俺の可愛いブランシェ」
しんと静まった朝に、再び優しく包み込むような低音が響いた。
「君なしじゃ、俺は生きていけないんだ」
恋人に囁く、隣人のアルバの声だと気付き、シーナはそっと窓の外を覗く。しかし。
薄暗がりの中では、アルバとその恋人の姿は見つけ出せなかった。
霧も深いようで、空気はしっとりとしている。
「そろそろ出かける時間だ。君も一緒に来てくれるだろう?」
揉めているのかしら。
お隣さんの痴話喧嘩を、これ以上盗み聞きするわけにはいかない。
窓を閉めようと、木枠に手をかけたその時だ。
突如、馬の嘶きが聞こえ、驚いたシーナは肩をびくりと震わせる。
もう少しで声をあげるところだったわ……。
両手で口元を押さえたまま、シーナは胸を撫で下ろした。
アルバが飼っている馬は、大人しい利口な馬だと聞いている。
シーナは再び窓の外を覗くが、馬の姿もやはり暗くてよく見えなかった。
「綺麗だよ。可愛いよ。君は最高だ。だから機嫌をなおしておくれ」
聞き耳を立てているシーナのほうが恥ずかしくなり、急いで窓を閉める。
色恋沙汰には疎いシーナであるが、恋愛が何たるかくらいは分かっているつもりだ。
きっとあれが、情熱的な恋というものね。
それでも、つれない恋人をとりなすアルバの様子を想像すると、おかしくなってくる。
物怖じしない普段の態度と、ずいぶんと違いがあるせいだろう。
背が高く逞しい体つきのアルバが縮こまっているのかと思うと、どうしても表情が緩む。
「いけないわ。人様のことを笑うなんて」
シーナは反省して、すぐさま表情を引き締めた。
手早く身支度を整え、屋根裏から下りる。店先で、ごとりと音がした。
用心深くそっと扉を開ければ、大きな牛乳缶が置かれている。
町の誰かが、搾りたてを届けてくれたのだろう。
店には毎朝のように、採れたての野菜や手作りの干し肉などの、様々なおすそわけが届く。そのたびに、支え合って生きる人々の輪の中にいるのを、シーナは実感していた。
「水につけて冷やしておくべきよね……」
牛乳缶を扱うのははじめてだ。
取っ手をつかんで持ち上げようとしたが、ずっしりとした牛乳缶はびくともしなかった。
馬の蹄が聞こえ、シーナは振り向く。
目を凝らすと、馬にまたがり颯爽と霧の中を走る、アルバの背中が薄っすらと見えた。
「さっきは笑ってごめんなさい」
やがて日が昇り、霧が晴れていく。木の葉に降りた雫が、光を受けてきらめく。
「アルバは出かけたようね」
母屋から、薄着のままのエルザが顔を出した。
「おはようございます。牛乳が届いていました」
「まあ、そんなにたくさん。ハルタに運んでもらって、さっそく朝食にいただきましょう。バターやチーズを作るのもいいわね」
エルザは楽しそうに頭を悩ませる。
ゆったりとはじまった朝は、シーナの表情を柔らかに映すのだった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




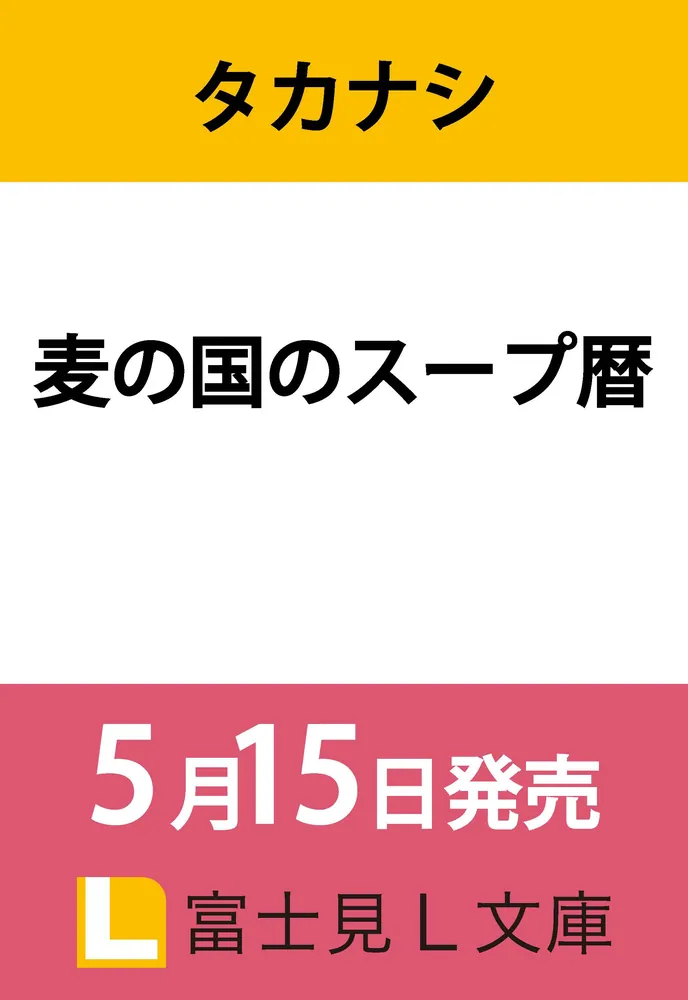
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます